
TOC(制約理論)で行政を改革する by Kristen Cox ④
こんばんは。
『行マ研サポートライター』の狂さん(Linkedin HN)こと、山﨑です。
今晩もよろしくお願いします。
いつもお知らせしている『行マ研(全体最適の行政マネジメント研究会)』の4年ぶりのリアルセミナー
『仕事の生産性は上がってますか? 行政課題解決セミナー』
まであと3日となりました。

お申し込みがまだの方は、是非お申し込みいただければと思います。
クリステン・コックスさんが日本に来られて講演された動画を、今日もご紹介したいと思います。
この動画ですが、TOCクラブの会員(登録無料)であれば誰でも見られるものなのですが、YouTubeなどでの一般公開はされていません。
ただその内容は、正に『TOC(制約理論)で行政を改革する』という、とてつもなく大きなチャレンジそのものであり、そしてそれを成し遂げられた実践報告でもあります。
発表の中でクリステン・コックスさんがいくつかの章に分けて発信されていますので、その章ごとに分けて記事を書いていきたいと思います。
動画の視聴方法
目が不自由でありながら、米国のユタ州の行政改革をリードし、Business & Enterprise Awardを受賞した米国を代表する女性経営者の一人、クリステン コックス・エグゼクティブディレクター。
納税者から託された貴重な、そして限られた予算でいかにして住民のためのマネジメントをするか、この課題に真正面からTOCで取り組んだ事例を紹介しています。
コンテンツはもちろんですが、明るい人柄と目が不自由であることを感じさせないプレゼンには、いつも圧倒され、勇気をもらえる素晴らしい内容となっています。
この動画に行き着くには、まずTOCクラブの会員登録(登録無料)をしていただいてから、トップメニューにある
[TOCクラブ・アーカイブ]
を選択してもらい、そこにドロップダウンリストがでるので、下から3番目の
[行政・社会貢献]
を選択してもらって、その後で開かれるページの一番下。
[TOCで行政を改革する by Kristen Cox]
を選んでいただくと、動画が視聴出来ます。
と、とりあえず紹介させていただきましたが、コレってどれだけ興味がある方でも、TOCクラブのサイトに行って、会員登録をして、その後動画まで辿り着くのに、これだけの数のリンクをクリックしなきゃならないというのは、余りにハードルが高すぎると思ってます。
(だから記事にしようと思ったってのもあるんですが・・・(😅))
しかしその内容は、特に行政職員の方であればあるほど、一見の価値ありとオススメ出来るものです。
また民間の方であっても、会社が官僚的な組織になりつつあるなどのお悩みがある方にとっては、本当にヒントになる内容が満載です。
1時間少々の動画ですが、ぜひ一度、ご覧いただけたらと思います。
「私たちはゴールについて度々話題にします。
これはシンプルなことに思われます。
特に民間の場合は明確なゴールがあります。
社会的なゴールもありますが、とどのつまりは利益を出すことがゴールですよね。
では州政府におけるゴールとは何でしょうか?」
民間企業であれば「利益を出すことがゴール」という、明確なものがあります。
ですが、行政府・州政府であった場合はどうでしょう。
「これが州政府のゴールである」と、明確に提示できるでしょうか?
そのことについて昨日予告させていただいたとおり、クリステン・コックスさんの講演内容をお伝えしたいと思います。
流れと集中

州政府のゴールについて、クリステン・コックスさんは語っていきます。
「決して耳障りは良いけれど、捉えどころが無いゴールのことではなく、とても具体的で計測可能な、組織を動かすゴールです。
ゴールの設定はとても重要なのです。」
「流れについて話しましたが、少なくとも、アメリカの行政においては新しい概念です。
流れの概念など、そもそも存在せず、代わりに政策やその他諸々について語ります。
流れは、行政では欠如している概念です。
でも有権者に対するものやサービスの流れを滞らせないようにしたいのです。」
有権者に対するものやサービスの流れを滞らせない。
これは当然のことのように思われます。
ですが実際にはどうでしょうか?
コロナ禍において、各都道府県、各市町村において、ワクチン接種の対応は、ハッキリ言ってまちまちでした。
高齢者のような、抵抗力の低い世代から、ワクチン接種は始まりましたが、その流れには大きな差があったと言わざるを得ません。
一部の地域では間違いなく、ワクチン接種の流れが停滞していたのです。
その理由は様々ですが、本来ならどの地区であってもそれに差が出ていてはおかしいのです。
にもかかわらず、サービスそのものが滞るところと、スムーズに流れるところに差が出てしまう。
故に、行政のゴールの一つとして、「流れ」を選ぶことは当然のことなのです。
クリステン・コックスさんは続けて語ります。
「次は集中についてです。民間でも行政府でも、『より多くの仕事をこなせば、より自分は成果を出している』と考えがちです。
改善の機会は至るところにありますが、それらが同じ結果をもたらすとは限りません。
したがって、最大の効果をもたらす、ごく僅かな事に集中することが重要です。」
「これ自身、チャレンジであり、鍛錬が必要です。」
「少ないことに集中することが、より多くの成果をもたらすと信じるのです。」
クリステン・コックスさんは、
「多くの仕事をこなすよりも、最大の効果をもたらすことに集中した方が、限られたリソースを有効活用できる。」
と語っておられるのです。
そしてそれこそが、今までに無い視点を持つことになり、だからこそ彼女は、
「これ自身、チャレンジであり、鍛錬が必要」
と言っているのです。
イノベーション(Why innovation matters)

「何故イノベーションが重要なのでしょうか?」
クリステン・コックスさんは問いかけます。
「私たちが取り組んでいるのは、現有のリソースを最大有効活用するということです。
税金を有効活用し、設定した成果を確実にもたらすように、することです。」
「私の好きなアインシュタインの言葉に、
『問題はそれが発生した時と同じ程度の理解では、解決することはできない』
というのがあります。
私たちは、もう一段高い次元で考える必要があります。」
このクリステン・コックスさんの言葉は、正に『問題を明確に定義する』と同義でしょう。

『問題を明確に定義する』とは、『問題とは目標と現実のギャップ』であるという考えに立つことです。
目の前にある現実を、ただ「問題だ」と言って騒いで、解決策ばかり求めていては、『永遠に終わらないモグラ叩き』を始めることになります。
『問題とは目標と現実のギャップ』という考えを受け入れ、もう一段高い次元で考えることこそ、必要であると彼女は訴えているのです。
彼女はこの後、『世代間の貧困問題』や『刑期を終えた囚人の社会復帰問題』、『児童虐待問題』などの大きな課題があることを告げます。
「州政府が健全に昨日するためには、新たな体型だった方法で解決策をもたらす必要があります。
ゴールドラットコンサルティングのイノベーションに対する取り組みは素晴らしいと思います。
来年には、州政府で同じような取り組みを広げたいと思っています。」
「思考プロセスは、仮説を確かめるために、色々な場面で有効ですが、さらに進んで、新たな解決策を実行に移すところまで持って行きたいと思っています。
そうでなければ、州政府はいつまでもこれらの課題を解決できずにいることになります。」
「これらが取り組んできた重要な考え方ですが、これは始まりに過ぎません。
この取り組みを始めた時、私たちは『さあ、州政府全体を改革するのだ』『それってどういう意味だ? そのスコープは? 大仕事だ!』という具合でした」
この時、彼女を始めとした州政府の人たちは、何をどのようにすれば良いのかが分かっていませんでした。
「科学的にものごとを分類する方法を、TOCから学びました。
その結果、多くの部局の状況を調べていくうちに、どこの部局でも共通の事象があることが分かってきました。
多くの人々が同じ問題を抱えているという、パターンが見えてきました。
そこで業務の分類を始めました。」
「例えば動物界では、哺乳類や鳥類などの分類があります。でも何故、分類するのでしょうか?
学習が加速するからですね。違いますか?
哺乳類に遭遇する度に改めて研究する必要はありません。犬や猫には共通なものがあることを知っています。
鳥類や魚類やは虫類でも同様です。
分類することによって解決策により早く辿り着けるのです。」
「多くの部局を巡るうちに、州政府システム内には、共通の課題を持ち・・・、共通の解決策、共通のゴール、共通のスループット、共通の評価尺度を持つ、種々の分類があることが分かりました。
それらの異なる業務環境に見合った簡略化した、『戦略と戦術のツリー(Strategy & Tactics Tree:S & T Tree)』をテンプレート化することにより、一々作り直す必要はなくなりました。
8つの分類があるのですが、TOCを職員と繋げるために次のようなステップを踏みました。」

「障がい者と一緒に働いている職員に対して、『あなたはプロジェクト環境にいるのだ』と言っても通じないので、現場の人々に共感を呼ぶような言い方にしたのです。」
Project(プロジェクト)
道路を造ったり、ITシステムやソフトウェアを開発People/Social Service(住民/社会福祉)
刑務所を出所した人、子どもたち、薬物中毒の人々など、住民に対する仕事policy(政策)
政策の立案と実行があり、政策立案にはイノベーションが必要Regulatory(規制)
必要な規制を決めるResource Management(リソース管理)
車両、森林、公有地などの資源管理を行うTransactional(各種処理業務)
生産と似たもので、営業許可などの許認可業務Inventory/Distribution(備蓄/分配)
主に流通業務Marketing & Outreach(マーケティングと貧困者救済業務)
TOC(制約理論)において最もパワフルな、S&Tツリーがある分野
「行政がやっている業務は、多少の変化があるかも知れませんが、経験的には、これらのカテゴリに分類されます。
『うちは特別だから当てはまりません』という考えは、正しくないことが分かります。」
「それぞれの業務で大きな成功がありました。
私たちは実際の業務を理解するために、その本質を学びました。
エキスパートと共に働き、よくある解決策と、日々直面している問題を学びました。
業務を分類することで、学習が加速しました。」
ロードマップ

業務を分類した彼女たちは、ロードマップを造り、計画を実行していったのです。
「まず各部署を調べるところからスタートしました。『部署プロファイル』というものを作りました。
要するに『業務範囲はどこまで?』『どんな問題に対処する必要があるか?』『いくつのシステムを抱えている?』に答えるものです。
詳細なプロセスに分け入らず、俯瞰した議論をしたいのです。
共通のゴールを実現するために、各部署がどんなふうにつながって機能しているか理解したいのです。
こうして各部署のプロファイルを作り、優先順位を付け、システムの流れ図を作りました。
ゴールを理解し、スループットを理解し、制約がどこかを理解しました。」
「多くの場合、制約はキャパシティ制約でした。
共通する課題を見つけ、それらの課題に、TOCやTOCから学んだ思考ツールなどを適用しました。」
「次に戦略を立案しますが、もっとも困難なのは、その実行です。」
「これらの課題への解決策を見つけるのは、難しいことではありません。
同意していただけますか? 戦略の立案は難しくありません。
考えることは必要ですが、努力すればできます。政府がよく失敗するのは実行の段階です。」
「つまり戦術を実行させるところです。
それだけで別の話ができます。
迅速に決断する方法。障害を取り除く方法。プロセスに集中する方法。
そうした正しい構造を組織に作りこんでいきます。
政府はマルチタスクによって、大失敗してしまいます。」
「立法の問題。ステークホルダーの問題があり、集中を実現するというのは難しいものです。
実行のための戦略も準備できたし、TOCコミュニティから学び続けていますから、これからも改善し続けていくつもりです。
実行においては、まだ改善の余地がありそうです。」
「改善のサイクルを繰り返しています。そんなに難しいことではありません。これが改善のロードマップです。」
許しがたい4つの言葉

「政府で使われる許しがたい言葉が4つあります。」
クリステン・コックスさんはこう語った後、言葉をつないでいきます。
「何度も使われすぎて、もはや意味を成さないからです。
『調整』『融合』『協力』『連携』
良さそうな言葉ですよね?
良さそうに聞こえますが、余りにも使われすぎて、行政においては何の意味もありません。」
「私たちのゴールは、『連携』を現実のものにすることです。
今お話をしたような活動が、『連携』という言葉に意味を持たせることができると信じて連携しています。」
「これが基本的なロードマップです。
これに加えて、イノベーションの活動があります。」
貧困の問題。囚人たちの社会復帰の問題。再び刑務所に戻ってこないようにするなど、全ての評価尺度を85%をターゲットにしているのです。
クリステン・コックスさんたちの活動は、このように非常にシンプルな活動をして
2.How do we improve?
どのように改善するのか?
を実現しようとしているのです。
仕事の生産性は上がってますか? 行政課題解決セミナー
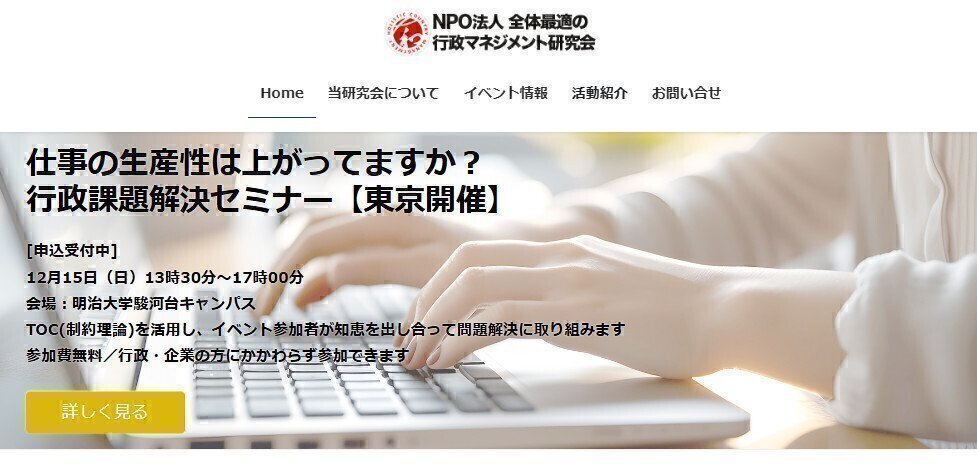
行マ研では、『セミナー』や『オフ会』を通じて、TOC(制約理論)の問題解決を学び、それを現場に活かしていきたいと考えています。
『全体最適のマネジメント理論』TOC(制約理論)を一緒に学び、実践する仲間を一人でも増やしたいと考えています。
そしてこの度、「仕事の生産性は上がってますか?」というテーマで、
4年ぶりにリアルの『行政課題解決セミナー』が以下の予定で開催されます。
12月15日(日)13時30分~17時00分
会場:明治大学駿河台キャンパス
TOC(制約理論)を活用し、イベント参加者が知恵を出し合って問題解決に取り組みます。
参加費無料/行政・企業の方にかかわらず参加できます。
『セミナー』のお申し込みは、
こちら(👇)からお願いいたします。
この4年ぶりのリアルセミナーに、1人でも多くの方が集まっていただきたいと、切に願っております。
官・民の枠を超えて、メンバーを募集していますので、是非このセミナーにご参加いただきたく思っております。
