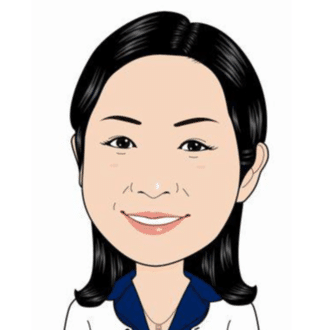言葉の「重さ」はどこからくるのか
年末に参加したインタビューワークショップの録音を聴き返している。
5日間、ペアを変えながら相当な回数をやったので、結構な量だ。
毎日ちょっとずつ、「聴くことに取り組んでいる様子」を聴いている。
自分の聴き方に、「いやいや、あなたもうちょっと待とうよ、もうちょっと受け止めようよ」などと、ツッコミを入れつつ、相手の話に、3か月を経て、もう一度じっくりと耳を傾けている。
自分が話した内容にも、他の人の話を聴くときのように耳を傾ける。
するとだんだん、言葉の「軽さ」「重さ」の違いが、くっきりと感じられるようになってくる。
軽い言葉は、はやく流れる。比較的一定のスピードで。
重い言葉は、ゆっくり進む。結構立ち止まる。足踏みをする。声が低く、小さくなる。前後に大きな呼吸の出入りが伴う。
「人は話しながら歌っている」
と西村佳哲さんは言っていた。
「歌を聞くときに、歌詞だけを聞く人はいないでしょ。
メロディがあって、伴奏があって、そして、歌っている人の声や歌っている様子、そういうものにのっかって伝わってくるもの、そういうのを全部聞いているよね」と。
言葉の「重み」を生み出すものは、決して言葉そのものではない。
言葉は「入れ物」や「パッケージ」に過ぎない。
その人の深くに沈んでいる「何らかの感じ」が、言葉に入れられて、言葉に包まれて、出てくる。
重いものほど深く沈んでいるのは当然だ。
そして、その「感じ」をひっぱり上げるのには、それなりの作業や手続き、時間が必要だ。
長年奥底に沈み過ぎていてその存在自体に気づけない人もいるし、
箱に入れて厳重に鍵がかかっている人もいるし、
なんかいろんなものと混ざり合って石化している人もいるし、
そういうのを経ていると、よけいに重くなる。
でも、たとえ出てきたものが、聞き古された、ありきたりの言葉であったとしても、その人が必死にひっぱり上げた言葉は、まるで今生まれたばかりの赤ちゃんのような、エネルギーのかたまりの、個性に彩られた「その人の言葉」になる。
さらに、そうやって生まれ出るためには、助産師さんのような存在が必要だ。
生まれることを信じて待っていてくれる存在。
生まれる痛みを理解している、大丈夫だよと言ってくれる存在。
私は昔から、論理的に、わかりやすく話せる人に憧れを持っていた。
そうなりたいと思っていた。
自分が懸命に話しても、相手が反応してくれるところが「そこじゃないんだよな」とすれ違いを感じたり、話しているうちに相手の目が虚空を見るような「きょとん」とした表情になったりすることが多かった。
そういう経験が増えるごとに、そうなることがこわくて、最初から「そそくさ」と話を終わらせようとするか、とにかく伝えようとしてやたらと前置きや詳細が長くなるということを重ねてきた。
でもそれを続けていると、まったくもって自分が本当に言いたい言葉から離れていく。それで出てくる言葉は、相手にどう思われるかという恐れや、わかってほしいという欲求をまぶした、メッキに覆われた言葉だ。
結局、順番を間違えていたんだと気づく。
本当に言いたいことを言葉にしたいのなら、まずは自分が自分を待ってあげなくてはいけない。
自分の中でさえ、恐ろしいほどの否定的な声やツッコミが入る。
でも、きちんと待って、やっと出てきた言葉なら、きっと伝わる。
言葉の意味が伝わらなくても、「何らかの感じ」は伝わる。
そういうことを身体を通して知っていればこそ、他の人の言葉を、待つことができるのではないか。
つまり、自分がそもそも、「何らかの感じ」の深さと重さを知っていないと、誰かの本当の言葉を聴くことができない。
勘違いしてはいけないことは、「重い」「軽い」を、「いい」「悪い」と結びつけたり評価したりしないということ。「イリジウムはよくて、水素は悪い」とは誰も思わない。
自分も含め、「その人の言葉」が生まれ出ることを祝福しよう。
いいなと思ったら応援しよう!