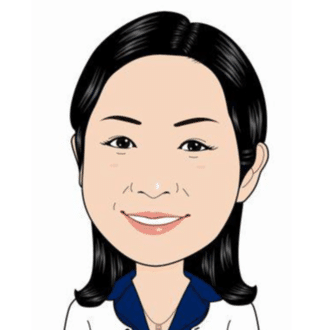駄菓子屋のおばちゃんという生き方
日本中にコンビニエンスストアができる前の1970年代には、どんな町にも駄菓子屋があったのではないだろうか。東京近郊の町にあったその駄菓子屋も、そんなお店のうちの一つだ。3坪ほどの店内には、所狭しとカラーボックスが積まれていて、あんこ玉、餅太郎、さくらんぼ餅、ミルクせんべい、梅ジャム、よっちゃんいかなど、種々様々の駄菓子が見本市のように並べられている。学校から帰った近所の子どもたちは、小銭を握りしめて日課のように駄菓子屋に向かう。小さな店の中も外も、いつも子どもたちで賑わっていた。
その駄菓子屋を切り盛りしていたのが、私の母だ。私が4歳の頃、自宅のすぐ近くに新たに小学校ができた。そこで家を改装して文房具店を始めたのだ。当初は文房具の他、名札や赤白帽子など学用品を取り扱っていたが、あるときから、お店の一角に駄菓子を置くようになった。当然、文房具よりも駄菓子の方が人気が高い。文房具たちがじわじわとその領域を圧迫され、駄菓子の棚の一角に置かれるようになるのには、そう時間はかからなかった。
そんな町の駄菓子屋は、日曜日が仕入れの日。朝5時前には家を出て、日暮里の問屋街に向かう。顔なじみの問屋のおじちゃん、おばちゃんは、私たち姉妹にはいつも何かおまけをくれた。冬の早朝はものすごく寒いので、問屋のおばちゃんが一斗缶で焚火をしてくれて、みんなでそこで暖をとる。仕入れが終わると、車のトランクはもちろん、後部座席の窓の部分まできちきちに駄菓子屋を詰め込んで帰る。仕入れたお菓子は居間の押入れにしまう。そんな一連の仕入れや毎日の品出しを手伝うのが、私たち姉妹の日常だった。
小学校中学年くらいになって物心がついてくると、私は母の商売を「はずかしい」と思うようになった。学校ではみんなに駄菓子屋の娘と知られている。トイレを貸してという子には、決して広くもきれいでもない家の中を見られる。その中には、好きな男の子だっていた。毎日のおやつはもちろん駄菓子。スーパーで売っている大きな袋のお菓子が食べたいと切望していたあの頃の私は「全部、お母さんが駄菓子屋なんかやっているからいけないんだ!」と理不尽に腹を立てていた。
そんな生活が、小学校5年生のときに突如変わった。その頃、母は急激に痩せはじめ、嘔吐を繰り返すようになった。早く病院に行けとせっつく父に、お店があるからとなかなか腰を上げない母。そこで父は私に、「お母さんを病院に連れていけ!」と命令した。私は幼い頃から皮膚が弱く、母といつも病院に通っていたので、わが家で病院といえば私と母のペアなのだ。
母の運転で、車で15分ほどの国立病院に向かった。
診察中、待合室で一人待っていると、看護師さんに呼ばれた。診療室に母はおらず、眼鏡をかけた医師に厳しい表情で言われた。
「お母さんはすぐに入院します。あなたは一人で帰って、入院の道具を持って、お父さんとまた来てください」
その言葉は、これまで家族の誰も入院したことがない家庭の小学生には衝撃が大きすぎた。大きな不安を抱えたまま、看護師さんの助けでタクシーに乗り、家に帰った。母の体はがんに侵されていたのだった。
その日から、町の駄菓子屋のシャッターには、「都合によりしばらく休業します」という手書きの張り紙が貼られた。毎日の駄菓子を楽しみにしていた子どもたちは、放課後の行き場を一つ、失った。
母の入院中は、ほぼ毎日、家族でお見舞いに行った。退院してからも、胃を全適した母はまともに食事をとれず、店を営業できるような体力もない。駄菓子屋のシャッターは下ろされたままだった。
最初の診察から3年半後、母はこの世を去った。お通夜と告別式には、鯨幕と花輪に包まれた元駄菓子屋に、近所の人たちだけでなく、たくさんの制服をきた子たちが訪れた。駄菓子屋のおばちゃんに、最後のお別れを言いに来てくれたのだ。母の闘病の年月は、いつも駄菓子を買いに来てくれていた近所の子どもたちを、制服を着る年代にしていた。
宮城の田舎で生まれ、保育士として働いていた母。父と結婚し、3人の娘を産んで、駄菓子屋のおばちゃんという人生を送った母。おっとり、おおらかで、おっちょこちょい。なかなか怒らないけど、一度怒ると超頑固。誰にでも分け隔てなく接し、親しまれる人だった。子どもたちが小銭を握りしめてこの店に通ったのは、駄菓子の魅力だけでないはずだ。
そんな母の死から30年以上が過ぎた。元駄菓子屋は、拡張した道路の一部となり、跡形もない。子どもたちのおやつは、コンビニ、スーパーなどそこかしこで手に入る。仕入れに通っていた日暮里の駄菓子問屋街も、再開発で無くなった。
だけど。その時代、この町で、子ども時代を過ごした多くの人の記憶の片隅に、母はきっとニコニコ笑顔の駄菓子屋のおばちゃんとして、刻まれている。そしてそれは、とても立派な、誇らしい生き方だったと、思うのだ。
いいなと思ったら応援しよう!