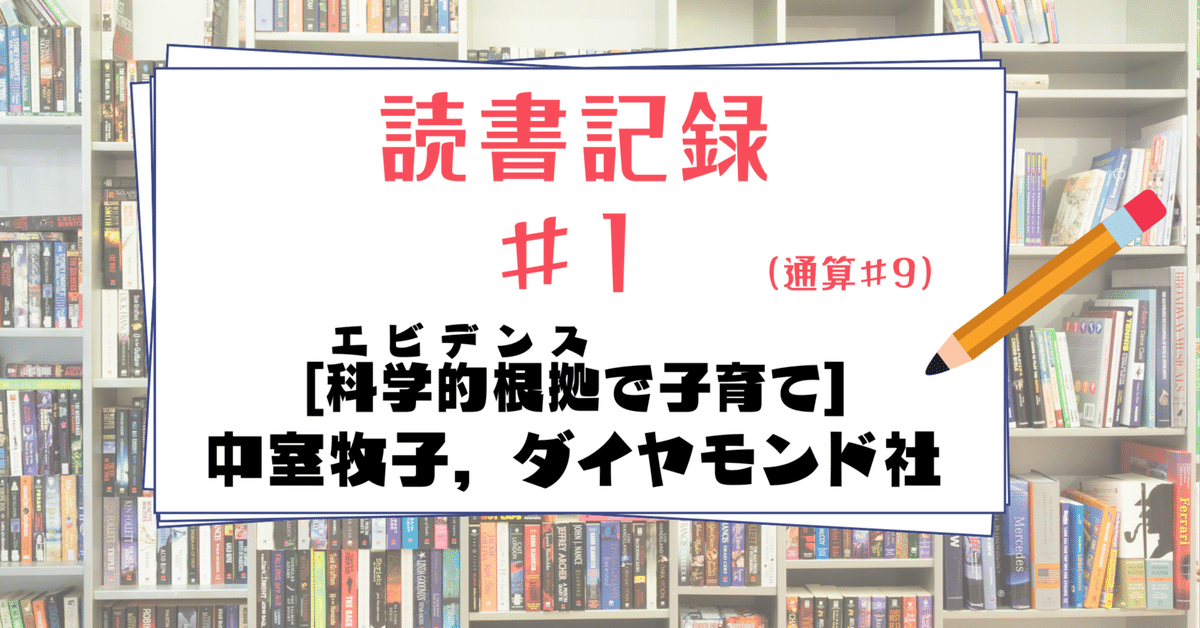
『科学的根拠で子育て 教育経済学の最前線』(中室牧子著)永遠に未知の分野ではなかろうか?
私は、地方の市公立小学校教員です。
今回は、読書記録#1として、中室牧子さんの著書を読んで考えたことを言語化してみました。
中室牧子さんといえば『「学力」の経済学』(ディスカヴァー携書 2015年6月18日初版発行)の著者としても有名な方です。
私も昔読みました。
今回この新しい著書を読む前に再読もしました。
当時とは少し違った視点で読むことができ、新たな発見が多くありました。
と同時に、忘れていたことも多くあったのでやはり同じ本でも二度三度と定期的に読み直すこともいいなと思いました。
さて本題です。
今回は特に「教師」という仕事の上で気になった箇所を中心に言語化をしていきます。
(「親」という視点に立つと、また違った景色が見えてくるのですが、今回は割愛します。)
第3章 非認知能力はどうしたら伸ばせるのか
生徒の非認知能力を伸ばせる「先生」がいる
どういう先生が非認知能力を伸ばせるのかはまだわかっていない
第5章 勉強できない子をできる子に変えられるのか?
友達とチームを組むことで勉強量が増える
第9章 日本の教育政策は間違っているのか?
結局、教員こそが教育の核である
第10章 エビデンスはいつも必ず正しいのか?
今、学校に必要なのは「手術室を1つ空けておく」こと
第3章を読んで
この書籍の大きなテーマの一つは「非認知能力」だと感じました。
前半の章にはこの非認知能力という言葉が何度も登場します。
第2章では、まるまる非認知能力についての解説も載っています。
これからますます重要になっていく能力・スキルの一つだと思います。
私の以前の固定記事である
この21世紀型スキルの大部分が非認知能力として紹介されている能力(スキル)と同じであることから、頭の中で再整理をしました。
また、学校や家では比較的「勉強しなさい」と言われる頻度が高いのに、社会に出たとたんに「コミュニケーション能力」「協調性」「チャレンジ精神」が大切と言われるのでは、あんまりだというのにも納得です。
非認知能力は学力を伸ばすが、その逆は起こらない
また、上記からもいかに非認知能力が大切であるかがわかります。
ただ、この非認知能力を伸ばすということについて「学校」や「教師」が何ができるのか、というところが私の中でのこの本の一番の考えどころでした。
というのも、事実としても感覚としても「子どもの非認知能力を高める先生がいる」ということは理解できます。
私の周りにも実在します。
しかし、果たしてそれで良いのか?というのが自論です。
「あの先生に持ってもらってよかったね」
という言葉の存在は
「あの先生は・・・(ネガティブな言葉)」
の裏返しでもあります。
一個人である教員の(スーパーな)力によって高まるのではなく、学校としていかに非認知能力を高めることができるか、という視点が大切なのではないかと思います。
それが全ての子どもたちにとっても良いはずです。
とはいえ、これも主語が大きくなっただけで
「あの学校は・・・」
という話になってしまうので、この非認知能力を伸ばすという分野において全教職員が一丸となって進んでいく必要があると思っています。
葛原さんが提唱している「けテぶれ QNKS 心マトリクス」などは、ここにズドンと重心が置かれている気がします。
第5章を読んで
5章の終わりの方を読んで私が感じたことをそのまま書きます。(少し毒を吐きます)
友達とチームを組むことで勉強量が増える
については「逆」を考えました。
チームがないと勉強量が減る
ということです。
個人的には、コロナによる休校の時に強くこれを感じました。
変わらずに学習を続けた一部の子と、一気にゲームや動画に飲み込まれていった多くの子と・・・
学校で、ある程度の同調圧力(あえてこの言葉を使う)がある中での生活とでは勉強量が変わるのは当たり前なのだと。
ただ、勉強量が減ったことで「学力」は下がったのかと?
日々こなしてだけの「宿題」に意味はあったのかと?
私が休校が明けた後に、感じたのは
「学力」の低下ではなく「非認知能力の大きな低下」
の方でした。
そこから私は勉強の量だけでなく質にもこだわるようになりました。
(ただ質を高めるためには量をやってみないと・・・というジレンマがありますが)それを助けてくれるのが学級の仲間かなとも思っています。
チームで学びを最大化していくのは今後の私のテーマの一つでもあります。
第9・10章を読んで
さて、ずいぶん長くなってきました。
しかし、本当にこの本は考えるきっかけを次々に投げかけてくれます。
この本は10章で終わりなので、最後に再び「学校」や「教員」についての話題が出てきます。
私の感想として、10章の
今、学校に必要なのは、「手術室を1つ空けておく」のと同じ、(新たな挑戦のための)「余剰」を作り出すことではないかと思われます。
という一節が心に残りました。
まさに今求められている働き方改革の文脈にも、教師という仕事のやりがいにとっても必要なことだと思います。
手前味噌な話で申し訳ありませんが、私の勤務校は昨今にしては珍しく人員が足りています。
それゆえ、昨年末のインフルエンザが蔓延したときも、教員が10数名休みましたが、なんとかなりました。
これも普段から一杯一杯だとそうはいかないのだと思います。
また、これは高校生ぐらいの時に読んだ落合博満さんの著書からの受け売りなのですが、極論を想定しておくというのも大事です。
現実的ではないことはわかっていますが、例えば50人の教員が働いている現場では、年休の所得を普段の学期途中に使ったとして、50人×20日で1000日分の空白が生まれます。
その1000日分の空白を想定した学校運営である必要があると思っています。
全員が全員長期休業に取るという前提ではどこかで破綻すると思います。
それが、「手術室を1つ空けておく」に対する私なりのアンサーです。
まとめ
この本は冬休みの間に読んだので妻にアウトプットしながら本当に色々と考えることができました。
しかし、本を読み終えて一番感じたのはこれらのエビデンス、日本でも成り立つの?
という疑問です。
やはり教育に関する実験的なものはほとんどが海外にデータを求めたものがほとんどです。
また、日本のデータがあったとしても、日本の子どもを取り巻く環境はすごいスピードで変化しています。
教育に関わる父親•母親の割合も昔のデータとは違います。
そんな中で、今の子どもたちに当てはまるのかという疑問があります。
書籍の中でもそれらのことには触れられています。
私個人としては、そうであったとしてもエビデンスは何かという習慣が日本の教育界に文化として根付いていくことを期待しています。
数字で語ることは教育という分野ではそぐわないという考えもありますが、決して目を背けてはいけないとも思います。
