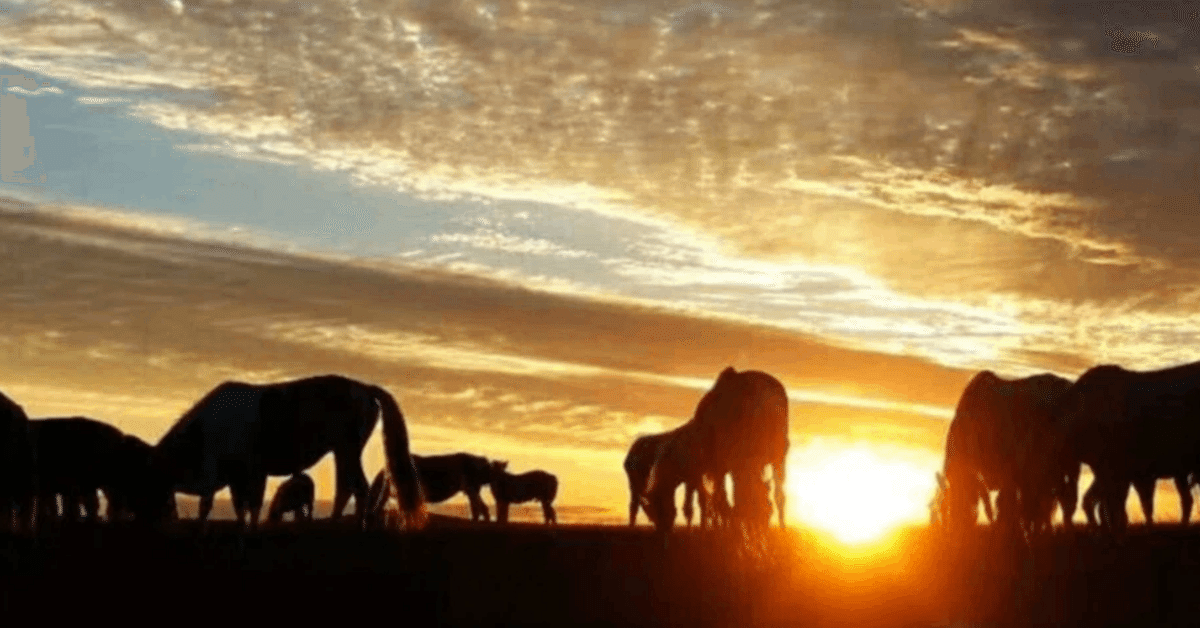
「隋唐帝国 対 突厥 ~外交戦略からみる隋唐帝国~」(4)
第一部、 隋・文帝の離間策と突厥の東西分裂
4、「レビラト婚」と後継者
突厥が東西分裂した翌年の584年、千金公主がついに文帝・楊堅と和解し、その養女となって「大義公主」に改封されます。夫・沙鉢略可汗も晴れて隋に帰順して、「臣」を称しました。
「沙鉢略可汗の下での突厥の存続」を目指した処羅侯・染干父子の願いが叶った瞬間でした。
張啓雄氏によれば、こうして文帝と沙鉢略可汗が「義理の父子」となり、「天下一家」の国際秩序ネットワークが整いました。
そして、「中国と胡人民族にとって、「和親」は、和平共存を求め、後顧の憂いを断つための国交関係となった」とされます。
587年、沙鉢略可汗が亡くなり、弟・処羅侯が莫何可汗【在位・587~588】として即位しました。さらに翌年、沙鉢略可汗の子・都藍可汗【在位・588~599】が即位します。

ここで僕が着目したのは、千金公主改め大義公主の「レビラト婚の矛盾」という点です。
本来、遊牧民族にみられた「レビラト婚」とは、先代の可汗の寡婦(未亡人)を新たな可汗が妻(可賀敦)として迎えるものでした。
しかし、大義公主は沙鉢略可汗の死後、次代の莫何可汗には嫁がず、「一代置いて」、都藍可汗に嫁いでいるのです。
池田知正氏は、「大可汗位は沙鉢略可汗から都藍可汗へ伝わった可能性が高く、僅差で(その間に)莫何可汗を経由した可能性が高い」とされます。
僕は文帝の第二の離間策とは、「沙鉢略一家と莫何一家の分裂」だと推測します。
歴史書の記述を比較すると、『資治通鑑』が、「沙鉢略可汗の遺言によって莫何可汗が即位した」とするのに対し、『隋書・長孫晟伝』は、「長孫晟の立ち合いの下、莫何可汗が「隋によって」擁立された」とあります。
突厥における後継者の選択は、最高権力者の大可汗と有力者の協議によって決定されました。沙鉢略可汗以前の二代の大可汗は、いずれも先代の大可汗の「弟」ではなく「子」でした。
そのため僕は、突厥の有力者が推したのが、「沙鉢略可汗の子・都藍可汗」だったのではと考えます。
これに対して隋は、結果的に最後まで対立しなかった沙鉢略・莫何兄弟を、内心苦々しく思っていたと想像されます。
そのため隋は、突厥全体が次期候補に推す都藍可汗ではなく、「沙鉢略可汗の弟・莫何可汗」を、「沙鉢略可汗の遺言による指名」という名目で即位させ、莫何可汗と都藍可汗との対立の火種にしようとした、と推測します。
他方、即位した莫何可汗は、「弟が兄に代わることは先祖の礼を失っている」(『隋書・突厥伝』)と述べ、何度も甥・都藍可汗に大可汗の座を譲ろうとします。
これは莫何可汗が、「大義公主を娶るのを避けるため」であったと、僕は思います。レビラト婚の習わしに基づけば、莫何可汗が大義公主を娶った場合、次に娶るのは息子・染干となり、都藍可汗の立場がなくなるからです。
莫何可汗は、あくまでも自身を「中継ぎの大可汗」と位置づけ、都藍可汗に大義公主を娶らせることで、彼を「レビラト婚に基づいた正統な次期大可汗」とし、再び隋の離間策を平和裏に解決しようとしたのです。
翌年、莫何可汗が西方への遠征先※ で戦死すると、都藍可汗が即位して、大義公主を娶りました。

(次回へつづく)
※ 西突厥の達頭可汗、または、ササン朝ペルシア(イラン高原・メソポタミアなどを支配。イラン帝国。226年~651年)への攻撃とされる。
