
「保護者対応専門部署」が示す教育現場の未来
2024年4月、「理不尽なクレームに疲弊する教育現場 保護者対応専門部署の設置で教員離れに歯止め」という記事が注目を集めました。この記事は、天理市が「ほっとステーション」という保護者対応の専用窓口を開設したことを報じていました。
その後、この背景に迫る取材記事を読み、教育現場が抱える課題の深刻さを改めて実感しました。
この記事によると、天理市の教職員の多くが保護者対応に大きな負担を感じており、過度なクレームや要求が教育現場を疲弊させている現状に危機感を抱いた天理市長と教育長がこの取り組みをリードしたそうです。特に、学校や園の教職員が保護者からの理不尽なクレームに苦しみ、心労による休職や退職が相次ぐ深刻な状況が明らかになっています。
「本市の山間部の学校では1クラス10人前後しかいませんが、保護者対応の負担は学級人数に関係ないんですよね。課題を抱えるお子さんやご家庭があれば、先生はその対応で疲弊し倒れてしまうことはあるのです。最近は働いているご家庭が多く、保護者の要望に個別対応しようとすれば夜の7~8時に呼び出されて残業時間が増えてしまう。そのまま日付が変わるまで教員が叱責されるケースも珍しくないことがわかりました」(並河氏)
年々保護者の要求は厳しくなっており、子どもへの悪影響も懸念された。過度な要求に対して教職員が我慢をして頭を下げた結果、子どもの口から「うちの親が言えば、学校は何でも聞いてくれる」「先生を辞めさせろ」といった発言が飛び出すことがあったのだ。
この記事で明らかになった他の弊害として、管理職を避ける教職員の増加や人材不足、そして教育業務に集中できないことでの現場全体の疲弊が挙げられています。
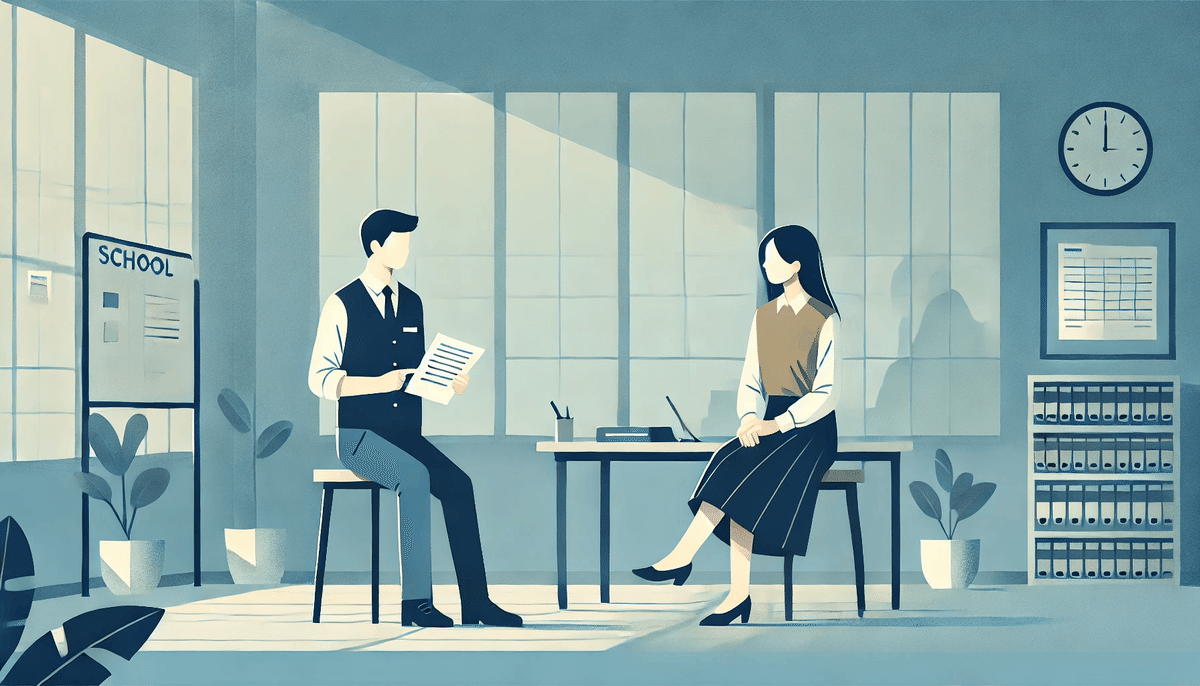
教育業務に集中できないことでの現場全体の疲弊を引き起こすことに。
そんな中、「ほっとステーション」の設置によって、以下のような効果が出ています。
小中学校を中心に、教職員の残業時間が大幅に減少した。
専門の相談員や心理士が保護者対応を担当することで、教職員の精神的負担が軽減された。
保護者からの過剰な要求やクレームが減少し、教育現場が徐々に安定を取り戻しつつある。
一方で「専門家の介入」に関して、興味深い記載がありました。
ほっとステーションの開設に当たっては、仕事に熱心な教職員ほど反発し、「私たちの頑張りを否定しているのか」「保護者との信頼関係の下で教職員は育っていくのに、別部隊に任せてしまったら後進を育成できない」という意見もあった。しかし、専門家による研修を通じて、教職員たちの見立ての重要性に対する理解が深まってからは風向きが変わってきたという。
例えば、交通事故の場合、事故の当事者同士で直接対応するのではなく、保険会社などの第三者を介在させることで、より円滑な解決につながります。
「ほっとステーション」の成功も、教育現場における専門家の介入の重要性を浮き彫りにしています。多くの教員は、保護者対応を自分たちの責任として捉える傾向がありますが、この考え方を見直す時期に来ているのではないでしょうか。
教育現場においても、保護者対応に専門家が介入することで以下のようなメリットが考えられます。
専門知識の活用:子どもの心理に詳しい専門家や、不平を持つ人へのコミュニケーションの専門家が介入することで、より効果的な対応が可能になる
客観的な視点の導入:第三者が介入することで、問題を客観的に捉え、より適切な解決策を見出すことができる
教員の負担軽減:専門家に任せることで、教員は本来の教育業務に集中できる
教育現場における保護者対応の負担軽減は、教員離れを防ぎ、より良い教育環境を守るために必要不可欠な課題です。今後もこのような取り組みが広がり、多くの自治体で同様の解決策が導入されることを願います。
いいなと思ったら応援しよう!

