
まだそこに生きている ーーチェン・カイコー『さらば、わが愛 覇王別姫』
チェン・カイコーは歴史を憎まない。それを谷間を抜ける風や浜辺に寄せるさざ波のように、自然的なものとして受け入れる。たとえそれが屋根を吹き飛ばし大地を抉るほど強大で残酷なものであっても。
彼の人生は、有り体に言えば波瀾万丈だ。映画監督の父の家に生まれ、経済的にも文化的にも恵まれた幼少期を過ごすが、反右派闘争や文化大革命の過激化に伴い次第に凋落。反共的で穏健派の父親に失望し、遂には自ら紅衛兵となる。文化大革命末期には雲南省の山奥に下放され、そこで幾年もの間過酷な農作業に従事する。

毛沢東主義が下火になると北京へ戻り、北京電影学院で中国映画第5世代もう一人の英雄、チャン・イーモウと出会う。彼と組んだ『黄色い大地』は国外批評で大成功を収め、以降チェン・カイコーは(そしてチャン・イーモウも)中国屈指の名監督へと成り上がっていく。

1939年の陝西省を舞台に、貧農の村娘と八路軍の青年の交流を描いた中国映画。撮影は『初恋のきた道』『あの子を探して』のチャン・イーモウ。
センシティブな主題を取り上げることも多い彼が中国国外のみならず国内においても日の目を見ることができたことには、当時の中国が文化大革命と天安門事件の間の政治的に凪の時代だったことも大いに関係している。ちなみにこのあたりの話は彼の自伝『私の紅衛兵時代-ある映画監督の青春(講談社現代新書)』に詳しい。
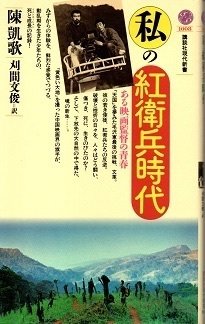
ちなみに当館「第8電影」にも置いてあります。ぜひ手に取ってお読みください!
さて、このように彼は戦後中国史に散々振り回されてきたわけだが、「政治が悪い」「国が悪い」といった紋切り型の左翼的論調からは慎重に距離を置く。もちろんそれは中国共産党の主導する現代中国の政治体制に賛同することを意味しない。そうではなく、彼は主語を肥大化させることで問題が政治・社会批判の次元に抽象化されてしまうことを危惧している。彼が描きたいのは、歴史のダイナミズムにひたすら耐え続ける個々人の尊厳なのだ。
レスリー・チャン演じる蝶衣は京劇『覇王別姫』の虞美人役を務める女形役者。相手役の項羽を務めるのは小さい頃から兄貴分の小楼。幾度となく修行と公演を重ねるうちに、蝶衣は次第に小楼のことが好きになっていく。彼が虞美人という役柄に入り込み過ぎてしまったがゆえの恋慕か、それとも単なる同性愛か、そのあたりはよくわからない。重要なのは、男が男を好きになってしまったという客観的事実だ。


中国は今なお同性愛に厳しく、そうしたテーマの文芸作品は基本的に製作を禁じられている。ましてや日清戦争から文化大革命の時代にそうした「自由主義的思想」を持つことは国賊の謗りを免れ得なかったに違いない。蝶衣の感じた孤独や閉塞感は計り知れない。
また、彼らが演じる京劇という文芸も、時代の変遷に伴い徐々にその足場を狭めていく。映画冒頭、1920年代においては「いまだかつてこれほど隆盛を極めたことはない」と言われていた京劇は、文化大革命の折には反共的なブルジョワ趣味と見なされ、大衆に顧みられなくなる。蝶衣と小楼が紅衛兵率いる群衆の前で総括を迫られるシーンは胸が締め付けられる。

ちなみにチェン・カイコーは彼を題材とした映画『花の生涯〜梅蘭芳〜』を撮っています。
小楼は蝶衣を裏切り、彼の日中戦争時代の親日的態度や阿片中毒に陥った過去を暴露する。追い詰められた蝶衣は小楼に向かって反撃に出るかと思いきや、なぜか小楼の妻、菊仙の悪辣を大声で暴き立てはじめる。そのさまはほとんど八つ当たりに近い。
思えば蝶衣と小楼の蜜月関係にヒビを入れたのは他ならぬ菊仙だ。もちろん彼女に悪意があったわけではない。小楼と菊仙はただ運命の導きによって惹かれ合ったに過ぎない。しかし蝶衣にとっては残酷すぎる日々だった。最愛の彼を女郎屋の女に取られ、しかも彼もまた彼女を愛している。

同性愛嫌悪、京劇の衰退、そして愛の否定。蝶衣は歴史がもたらすさまざまな不条理に押し潰され、遂には壊れてしまった。ゆえに彼は舞台上での凜として美麗な立ち振る舞いとは真逆の、八つ当たり的な絶叫に及ぶ。「その女を殺せ!」
波乱の文化大革命は終了を迎え、中国にひとときの平和が戻るが、けっきょく蝶衣は自ら命を絶ってしまう。冒頭のタイトルカットの背景が自刃する虞美人だったことを思い返せば、彼の自殺は予め運命づけられたものであるといえる。

しかし我々には、彼がただ単に歴史に翻弄され、弱々しく蹲りながら絶命していったようには到底思えない。やはり思い出されるのは、舞台で舞い踊る蝶衣の凛と透き通った、それでいて芯のあるふたつの眼だ。その双眸は京劇という枠を超越し、今や映画史に深く刻み込まれた。
彼はまだそこに生きている。
今回はこのあたりで。最後までお読みいただきありがとうございました〜!
文章:岡本因果
