
言葉が生まれる瞬間を支える〜身体性と揺さぶりの力
作業療法士のしごととは?〜小松則登先生のしごとをみて、感じる〜
先日、学ぶ会&たまちき主催の「あなたの発達支援が⚫︎⚫︎かする!!」研修会に参加をしてきました。この研修会は、臨床のマスターである小松則登先生が、今までご自身が行ってきたセッションの動画を元に、作業療法士としての仕事を見せるという内容でした。
参加者にも話し合ってもらい、自分の仕事現場に役立てるという勉強会でした。
各セッション動画の関わりはアートであり、その考察には「作業療法とは何か?」「遊びとは何か?」「コミュニケーションとは何か?」という根本的な問いが散りばめられており、参加者と深める時間は刺激的でした。

事例から学ぶ言葉が生まれる瞬間
来てから帰るまでシリーズ その36
特に感銘を受けたのは、自閉傾向のある方へのアプローチで、「来てから帰るまでシリーズ その36」として紹介した内容です。
そのお子さんには「ママ」以外の発語がほとんど見られず、作業療法室に入るとドアの開け閉めに強いこだわりがあり、ドア操作の時は上方を見ているという特徴がありました。
先生のアプローチは、大胆かつ繊細でした。タッチで身体を確認し、長軸方向に圧を送りながら、ボールプールの縁や母親の背中といった「今、ここにあるもの」を活用して、お子さんの知覚体験を豊かにし、こだわりから少しずつ世界を広げていくサポートを行っていたと私は感じました。
(言葉で表現するとなんとも味気ない。。。私の言語力の限界と非言語情報のやり取りのなんとも豊かなこと!!)
言葉では上記のように説明できますが、このプロセスを進めていくには思考の柔軟性と思考の深さ、視野の広さ、そして何よりも瞬時に相手を察し対応していく身体性が求められます。すなわち「遊び」の達人である必要があります。
「おにぎりー!」
そしてこのセッションのクライマックス。
身体イメージを作り上げる非言語での対話的なやり取りを丁寧に重ねていくうちに、反り上がり傾向の背中も落ち着いきて、モノを見る余裕も出てきたので、現場にあった赤いビニールテープを切って、お子さんやセラピストの手足に貼ってそれを剥がす活動をしていっていました。。
そして、その剥がした赤いビニールテープを手でかき集めて丸めたところ、子どもから「おにぎりー」と言葉が発せられる瞬間がありました。このシーンには、思わず心が震えました。
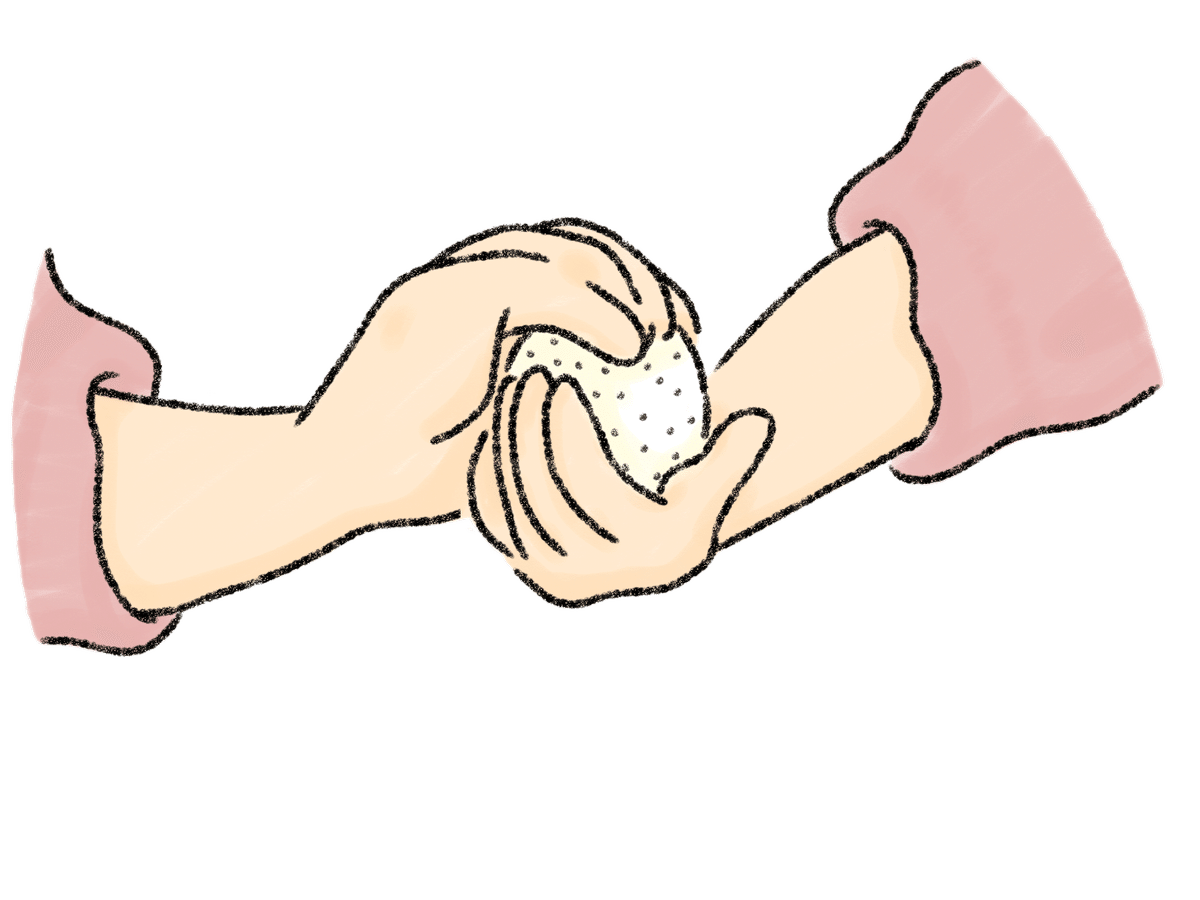
言葉が生まれる瞬間の背景
なぜ、いつも「ママ」しか言うことができなかったこのお子さんが、この場面で「おにぎり」という言葉を発することができたのでしょうか?
もちろん、過去におにぎりを食べた経験、あるいは手遊びなどを通じて培われた知覚体験が基盤としてあったのかもしれません。ご家庭や保育園でのそのような時間が記憶の奥にしまわれていたかもしれません。
ただし、「おにぎりー!」の発話は、ただおにぎりの絵を見せただけでは促されてはいなかったでしょう。
タッチや遊びを通じて、以下のような子どもの変化が生まれます。
反り気味だった背中の緊張が緩み、頭頸部や眼球に下方への動きのゆとりが生まれました。これにより、モノを観察することができるようになり、手にも着目できるようになりました。知覚情報が変化し、外部環境を探索したいという情動が喚起されたと考えます。発見の喜びを通じて、子どもは世界とのつながりを感じ始めます。「丸まった赤いテープ」と「おにぎり」を自身の過去の経験や感覚の中で結びつけることができたのです。「おにぎり」の発話は、身体を伴う具体的な経験と結びついた「意味のある言葉」として生まれた地に足がついた言葉だ思います。
このような世界を繋げていく過程において、言葉は非常に重要な役割を果たします。言葉は子どもの認識と理解を深め、環境との相互作用を豊かにする重要な媒体となっていくことでしょう。

言葉の学習の大変さと人間の報酬
言葉を獲得することは、子どもにとって非常に大きな挑戦です。成長の過程で最も困難な学習のひとつが「言葉をマスターすること」だといえるでしょう。
満3歳から7歳までの間、子どもたちは平均して1日に約15語もの新しい言葉を覚えていくようです 1)。
小学校6年生の語彙数の中央値は約19,267語に達するというデータもあります 2)。この膨大な語彙を身につけるプロセスは、子どもにとって非常にエネルギーを要するものです。
言葉の学習を支える原動力のひとつが、周囲からの反応です。
動物は、食べ物を報酬としますが、人間は周囲から注目されることを報酬とします。
生物として同じ仲間である他の存在が、注目を払ってくれることが心地よい。だから学習にせっせとはげむ・・・これは人間以外の動物には、まず、ない現象と言えるでしょう。
子どもが「丸まった赤いテープ」を握る感覚と「おにぎり」を握る感覚を結びつけ、「おにぎり」という概念を自ら発見したとき、周囲の反応は大きな喜びと励みになります。その反応は、さらなるコミュニケーションを生み出し、子どもの世界を広げていく原動力となります。
言葉の重要な機能の一つが「コミュニケーション機能」であるとすれば、言葉の習得には周囲の反応が不可欠であることは、むしろ当然のことと言えるでしょう。
繰り返しのようになりますが、言葉は単なる暗記によって得られるものではありません。身体を伴った「遊び」を通じて、子どもは観察し、考え、そして感情を揺さぶられながら言葉を獲得していきます。このプロセスを経てこそ、言葉は本当の意味で「腹落ち」し、実感を伴った深い理解が生まれるのです。
そのため、一緒に「食べる」、「遊ぶ」、「作る」といった非言語情報の身体性(表情、視線、身振り手振り、声のトーン、空間の使い方、姿勢など)と共通理解の基盤である言葉を介した共同作業は、豊かな人間の相互作用を生み出し、コミュニティや社会の基盤となっていくでしょう。
モーシェ・フェルデンクライスの言葉を思い出しました。
A brain without a body could not think.
身体のない脳は思考することができない。
身体と脳は切り離せない関係にあります。身体を通じての体験から思考し言葉の学習を深める鍵となっていくとと考えます。
固定化を自覚し、揺さぶりをかけることの重要性
このプロセスは、子どもや自閉傾向のある方々に限定される話ではありません。大人もまた、変わらない日常や固定化された行動の中で、新しい発見や世界との出会いを閉ざしてしまってはいないでしょうか。
一つのものが、一つの意味しかなさない世界は安定していて安心感をもたらします。
いわゆるコンフォートゾーンの世界。
居心地の良さがある反面、新たな可能性を見逃してしまうこともあります。
先の事例の子にとっては、扉の開閉は常に変わらず同じように応えてくれる安心できる行為だったかもしれません。
例えば、会議室でいつも同じような報告内容に留まり、創造性が生まれない状況に身を置いたことはありませんか?
変わらない日常の中で、私たちの思考や行動が硬直してしまうことがあります。

そんな時こそ、新たな知覚体験が必要かもしれません。現場にでて、五感だけでなく、身体を動かして揺さぶりをかけること。
先の事例の子どもが「赤いテープ」を丸めたものを「おにぎり」と感じ、そこから新たな言葉を発したように、体験を通じて感情が動くことで、私たちの中にも新たな概念形成やクリエイティブな発想が芽生えると思います。
大人もまた周囲の反応は報酬となります。いや、子ども以上かもしれません(私自身、ブログの反応が燃えた時は嬉しい)。なので、周囲の人の、遊びや発見に対しては、何か反応したサインが必要なのかもしれません。
オンラインツールの浸透と学びの課題
もう少し、広げて仕事の継承という視点で今回の研修の意義を考えたい思います。
コロナ禍を経て、Zoomやテレワークなどのオンラインツールが私たちの生活や仕事に欠かせないものとなりました。これらのツールは効率的で便利ですが、ひとつ大きな課題があります。
それは、先輩や上司の仕事を「観察する」という機会が失われたことです。特に身体を通じて「腹落ち」するような体験学習が難しくなり、仕事の伝達や継承が難しいと感ます。だとすると感じられないので、だとすると仕事から生まれる言葉も貧困になっていくのではないでしょうか。
特に、作業療法のように、クライアントや関係者と個別にやり取りし、身体的に働きかけながら思いや役割に深く関与する仕事では、オンラインではその微細なニュアンスが伝わりにくいという課題があります。
そんな中で今回の研修は、現場そのものではないものの、小松先生の臨床場面の動画を通じて、職場を超えた方々と「目で見て、話して学ぶ」ことは、自分の現場での大きなヒントになりました。
小松先生、運営スタッフの方々に感謝。
小松先生の臨床に触れる本
<参考文献>
1)正高 信男 (2008)動物の子育て 人間の子育て,そだちの科学, No.10 pp38-41.
2)藤田 早苗 他(2020)小・中・高校生の語彙数調査および単語親密度との関係分析, 言語処理学会第26回全国大会発表論文集.
今井むつみ、秋田喜美(2023)言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか,中公新書.
