
加藤清正公に捧げる「食べられるロボット」

今年5月、学術誌「Nature Reviews Materials」に「食べられるロボットとロボット食品に向けて」と題する論文が掲載されました。執筆者はスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)インテリジェントシステム研究所のDario Floreano所長が率いる研究チームです。

どこを食べるのか?
論文によると、研究はまだ道半ばで、既存のロボット部品の代わりになる食用材料をアレコレと探している段階なのだとか。現在実用化されているのは、ゴムの代わりのゼラチン、発泡体の代わりのライスクッキー、塗装代わりにチョコレートでコーティングといったところです。
まだまだ可食部分は少ない印象ですが、2023年にはIIT(イタリア技術研究所)の研究チームが極にリボフラビン(ビタミンB2)とケルセチンを使用した充電可能な「食べられるバッテリー」を開発しました。
このバッテリーは食べても安全な電圧である0.65ボルトで動作し、直列に2つ接続すると、LEDに電力を約10分間にわたって供給できます。 回路のショートを防ぐために海苔を使い、全体を蜜蝋でパッケージしてあるので、 丸ごと飲み込んで完全に消化できるそうです。

食べられるドローン
2022年、EPFLとワーゲニンゲン大学(オランダ)の研究者たちは、現状で成功している可食部品を使って「食べられるドローン」の開発に成功しました。このドローンは、ライスクッキーをゼラチンで接着して翼に加工してあり、秒速9mで飛行し、最大80gの飲料水を搭載できます。
これにより、大規模災害で交通が寸断された被災地の状態を確認するためにこのドローンを飛ばし、ヘリコプターよりも詳細な情報を収集することができます。その活動中、動けない被災者を発見した場合、すぐそばに着陸し、僅かではありますが命を繋ぐための緊急食糧として食べてもらうことが可能です。

食べられるロボット
将来的には完全に食べることができる、二足歩行ロボットが登場するだろうと思います。しかし、それには原材料の調達とともに、メンタルな部分の問題点もクリアしなくてはなりません。
具体的に言うと、例えば、ソフトバンクが販売していた人型ロボット「ペッパー」を思い出してください。あのペッパーくんがもっと自由に行動できる高度な自律型ロボットだとします。
被災地に派遣されたペッパーくんは、被災者を励ましながら、救助にあたります。人では動かせないガレキを取り除いて、下敷きになっていた人を救助し、燃え盛るの炎の中から幼児を助け出しました。
しかし、倒れてきた電柱が頭部を直撃し、故障してしまいました。「私を食べて下さい。元気が出ますよー」と言い残してシャットダウンしたペッパーくんを、気兼ねなく食べられるでしょうか?
姿形にも安心感があり、力強く、被災者を安心させる話術に優れ、初歩的な救急医療もこなす。災害救助用人型二足歩行ロボットには、そんな能力が求められます。そして、そんなロボットに被災者は好意を持ちます。好意を持ってもらえるように作ってあるのですから。しかし、好意を持てば持つほど、そのロボットを食べにくくなる。このジレンマは想像以上に深刻な問題になるでしょう。

食べられる食器
食べられるロボットに繋がる発想は20世紀からありました。おそらくその原点のひとつはソフトクリームのコーンカップ(アイスクリーム・コーン)です。アメリカ生まれですが、現在は日本のメーカーがトップレベルです。尚、この「コーン」は corn(とうもろこし)ではなく cone (円錐)です。

他にも とうもろこしや小麦・米を原料にした食べる食器はたくさん販売されており、近頃は家庭で食べられる食器を手軽に作れる「食べられる食器メーカー」も低価格で販売されています。


食べられる箸
そしてもうひとつ。食べられるお箸を紹介します。食べられるお箸だけでは驚かないのですが、なんとこれ「畳味」。

畳の原料である「いぐさ」は江戸時代までは薬用として食べていたそうで、現在も食用いぐさが販売されています。この製品の原材料は いぐさの他に小麦粉、砂糖、鶏卵と表記されています。プレス成型しているのでとても硬いのはマイナス点ですが、ほんのりと苦味があって、味は悪くありません。いぐさの香りも嫌な臭いではなく、「ほんまや! 畳や!」となるのですが、大阪では間髪を入れず「畳を食べたことあんのか ?!」とツッコまれます。
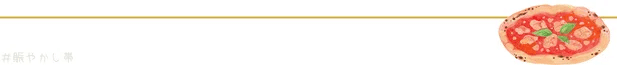
食べるスプーン
お箸があるならスプーンもあります。
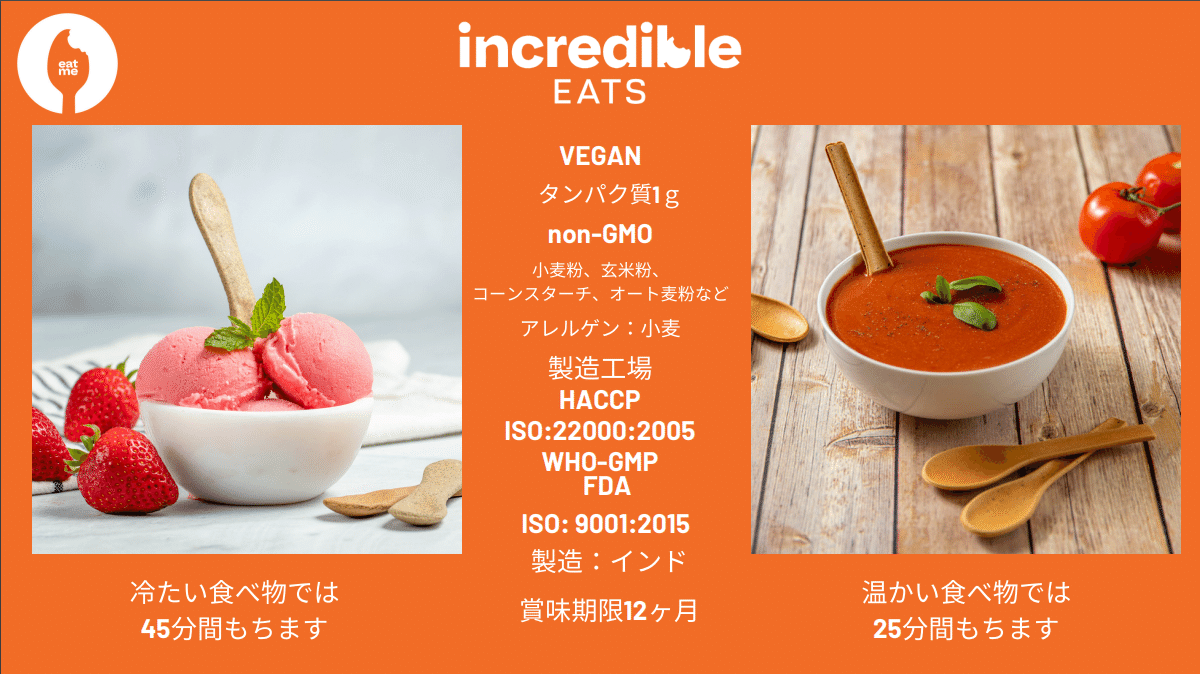
シチューを食べていて、スプーンがフニャフニャになってきたら笑っちゃいますね。

籠城非常食
もっと昔、日本で食べられる○○を妄想していた人達がいます。それは武士でした。
日本には天守が現存している12城を含め、たくさん城跡があります。その多くは石垣だけや、堀跡、また跡形もない城跡です。しかし、城が跡形もなくても、松の木がたくさん残っている所があります。日本の城には松がたくさん植えられていたのですが、それは景観のためだけではありません。松は籠城時の非常食として城内に植えられました。
ゴツゴツした松の皮の下には白い薄皮があります。この薄皮には脂肪やタンパク質が含まれています。この薄皮を臼で搗き、水にさらしてアクを抜き、乾かして粉にします。その粉を混ぜて餅を搗くと「松皮餅」です。もちろん、餅を搗く余裕がなければ粉をなめ、もっと切羽詰まると、松の木から薄皮を剥いで茹でてしがみます。

食べられるお城
松だけではなく、食べられるお城として有名なのが熊本城です。初代城主で築城者でもある加藤清正公は、薩摩藩との戦いが籠城戦になることを想定して食べられる城にしました。正に食べられる○○のパイオニアですね。
まず、城内の畳です。普通の畳は芯に藁を使うのですが、熊本城の畳の芯には里芋の茎が使われていました。里芋の茎は立派な食品で、畳表のいぐさも食べられます。また、土壁にも干ぴょうや里芋の茎が塗りこめられていました。土壁の土は崩して洗うことで取り除けるので、壁も非常食貯蔵庫です。
ところで、「熊本城、食べられる伝説」は後世の作り話だとする説もあります。と言うのも、熊本城は食べられることなく、取り壊されたり、焼失したりで、天守を含む主要部分が無くなってしまったからです。無くなってしまっては、実話かどうか確かめようがないですからね。
現在の天守は1960(昭和35)年に鉄筋コンクリートで復元されたものなので、畳や壁をかじったりしないで下さいね。

元祖食べられる…
忘れていました! 元祖食べられる〇〇は、これです!

いか徳利は数社が作っています。イカ猪口付き、おつまみになるゲソ付きなどがあり、北海道や東北・北陸で昔からお土産の定番でした。燗酒を注いでしばらく待ってから飲むのですが、これが美味しいのです! 香りもいい! そして、柔らかくなってきた徳利をかじりなから飲む。 冬はこれです!


大阪人は見た! 学校では教えない京都の黒歴史。

▶祇園祭の裏話
▶京都が京都と呼ばれない時代があった
▶京野菜と京都カースト
▶観光都市「京都」のプライド
▶聞きたくもない京都の裏情報
▶京都ランドのファンは読まないで下さい!

