
急拡大する組織に横串を通すため、マネジメントレイヤーに共通言語を——HENNGEの目指す“みんなで勝つ”ために選んだEVeMのプログラムとは
「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に掲げるテクノロジー企業、HENNGE株式会社。国内シェアNo.1(https://hennge.com/jp/info/news/20240404_iddasno1/)のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」をはじめ、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」などを展開。業種を問わず、上場企業から自治体まで、数々の有名企業に同社のSaaSが導入されています。2019年には東京証券取引所マザーズ市場に上場し、企業成長を加速させています。
IT業界を牽引する同社が、なぜEVeMのプログラムを導入したのか。HENNGEのPeople Division領域におけるExecutive Officer 髙須様と、Section manager 脇屋様にお話を伺いました。

拡大する組織に一体感を持たせるため、マネジメントレイヤーの統一を検討
―――国内No.1のクラウドセキュリティサービスとして順調な成長を遂げられている貴社ですが、これまでに人材育成の領域における課題感はあったのでしょうか。
髙須様(以下、敬称略):育成に関してという意味では、当時実は、明確な課題が顕在化していたという訳ではありませんでした。もともと、人事チームのスタンスとしては「各部門の中に最適解がある」という考え方で、各部門で必要な育成プログラムや研修が導入、運用されている状況だった為、育成について何かしら全社横断的な課題を感じていたわけではなかったのです。しかし、組織規模が大きくなるにつれて、全体としての一体感が希薄になりつつあるのではないかという感覚はありました。
HENNGEという同じ船があったとして、それに皆で乗っている意義が薄れていくのではないかという感覚をもったのは、ちょうど社員200人前後になった時期。今こそ一体感や、HENNGEのメンバーだからこそ、そこにあるべき共通項を改めてみんなで再認識していくことが必要で、これまではあまりやってこなかった会社全体に「横串」を通す、ということをそろそろ意思的にやっていくべきタイミングではないかと思ったのです。

脇屋様(以下、敬称略):「People Success」という人材育成ファンクションができたのは2022年10月と、比較的最近のことで、私はそこでオンボーディング施策やスキルトレーニング、英語・日本語学習支援などを進めていました。すでに各部門のマネージャーに対して必要最低限のトレーニングはありましたが、髙須の言うように、人数が多くなった今こそ全社での統一感が必要なのではないかと感じるようにはなりました。その頃から髙須と組織の「横串」についてよく話すようになり、私もピープルマネジメント領域に本格的に目を向けはじめました。
―――一方、既にマネージャーとして活躍する方は多くいらっしゃる状況でしたよね。
脇屋:マネージャー自体は各ファンクションにいましたが、全社的なマネジメント研修などは実施していない状況でした。それに伴い、マネージャーたちにも、マネジメントに対する漠然とした不安があるようでした。それは当然で、ある日突然マネージャーに任命されたものの、マネージャーとしての期待役割や取り組むべき業務については聞かされていないまま手探りで進めるわけですから。
結果、マネージャー個々人が模索しながらアウトプットするということが続いてきた中で、その不安の声の閾値が一定量を超えてきたなと感じたのが2021年の年末頃でした。
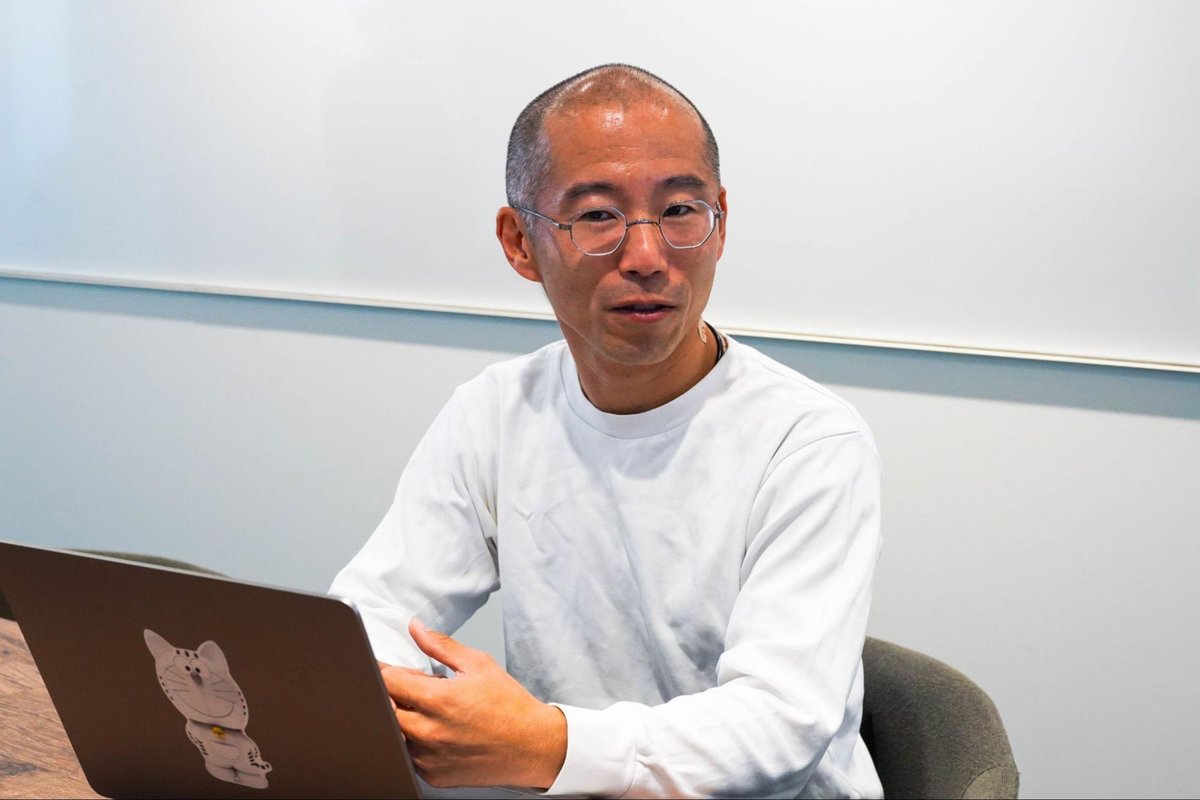
髙須:一人ひとりの努力と猛勉強により業務は何とか回っていて、課題も表面化してはいなかったと思います。でも、抱えている悩みによって思考のリードタイムが長くなっていた可能性はありますね。その頃、組織としての一体感をより高められるようになる為の横串施策として、ミドルマネジメントに対するアプローチが有効なのではないかというのは思っており、選択肢の1つとして、これまでやってこなかった部門横断的なマネジメント研修についても考え始めていました。
体系的に理解できるプログラムが、悩める組織のニーズに合致
―――そこから、どのようにしてEVeMのプログラム導入を検討されたのでしょうか。
髙須:私たちが部門横断的なマネジメント研修を考えはじめる前に、実は社員2人がEVeMのプログラムを各々、個人参加で受講していており、その2人からとても良いフィードバックは過去に受けていたので、EVeMについては認識がありました。また、個人的には、代表の長村さん(長村禎庸/EVeM代表)がnoteの記事でナレッジを公開しているなど、透明性を重視するオープンソースの文化にもシンパシーを感じ、勝手に好印象を持っていました。
当初は新任マネージャー向けの受講を検討していたのですが、その辺りで丁度経営合宿があり、そこでマネージャー陣から「勝ちにこだわるワンチームとして高い事業目標に挑む意識をもっと全体で共有したい」という声があり、弊社の行動規範であるHENNGE WAYに新たに「Win Together」(皆で勝つ)を追加しようとなったタイミングでもありました。そこで、EVeMのマネージャープログラムを思い出してピンときました。
体系的にマネジメントを学べる内容でありながら、個人のスキルも向上でき、何よりも勝ちに拘る思考性を感じるような内容だったのが魅力でした。きっかけは新人マネージャー研修検討でしたが、「組織の共通言語を揃え、一体感を持てるようになるために、新任マネージャーだけ受講しても仕方がない」と考えるようになり、よりスコープを広げようという意思決定をしました。

―――他のマネジメントトレーニングは比較検討されましたか。
髙須:特に比較検討はしませんでした。EVeMのプログラムに、タイミング、質の良さ、社員からの推薦、共感性など、決め手となるような要素が全部が揃っていましたので。EVeMが打ち出している「ベンチャーマネージメント」は、ベンチャー企業など急成長する企業向けの、限られたリソースと時間の中で結果を出すための「攻め」のマネジメントトレーニングだと捉えています。

脇屋:私もnoteを読んでいて、EVeMのベンチャーマネージャーのマニュアル自体に深く共感していました。とにかく体系化されていて、マネジメントの全体が非常に分かりやすいんですよね。どんなことを学ぶにも、まずは「型」を知る必要があると思います。それを知らずに我流で進めていた場合、最も不幸なシナリオはチームが機能せず、メンバーとの信頼関係も築けず、最終的に自分はマネージャーに向いてないと離脱してしまうことではないでしょうか。
その点EVeMのプログラムは、はじめにマネジメントのあるべき姿を示して進むべき道がわかるのが魅力的でした。マネージャーという漠然とした役割に対する疑問の回答が、このトレーニングの中で得られると思います。
―――実際に受講された皆さんの反応はいかがでしたか。
髙須:講義が終了してからは、すぐに良い感触がありました。主にセールスやカスタマーサクセスといった、よりお客様に近い所で成果を求められる部門の社員に受けてもらったのですが、「雰囲気、トレーナーからのフィードバックも含めて、今まで各自が受けてきた中で一番良かった研修だった」という声が挙がったのです。
脇屋:中にはベテランのマネージャーもいるのですが、「これまで自分の暗黙知や経験則で進めていた部分が、体系化され明確になった」という感想をもらいました。研修後は会話の中にマネジメントの「型」の一つである「GPKa」や「関与方針」、「事実の記録」 などの共通言語が行き交い、コミュニケーションの正確性が上がったと感じます。人事の私自身も、プログラムを受けるとマネージャーやリーダー層と会話をする時の引き出しが増え、ソリューションを提案しやすくなりました。

髙須:2025年1月からも、新メンバーの受講を決めています。ポジティブな声が個々に挙がっているので、組織全体としての効果を実感するのは、これからではないかと期待しています。EVeMと一緒に進めていること自体に意義があるので、結果を焦らず、リターンは中長期で得られればと考えています。
いま攻めたいと思う企業や、属人的でなく組織として成果を上げたいという企業に勧めたい
―――EVeMをどういう人・組織にお勧めしたいですか?
髙須:HENNGEの場合は、組織への横串の必要性や、「Win Together」という指針があって、そこにEVeMのプログラムがぴったりとフィットしました。同様に、シンプルに攻める時期に入っている会社や、社内に成果に拘る雰囲気を醸成したいと考えている会社にとって、EVeMのプログラムは良いと思います。
脇屋:昨今は価値観が多様化し、組織が複雑になる中でマネジメントしていくこと自体のハードルが上がっていますよね。多くの企業が守破離でいう「守」の知識を携えた上で、マネージャーが過度な不安を抱くことなく挑戦できる土壌を必要としているのではないでしょうか。EVeMはまさにその「守」を固めるためのエレメントだと考えていて、それによって、マネージャーが本来注力すべきことに安心感とスピード感を持って取り組めます。髙須のいうように、成果に拘る雰囲気を求めつつも、その成果の創出を属人化することなく、組織として皆で勝ちを上げたいという企業にお勧めしたいです。
―――最後に、HENNGEとしては今後どういった組織を目指されるのでしょうか。
髙須:正直、HENNGEで目指す組織像というものはありません。というのも、組織というのはやはり「何か」の軸で最適化されるものであり、その「何か」次第で在り方も変わるべきだと思っているからです。その意味では、究極に柔軟な組織であるために、1つの方向性に拘らりすぎず何もかもが変わり得るというスタンスが必要だと思います。ただ、企業理念であり存在意義でもある、Liberation of Technology(テクノロジーの解放)だけは拘って維持していきたいなと個人的には思っていますね。それ以外は、必要に応じて変化していける柔軟性と効率性を継続して持っていられればと思います。
脇屋:私としては、組織規模がこれからますます大きくなっていってもHENNGEが大事にしている「挑戦」の文化は高め続けたいです。私たちは数多ある企業の1つにすぎませんが、HENNGEとしての自分たちの挑戦の軌跡が、きたる日本社会の未来の中で一つのサンプルになれば嬉しいです。自社の歴史においても、たとえば成長過程の中にEVeMの存在があって、それによってマネジメントが機能し、その環境の中で一人ひとりのメンバーが挑戦と失敗を繰り返してこれた——そんな事実も作り上げられれば、素敵だなと思います。

髙須様、脇屋様、ありがとうございました!
EVeM HERO INTERVIEW
インタビュイープロフィール
HENNGE株式会社
髙須 俊宏 様
CHRO / People Division Manager
脇屋 貴司 様
People Division, People Success Section manager
※上記の部署名、役職はインタビュー当時(2024年12月時点)のものです
HENNGE株式会社様について詳しく知りたい方は、下記からご覧ください。
▼HENNGE株式会社
https://hennge.com/jp/
▼EVeMの法人向けプログラム(マネ型)についてのご相談・お問い合わせは、下記からお気軽にご連絡ください。
https://manekata.com/contact
