
デザイン経営シンポジウム「こわくないデザインvol.2 -経営とデザインとの付き合い方を探る-」開催レポート
「これからの地域を支えるデザイン経営」を本気で学ぶ場所として、2023年にスタートした越前鯖江デザイン経営スクール。2年目となる2024年度も、デザイン経営シンポジウムからスタートしました。本記事では、シンポジウム当日の様子をお伝えいたします!
【開催概要】
デザイン経営シンポジウム「こわくないデザインvol.2 -経営とデザインとの付き合い方を探る-」
日時:2024年7月16日(火)14〜17時
会場:福井ものづくりキャンパス (小ホール)
〈第1部 基調講演〉
講師: 西澤 明洋 氏 /エイトブランディングデザイン 代表
演題:ブランディングデザインと経営戦略
〈第2部 パネルディスカッション①〉
テーマ:他業種と協働するデザイン経営
パネラー:
増谷 浩司 氏 / 株式会社龍泉刃物 代表取締役会長
渡辺 弘明 氏 / 株式会社プレーン 代表取締役
モデレーター:内田 裕視 氏 / 株式會社ヒュージ 代表
〈第3部 パネルディスカッション②〉
テーマ:「ものづくり事業者の考える持続可能な産業」
パネラー:
吉川 精一 氏 / 株式会社キッソオ 代表取締役
澤田 渉平 氏 / 沢正眼鏡株式会社 専務
モデレーター:新山 直広 氏 / 一般社団法人SOE 副理事 / 合同会社TSUGI 代表
【シンポジウム開催の様子】

会場には、越前鯖江エリアのものづくり事業者やクリエイターを中心に、約120名の参加者が集まりました。シンポジウム冒頭には越前市・鯖江市の両市長から2年度目となるスクールへの意気込みやエールをいただき、会場内の熱気が高まります。
西澤 明洋さんによる基調講演「ブランディングデザインと経営戦略」

シンポジウムの第1部を飾ったのは、エイトブランディングデザイン代表の西澤明洋さんによる基調講演です。福井での登壇は3回目だという西澤さん。どのようなお話を聞けるのか楽しみです。
<西澤 明洋 氏のプロフィール>

「ブランディングデザインで日本を元気にする」をコンセプトに、18年間にわたってブランド開発に取り組んできた西澤さん。これまで手がけてきたブランドは、クラフトビール、スキンケア、農業機械メーカー、神社、美術館などなんと100以上。いずれもロゴやパッケージなどの表面上のデザインだけでなく、経営戦略からサービス・商品企画も含めてサポートしているのが特徴です。
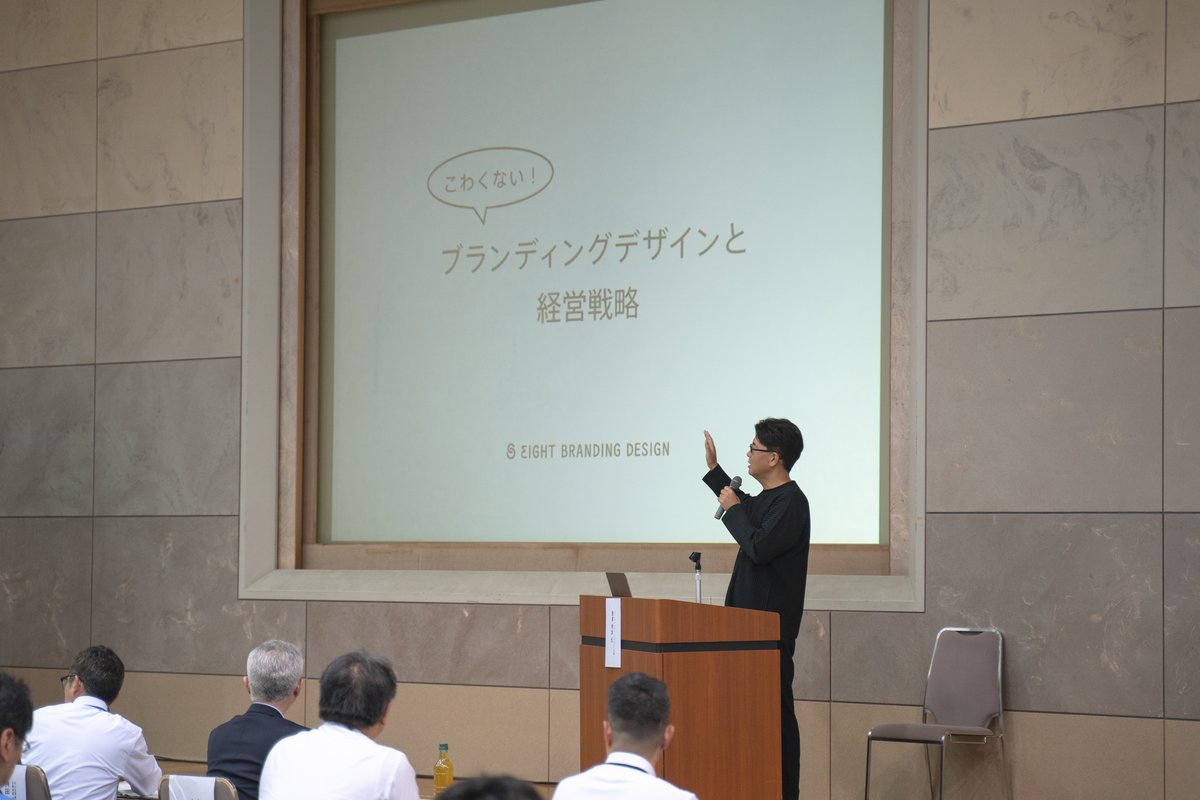
まずはブランディングの定義から。ブランディングとは、ある商品、サービスもしくは企業の全体としてのイメージに、ある一定の方向性をつくり出すことで他社と差異化すること。もともと自分の牛と他者が飼っている牛を区別するために焼き印をつけていたことがブランディングの語源だそう。
「財務的には順調なのに知名度がない会社や、いい商品を作っているのに売れない会社。それらに必要なのは、他社とはどう違うのかをお客さまに正しく伝えることなんです。また、差異化された価値が人から人へと『伝言ゲーム』のように伝わっていく状態にすることが重要です」と西澤さん。
ブランディング≒差異化、伝言ゲーム
また、マーケティング≒売るゲームであり、ブランディングができた状態でマーケティングに取り組むことでより効果を発揮するのだそう。

続いて、ブランディングと経営戦略の関係について、「ブランディングデザインの3階層®」という思考フレームをもとに解説いただきました。

ブランドを3つの階層に分けて考えます。
M(マネジメント):経営戦略。企業や商品価値を差異化できる最大の要因。
C(コンテンツ):プロダクトやサービスのこと。
C(コミュニケーション):ロゴ、パッケージ、WEBサイト、広告など企業のことを知ってもらうための様々なツール。
デザイナーが主に携わっているのはコミュニケーションの部分。ブランド価値が高まる(差異化できる)要因は、上のレイヤーにいくほど高くなるのだそう。

「ブランディングデザインとは、横のデザインを整えるのではなく、経営戦略の根っこをとらえて、商品企画に落とし込み、コミュニケーションのデザインにまで実装していく縦串のこと。MからCの一貫性がデザイン的に最も重要だと思っています」と西澤さんは強調しました。
【経営戦略とデザインの関係】
ブランディングデザイン=経営戦略からコンテンツ、コミュニケーションのデザインを一貫すること

また、実際のブランディングプロジェクトの進め方として「フォーカスRPCD®」というフレームワークと、クラフトビールブランド「COEDO」のブランディング事例を紹介いただきました。


そして、デザイナーが経営戦略をデザインする価値についても言及。
経営戦略=企業や事業の目的を達成するために設計された
「方針」と「施策」の組み合わせ
ブランディングデザインの経営戦略=ポジショニング×組織能力
「ブランディングデザインにおいてまず考えることは、ポジショニング戦略です。お客さまから選ばれ続けるためには、他社と同じ場所に居続けてはいけません。新しいポジションは奇をてらわずに少し背伸びするだけで十分。また、他社から見えにくい組織能力を掛け合わせることで、より強力な差異化につながります」と西澤さんは言います。
経営戦略におけるデザイナーの強みは以下の3つ。
①施策アイデアの具体性とキレ味
②戦略の見える化と構造化
③戦略の社内浸透・全社理解
経営者がデザイナーと一緒にアイデア出しをすることで、具体的でユニークなアイデアが生まれやすくなり、さらに戦略を見える化することで社内に浸透しやすくなり、経営者の思いを加速できます。
デザイナーが経営戦略をデザインする強み=経営戦略という抽象度の高いものをデザインで具体化すること

「経営者に必要なのはデザインを使いこなす力です。デザインを経営者の仕事の一部だと思って、デザインリテラシーを高め、自社にどのようなデザインが必要かを理解して発注しましょう。また、デザイナーも経営者と対等に向き合って話せるように、経営リテラシーを身につけましょう」と西澤さん。
最後に、真のブランディングデザインについて。
「真のブランディングデザインとは経営とデザインの融合であり、ブランド=約束と生き様だと思います。うちの会社は市場でこのポジショニングでやっていくという約束を作ったら、5年や10年かけてやり抜いてください。戦略を定めたら、あとはやるだけです」
そして、「デザインは経営に役立つもの、楽しいものと思いながら、皆さんの会社を元気にしていただけたら」と講演を締めくくりました。
パネルディスカッション①「他業種と協働するデザイン経営」
シンポジウム後半は、地域事業者やゲストによるパネルディスカッションです。パネルディスカッション第1部のテーマは「他業種と協働するデザイン経営」。小中学校の同級生でありながら、現在は刃物メーカーとデザイナーとしてタッグを組むパネラーのおふたり。どのようなお話が聞けるでしょうか。
<登壇者プロフィール>

増谷浩司さんは、2023年に創業70周年を迎えた株式会社龍泉刃物の代表取締役会長。2019年に自社のショップ兼ギャラリーをオープンし、現在は多くのインバウンドのお客さまを産地に受け入れています。
株式会社プレーンの渡辺弘明さんは、武生市(現:越前市)出身のインダストリアルデザイナー。主に家電製品や音響機器、情報機器のデザインが専門で、40年以上にわたってプロダクトデザインの仕事に携わっています。
モデレーターの内田裕規さんからパネラーのおふたりに質問する形で、パネルディスカッションが進みます。
ー龍泉刃物が刃物業界で先駆けてデザイン経営に踏み切ったきっかけは?
増谷さん:父から経営を引き継いだ2008年は、ちょうどリーマン・ショックが起きたタイミング。商品が売れず在庫がたまっていく苦しい状況を脱するために始めたのがブランディングでした。自社商品を作り、国内外の展示会に積極的に出て、自社の名前を知ってもらう活動を始めました。
ー渡辺さんが龍泉刃物に関わり始めたきっかけは?
渡辺さん:14〜15年前に中学のクラスメイトと集まったときに、ますこ(増谷さん)が来てくれたのがきっかけです。30年以上ぶりに再会して、別れ際に「プロダクトデザインが必要な仕事がある」と相談を受けました。
増谷さん:私は職人として鍛え上げられていたのでデザインの知識がなく、しかも過去に一緒に仕事をしたデザイナーさんの印象で、デザイナーにネガティブなイメージもありました。刃の切れ味は職人次第ですが、見た目の美しさや機能性は社内の力だけでは解決できませんでした。彼は友人でしたからコミュニケーションがとりやすく、結果的にプロダクトデザインを手がけていただいたんです。
渡辺さん:依頼内容は、今やフレンチ日本一となった浜田統之(のりゆき)シェフからのオーダーで、料理の世界大会で審査員が使うステーキナイフをデザインしてほしいという内容でした。最初は増谷くんの社交辞令かと思ったのですが、1週間後くらいに浜田さんを事務所に連れてきたので、本気なんだなと。
増谷さん:販売希望価格は2万円以上。ステーキナイフでは今まで存在しなかった価格帯でしたが、ぼくはこの値段で出したいと伝えました。今になれば、設定した金額は間違いではなかったなと。
ーデザイン料のやりとりはどうされましたか?
渡辺さん:プロダクトのデザイン料には「買取」と「ロイヤリティ」があります。買取は、あらかじめ決めたデザイン料を支払う契約で、売れても売れなくてもデザイン料は変わりません。予算が少ない場合は、売上のロイヤリティが一般的。デザイン料は売上の数パーセントなので、商品が売れなければデザイン料は発生しません。お互いにリスクをとろうというやり方です。
増谷さん:私は好き嫌いが顔に出やすいタイプなので、価格交渉は苦手です(笑)。ステーキナイフについては、目的や予算を伝えて、デザイナーさんにもリスクを背負ってもらうロイヤリティ契約でお願いしました。
ーステーキナイフのデザインはどのように進めましたか?
渡辺さん:ステーキナイフはシンメトリー(左右対称)のデザインが一般的ですが、テーブルマナーではナイフが右手でフォークが左手と決まっていることに着目し、「マナーをデザインする」というテーマで、左右非対称なナイフをデザインしました。
左右非対称のスケッチを浜田シェフに見せたところ、すぐにOKが出ました。従来の作り方とまったく違うということで、増谷くんが2年以上かけて開発。

現在は後継モデル「アシンメトリーSK08」を販売中です。
増谷さん:完成したステーキナイフ「アシンメトリーSK01」は、2013年度の日本代表の審査員のテーブルカトラリーに使われました。あまりの切れ味の良さに審査員の過半数がナイフを持ち帰ってしまったというエピソードもあり、現在も予約待ちが続く人気商品です。
ここ数年では世界の和食ブームに伴って日本の包丁に注目が集まり、フランスやデンマーク、アメリカの料理人も越前のナイフを使っているそう。

120〜130あったプロダクトのほとんどを受注生産に変更。
ーこれからデザイン経営に取り組みたい事業者や、デザイナーに向けたメッセージ
増谷さん:渡辺くんと協働するなかで、ブランディングにはデザイナーの力が必要だと実感しました。
デザイナーさんには、伝統工芸の技法を崩さずに、現代的なアイデアと融合するような商品開発を期待しています。ものづくりの現場に来ていただいて、素材や技術がなぜこの形になっているのかをじっくり見ていただきたいです。
渡辺さん:デザインする対象について、いかに既成概念を外して当たり前の前段階からスタートするかが大切です。「ナイフ=左右対称である」という既成概念からスタートしては新しいものはなかなか生まれません。いいデザイナーはアイデアの懐が深いと思っています。1つのプロダクトをデザインするのに100パターン以上のアイデアを出せるといいですね。
私はこれまで美大で工業デザインを教えてきましたが、本当は小中学生にもデザインを教えたいんです。デザインっていうのは、色や形ではなく発想の仕方そのもの。福井を、小中学生からデザインを学び、デザインでまちを作る「デザイン県」にしてはどうでしょうか。
パネルディスカッション②「ものづくり事業者の考える持続可能な産業」
パネルディスカッション第2部は、「ものづくり事業者の考える持続可能な産業」というテーマで、鯖江市内の眼鏡事業者2社に登壇いただきました。2023年度に当スクールの商品・サービス開発プロジェクトに事業者として参加された沢正眼鏡の澤田さんには、スクール参加の前後での変化についてもお話しいただきます。
<登壇者のプロフィール>

吉川精一さんは、眼鏡の材料商社である株式会社キッソオの代表取締役。次世代の眼鏡職人を育てるための勉強会を他社と協働でスタートするなど、産地の担い手育成にも力を入れています。
澤田渉平さんは、プラスチックフレームメーカーである沢正眼鏡の専務取締役。2023年度の越前鯖江デザイン経営スクールでは、会社や産地が抱える課題解決の糸口を探るべく商品・サービス開発プロジェクトに参加。
ー分業で進んできた眼鏡産業。商社とメーカーというそれぞれの立場で感じる産地の課題や可能性は?
吉川さん:世界で見ると鯖江は眼鏡の4大産地の1つ。自社ブランドを持たずOEMの受注に頼っている企業が多く、外部からの影響を受けやすいというのが産地の現状です。1990年代に大手商社の中国進出、2010年前後のリーマンショック、2020年代にはコロナ禍で売上が落ちるなど、危機のたびに業界が縮小している印象があります。
澤田さん:円安の追い風もあって注文が増えていますが、産地の生産体制が追いつかず1年待ちの状態です。廃業した会社の仕事が一部の会社に集中してしまったり、どこかの工程で詰まると産地全体のスピードが落ちたりと、分業制による影響が出てきています。
また、業界の高齢化も課題です。眼鏡の製造工程は手作業が多く、職人を育てるのに時間がかかります。若者を採用したくても各社の雇用体制が整っていないのが現状です。
ー沢正眼鏡は2023年度のデザイン経営スクールでその課題に取り組まれていましたよね。

井上さん:昨年度の商品・サービス開発プロジェクトでは、「『地域』で『眼鏡』をつくる。『眼鏡』で『地域』でつくる。」をテーマに掲げ、①社内の雇用体制の整備、②地域の住まいづくりにチームで取り組みました。
地域と眼鏡産業は密接に関わっているため、両方をよくしていかなければなりません。地域のおじちゃんおばちゃんが産地を支えている現状があり、地域で暮らす人が増えて、その人たちが眼鏡産業に関わる仕組みが作れないかなと。産業観光イベント「RENEW」などをきっかけに地域にやってくる若者が増えているので、地域の受け皿となる住宅として、物件を購入しシェアハウスを整備中です。
ー沢正眼鏡チームの取り組みは、産地への小さな革命だと思われます。若い人を育てることに力を入れている吉川さんはどう感じていますか?
吉川さん:場所があれば若い人が来てくれて、若い人が集まると次の若い人が来てくれることをここ数年で目の当たりにしました。澤田さんが河和田地区に住宅を作ろうとしているので、神明地区にも住宅を作れたらと思います。キッソオにも県外から移住してきてくれた社員がいますし、眼鏡業界に入りたい若者は産地に来ているはず。
ー眼鏡業界に入りたくても全工程を学べる場所がほとんどなかったり、事業者側も雇い方がわからなかったり。仕組みさえ整えたら産地が変わるはず。澤田さんは社内改革を始めてみてどうですか?
澤田さん:法人化して約42年の会社ですが、先日ようやく就業規則が整備されました。眼鏡業界は家族経営で5人未満の事業者が多く、産地としての課題は多いですが、裏を返せばのびしろだらけ。総務や労務に手をつけていない会社が多いので、劇的に変わる可能性を秘めていると思います。
ー越前鯖江エリアにおける、持続可能な産地への展望はありますか?
吉川さん:自社ブランド「KISSO」を伸ばしたいという目標と、鯖江を眼鏡の聖地にするという夢があります。RENEWやSOEと一緒に、越前鯖江を日本一の産業観光のまちにしたいです。
澤田さん:越前鯖江デザイン経営スクールに参加してみて、自社でできることや検討できること、学べることにも限界があると知りました。他社に頼れずに悩んでいる事業者も多いと思うので、心強いみなさんの力を借りながら、会社や産地をますます伸ばしていけたらと思います。
シンポジウム終了後、懇親会の様子


シンポジウム終了後には、講師やパネラーを交えた懇親会を開催しました。参加者同士での名刺交換や講師との意見交換など、充実した時間となりました。
***
以上、デザイン経営シンポジウムの開催レポートでした。2024年度もこちらのnoteにてスクールの様子をお届けしていきます。
(文:ふるかわ ともか)
