
「法人からの仕事受注を増やす」目的のプロジェクトが失敗した理由
8年ほど前だったかーー💬。法人からのお仕事受注を増やすことを目的に、弊社含めたBtoB専門の中小企業が9社集まり、プロジェクトを立ち上げたことがありました。
が…結局はうまくいかず1年もせずに終了。当時は「なぜうまくいかなかったのか?」の振り返りを行わないままだったのですが、ある書籍を読んでたら「だから上手くいかなかったのかぁ」と、8年経過した今になって合点がいきました。お仕事の受注を増やしたいと考えるBtoBの中小企業さんには、弊社の失敗事例が参考になる内容かなと思うので、noteでシェアさせていただきます。
「法人からの仕事受注を増やす」目的のプロジェクト
集結した9社はいずれも、ヘルスケア領域を専門にBtoBソリューションを提供している会社。とはいえ、提供ソリューションがそれぞれで異なっていたため、カニばることはなく、とんとん拍子でプロジェクトは進行していきました。
気付いたときには自然消滅
プロジェクト専用のHPも立上げ、ミーティングも定期的に実施。業界人が集まるプチ交流会を開催したり、100社程度が集まる勉強会も開催するなど初速は良かったのですが時間の経過とともに、1社抜け、2社抜け…気づいたらプロジェクト自体が停滞し、自然消滅してしまいました。
プロジェクトが失敗した理由
「それなりのリソース(時間、人、お金)を割いたのに、なぜうまくいかなかったのか?」の振り返りを行う時間&工数的余裕は、当時の弊社にはなくて、いわゆる「やりっぱなし」状態だったのですが、「小規模組織の特性を活かす イノベーションのマネジメント」という書籍をたまたま最近読んでたら、ふと当時を思い出し、あの当時はなぜ、うまくいかなかったのか?理由が今になって明らかになりました。
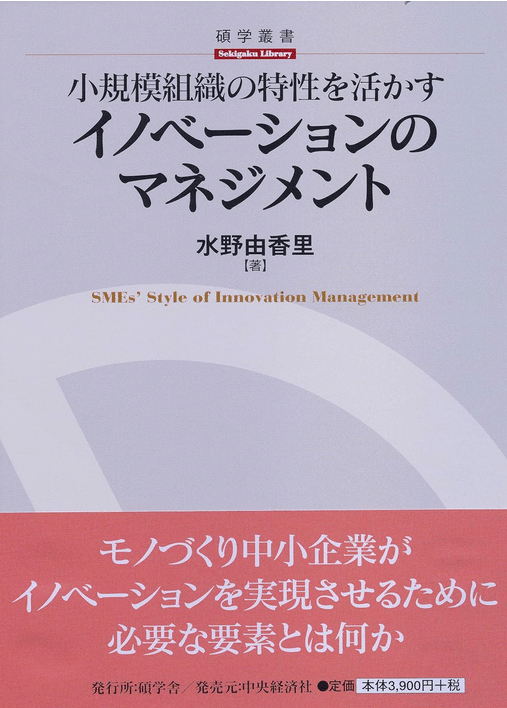
中小企業は、どのようにイノベーションを起こしてるのか
同書は「モノづくり中小企業がイノベーションを実現する論理を明らかにする」ことをテーマにしています。経営学部の准教授さんが著者ということもあり、いわゆる「研究論文」的な特有の読みづらさはあるのですが、大企業と比較してあらゆる面でリソースが不足している中小企業がどのようにイノベーションを起こし、成果を上げ続けているのか?を豊富な事例を掲載していて、読み応え抜群です。
ある協同体の成功事例
同書で成功事例として取り上げられている一つが「京都試作ネット」さん。2001年、京都府を拠点とするモノづくり専門の中小企業が10社集結し発足した協同体で、試作品の開発や製造を共同で受注することを目的としています。今現在も協同体は運営されていて、発足から19年で相談件数は8,000件を超えてるそうです(同社HPより)。
異なる組織が集結して共同受注を目指したり、同じ目標に向かって活動することってどの業界でも活発に行われてますが、組織が異なる者同士が集まると、スタートは和気藹々とスムーズに進んでも、利害の不一致や顧客の取り合い、売上分配、モチベーションの差など様々な点で問題が発生しはじめ、うまくいってるケースはかなり少数なんじゃないかなーって思います(弊社の過去事例も含めて)。
にも関わらず、同協同体はJAXAからも受注するなど、なぜ長きにわたり運営できているのか?詳細は同書を読んでいただきたいのですが、その理由を一部引用でご紹介させていただきます。
「費用対効果を考えると、(協同体に参画することは)うま味の少ないビジネスである。」とメンバーは口を揃える。(協同体の目的である)共同受注に参加していても、メンバー企業はこの業務から大きな利益を得ているわけではない。それにもかかわらず、メンバーは会費を支払い続け、(中略)複数の会議に参加するという多大な物理的および時間的負担をになっている。
(にも関わらず、参画企業の)メンバーが京都試作ネットのメンバーであり続ける理由は、メンバー企業がそれぞれの本業から利益を得ており、京都試作ネットの業務で利益を計上する場と認識していないこと(※)、そして、メンバーが京都試作ネットでの活動の場を次のように認識しているためである。
「(中略)自分たちで汗・水たらして働くことにより、自社に足りないものが見えてきた」こと、「非常に貴重な経験をしてきた。たくさん勉強した」こと、「この試作の仕事を受注して、大きく変わった。汗をかいて情報を得ることの重要性がわかってきた。そして、『自分の強みを活かさないといけない』ということに後から気が付いた」こと、を強調する。すなわち、メンバーは、京都試作ネットでの業務を自社の成長の機会と位置付けていることが確認される。
(※)この点から、メンバー企業は、京都試作ネットに「依存」していないことが確認される。
もちろんメンバー企業さんの中には、実際に新規取引先の開拓(=売上増)につながることも多々あるようですが、実際にメンバー企業さんたちが実感してるメリットは上記の通りなんですよね。 とはいえ、(資本関係が一切ない)異なる組織が共同で一つの組織となり、活動し続けるのは容易ではないはず。ではどうしてるのか?と言うと、同協同体では、公式的な組織化を行い、下記をルールとして徹底しているそうです。
理事会は月1回開催
営業活動会議は週1回開催
メンバー企業すべての保有技術や設備に関する知識を覚えること
半年間の研修を受けること(ドラッカーの輪読)
など
そのほかにも、同協同体に所属し続けることは年会費や、自社人員の動員などが義務付けられています。でも、そもそもはこれだけの厳格なルールを設けないと、複数の組織が一つになって共に成長し続けるってできないってことなんですよね…
ギブはせずに、テイクばかりを期待
弊社の話に戻りますが、当時メンバー企業の中で最も小さい会社は弊社で、他8社は売上が100億クラスの企業ばかりだったので弊社自身、いわゆる「フリーライダー」になろうとしていたのかもしれません。
つまり「ギブはせずに、テイクばかりを期待してた」。そのつもりは当時は全くなかったのですが、結果的には「ウチよりも大きい会社ばかりだから、仕事を獲得できるぞ!」というフリーライダーな甘えがあったのかもしれません。
さらには、当時集結した9社間では、ルールは一切とりきめていなかったこともあり、リーダー企業は誰なのか?何かあったときの責任は誰がおうのか?役割分担は?どの企業が案件を獲得してくるのか?など全てが曖昧だったので、初速はよくとも、あっという間に自然消滅したことは、今となると納得です。
法人からの仕事受注を実現するなら…
異なる組織同士が連携して、プロジェクトを発足させ、共に市場を開拓したり、販路を拡大を目的に「一緒に何かやろうよー🥰!」は、安易にスタートできるぶん、自然消滅や空中分解、頓挫する可能性も高いものです。
一方で同協同体のように、やり方次第では参画企業各社に多様な成果が自社にもたらされることもあるわけで。中小企業が、大海で自社1社のみで闘っていくことは大変なことですが、複数社で大海に出れば、市場競争力は格段にあがりますからね。8年経過して、当時の失敗理由を明確に理解できたと同時に中小企業にとっての協同体の強さ、魅力を改めて感じました。同書は参考になることが多かったので、オススメです。
先日、弊社が運営しているビジネスメディア『ウーマンズラボ』で取り上げた下記のプロジェクト。事業領域が明確に異なる企業が集結している点など、興味深い取り組みだなーと思いました(京都試作ネットさんも、参画メンバー同士がカニバらないよう、メンバー同士の差別化を明確にしているそうです)。
学びとネットワーキングの場
ちなみに、弊社では共同体なるものは運営してないのですが…ヘルスケア事業を行う企業様同士のネットワーキングの場「ウーマンズ・ミートアップ」を運営しています。
8年前に立ち上げたプロジェクトは自然消滅したものの、そのプロジェクトに参画していた各社さんとは当時、個別でお取引させていただいてて、随分と助けていただいてて(発注させて頂いたり、ご発注いただいたり)、企業同士のつながりがいかに重要なものなのかについては、十分に実感していました。結局お仕事って、人と人とのご縁からスタートする方が圧倒的に多いんですよね。
そんな背景もあり、企業様同士が繋がれる場を各社様にご提供させていただく、ということもウーマンズ・ミートアップ!の目的としています。「学び」と「ネットワーキング」をセットにした場で、少ないときで10社様程度の参加、多い時で900社様にご参加いただいてます。定期的に開催していますので、ご参加お待ちしております!詳細は下記にまとめています。
また、本稿でご紹介したプロジェクトの失敗から8年経過した今ーーー(汗)。今現在は、全国的な法人ネットワークが強みとなり、ヘルスケア業界に特化したBtoBの販路開拓支援、プロモーション支援を行わせていただいています。どうやって、法人ネットワークを構築し、それが強みとなり、サービス化できるようになったのか?は、話が長ーーくなるので、今回は割愛しますが(苦笑)、これまでのご支援事例など下記にまとめています。
スタートアップ様~上場企業様、グローバル企業様まで、豊富な支援実績がございます。「法人からのお仕事受注、増やしたいよー!でも戦略や施策が分からない~」という企業様は、下記の情報をぜひお役立てください🥳。
