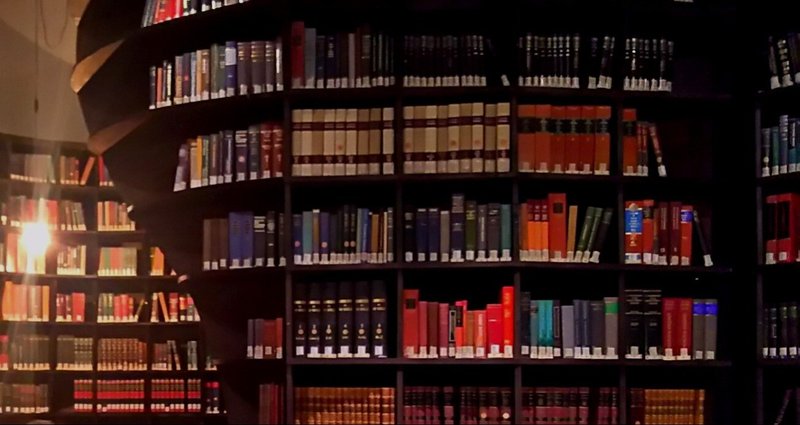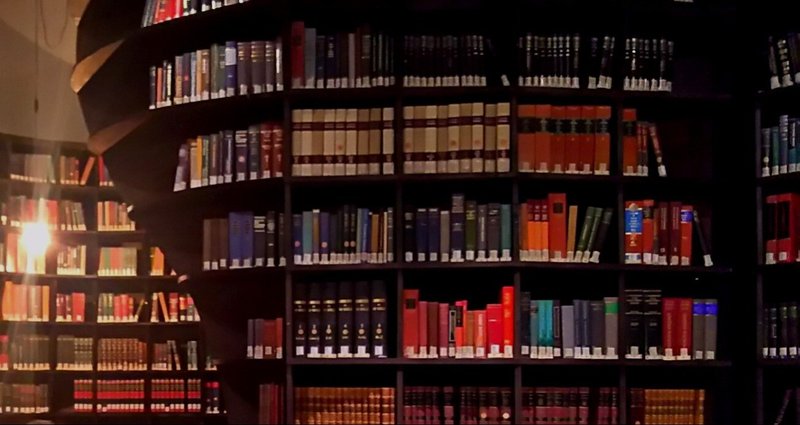クラシック音楽を保護する「プリザビング・マシン」
文芸誌MONKEYの「いきものたち」号では、伊藤比呂美の「ヒルディスヴィーニたち」に加えて、フィリップ・K・ディックの'Preserving Machine’(柴田元幸 訳)も面白かった。
邦題が「プリザビング・マシン」で、最初は「Preserve」のことだとは気づかなかった。絶滅危惧種を保護する、というときのPreserveなのね。
モーツァルトの楽譜をこのマシンに入れると美しい鳥になって出てくる。ベートーヴェンの楽譜を入れると、厳しく堂々たるカブトムシに。さて、生まれ