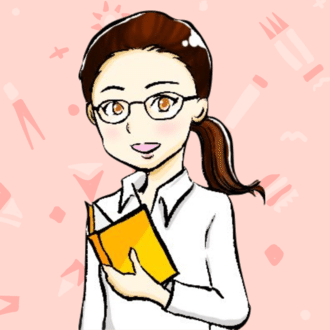Scienceのキャリアニュースを読んでみた〜20年ぶりに研究の世界に戻ってきた女性研究者の話
先日、ScienceのHPを見ていたら”Latest News(最新ニュース)”だけではなく、”Career News”なるものもあるをとを発見しました。

研究者のキャリアについては、様々な学会でサポートされていて研究者とポストとのマッチングを手伝ってくれたり、求人募集のお知らせなどを掲載していることは知っていました。が、科学雑誌にもキャリアを考えるニュース枠があるのは少し驚きでした。
面白そうな記事がいくつかあったので英語力を上げるためにも、この”Career News”を読んでまとめてみようと思います。
今回、ご紹介するのは2020年3月に書かれたこの記事。
タイトルは「22年後に研究に戻ってきた。その22年間の断絶はずっと続いてはいけない」。
記事を書いているKathy Gillenさんはケニオン大学(米 オハイオ州)の准教授をされている方。生物学(特に細胞生物学)がご専門で、酵母をモデルとした膜標的Gタンパク質のサブユニットに関する研究で1995年エール大学で博士を取られました。
22年間なぜ研究をしていなかったのか、どのように研究の世界に戻ってきたのか?が書いてあるのでは?と言うことが書いてありそうだったので読んでみようと思います。
—————
◇ 研究を離れた理由と研究に戻るまで
20年ほど前。私の夫が教養課程の大学で終身ポストを得た(エール大学があったコネティカット州からかなり離れたところ?)ので、研究から離れることにしました。
引っ越してから数年後、大学で教える機会に恵まれました。大学の人たちは「研究に戻りたいのではないか?」と聞いてきて「今の仕事はとっても楽しいですよ」と答えていたのですが、全部が本心というわけではありませんでした。
夫が、研究費を獲得したり論文が掲載されたのをお祝いする一方で私も同じように研究したいという気持ちが抑えられずにお腹の中がチクチク痛くなったりしました。
一番心苦しくて後悔したのは、教えていた学生さんが「どうやったら先生の研究室に入れますか?」と聞いてきた時に「研究室はないのよ」と答えた時。自分は研究をこれ以上やらないと言っているようでした。
数年後、研究の現場から離れた後悔が頂点に達する出来事が起こりました。とても優秀な2人の学生さんが私の授業を聞いて自分が所属している研究室のプロジェクトとは別に、彼らが独自で研究プロジェクトを立ち上げたいと言って来た時。この学期が終わった後に、このような熱意のある学生さんと一緒に仕事をしたいと思いました。それが可能であるか検討しなければならない時期だったのかもしれません。
私は終身雇用の教授ではないので、研究プロジェクトは持っていないと学生さんに言い続けていました。しかし、それが本当に研究をしない理由だったのでしょうか?自分の立場にする方が研究室を立ち上げて動かすよりも簡単だったのではないか?研究に戻って失敗するのが怖かったのではないか?
◇ 22年の時を経て研究に戻ってきた!
それから数カ月の間、”研究をしないこと”に関するリスク(退屈である、後悔の念が消えないこと、夫をお祝いして落ち込むなどなど)は、”研究をすること”に関するリスクを上回るようになりました。そして、私は研究の世界に戻ることを決意したのです。
学部長に連絡を取ったところ、学生を指導している間は私の計画を支援してくれるということでした。同僚たちは実験機器や専門知識、実験スペースを共有してくれました。大学からの開発費があったので実験を始めるための試薬を買うお金は十分ありました。
研究課題については、私が教えている時に”Lumbriculus variegatus(ブラックワーム)”という虫が安く手に入り、実験に使えることを知りました。準備は整っていました。
2019年の6月、私は最初の学生さんに指導を始めました。自分の技術が錆び付いているのではないか?時代遅れではないか?実際に私が学生時代に日常的に使っていた技術はもはや使われなくなっていました。
しかし科学の核である、問題提起、実験を組み立てること、データを解釈することは変化していませんでした。そして、私のトラブルシューティング技術はすぐに身につき、最初にやったWestern Blottingはロールシャッハ・テストのようでしたが、何週間もかけて細かい検討したところ解釈可能なブロット像が検出できるようになりました。
参考までにロールシャッハ・テストの写真を↓
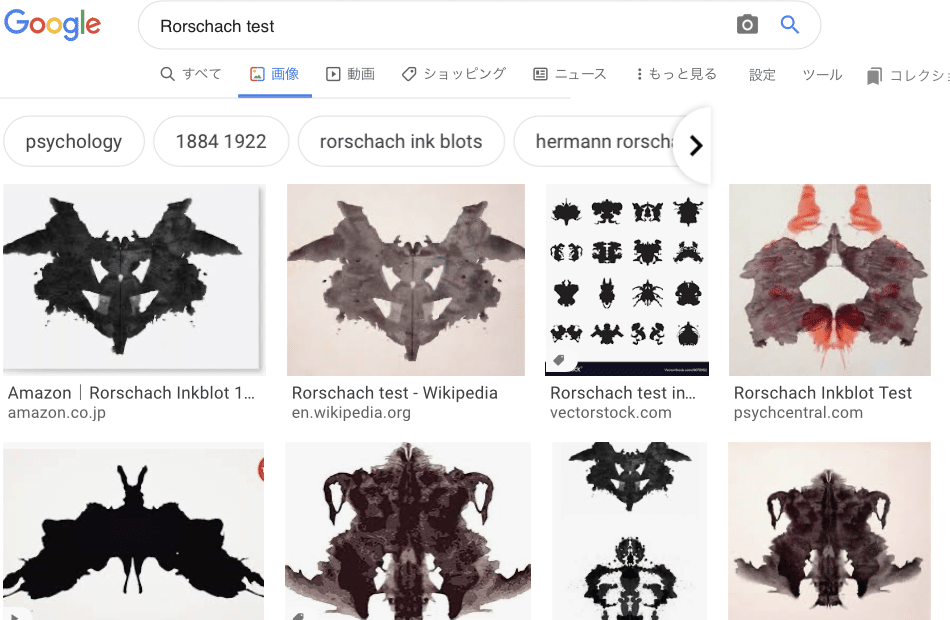
夏の終わりには次の年の1月に学会でポスター発表するのに十分なデータが得られました。学会も無事に終えられて、研究が楽しく、将来的に向けて活力をもらい、なんでこんなに長い間研究に戻らなかったんだろうと思いました。
◇ COVID-19に負けない!
学会からわずか3ヶ月後、COVID-19の蔓延により研究が中断してしまいます。私はコロナ禍でも研究を続ける方法を模索し、この夏に来るはずだった学生さんとリモートで研究を行っています。
学生さんが実験をデザインし、私が実験をし、彼がデータを解釈するというもの。そして次に何をするべきかを学生さんが考えるのです。理想的な形ではないですが、少しずつ進歩しています。
普通の状態でも研究室は大変。今年の夏は、結果が思うように出ずにタオルを投げ出したくなることもありました。しかし、2019年の夏。どれだけ楽しかったことか。
私が恐怖心を克服して22年ぶりに研究に復帰できたのであれば、今は突き進むのみです。
————
まず、日本では戻ってくるのはかなり難しいのでは?と感じました。一つは女性に対する差別が少なからずあるから。もう一つはキャリアが続いていることを大事にする風潮があるから。
私はキャリアが断絶しないように、仕事は続けなさいとよく言われています。(子育てをしていて休みたい!仕事なんてしたくない!やめてやる!って思うことは多々あるのですが...)
Kathy先生はかなり優秀でやり手の女性であること。これが研究への復活ができた理由ではないかと思います。
研究者というのは研究の魅力に取り憑かれてしまった不憫な存在なんだなとも...
それでは、また!
いいなと思ったら応援しよう!