
最後の講義 完全版 大林宣彦
NHKの番組「最後の講義」の未放送分を含む完全書籍化です。

週刊文春の2020年8月13日・20日夏の特大号に「戦後75年特別企画戦争映画燃ゆ」という特集があったのですが、大林宣彦監督の作品について一言も言及がありませんでした。
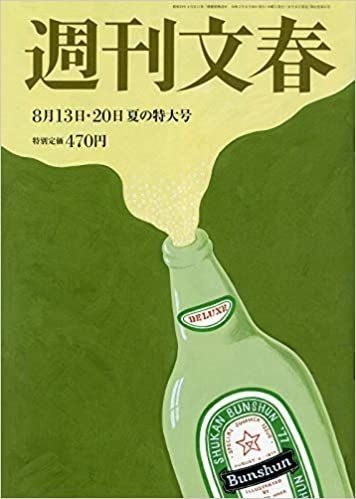
本書を読むと大林宣彦監督がいかに戦争映画と向き合って来たかがよくわかります。



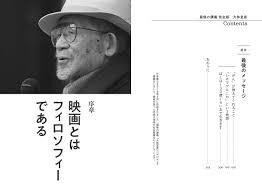
序章:映画とはフィロソフィーである 淀川長治、手塚治虫、黒澤明との親交を通じて導き出した生涯にわたるテーゼを説明しています。



第1章:「あの時代」の映画に込められていたメッセージ サイレント映画から紐解き、『七人の侍』、『ハワイ・マレー沖海戦』、『秋刀魚の味』、『血とバラ』まで映画表現の変遷を独自の視点で解説しています。




第2章:「平和孤児」にとっての戦争、「今の子供たち」にとっての戦争 自分の立ち位置を「平和孤児」として定義。デビュー作の『HOUSE/ハウス』も戦争映画だったと回想しています。「戦前」を生きる「今の子供たち」に向けて『この空の花 長岡花火物語』、『野のなななのか』、『花筐』を作ったのだと。




第3章:ネバーギブアップとハッピーエンド この章でハリウッド映画のフィロソフィーがハッピーエンドである理由を分析(ここは眼から鱗です)。「政治や経済がアクションで表現はリアクション」という分析も鋭い。ハリウッドが『アーティスト』をアカデミー作品賞を選んだあたりから時代の流れの変化を感じたと。

第4章:自分に正直に生きるということ 尾道時代の「敗戦少年」としての思い出が語られます。「自分がやりたい道に行けるのは平和の証拠」だと。小津安二郎の『東京物語』が『明日は来らず』を下敷きにしているとか、今井正の『望楼の決死隊』についても説明があり、本当に沢山の映画を見てきたのがわかります。



第5章:映画がいらない時代が来るまでは... 塚本晋也監督の『野火』を例に取り、「こんな戦争が二度とこないようにしたいと努めていかなければならない」と。『きけ、わだつみの声』、『ビルマの竪琴』、『独立愚連隊』、『肉弾』などの反戦映画、戦争アクション映画を挙げながら、「バトンタッチ」で作っていくのが平和だと説くのです。





終章:最後のメッセージ ここまで読んできて最後のメッセージを現在公開中の『海辺の映画館 キネマの玉手箱』に込めたのだということがよくわかりました。

本書こそ、戦後75年特別企画戦争映画燃ゆ だと思います。
いいなと思ったら応援しよう!

