
【メルマガ絵本沼】vol.27 アニメ絵と絵本:『赤ずきん』(POP)を再読する
絵本を読み、愉しみ、考えて、ハマる、【メルマガ絵本沼】。
今回のテーマはアニメ絵(=萌え絵)に徹底的こだわってつくられた絵本「POP WONDERLAND」(ポプラ社)の中から、『赤ずきん』を取り上げ、「アニメ絵と絵本」について思うところをつづりました。
ひとときお付き合い願えれば幸いです。
【お知らせ】
■第二期絵本沼読書会#5『モチモチの木』(岩崎書店)を開催します。
同じお題絵本、同じ内容での2回開催となります(メンバーだけ入れ替わり)。日程と募集人数は下記となります。6/1(土)より受付開始で、あっという間に満席になるのでお早目にお申込みくださいー。
・6/8(土) 21時~22時半 見学者3席(参加者は受付了)
・6/13(土)21時~22時半 参加者6席&見学者3席
※「参加者」と「見学者」の違いについて。
「参加者」は事前にお題絵本を読み込んで、感想と次に読むおすすめ絵本を発表します。「見学者」は発表ナシで見学のみとなります。ご自由にお選びくださいー。
【メルマガ絵本沼】
アニメ絵と絵本:『赤ずきん』(POP)を再読する
■定期的にあがるネタ
絵本業界で定期的にあがるネタに「アニメ絵と絵本」というものがある。
これは毎回のように「アニメ絵は絵本にふさわしくないのでは?」というアンチテーゼが発端となり、それに「絵本にそんな基準などあるのか?」というカウンターが入り、内容は「いい・わるい」の話ではなく、発言者の絵本観が垣間見えるポリシーの対立となるので、私はこのネタが大好きなのだった。
しかし最近は珍しく発生してなくて、調べてみると一番最近のものは5年ほど前の下記の記事だった。
・絵本・児童書の“萌え絵”論争――「子どもに悪影響」の声に、児童文学評論家が反論
かん子さんらしい回答だと思った。
で、記事の内容以上に気になったのは、ここでは「アニメ絵」や「漫画絵」ではなく「萌え絵」と表現されていたことで、なるほど、今はそう呼ぶ方がしっくりくるのかもしれない。
独語、アニメ絵の絵本を今読んでみたら、自分はどう感じるんだろうか?と思った。
そこでポプラ社のあの萌え絵の絵本を書架から抜き、ひさびさに頁をひらいたのだった。
■萌えの力と当時のポプラ社の勢い
話をすこし遡ると、私がネット書店に勤めていた2003年、ある英単語帳が大ヒットした。

それは解説に萌え絵を使ったもので、タイトルはずばり『萌える英単語~もえたん~』(渡辺益好/鈴木政浩/2003/三才ブックス)というものだった。
私はこの本が勢いよく売れていく様を目の当たりにし、萌えってすごいなーと実感したものである。
そしてこの萌え絵を担当したのは絵師のPOP(ポップ)さんで、この本はPOPさんにとって商業出版デビュー作となった。
で、私がPOPさんという絵師の存在を知ったのもこの時だった。
その3年後にPOPさんの絵本が出るというニュースをネットで見かけた。
絵本出すのかー、しかも出版社がポプラ社なのかと、私は「なるほど」と頷いたことを覚えている。
ポプラ社は今日も児童図書出版社のトップ出版社だが、この頃は少年漫画雑誌『コミックブンブン』、心理学雑誌『月刊psikoプシコ』を立て続けに創刊して雑誌業界に本格参入したり、あの『KAGEROU』(齋藤智裕(水嶋ヒロ))を生み出した「ポプラ社小説大賞」を創設したりと、とにかく、貪欲に新しいことに取り組む出版社という空気をまとっていた。
そしてこの時期は坂井元社長の全盛期でもあった。
かような中で登場した本作だったが、当時の私の感想は、「どれくらい売れるのだろうか?」ということなのnだった。
まあ、商売柄、たいていの絵本に対して私が最初に思うのはこれなわけだが。
■アニメ絵にこだわった絵本

POPさんの絵本は「POP WONDERLAND」というシリーズ名で刊行され、『赤ずきん』(ぽっぷ(POP)/はやのみちよ/2006/ポプラ社)はその中の2冊目になる。
奥付には「企画・デザイン/マスターピース」とあり、本作の企画立案はポプラ社本体ではなくマスターピース社によるものだと思われる。
企画の前提として、『赤ずきん』という童話は『グリム童話』の中でもトップバッター的な立ち位置であり、絵本化されたものは古今東西の出版社から発売され、大物翻訳者が文章を担当することも珍しくない。
なので本作の文章を担当した早野美智代さんも実績のある方なんだけど、本作のコンセプトはなんといっても、シリーズ名にもあるように「POPさんの萌え絵で絵本がつくること」であり、もう、企画の幅としては「これ一本勝負」という感じになっている。
が、冒頭で触れたように「アニメ絵(≒萌え絵)の絵本」にアレルギーを持つ人は、今も昔も確実に一定数いる。
そしてその人たちは、本作をまず買わない。
ということは、本作の企画者はそのハンデよりも、萌え絵による上乗せの方がでかいと判断したということなのだろう。
企画は博打だ。
なので、売れるかどうかは置いといて、私はこういう一発勝負的な企画に対し、潔くて清々しさを感じてしまうのだった。
■文章はどのようにつくられたの?
そんな中、今回再読して思ったのは、まず、本作はとても丁寧につくられた「子どもの本」であるということだった。
仕上がりも非常によい。
そんな中引っかかったのは、本作の文章はどのようにつくられたのだろうか?という、萌え絵以外の部分なのだった。
奥付の著者区分が「訳」ではなく「文」とあるので、それは、この15場面に置かれた文章は『Grimms Märchen』からの翻訳ではないということになる。
となると本作は翻訳ではなく翻案になるので、本作を他の有名な『赤ずきん』絵本の本文と比較してみたところ、おそらく、岩波書店の生野幸吉(1924-1991)訳が翻案元だと推察。
大塚勇三(1921-2018)訳や佐々木田鶴子(1942-2016)訳とも読み比べてみても、構成は生野訳がもっとも近かった。
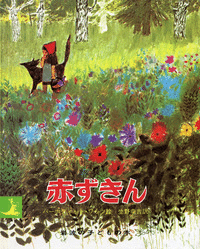
私の書架に刺さっている生野訳は1975年初版の「岩波子どもの本」版なので、ならばと念のため図書館で大型版の方を確認したところ、ラッキーなことに当時の解説チラシが挿入されており、そこには「訳者のことば」として以下の文章が記されていた。
・文章はグリムの原文と同じドイツ語から、子どもにもわかりやすく、しかし、まったく省略せずに訳しました。
ここから、生野訳は翻案元としてもじゅうぶん信頼できるものであることがわかる。
と、念のため言うと、こういう形の童話・昔話等の翻案はNGでもなんでもない。
そもそもグリム童話は創作ではまったくなくて、グリム兄弟が採集した民話・昔話をまとめたものだし、昔話って「伝承」という伝言ゲームの最大公約数的なものであるべきじゃないのと、私なんかは思っていたりするし(とか言うと専門の方から叱られそう)。
■その後
その後もじっくり再読したが、文章については上記のようにひっかかったが、萌え絵についてはほんとに、何も感じなかった。
絵本としてなにも問題が無いように、私は思う。
でだ。
本日現在、ポプラ社ホームページで本作を検索すると在庫表示が「品切」になっている。
どうも、最終的には売れなかったということなのだろう。
ハンデの方がでかかったということなのかなあ。
まあ、そもそも昔話絵本自体がレッドオーシャンなので、今から新作を出してヒットにつなげることは相当に難しいとであるという現実もある。
もうひとつ。
「POP WONDERLAND」はシリーズ5冊刊行されたんだけど、私の書架にはなぜ『赤ずきん』しか刺さっておらず、そしてなぜ『赤ずきん』だけ入手したのかまったく思い出せないのだった。
一巻目の『アリス』の方がだんぜん好きのなのに…。
というわけで、次回の「アニメ絵と絵本」論争が待ち遠しい次第。
(了)
最後までお読みいただきありがとうございました(^^)/
ご感想いただければ幸いです。
※バックナンバーは下記となります。
https://note.com/ehonnuma
次回は6/24(月)配信予定です。
■【メルマガ絵本沼】(毎月最終月曜日発行)
■(C)吉田進み矢
■本メルマガの無断転載はご遠慮ください。
■ご意見、ご感想は info@ehonnuma.com までご連絡ください。
-絵本を読み、愉しみ、考えて、ハマる。-
絵本沼|https://www.ehonnuma.com
