
インタビュー #004 看護師グループリーダー 守田さん
「児童発達支援 えほんの木 相生山」(以下、「えほんの木」)、開設1周年を記念したスタッフインタビュー企画、4人目は看護師グループのリーダー、守田さんです。
医療現場での経験が長い守田さんが、保育園を経て「えほんの木」に来ることになったきっかけや、「えほんの木」での嬉しかったエピソードについて聞きました。
さっそくですが、これまでの経歴を教えてください。
「えほんの木」に来る前は1年半ほど保育士として保育園で働いていました。ただ、看護師歴の方がずっと長いです。父の見舞いで病院に行った時に見た看護師さんの働く姿にあこがれて、看護師を目指すようになりました。学校を卒業して看護師になってからは終末期医療に携わることを志して、外科や内科、呼吸器系や循環器系で経験を積んで、ホスピスで働いていました。

その後、妊娠や出産を経て医療の仕事に復帰したのですが、子育てをする中で子供の可愛さに改めて気づいて。子供と関わることを仕事にしようと考えて、保育士の資格を取得し、「えほんの木」に来る直前まで保育園で働いていました。
医療の現場と保育園を経て、「えほんの木」に加わった経緯が気になります。
看護師と保育士の資格を持っていて、それを生かせる職場はどこだろうと考えていた時に、「えほんの木」の求人を見かけました。医療的ケア児が増えているということはニュースなどで見聞きしていたので、ここで自分ができることがあるならなと思って、求人に応募したのがきっかけです。
「えほんの木」に来て新しく感じたことはありますか?
現場に医師がいない中で子供たちの健康管理を担う部分にはやりがいとともに大きな責任を感じています。また、子供を中心に、お父さんお母さんやお子さんの通っている病院の主治医の先生の間でのコミュニケーションはいつも模索しています。難しくて悩んだ時は管理者のなみさんになどに相談して、お父さんお母さんとも情報共有しながら、支援の方針を決めるようにしています。
例えば投薬のときも、大きな方針は決まっているのですが、細かいタイミングや量に関しては悩むことがあって。直接主治医とお話できる機会があると良いのですが、なかなか難しいので、受診の時にお父さんお母さんに伝えて、主治医の先生と相談してもらったりしています。
あとは私自身、医療的ケア児の支援について学ばなければならないことがまだまだたくさんあるんですけど、できるだけ色々な方に利用してもらえるように、知識を得るなり、研修を受けるなりして、受け入れられる幅をあまり狭めたくないな、広げたいなといつも思っています。

嬉しかったエピソードがあれば教えてください。
通い初めの頃、お母さん以外の人と接することにすごく抵抗を示していた子がいました。当初はケアの際も安全確保が必要なほどでした。それが去年の夏に水遊びに参加したぐらいから変わり始めて。すごく表情が豊かになり、保育者の膝によじよじ登って甘える姿があったり、他のお友達のところに行ったり。周りと関わる姿がすごく出てくるようになって、とても嬉しかったのが印象に残っています。

仕事をする上で心がけていることはありますか?
これは看護の職場の時も一緒なのですが、利用されているお子さんや利用されている患者さんの前では自分の感情、とくに緊張などの負の感情を表に出さないように心がけています。ケアの際にも自分が緊張して不安に思ってしまうと子供はもっと不安になってしまうので。
医療的ケアが必要な子を家で見るのはすごく大変なことだと思うので、安心してお子さんを預けていただいて、お父さんやお母さんの時間が少しでも作ってもらえたらと思っています。
最後に、「えほんの木」の利用を検討している方や働くことを検討している方にメッセージをお願いします
利用を考えている方に向けては、ご家庭で不安に思っていることやお悩みを、遠慮なく伝えてもいただきたいです。子供の成長を一緒にお手伝いできるよう支援に取り組むので、安心して利用してください。
「えほんの木」で働いてみようかなと思う方に向けては、子供のケアはもちろん、そのお母さんたちの支援も視野に入れて一緒に仕事に取り組めるとすこぐ嬉しいです。仲間を増やしたいと思っているので、よろしくお願いします。
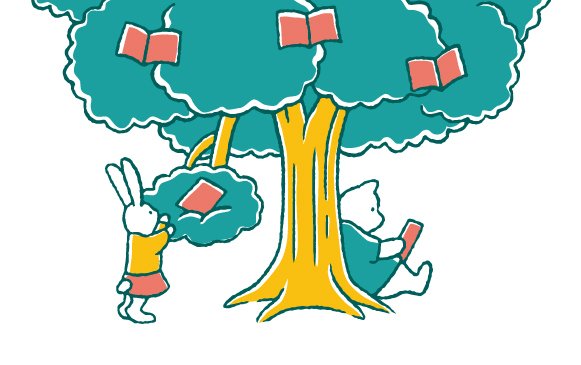
もしこの記事が参考になったと感じていただけたら、ぜひ「スキ!」や応援コメントをいただけると嬉しいです。みなさまの応援が、今後の投稿の励みになります!
