
福北ゆたか線という「ブランド」形成と、都市間ライトレールの「元祖」の今
川西池田から
普通|木津
サハ321-32
朝の明けるのが若干遅くなったか。

福知山線の「初電」に乗車。
街からの「初電」は昨夜帰れなかった客が一旦帰るため、あるいは深夜営業の従業員が「退勤」するため、なんて生活臭漂うイメージがあるが「街へ」行く初電は純粋に通勤客だけなので至ってドライだ。4時59分、発車。
伊丹、猪名寺と進むも席が埋まることもなく尼崎着。僕はここで降りたが、列車は東西線へ進む。
尼崎から
普通|京都
モハ207-515

先程の福知山線の列車とは大違いで、こちらは立ち客も多く既にもうラッシュが始まっているようだ。
31分、発車。

淀川を渡り39分、大阪着。
かなりの客が降りたが車内は相変わらずのラッシュ状態。

再び淀川を渡り44分、新大阪着。
これだけ乗っていれば蒸し暑さもあろうものだが、強力な冷房に救われた。
新大阪から
ひかり591号|博多
786-4212
(「乗ってみました」に記録)
博多から
普通|直方
クハ816-1602

新幹線から篠栗線に乗り換え。
仕事電話を数本済ませ、この記事向けにカットを撮ったりしてもまだ余裕があった。
国鉄篠栗線として独立していた頃は、本数も少なくそれこそ1本乗り逃がしたら・・・だったが、フリークエントが組まれた「福北ゆたか線」の一員になってからは安心感が出来たのも事実だ。

柚原で博多行きと行き違い。
かつて鹿児島本線で活躍していた813系だ。
原町、長者原、門松と進んで猛然と加速。なかなかキビキビと走らせていて気持ちがいい。

59分、篠栗着。
この駅始発の博多行きが発車待ちをしていた。ここまでが博多都市圏ということなのか。

国道201号八木山バイパスを見ながら筑前山手・城戸南蔵院前を過ぎ、比較的長い篠栗トンネルへ。
篠栗までは古くに開通していたが、桂川まではトンネル技術が熟成する昭和40年代まで待たなければいけなかった。

10時10分、九郎原着。筑豊に入った。
心なしか、暑さもパワーアップしたような感じだ。
筑前大分で2回目の行き違いをし、

ひょろひょろとした線路(筑豊本線)がやってきて桂川着。
このひょろひょろした線路も、かつては石炭列車が行き交う「大幹線」だったんだがなぁ…福北ゆたか線として整備されたのが篠栗線だった訳で、桂川から南の「切り捨てられた」感がひしひしと伝わる。

21分、天道着。仕事のため一旦離脱。
天道から
普通|新飯塚
クハ817-2027
用事を1件済ませ、天道駅へ舞い戻る。

来たのは新飯塚行き…
本当は直方あたりまで行きたかったのだが、暑い中に目的の列車までガマンするよりはマシなので、とりあえず乗る。

817系の2000番台という、比較的新しい車両だ。
左(銀色)は初期車、右の白いのが2000番台になる。

違いはクロスとロングの入り混じる初期車に対して、オールロングなのが2000番台車だ。
ま、冷房が効いていればどういう形式だっていい(笑)
新飯塚から
快速|直方
クモハ813-118

やっと目的の列車を捕まえた。
天道に向かう列車に乗っていた時、813系ばかりとすれ違ってて「乗れないかな…」と思っていたところだった。

JR九州といえば、この「豹柄シート」だろう。
色々な意見があると思われるが、逆に通勤電車にこんな奇抜なデザインのモケットを入れるかって思わせる「意外さ」に、何となく惹かれる。
筑豊らしい風景といえば、ぼた山と田畑が続く…なんだろうけど、僕は不幸にもそういった時代の筑豊の風景を見ていない。

今見ているのは、福岡・北九州のベットタウンとなった筑豊の風景だ。

でも、遠賀川を渡る直前なんかは「これが客車列車だったら壮観だろうな」と思わせるシチュエーションだったし、

小竹手前の幸袋線の廃線跡を見たりすると「筑豊に来たんだなぁ」と、ちょっと感慨に浸れる。

快速らしく次の勝野は通過し、54分、直方着。
仕事で途中離脱したが、総じて便利な福北ゆたか線だった。興味深かったのは、大掛かりな施設更新はなるべく抑えて現行の施設をフルに活用し、都市間連絡路線を形成しているという点。
その結果、筑豊本線を「分断」する結果にはなったものの、JR九州が福北ゆたか線という「ブランド」を本気で確立しようとしている態度の「発露」であるとするなら、致し方ないのかもしれない。
筑鉄直方から
普通|黒崎駅前
3007B
「ちくてつ」は何回か乗っているが、記録付けの意味で再乗車。

ホームで「照焼き」になった気分で待ってたら、黒崎駅前行きが到着。
2両編成に客は3人。
12時40分、発車。

すぐに遠賀川を渡る。
短い編成の電車には途方もない長さに思える。

2つ目の遠賀野で貸切状態に…納涼電車あたりだと団体貸切で「独占」することはあるけれど、たまたま乗った定期列車では初めてだ。
まあ、北九州市に入った次の木屋瀬ですぐ客が乗ってきたので「独占」時間は、僅か数分だったが。

50分、楠橋。
車庫があるせいか時刻表を見ているとこの電停止まりという電車が多い。
特徴的なのは各電停から乗ってきた客の大半が着席せず、まずはエンド側(最後尾側)の出口にある運賃箱で交通系ICカードにチャージしているという事。
バスならば降車時に…というパターンをよく見かけるが、ちくてつのそれは「事前チャージ」が徹底しているようで降車がスムーズだ。
客がセルフでやっているし手慣れたものだから、もはやこの沿線利用者の「特性」と言ってもよさそうだ。

56分、筑豊中間。
電停名にわざわざ「筑豊」がつくあたり、JRの中間駅と「区別」するためか。
ちょっとした秘境感ある西山を過ぎて、

13時4分、永犬丸。「えいのまる」と読むのだが、難読だし何かすごい「謂れ」がありそうで惹かれる。
終点にほど近い萩原で学生がわんさと乗ってくる。期末テスト期間だろうか。

16分、黒崎駅前。終点に着いた。
路面区間はなくすべて専用軌道を走る「ちくてつ」だが、昨今その存在をもてはやされている「宇都宮ライトレール」よりも遥か昔に、すでにライトレール的なサービスを北九州と筑豊の都市間連絡で行っていた、という事実に改めて驚かされる。
戸畑から
特急ソニック40号|博多
(車番メモ失念)
用務先で色々あったので、ちょっと発散の意味で特急課金。

やってきたのは特急「ソニック40号」883系。
青色メタリックの車体はやはり渋い。
3分遅れの47分に発車。

うーん、やはり通過するときの景色の「吹っ飛び方」が気持ちいいな…

指定席デッキに立ち客がいるのだが、車掌は検札に来ないし扱いとしてはどうなるのか…

57分、折尾発車。
しかし折尾も変わったよなぁ…感覚的にはほんの数年前まで蒸機時代の煤けた雰囲気の残る、駅や街並みだったような気がする。

海老津を過ぎたあたりで日の傾きを感じる。とは言ってもまだまだ明るさは夏のそれのままだ。
城山トンネルの中で車内から大いびきが…まあ、行楽地発の列車なので観光疲れがあるのだろうけど、それにしてもよく響くなぁ…

17時7分、赤間着。
ポツリポツリと降りていく。北九州エリアであった乗車客は見かけなかった。

城山トンネルを抜けた事で北九州から福岡都市圏に入ったのだが、ここは宗像エリア。
博多や香椎のような都市然としたものはなく、まだまだ緑は多い。
東郷〜東福間の撮影地として有名な大カーブを、ゆるゆると車体を傾けながら越えていく。先日乗った「やくも」にも付いていた、制御振り子の機構が動作していてその威力はなかなかのものだ。
ぼんやりと外を眺めていたら、唐突に到着案内が流れた。そうだ、香椎にも停まるのだった…
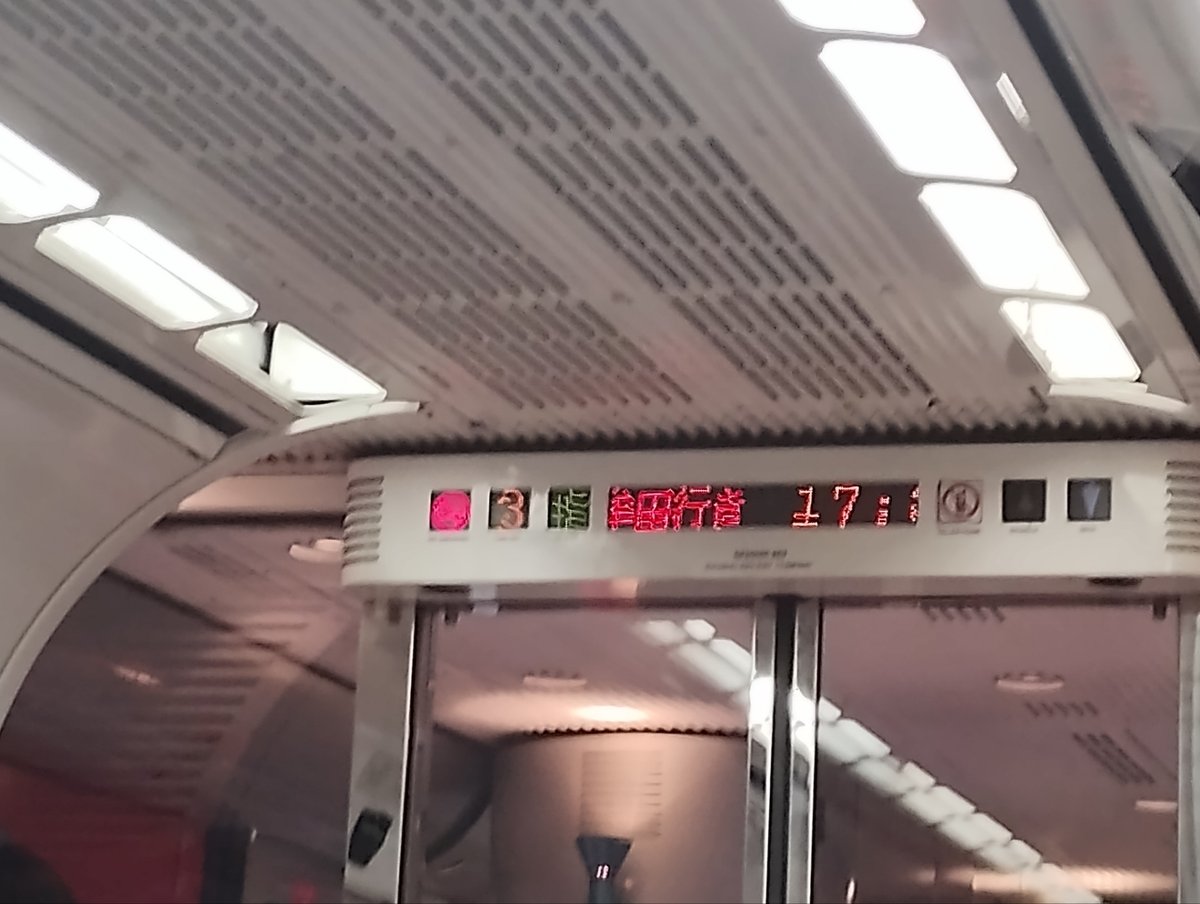
乗り換え列車の行先と発車時刻がデッキ上のLED表示器に流れる。さらに車掌からの案内もあって、列車廻りの案内を「WESTER」に半ば「投げている」地元のJRに比べると、なかなか徹底している。
21分、香椎着。やはりパラパラとしか降りていない。ほとんど博多へ行く客ばかりということか。

九州でも随一の規模を誇った香椎操車場も数本のレールを残すのみで、あとはマンションに生まれ変わった。その一角に出来た千早を通過・・・

29分、博多着。あっという間だった。
【令和6年7月9日乗車】
【完乗】JR西日本 山陽新幹線
JR九州 篠栗線
筑豊電気鉄道 筑豊電気鉄道線
JR西日本 福知山線 川西池田~尼崎 11.0km
東海道本線 尼崎~新大阪 11.5km
山陽新幹線 新大阪~博多 553.7km
JR九州 鹿児島本線 戸畑~博多 61.0km
篠栗線 吉塚~桂川 25.1km
筑豊本線 桂川~直方 20.5km
筑豊電気鉄道 筑豊電気鉄道線 筑鉄直方~黒崎駅前 16.0km
小計 698.8km
