
サイエンスとアートから、「分かる」とは何かを考えよう。認識論を刷新する哲学者キャサリン・Z・エルギン入門
認識論と呼ばれる哲学ジャンルでは、知るとは何か、分かるとは何かが議論されきた。これまで科学にフォーカスが当てられてきたが、近年、芸術を創り・鑑賞するときに起こる私たちの認識の変化にも注目が集まっている。その先導を行くのが、サイエンスとアートの認識を同時に研究する稀有な哲学者、キャサリン・Z・エルギン。彼女の魅力的な思想を紹介しよう。文=難波優輝
人生を変えるような芸術作品に出会ったとき、あるいは、科学的シミュレーションを操作したとき、意外にも似た感動が訪れたことはないでしょうか? 「世界をより分かった」と感じるようなあの感動が。私たちが何かを「分かる」とはどういうことか、サイエンスとアートを通じて世界をより深く理解するとは何か。こうした問いを現在進行系で考えているキャサリン・Z・エルギンという哲学者がいます。
彼女の哲学は、本邦ではほとんど紹介されていません。しかし、ビジネスでは「SFプロトタイピング」といったアーティスティックな世界の見方が重視され、同時に未来を考えるためのサイエンスの知見がいっそう重視される現在、サイエンスとアートが可能にする理解とは何か? そもそも理解とは何か? を哲学する彼女の思考は誰にとっても見逃せないものになっていくでしょう。
こうしたモチベーションから、2022年度哲学若手研究者フォーラムにて発表した「サイエンスとアートは世界をどう認識するのか?––––True Enoughを中心にキャサリン・Z・エルギンの認識論を紹介する」の発表原稿を配布中です。このページでは、発表の内容を再録します。

特集=CATHERINE Z. ELGIN サイエンスとアートは世界をどう認識するのか?
イントロダクション
私たちはどんな風にして世界を理解することができるのだろうか?
この根本的なクエスチョンを考えるのが認識論だとすれば、科学の営みを分析するだけではなく、芸術によって生まれる理解も扱わなければならない。なぜなら、芸術作品・自然を鑑賞しているときにも、私たちは深い人生の理解に達したり、人生の悩みに対するヒントを得たりするからだ。
そんな洞察に導かれ、記号論と認識論をはじめたのが、アメリカの美学者、キャサリン・Z・エルギン。本発表では、彼女の最新刊、True Enoughを中心に、「理解」「例示」「反照的均衡」「社会認識論」の4つのキーワードから、エルギンの思考をあらましを紹介する。
エルギンの認識論の紹介は、管見の限り本邦ではほとんどなされていない(伊勢田(2006)や谷川(2021)で取り上げられている)。エルギンの思考のおもしろさやその広い射程を可能な限り伝えられればと思う。なお、本発表は、発表資料の形式として雑誌的な編集を行うとどうなるかの実験でもある。
本発表では次の略号を用いる。
CJ Considered Judgment(1996)
TE True Enough(2017)記載のない限り、引用の強調は発表者による。
Border Crosser|認識論と美学を横断する
キャサリン・Z・エルギン。彼女の名は現代哲学における重要度にも関わらず、とくにこの日本では知られていない。ウィトゲンシュタイン研究からキャリアをスタートし、いまや認識論の大家となった彼女の研究の軌跡を辿ろう。

認識論と美学を横断する
1948年生まれ。認識論者。美学者。博士論文提出後、グッドマンと研究を始めたエルギンは、最初の単著、①With Reference to Reference(1983)にて、ネルソン・グッドマンの記号論を彫琢し、続く、②Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences(1988)にて、グッドマンと共著で芸術と認識論の関係を論じている。この2冊からも、エルギンはグッドマン哲学のよき理解者でありながら、記号論と認識論に関してオリジナルな思考を行っていることが伺える。
新たな展開をみせる③Considered Judgment(1996)のなかでは、反照的均衡を合理的な認識の基礎におき、基礎づけ主義でも規でも規則主義でもない新しい認識論的立場を模索している。④Between the Absolute and the Arbitrary(1997)では、メタファー論や記号論とともに事実の構築性や信念に関する議論を行っている。最新刊である⑤True Enough (2017)では、科学は「適切な誤り」を反照的均衡の中で提示する営みであるとして、ダンスやフィクションの認識論などを取り上げることで、科学的認識と芸術的認識の相同性についても語っている。
一言で言えば、エルギンの認識論は、認識論と美学の越境だ。認識論がこれまで扱ってこなかった芸術の認識論に美学者として真正面から取り組み、同時に、美学が扱いそこねていたモデルや思考実験、認識における情動の価値を明らかにしようとする。
とはいえ、エルギンとグッドマンならこう言うだろう。いや、美学こそが認識論なのだ、と(cf. グッドマン&エルギン 2001, ch.1)。
エルギンの認識論のトピックは幅広いが、本稿では、そのエッセンスを「理解」「例示」「反照的均衡」「社会認識論」の4つから紹介する。
Understanding|知識から理解へ?
知識だけが「知識」の名に値するのだろうか? 認識論における知識から理解へのフォーカスシフトを企てるエルギンの試み。

知識から理解へ
もし現在の認識論で論じられているような知識(e.g., 正当化された真なる信念)だけが「知識」の名に値するとしたら、地図や図や絵画や音楽やダンスや映画が届けてくれる洞察は、せいぜい知識の補助にはなっても「知識」の名に値しない。
もちろん、隠喩や詩や文学が与えてくれる気づきもまた、認識論に居場所はほとんどなくなってしまう。
だが、私たちは科学的な知識と同じくらい、映画や音楽に触れて何か重要なことに気づくのではないだろうか? だとしたら、こうした非言語的で非命題的な表象たちがもたらす認識的役割を論ずるための場所を認識論につくるべきではないだろうか? そのための概念が「理解」である(cf. グッドマン&エルギン 2001, 5-6)。
知識は本当に分かることの核心なのだろうか? 私たちが何かを「分かった!」と感じたとき、私たちは正当化された真なる信念に辿り着いているのだろうか。
エルギンはNOと答える。私たちが何かを分かるというとき、私たちは何かを「理解(understand)」しているのだ。そして、知識は理解の一つのあり方なのだ。エルギンの立場を強調してこう言ってみよう。「理解第一主義」。
では理解とは何だろうか? エルギンによれば、理解とは①「対象のある(objectual)」②「体系的で」③「非叙実的な(non-factual)」④「ノウハウ(know-how)」である(TE, ch.3)。
まず理解とは①対象を②体系的に分かっていることである。「東京の地下鉄を理解している」「自転車を理解している」「進化論を理解している」といった「対象」について理解が成立する。かつ、単一の孤独な命題ではなく、命題、概念、行為、出来事の集まりといった一まとまりの信念の集まりについて分かっていることが理解だ。例えば、東京の地下鉄を深く理解している人は、非公式の乗り換え益について理解しているし、いつ電車が混みそうかも分かっている。もしかしたら一番安く済む乗り継ぎの仕方も分かっているかもしれない。逆に、路線図だけは知っているが、駅間の遠さや、最短ルートを知らない人は、東京の地下鉄をあまり理解していない。
エルギンはギルバート・ライルを引いて、④理解とはノウハウであると言う。地下鉄を理解している人は地下鉄をうまく利用できるし、使い方をアドバイスできる。自転車を理解している人は、身体の使い方だけでなく、整備の仕方や、おすすめのパーツショップも知っているかもしれない。進化論といった物事の枠組み=理論を理解している人は、それをうまく使って様々な現象を体系的に整理し、理論に基づき未来の出来事を予測したりできる(cf. TE, 44-50)。
これらの特徴づけは説得的だが、それほど意外ではないかもしれない。また、①、②、④ならば、命題的知識でも置換できるかもしれない。
しかし、エルギンは、知識概念に挑戦的な議論を始める。まず、彼女は、科学は知識を積み上げる営みでもなく、たんにパラダイム内でのルールに従ったゲームでもないと言う(cf. CJ, ch.1-3)。ではどんな営みか? 彼女は、正しい信念を一つずつ「確信(convict)」していくのではなく、信じられる前提をとりあえず「受容(accept)」し、それらを改訂していくことで、少しずつ進んでいく営みとして科学を特徴づけている。
そうした漸進的認識活動を特徴づけるためにエルギンが主張するのは、③理解の非叙実性である。まず、理解が叙実的(factive)であるとは、認識論における理解の議論の主要なプレイヤーの一人であるクヴァンヴィクが言うように、理解の要素が「事実である」ということだ。
たとえば、政治を理解するということは、政治についての信念をもつということであり〔……〕、これらの信念が真であることを必要とする。(Kvanvig 2003, 191)。
とはいえ、理解の構成要素の信念がすべて真でなければならないとすると困ったことになる。なぜなら、理解は体系的なものであるため、一つでも偽なる信念がある対象についての信念の体系に混じっていると、それだけでその対象を理解していないということになってしまう。そこで、彼は、体系の中心的な信念さえ真であればよいとする(Kvanvig 2003, 201f.)。
しかし、エルギンは、理解の中心的な信念でさえ真である必要はないと言う。なぜなら、科学的認識実践には、第一に、中心的信念を置き換えながら段階的に理解が進展する場合にも「理解」といえるからだ(TE, 37)。例えば、プトレイマイオスは「星々は真円の軌道を描く」という真ではない中心的信念を持っていた。しかし、彼はそれ以前の人々より星々の運動について理解していたと言える。第二に、科学的実践中心的信念に理想化を含むケースがあるからだ。エルギンはこう言う。
わたしは、効果的な理想化は適切な誤り(felicitous falsehoods)だと主張している。それらにちょうど対応するものが世界にはないため、記述としては誤りであるが、識別困難だったり識別不可能だったりする事実の事柄に認識的なアクセスを与えるという点において、それらは適切なのだ。理想化は、事実の繊細な事柄や、曖昧な事柄を強調するために特別に設計されたフィクションである。(Elgin 2007, 39)強調は発表者。
「適切な誤り」とは、太陽系の運動モデルであったり、ゲーム理論であったり、pV=nRTであったりというような、理論、方程式、モデル、シミュレーションなどを指す。これらは厳密には「誤りである」。しかし、科学者たちはこうした間違いなしでは世界を理解できない。
私は、認識論的主体が適切な誤りを信じているとか、信じるべきだとは主張しない。現役の科学者は、自分たちのモデルが正確でないことを十分承知している。それでも、彼らはそのモデルを受容(accept)できると考えている。私の考えでは、認識論的受容性とは信念の問題ではない。ある命題を受容するということは、認識的な目的のために推論や行動を行うとき、その命題を進んで使うことができることである。(Elgin 2022a, 1579)
科学は、適切な誤りを理解の中心的信念として受容し、理論を元にデータを収集し、データから理論を修正していく振り子のような実践であり、知識を積み上げるだけでも、パラダイムに従うだけでもない動的な認識活動なのだ。谷川(2021)が批判するように、エルギンの理解説は議論の的になるが、科学的認識活動の中核にフィクション的対象が場を占めているという主張こそ、エルギンの認識論の土台をなしている。
例示|記号的認識論へ、ようこそ
モデル、フィクション、ダンス……これらすべての認識的価値をある一つの記号的機能から説明できる……。その名も例示。

認識論と記号論
「すべてのモデルは間違っている。ただいくつかが有用なだけである」と統計学の大家ジョージ・E・P・ボックスは言った。
巧妙に選ばれた簡略化されたモデルによって、驚くほど有用な近似が得られることがよくある。例えば、「理想」気体の圧力P、体積V、温度Tを定数Rを介して関係付けるPV=nRTの法則は、実際の気体に対して正確に正しいわけではないが、有用な近似を与えることが多く、さらにその構造は、気体分子の挙動に関する物理的パースペクティブに由来しているために有益な情報を与えうる。
このようなモデルに対して「モデルは真か?」と問う必要はない——もし「真」が「完全なる真」を意味するとしたら、答えは完全に「NO」である。次の問いだけが重要なのだ。「そのモデルは有用か?」。(Box 1979)
モデルは、「間違っているが正しい」のではなく、「間違っているから正しい」。もし気体の振る舞いについてのデータに完全に正確に従うモデルを作ったとすれば、複雑過ぎて、人間の手には負えなくない。それだけでなく完全に正しいモデルでは気体の圧力と体積と温度の関係を図式的に理解できない。例えば、グラフ化は難しくなる。現実の事象をそのまま集めてきただけでは、私たちは現実をうまく理解できない。
すべての物体は無限に多くの性質を持ち、無限に多くの関係性を持っている。これらの大部分は何の関心も惹かない。いくつかの興味深く重要なものは、字義通りの語彙によってきちんとラベルづけされている。それらは直接、字義通りに表現することができる。しかし、その他のものは、意味論的にしるしづけられていない。例えば、ニュートン以前は、リンゴが落ちること、潮の満ち引きが変化すること、月が軌道を回ることに共通する性質はしるしづけられていなかったのである。このような性質や関係を認識しようとすれば、間接的に示す必要がある。その方法の一つが、それらを表す対象を、かのように的(as-if-ishly)に特徴づけることだ。気体分子が球体であるかのように〔……〕、あるいは、月が地球に向かって落下しているかのように。(Elgin 2022a, 20)
モデルは世界をしるしづける。こうしたしるしづけの力が「例示」という概念から説明される。
例示とは、記号がそれ自身の特徴のいくつかを表示する表示様式である。例示は特徴を強調し、際立たせ、顕在化させる。例示は、あるサンプルとそれがサンプルとなるものとの関係である。モデルは例示するもの(exemplars)だ。絵の具のサンプルのように、特徴のいくつかを際立たせるように設計されている。これらの特徴は、単項か多項か、静的か動的か、抽象的か具体的か、などである。例えば、ハーディー・ワインベルクモデルは、個体数を無限として表象することで、対立遺伝子の再分配がランダムな揺らぎに影響されないという側面を見せる。例示は選択的である。ある特徴を強調するために、例示は他の特徴を周縁化したり、隠蔽したりする。(Elgin 2022a, 17)
例示はこれまで隠れていた特徴を際立たせる。例えば、潜伏期間や発症期間、基本再生産数を変数として持つ感染症の流行モデルSEIRは、これらの変数によって現実を大胆に切り取る。感染症がいかに拡がるのか、数理的振る舞いが強調され、際立たせられる。感染対策に役立つこのモデルは適切であるが、しかし、現実そのものの記述としては誤りである。エルギンは、有用なモデルを「適切な誤り」と呼び、それが理解の中核をなすがゆえに、理解の非叙実性を擁護しているのだ。
ここからフィクションの認識的価値も明らかになる。『高慢と偏見』は、男女がどのように互いの好意に気づき、関係性を構築していくのかの一つの思考実験であり、現実には存在しない状況を描きながら、人間間の行動や情動の動きのある種のシミュレーションモデルとなっているのだ。
ダンスは、人間の身体の動きの無数の可能性を実際に動いてみせることで例示する。私たちが普段の生活では見過ごしていた身体の動きを強調し、際立たせることで、私たちに身体の美しさや、人体の能力を知覚させる(TE, ch.10)。
モデル、フィクション、ダンスはいずれも、例示の力を用いて、世界の性質を強調することで、世界についての新たな気づきをもたらし、理解の助けとなる。モデルが気体の運動を、フィクションが他者の心を、ダンスが身体の可能性を、私たちに理解させる。
反照的均衡|新しいバージョン
ロールズの『正義論』で有名になり、いまや倫理・政治・法哲学の基本ワードとなった「反照的均衡」。実はグッドマンが源流だと知っていただろうか? その後継者エルギンはこの考えをあらゆる認識に広げているのだ。

認識論的な反照的均衡入門
「人は見た目が9割」。ときに差別的な主張にも転化しうるこの主張を私は信じはしないが、初めて会った人の「第一印象」はとても重要であることは、あなたも納得してくれるはずだ。なぜなら、それは相手を理解するために欠かせない認識的な役割を持っているからだ。
第一印象はある種の理論である。ここで理論とは、複数の信念を正当化する信念だ(cf. Beisbart&Betz&Brun 2021)。第一印象を抱いた瞬間、私達はその人がどんな振る舞いをするのか、複数の予想を立てられるようになる。その多くは間違っているかもしれない。
あなたは後輩とご飯を食べに行くことになった。後輩は身体の線が細い。あなたの弟に似ている。ふむ。こういう人はあまりご飯を食べない。だから軽食を食べることにしようか。しかし、一緒にご飯を食べていると、来た皿を次々と平らげ、新しい料理を注文していく。
あなたは第一印象=理論を修正する。なるほど、線が細くともよく食べる人もいるのだ。
反照的均衡(reflective equilibrium)はジョン・ロールズの『正義論』において提示され、特に倫理学や政治哲学の分野で普及しているが、エルギンはそれを認識的活動の中心に据え付ける。というより、反照的均衡の営みこそが私たちの認識的実践のプロセスそのものなのである。
反照的均衡のプロセスに登場するのは「まず支持できるコミットメント(initially tenable commitment)」と「裁定(adjudication)」である。まず私たちは何らかの前提にコミットする。例えば、「線が細い人は少食である」という理論にコミットする。こうしたものを「まず支持できるコミットメント」と呼ぶ。これらは、偏見でも、データでも、理論でも、直感でも直観でも、非命題的な表象でもなんでもよい。どれだけ不正確であっても、次の思考や行動の動因となるためのガソリンとなる。
このコミットメントに基づいて、推論したり、行動する。例えば、〈軽食を食べることにする〉。行動の結果、ほぼ必ず、まず支持できるコミットメントでは説明できない出来事を目の当たりにしたり、データとして得る。例えば、〈線が細い人が大食いである〉。そこで、私たちはまず支持できるコミットメントの支持できない部分を捨て、新しいコミットメントを採用する取捨選択を行う、つまり、裁定する。〈線が細い人の中にも大食いの人がいる〉。こうして一つの反照的均衡に至る(TE, ch.4)。
反照的均衡のプロセスから認識的実践を眺めると、私たちがどのように理解を深めていくのか、高い解像度で捉えられるようになる。こうした反照的均衡による認識的実践の理解はエルギンのユニークな議論なのだが、類似した立場もないわけではない。名前が上がるのは「整合主義(coherentism)」だ。整合主義とは、信念体系のそれぞれの信念が矛盾しないように体系構築を行うことで信念体系の正当化を行える、とする認識論の立場である。整合主義には3 つの批判がなされるが、反照的均衡モデルはこれらをうまく回避できるのだ。
1つ目は、孤立問題である。可能な限り狭く整合させなければならない信念を選ぶことで楽に整合させることができる。2つ目は、選択問題である。「神は存在する」「神は存在しない」といった矛盾した2つの信念を正当化しうる整合的な信念体系はいくらでも作ることができてしまう。3つ目はメタ正当化問題である。なぜ整合すると信念体系が正当化されるのだろうか(上枝 2020, 128)。
反照的均衡モデルの応答はこうだ。まず、整合させるべき信念は命題レベルだけでなく、認識的手続きや基準、統計的確度や手法といったメタレベルの信念も含まれる。そのため、整合は容易に行えない。そして、私たちはふつうまず支持できるコミットメントを簡単に棄却しない。そのため、整合の都合が悪くなっても最初のコミットメントを捨て去ることはなく、恣意的な整合を許さないために孤立問題に答えうる(TE, 84-85)。
選択問題に関しては、たとえ最終的に誤った結論に達する体系であっても、それぞれの反照的均衡のプロセスの適切性は多様であるため、矛盾する2つの信念を正当化する整合的な信念体系が無数に存在しうることは、それらが適切に反照的均衡のプロセスを踏んでさえいれば問題ではないといえる(cf. TE, 85-86)。
メタ正当化問題に対し、反照的均衡と独立な何か、もし「真理」が反照的均衡を正当化するなら、真理の正当化能力の正当化が必要になる。エルギンは、正当化の基準さえも反照的均衡の中でしか決定できないとし、メタ正当化問題そのものを棄却しているようだ(cf. TE, 89-90)。
ではなぜエルギンは、反照的均衡モデルを認識的実践のモデルとして採用できるのだろうか? それは、エルギンが理解の深化を認識的目的として設定しているからだろう。理解を深めるためには対象の体系的で非叙実的なノウハウを深める必要がある。これを深めるためのプロセスとして反照的均衡のプロセスが認識的実践のモデルとしてもっとも適合している。ゆえに、エルギンは反照的均衡モデルを認識的実践のモデルとしてみなす反照的均衡に至ったといえるのではないだろうか? これはかなり独特なエルギンの理解かもしれず、多くの議論が必要だが、今の所もっとも整合的な解釈だと考えている。
社会認識論|すぐに結論に至るなんて、つまらないじゃないか?
なぜ私たちは集まって喋るのだろうか? それは私たちの偏りを混ぜ合わせることで世界のよりよい理解に到れるからだ。エルギンの認識論は、認識を行う私たちの態度の違いにまで光を当てる。
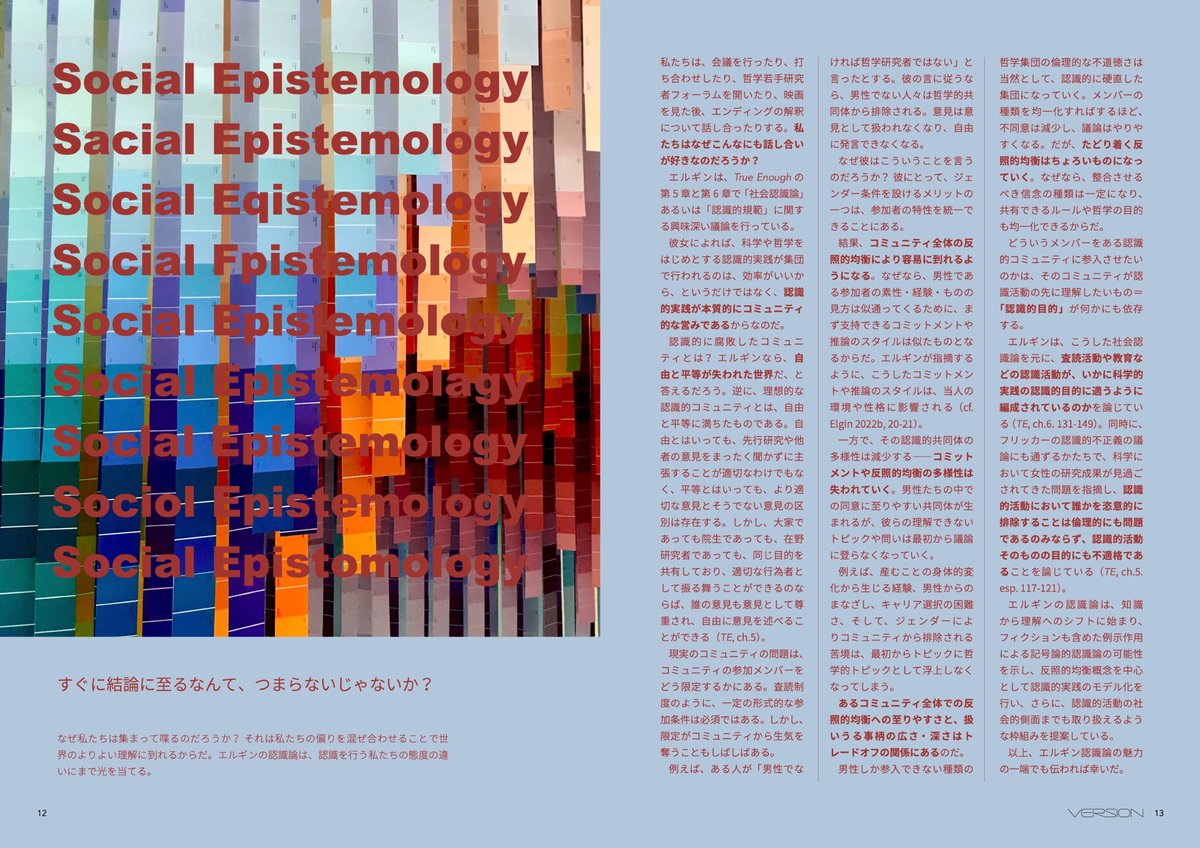
社会認識論
私たちは、会議を行ったり、打ち合わせしたり、哲学若手研究者フォーラムを開いたり、映画を見た後、エンディングの解釈について話し合ったりする。私たちはなぜこんなにも話し合いが好きなのだろうか?
エルギンは、True Enoughの第5章と第6章で「社会認識論」あるいは「認識的規範」に関する興味深い議論を行っている。
彼女によれば、科学や哲学をはじめとする認識的実践が集団で行われるのは、効率がいいから、というだけではなく、認識的実践が本質的にコミュニティ的な営みであるからなのだ。
認識的に腐敗したコミュニティとは? エルギンなら、自由と平等が失われた世界だ、と答えるだろう。逆に、理想的な認識的コミュニティとは、自由と平等に満ちたものである。自由とはいっても、先行研究や他者の意見をまったく聞かずに主張することが適切なわけでもなく、平等とはいっても、より適切な意見とそうでない意見の区別は存在する。しかし、大家であっても院生であっても、在野研究者であっても、同じ目的を共有しており、適切な行為者として振る舞うことができるのならば、誰の意見も意見として尊重され、自由に意見を述べることができる(TE, ch.5)。
現実のコミュニティの問題は、コミュニティの参加メンバーをどう限定するかにある。査読制度のように、一定の形式的な参加条件は必須ではある。しかし、限定がコミュニティから生気を奪うこともしばしばある。
例えば、ある人が「男性でなければ哲学研究者ではない」と言ったとする。彼の言に従うなら、男性でない人々は哲学的共同体から排除される。意見は意見として扱われなくなり、自由に発言できなくなる。
なぜ彼はこういうことを言うのだろうか? 彼にとって、ジェンダー条件を設けるメリットの一つは、参加者の特性を統一できることにある。
結果、コミュニティ全体の反照的均衡により容易に到れるようになる。なぜなら、男性である参加者の素性・経験・ものの見方は似通ってくるために、まず支持できるコミットメントや推論のスタイルは似たものとなるからだ。エルギンが指摘するように、こうしたコミットメントや推論のスタイルは、当人の環境や性格に影響される(cf. Elgin 2022b, 20-21)。
一方で、その認識的共同体の多様性は減少する——コミットメントや反照的均衡の多様性は失われていく。男性たちの中での同意に至りやすい共同体が生まれるが、彼らの理解できないトピックや問いは最初から議論に登らなくなっていく。
例えば、産むことの身体的変化から生じる経験、男性からのまなざし、キャリア選択の困難さ、そして、ジェンダーによりコミュニティから排除される苦境は、最初からトピックに哲学的トピックとして浮上しなくなってしまう。
あるコミュニティ全体での反照的均衡への至りやすさと、扱いうる事柄の広さ・深さはトレードオフの関係にあるのだ。
男性しか参入できない種類の哲学集団の倫理的な不道徳さは当然として、認識的に硬直した集団になっていく。メンバーの種類を均一化すればするほど、不同意は減少し、議論はやりやすくなる。だが、たどり着く反照的均衡はちょろいものになっていく。なぜなら、整合させるべき信念の種類は一定になり、共有できるルールや哲学の目的も均一化できるからだ。
どういうメンバーをある認識的コミュニティに参入させたいのかは、そのコミュニティが認識活動の先に理解したいもの=「認識的目的」が何かにも依存する。
エルギンは、こうした社会認識論を元に、査読活動や教育などの認識活動が、いかに科学的実践の認識的目的に適うように編成されているのかを論じている(TE, ch.6. 131-149)。同時に、フリッカーの認識的不正義の議論にも通ずるかたちで、科学において女性の研究成果が見過ごされてきた問題を指摘し、認識的活動において誰かを恣意的に排除することは倫理的にも問題であるのみならず、認識的活動そのものの目的にも不適格であることを論じている(TE, ch.5. esp. 117-121)。
エルギンの認識論は、知識から理解へのシフトに始まり、フィクションも含めた例示作用による記号論的認識論の可能性を示し、反照的均衡概念を中心として認識的実践のモデル化を行い、さらに、認識的活動の社会的側面までも取り扱えるような枠組みを提案している。以上、エルギン認識論の魅力の一端でも伝われば幸いだ。
ブックガイド|エルギンともっと先に行く
エルギンの枠組みを使ってどんなことが考えられるだろうか。その応用の可能性を少しだけ提案してみたい。

ブックガイド
シミュレーション
ビデオゲームはしばしばシミュレーションの観点から語られる。都市開発を再現してみたり、存在しない世界の法則の中で遊んでみたり。虚実のあいだにあるゲームナラデハのシミュレーションはどんな認識的価値を持っているのか? ゲームのおもしろさは、まさに世界の理解を独特な仕方で促進するところにあるのかもしれない。
『ビデオゲームの美学』松永伸司、慶応義塾大学出版会2019
不同意
「哲学者は考えうる限りあらゆる立場に対して不同意できる」とエルギンは近著「哲学における不同意」で指摘している。社会認識論における不同意のトピックは近年注目を浴びている。なぜ研究者たちは、とくに哲学者たちは、同意にいたらないのか? なぜ私たちは説得的な主張を聞いても、そう簡単には自分の立場を変えられないのか? 不同意はむしろ理解に役立つのだとしたら?
「認識的不同意をめぐる論争」萬屋博喜『哲学の探求』2019
感情
感情は排除すべきノイズだろうか? エルギンはNOと答える。とくにConsidered Judgmentにおいて、感情が果たす認識的役割が論じられている(CJ, ch.4)。感情は、まず支持できるコミットメントの一つとして役立つ、認知的営みに欠かせないピースなのだ。たとえば、赤児を育てる親は我が子の泣き声に不安に「なれる」ために、他人では認識できない微細な変化を聞き分けうる。
『シンボルの哲学』S・R・ランガー、岩波書店2022
スタイル
エルギンは「推論スタイル」という概念を提示している(Elgin 2021b)。同じ証明に対して幾何学的 / 代数的アプローチのどちらかを好むか違いがあるように、好みの推論の仕方があるという。なら「理解のスタイル」もあるかもしれない。世界、自己、他者理解の要因として風土を取り上げた和辻は、気候をガイドに世界理解のスタイルの学を始めようとしたと言えるではないだろうか。
『風土』和辻哲郎、岩波書店 1979
分析 / 大陸
分析哲学者と現代思想の研究者はまったく違う営みをしているようで、どこか似ている部分もある。 両者の同一性と差異は、深めたい認識的目的の違いにあるのではないか? 分析哲学は明確で一貫した体系=理論を提案して、現代思想は極端な理論を提案するとしたら、分析哲学はどちらかといえば科学的な営みに、現代思想はどちらかといえば芸術的な営みに類似していると言えるかもしれない。
『現代思想入門』千葉雅也、講談社2022
Editor's Note
「研究発表とはどうあるべきだろうか?」。この発表資料を作っているときにつねに考えていたことだ。たとえば、テキストを中心とした発表は、議論をていねいに検討してみたり、共有すべき前提を確認したりできる。スライドを用いた発表は、発表者が考えていることの全体像を伝えやすい。でも、もしかしたら研究発表の形式はまだ堀り尽くされていないんじゃないだろうか?
あるべき発表の姿は、発表によってどんな体験を生み出したいかから考えるべきだろう。議論の細かいポイントを検討したいのか、研究の全体をシェアしたいのか。それとも……。
私にとって研究発表の価値は「こんな研究があるんだ」と研究者に紹介し、トピックについての関心を生みだし、関心を共有する人と出会う場だ。私は哲学研究の流れを創り出してみたい。この目的にぴったりなものといえば、そう「雑誌- ZINE」だ。
というわけで、そうした発見の共有と出会いの場づくりにフォーカスして、研究ZINEを作ってみた。文字だけではない紙面は、新しい例示の可能性を持っているような気がする。ぜひ感想をつぶやいたりしていただけたらうれしい。
こんな研究のつながり方もあるんじゃないか、と霊感を与えてくれたのは、私にとっては他でもなくエルギンであり、このZINEは彼女の認識論の実践でもあると自負している。読んでいただいたあなたにも、エルギンの認識論のおもしろさを発見していただければと思う。
発行にあたって、ZINEの名前をつけてみた。『VERSION』。私がもっとも好きな哲学書『世界制作の方法』からとっている。作業を終えて、私は「哲学ZINE」を作りたくなった。いろいろな研究者やアーティストをお呼びして、対談があったり、企画があったり、表現があったり……無数のバージョンが組み合わさっているような新しい研究や洞察の場としてのZINE。もしかしたら未来にいろいろな『VERSION』を発行することになるかもしれない。あなたに声をかけるかもしれない。そのときはよろしくお願いします。
参考文献
Beisbart, C., Betz, G., & Brun, G. (2021). Making Reflective Equlibrium Precise: A Formal Model. Ergo(8).
Box, G. E. P. (1979). Robustness in the strategy of scientific model building. in Launer, R. L., Wilkinson, G. N., Robustness in Statistics, Academic Press, 201-236.
Elgin, C. Z. (1983). With Reference to Reference, Hackett.
Elgin, C. Z. (1996). Considered Judgment, Princeton University Press.
Elgin, C. Z. (1997). Between the Absolute and the Arbitrary, Cornell University Press.
Elgin, C. Z. (2007). Understanding and the facts. Philosophical Studies, 1(32), 33–42.
Elgin, C. Z. (2017). True Enough, MIT Press.
Elgin, C. Z. (2022a). Models as Felicitous Falsehoods. Principia: An International Journal of Epistemology, 26(1), 7-23.
Elgin, C. Z. (2022b). Disagreement in philosophy. Synthese, 200(1), 1-16.
Kvanvig, J. L. (2003). The value of knowledge and the pursuit of understanding, Cambridge University Press.
Goodman, N.& Elgin, C. Z. (1988). Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences, Routledge.(N・グッドマン&C・Z・エルギン.『記号主義——哲学の新たな構想』菅野盾樹訳. みすず書房, 2001年)
伊勢田哲治. (2006). 広い反照的均衡と多元主義的基礎づけ主義. Nagoya Journal of Philosophy(5), 29-53.
谷川綜太郎. (2021). 「認識論における理解の叙実性について」『客観的世界と人称的世界についての研究(2019〜2020年度)』千葉大学大学院人文公共学府研究プロジェクト報告書 第359集所収、秋葉剛史編、千葉大学大学院人文公共学府. 40–49.
上枝美典. (2020). 『現代認識論入門——ゲティア問題から徳認識論まで』勁草書房.
松永伸司. (2017). 「概要」『芸術の言語』所収, 313-320.
難波優輝(newQ / 立命館大学衣笠総合研究機構客員研究員)
Twitter: @deinotaton
researchmap: https://researchmap.jp/deinotaton
