
睡眠ガイド2023が新たに採用した睡眠休養感が導く健康で幸せな生き方
おはようございます!ニュース連動型おじさんだっくでございます。
今日は2月16日は、天気図記念日!1883年(明治16年)のこの日、日本で初めて天気図が作られました。
天気図(weather map)とは、様々な規模の気象現象を把握するために、地図上に天気、気圧、等圧面における高度、気温、湿数、渦度などの値を、等値線その他の形で記入した図のこと。
1820年(文政3年)にドイツの気象学者ハインリッヒ・ブランデス(Heinrich Brandes、1777~1834年)が観測データを郵送などで集めて発表した天気図が世界初だそうです。
僕は、天気予報では地元のお天気マークと気温や雨雲レーダーくらいしか見ないけれど、あれが読み解けると楽しそうだなと常々思います。
さて、今日は睡眠のお話。
2023年、厚生労働省が発表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」は、日本人の睡眠に関する新たな指針を示しました。
このガイドは、単なる睡眠時間の推奨にとどまらず、睡眠の質や個人差を考慮した包括的なアプローチを提案。僕も興味が強めなお話なのであれこれ調べてみたので読んでみてください。
睡眠時間だけでなく、「休養感」も重視
新ガイドの最大の特徴は、睡眠時間だけでなく「睡眠休養感」という概念を導入したことです。
睡眠休養感ってなーに?
睡眠休養感とは、簡単に言うと「ぐっすり眠って、朝起きたときに『ああ、よく寝た!』と感じる気持ち」のこと。気持ちと書くくらいですから、主観的な指標で客観性には乏しいです。
夜にしっかりと質の良い睡眠をとることで、体も心も十分に休まり、朝起きたときに「スッキリした!」「元気いっぱい!」と感じられる状態を指します。
たとえば、朝起きたときに「気分がいいな」「体が軽いな」「頭がスッキリしているな」と感じたら、それは睡眠休養感がある証拠です。
逆に、たくさん寝たはずなのに「体がだるい」「疲れが取れていない」「なんだか気分が乗らない」と感じる場合は、睡眠休養感が足りていないかもしれません。
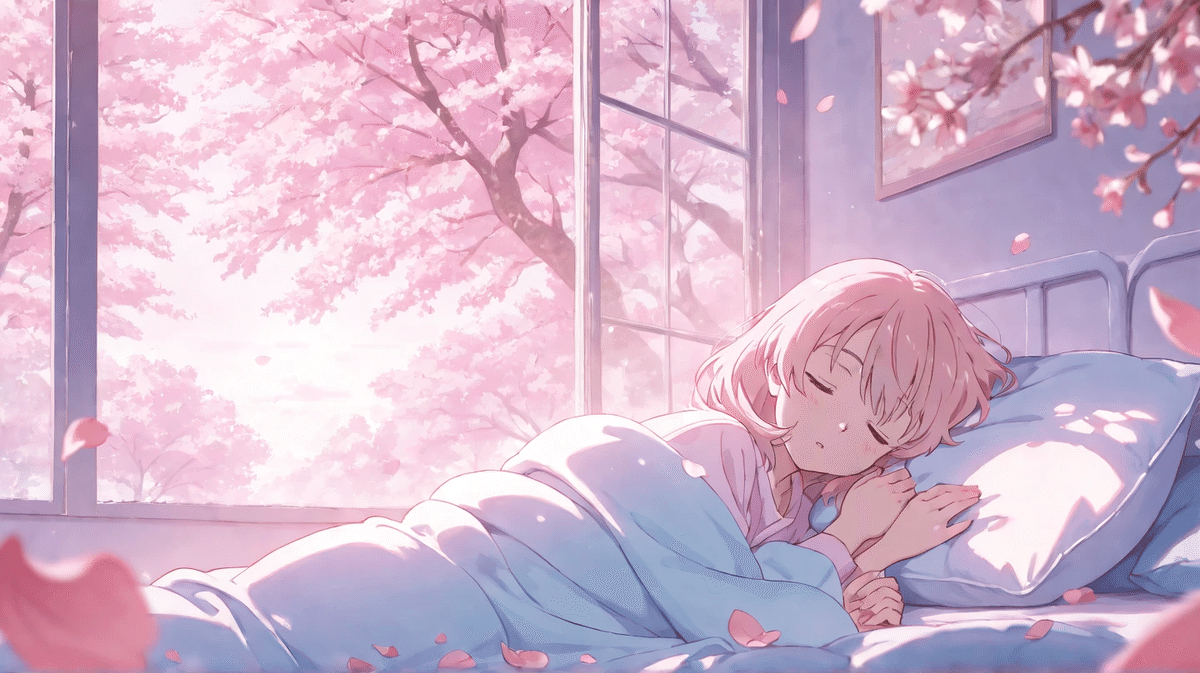
そんなふんわりしたもの必要?
睡眠休養感は、私たちの健康にとってとても大切なものです。なぜなら、睡眠中に体や心の疲れをしっかりと取り除くことで、心臓病や高血圧、肥満や糖尿病といった病気のリスクを減らすことができるからです。
また、心の健康にも深く関わっていて、睡眠休養感が不足すると、イライラしやすくなったり、悲しい気持ちになったり、集中力が続かなくなったりすることがあります。
睡眠時間が同じでも、人によって疲労回復の度合いは異なります。そのため、睡眠休養感を重視することで、より個人に適した睡眠の質を追求できるようになったという訳。
確かにふんわりしているけど、普段生きていて睡眠時間だけで測るのはしっくりこない場面は結構ありますよね。だから、必要なんです。
成人の推奨睡眠時間は6時間以上を目安に
成人の推奨睡眠時間については、「毎日の睡眠時間を6時間以上」と設定。
これは、健康を害するリスクが高まる6時間未満の短時間睡眠を避けるべきという考えに基づくのですね。
必要睡眠時間の個人差が大きいだけではなく、働く世代は長時間の通勤や労働、夜勤・交代勤務問題などもあって睡眠時間を確保することが難しいため、「せめて健康を害する危険性が大きく高まる6時間未満の短時間睡眠だけでも避けてほしい」という意図が込められています。
ただし、必要な睡眠時間には個人差があるため、一律の目標値を設定することは難しいとされています。ここで、やはり睡眠休養感に着目が必要となるのです。
睡眠休養感が低いということは、体と心の健康に悪影響を与える可能性があります。研究によると、朝起きたときに「よく眠れた」と感じられない人は、様々な病気にかかりやすくなることがわかっています。
例えば、心臓の病気(心筋梗塞や狭心症)、高血圧、糖尿病、うつ病などの リスクが高くなります。さらに、長生きできる可能性も低くなるそうです。
「長生きできる可能性を低くしてしまう」と言う観点では既存コホート研究データの再解析やメタ解析など科学的見地でも明らかになっているそうですから、指標がふんわりしていても結果はなかなかシビアです。
ライフステージに応じた睡眠ガイド
結構これまでは全年齢一律でこれくらいが望ましいという睡眠ガイドがたてられがちだったのですが、ライフステージごとに立てられるようになりました。これは、実態に寄り添った正しい変化だと思います。
細かい話ですが、過去には睡眠「指針」だったものを睡眠「ガイド」というワーディングにしたのも良いです。
「べき」で強く詰められると反発もしますが、「この方が良いんじゃない?」的なのりしろのあるアプローチの方が受け入れられやすいと思うのです。

子どもの睡眠は、成長に合わせた細やかな設定を行う
子どもの睡眠時間については、年齢に応じて細かく設定されています。
例えば、1〜2歳児は11〜14時間、3〜5歳児は10〜13時間、小学生は9〜12時間、中学・高校生は8〜10時間。
これは、成長段階によって必要な睡眠時間が大きく変化することを考慮したものです。
高齢者の睡眠は、質を重視したアプローチを考える
一方、高齢者の睡眠については、睡眠時間よりも睡眠の質を重視しています。
加齢とともに睡眠の構造が変化し、浅い睡眠が増える傾向にあるため、単純に睡眠時間を延ばすだけでは十分な休養が得られない可能性があります。
そのため、個々の生活リズムに合わせた睡眠習慣の確立が重要とされています。

僕もね、入眠が下手すると20時や21時です。でもって、覚醒が4時くらい。でも、それで固定な訳じゃ無くって、その日のノリ次第では1時くらいまでおきていて6時くらいに起床。
安定させたい一方で、調子が良いかどうか次第で長くても駄目だし、短くてもアリな時もあるなあと実感しています。
睡眠と健康、その深い関係性
生活習慣病予防と睡眠
適切な睡眠は、生活習慣病やがん、うつ病などの予防に重要な役割を果たします。
睡眠不足や質の悪い睡眠は、心筋梗塞や狭心症、高血圧、糖尿病などのリスクを高めることが研究で明らかになっています。
そのため、睡眠を健康維持の重要な要素として位置づけ、積極的に改善を図ることが推奨されています。
働く世代の睡眠問題
特に働く世代の成人では、約3割が「休養感がない」と回答しているという調査結果があります。
厚生労働省が毎年行っている国民健康・栄養調査では、「睡眠による休養が十分取れていないと感じている人の割合」を調査しています。2022年の調査結果では、国民の約2割が「休養感がない」と回答し、09年からの推移を見ると「休養感がない」と答えた人の割合は男女ともに有意に増加しています。特に、働く世代の成人では約3割が「休養感がない」と回答しており、働き方改革などとも連動して健康日本21の取り組みを進める必要があります。
長時間労働や通勤時間の長さ、夜勤・交代勤務など、現代社会特有の問題が睡眠の質を低下させている可能性があります。
このような状況を改善するためには、個人の努力だけでなく、社会全体での取り組みが必要不可欠です。
実は「春眠暁を覚えず」ではなく、冬によく眠る
睡眠の季節影響というのもあるんです。
これも多分、実感としては或物の裏付けを知らないから「どうなの?」と思っている人が多そう。大正解です。季節によって睡眠時間が違うのが普通です。

夏季に比べて冬季に10〜40分程度、睡眠時間が長くなることが示されていま
す。この主な原因として、日長時間(日の出から日の入りまでの時間)の短縮が考えられています。
冬眠こそしないものの人間も動物なんですよ。自然に逆らうのはよろしくありません。
労働時間と睡眠の関係性
過労死ラインとは、健康に深刻な影響を与える可能性が高い長時間労働の目安となる基準です。具体的には、以下の2つの基準が設定されています。
発症前1ヶ月間に100時間を超える時間外労働
発症前2~6ヶ月間の平均で月80時間を超える時間外労働
これらの基準を超えると、脳血管疾患や心臓疾患などの健康障害と業務との関連性が強いとされ、労災認定される可能性が高くなります。
過労死ラインは、単なる目安ではなく、労働者の健康と生命を守るための重要な指標です。しかし、この基準を下回っていても健康リスクがないわけではありません。厚生労働省の見解では、月平均45時間を超える残業から健康障害のリスクが高まるとされています。
で、これを睡眠にあてはめてみても明らかな有為差が出るので知っておいてください。

1日当たりの労働時間が7時間以上9時間未満の人を基準とした場合、男性の場合は睡眠時間が6時間未満になるリスクは、労働時間が9時間以上の人は2.76倍、11時間以上の人は8.62倍に著しく増加することが報告されています。
女性の場合も、労働時間が9時間以上の人は2.71倍、11時間以上の人は5.59
倍に増加することが報告されています。
さらに、時間外労働が1日当たり5時間を超えると睡眠時間は著明に短くなるとの報告もあり、睡眠時間の確保のためには、長時間労働の是正等の労働時間の管理も重要です。

人間死んでしまってはおしまいです。仕事やお金は確かに大事ですけど、あの世に持っていくことは出来ませんから、今を生きることを大事にした方が良いですよ。
健康的な睡眠を実現するためのヒント
色々あるので目移りするかとは思いますが、一気にやろうとするのではなく自然に生活に取り入れて習慣化するのが望ましいです。
睡眠環境の最適化
快適な睡眠を得るためには、適切な睡眠環境を整えることが非常に重要です。寝室は睡眠のための聖域として扱い、リラックスできる空間づくりを心がけるのが望ましいです。
まず、寝室の温度と湿度の管理が重要です。一般的に、寝室の適温は18〜22度程度、湿度は50〜60%程度が理想的とされています。
光の管理も重要です。夜間は部屋を暗くし、必要に応じてアイマスクを使用することで、メラトニンの分泌を促進し、良質な睡眠につながります。朝は自然光を取り入れることで、体内時計のリセットを促進してみたり。
騒音対策も忘れずに行いましょう。静かな環境を維持するために、必要に応じて耳栓やホワイトノイズマシンを活用するのも一つの方法。
寝具の選択も睡眠の質に大きく影響します。自分の体型や寝方に合ったマットレスや枕を選び、定期的に清潔に保つことで、快適な睡眠環境を維持できます。
規則正しい生活リズムの確立
体内時計を整えることは、良質な睡眠を得るための重要な要素です。極力毎日同じ時間に起床し、就寝時間も一定にすることで、体内時計が安定し、睡眠の質が向上します。
朝の光浴は体内時計の調整に効果的です。起床後30分以内に15〜30分程度、自然光を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜の良質な睡眠につながります。
就寝前のブルーライト対策も重要です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの電子機器から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を抑制し、睡眠の質を低下。
就寝の1〜2時間前からはこれらの機器の使用を控え、代わりに読書やストレッチなどのリラックス活動を行いましょう。
適度な運動習慣も睡眠の質を向上させます。ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果になる可能性があるため、運動は夕方までに終えるようにしましょう。軽いストレッチや瞑想は就寝前のリラックスに効果的です。
僕もやってますが、チョコザップとか手軽だし、習慣化には便利ですよ。
ストレス管理と睡眠
ストレスは睡眠の質に大きな影響を与えます。日中のストレス管理が、夜の良質な睡眠につながります。

ストレス解消法は人それぞれですが、深呼吸、瞑想、ヨガ、アロマセラピーなどのリラクゼーション技法を日常的に取り入れることで、ストレスレベルを下げることができます。
就寝前のリラックスルーティンを確立することも効果的です。例えば、ぬるめのお風呂に入る、ハーブティーを飲む、静かな音楽を聴くなど、自分に合ったリラックス方法を見つけ、毎晩実践することで、心身の緊張をほぐし、良質な睡眠への準備ができます。
また、睡眠の悩みを一人で抱え込まず、必要に応じて専門家に相談することも大切です。睡眠障害が疑われる場合は、早めに医療機関を受診し、適切な対処法を見つけることが重要です。
健康的な睡眠は、単に長時間寝ることではなく、質の高い睡眠を取ることが重要です。
個人に合った睡眠習慣の確立を
新しい睡眠ガイドは、睡眠時間だけでなく睡眠の質や個人差を重視しています。
健康的な睡眠は、単に長時間寝ることではなく、個々人に適した睡眠習慣を見つけ出すことが重要です。
自分の生活リズムや身体の状態に合わせて、睡眠時間と睡眠休養感のバランスを取りながら、最適な睡眠パターンを探っていくことが、健康的な生活の基盤となるでしょう。

健康づくりのための睡眠ガイド 2023は48ページもありますけれど、自分に関係ありそうだなとか自分の属性にあてはめて部分読みしても大丈夫です。それに政府のドキュメントの割にとても分かりやすくて読んでいて面白いと感じられる工夫も随所に見られます。ぜひご一読を。
僕個人としても、なんとなく「こうなんじゃないのかしら?」と思っていた部分が、科学的に正しそうだという確信が得られて、とても勉強になりました。
ではまた
マシュマロやっています。
匿名のメッセージを大歓迎!
質問、感想、お悩み、
読んでほしい本、
深掘り(ふかぼり)して調べて欲しいニュース、
取り上げて欲しいこと、エトセトラ。
ぜひぜひ気楽にお寄せください!!
日々、音声でも発信してるますよ!内容はニュースとnoteの読み上げです。気にいればどうぞお耳をお貸しください。
後はTherads(スレッズ)であれこれ流してます。結構辛口かも。
日経電子版、Foreign Affairs Magazine等の有償情報ソース、書籍に使わせていただきます!なかなかお小遣いでは購読が難しいのですけど、ここらへん充実できると記事に是非反映してお返し出来ればと思います。

