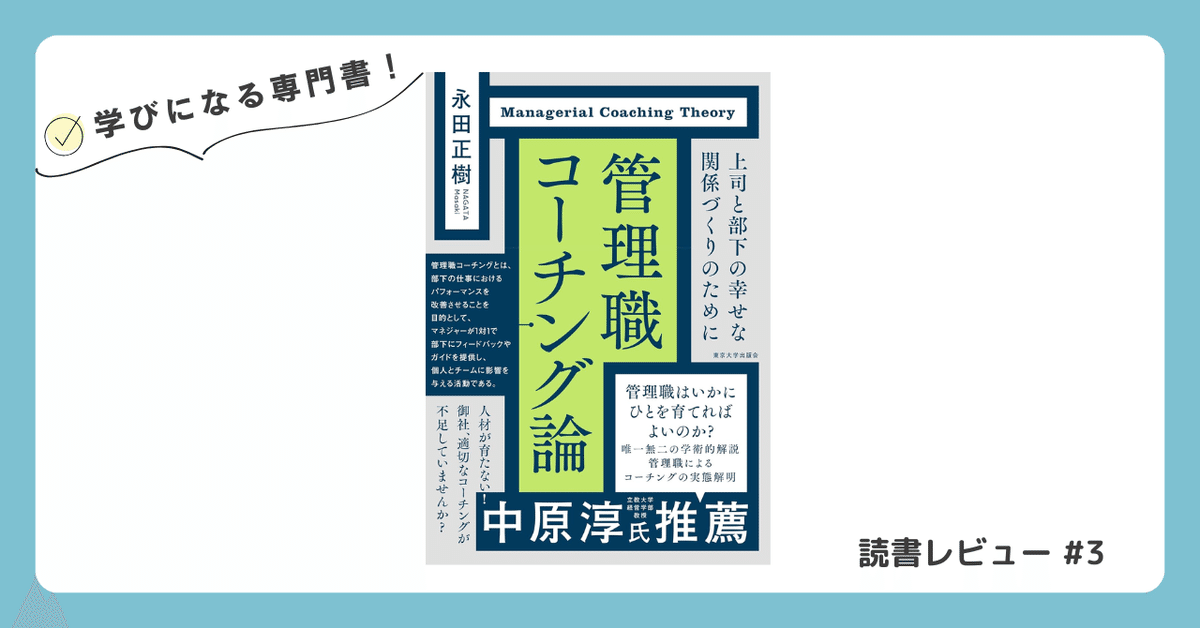
「経験学習」ってなんだ? 代表理論をざっくり解説します ~読書レビュー『管理職コーチング論』#3~
こんにちは。紀藤です。先日より「管理職によるコーチング」の唯一無二の専門書である『管理職コーチング論』(永田正樹/著)をご紹介しております。本日も続けます。
本日は、「第2章 経験学習・リフレクションに関する理論」からポイントをまとめていきたいと思います。それでは、どうぞ!(前回の話はこちら)
「振り返り」の威力
12年前、」あるセミナーで「自己省察」が大事であることを学びました。
当時、「省察?なんじゃそりゃ??」と思いましたが、「1.新しい行動をする」「2.1日の終わりにやったことを振り返る」という、ただそれだけの話でした。
当時の私からすると、大変高価なセミナーだったので、「元をとらねば・・・」と、事後課題に出された「自己省察」に100日間、一生懸命取り組んでいました。すると、かなりの成長感を得られたのです。
たとえば、「自分で勉強会を主催した(経験)」→「良かった点や改善点はどこか?(振り返る)」→「サンドイッチを出したのが喜ばれた、あと対話の時間を多くとると満足度が高い(教訓)」みたいな小さな気づき。
または、「領収書をもらうときに、会社名をメモした(経験)」→「めんどくさい。この時間もったいない(振り返る)」→「名刺の社名に◯をつけて領収書の依頼とともに渡せばよいんだ!(教訓)」みたいな、ごくごく小さな改善への気づきなど。
こうした「小さな気づきのかけら」は、自らの課題を改善したり、生産性を高めてくれたり、自分を望ましい方向に近づけてくれます。チリツモ(塵も積もれば山となる)なので、100日やると、その変化感に驚きました。
また、別の角度では、「ショッキングな出来事」があったとき、それを深く内省し、言葉にすることもしました。すると「自分の考え方や在り方」について、批判的に立ち止まることにもなりました(例えば、妻とのケンカとか)。
そして100日続けると、その効果を如実に感じて、「自己省察すげえ・・・!」と確信したのでした。そう、10年前の話です。
経験学習とリフレクションの先行研究
さて、前置きが長くなりましたが、こうした行為は、学術的には「リフレクション(内省)」、経験→内省→教訓化→実践の流れを「経験学習」と呼びます。
こうした考え方が学習理論になっていることを、大学院に入って学び、ものすごく感動したのを覚えています。
余談ですが、今は亡きおじいちゃんが、高校入学のお祝いに「5年日記」をくれて、書くように勧めてくれたことを、ふと思い出しましあt。あのときは、勉強とは知識習得としか思っていませんでしたが、こんな学習方法(経験学習)があると当時は気づかなかったな・・・と思い返してみたり。
▽▽▽
さて、本書では、このリフレクションと経験学習にまつわる、代表的な理論を歴史とともにまとめてくれています。これを見ることで「振り返りから学ぶプロセスって、こんなに深いんだ・・・」と改めて考えさせられました。
ということで、経験学習に関わってきた人物、経験学習の理論史を、デューイ、コルブ、ショーン、ギブス、コルトハーヘンという主要人物の考え方からまとめてみたいと思います。
1. ジョン・デューイ:経験と教育の統合 (20世紀初頭)
デューイは、知識の詰め込みを批判し、経験を重視する教育を提唱しました。経験は思考と行動が連動する中で意味を持ち、探求学習や民主主義的教育を重視しました。プラグマティズムに基づき、知識の有用性を重視しました。デューイの思想は、その後の教育改革と経験学習理論の基礎となりました。経験の理論として「経験の連続性」「相互作用性」の2つを述べました。
2. デイビッド・コルブ:経験学習サイクル (1984年)
コルブは、「経験学習サイクル (具体的経験、内省的観察、抽象的概念化、能動的実験) 」を提唱し、経験から学び成長するプロセスを明確化しました。また、発散型、同化型、収束型、適応型という4つの学習スタイルを提唱し、個人の特性に合わせた学習方法を考える上で役立ちます。経験学習サイクルは、経験学習のプロセスを可視化し、理解を深める上で大きな貢献をしました。

3. ドナルド・ショーン:行為の中の内省 (1983年)
ショーンは、「行為の中の内省」という概念を提唱し、実践者が行動しながら学び、状況に応じて臨機応変に対応する能力に着目しました。熟達した実践家は、暗黙知を活用し、行為の中の内省を実践するリフレクティブ・プラクティショナーであると考えました。技術的合理性を批判し、複雑な現実の問題に対処するために、行為の中の内省が不可欠であると主張しました。
4. グラハム・ギブス:リフレクティブサイクルモデル (1988年)
ギブスは、「リフレクティブサイクルモデル (記述、感情、評価、分析、結論、行動計画)」 を提唱し、内省を体系的に行うためのフレームワークを提供しました。内省を構造化し、実践的な行動につなげるための具体的なツールとして、教育、看護、ソーシャルワークなど、様々な分野で活用されています。

5. フレッド・コルトハーヘン:ALACTモデル (2001年)
コルトハーヘンは、「ALACTモデル (行動、振り返り、自覚、代替案、試行)」 を提唱し、教師教育における内省的な実践を促進するためのフレームワークを提供しました。具体的な場面の重視、内面の変化の重視、持続的な改善の重視を特徴とし、教師の自己成長を促進するためのツールとして活用されています。

▽▽▽
なお、リフレクションのタイプとして「経験を意味づけるリフレクション」と、「すでに持っている信念・価値観・前提の妥当性を検討するクリティカル・リフレクション」は区別すべきである、とする研究者もいて(Gray,2007)、本書ではこの点についても補足をしています。
「経験学習モデルの改訂版」のご紹介
本章では、これまでの経験学習モデルに、社会的要因やクリティカル・リフレクションの学習プロセスを考慮して、「経験学習モデルの改訂版」を著者らが作成しています(Matsuo, Nagata, 2020)。
このモデルが、具体的な振り返りのための質問も丁寧に紹介されており、実践に活用しやすいと思いました。(こちらはよろしければ本書をご参照くださいませ)

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
