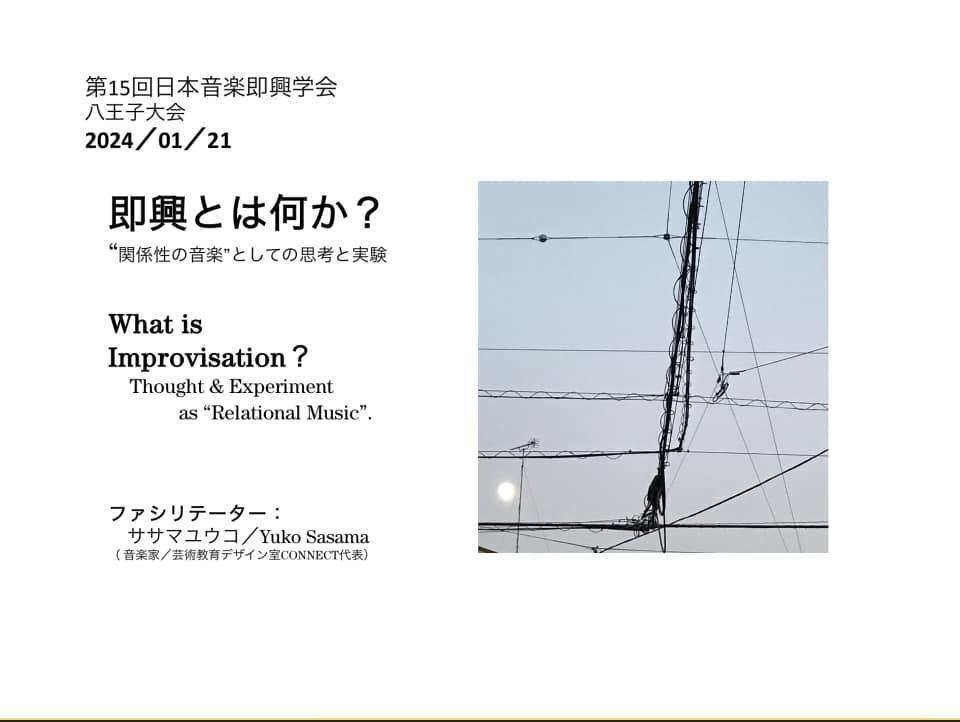冬至から節分まで~世界をきく
昨年のちょうど冬至の少し前に左足首を骨折した。そこから足首が固定され、杖を使う時間を過ごし、節分の前日にその生活から解放された。
不慣れな身体の使い方に慣れること、文字通り「足を止めて」考えること。年始年末の多忙期に家族には多大な迷惑をかけてしまったが、この状況を受け入れるしかない周囲が生き生きと動き出す世界を、実は申し訳なさよりもどこか複雑な気持ちで眺めていた。もしかしたら日頃、自分はいろいろ「やりすぎて」いたのではないか。なんだ、みんなやればできるんだ。私がやるから、やらない。世界はウチとソトの関係性、ただそれだけのことだったのかと思う。むしろ3.11以降、コロナ禍を含む厄介な日々をひとり背負ったような気になっていたと反省する。
ちょうど足を折る直前に、ふとヴァージニア・ウルフの「自分ひとりの部屋」を古本で手に入れて読んでいた。今思えば、あれは啓示だったかもしれない。ひとり本を読み、音楽をきき、そして誰にも邪魔されずに考える。若い頃の時間の使い方、自分だけの世界の在り方を徐々に思い出す。アートとケア、芸術と日常の融合はおそらく自分の人生の最大のテーマだったはずで、大人になった今、流石に芸術だけの世界に戻りたいとは思わないけれど、「自由に歩けない」という事実が強制的に記憶を巻き戻していく。こうやって朝から晩まで、本を読んだり、音楽を聴いたり、映像を観ていても誰にも文句を言われない時間をすっかり忘れていた。空間だけでなく、身体が不自由になることで手に入る自由もあると知った。
1月半ばに日本音楽即興学会で「関係性の音楽」から「即興とは何か」を考える対話型ワークショップを発表した。サウンドスケープ思想やサウンド・エデュケーションの応用として、「1分間」という時間をウチとソトから対峙しながら世界の多様性に思いを馳せる内容だ。雨のなか杖を使って心許ない足取りで会場に向かうと、若い研究者の皆さんが温かく迎えてくれた。初対面でも不思議と自分の心もオープンになっていたように思う。
魔法の杖。今年60歳になる私はもう若くないし、完璧にはできない。それを杖が代弁してくれて心が軽くなったのだとも思う。
2月2日、節分の前日に足首が解放され、少し寂しいが杖を手放すことになった。そして今はリハビリ期だ。ここから、自分ひとりの力で歩いていた感覚を取り戻さなければならない。生まれて初めて歩けるようになってから、おそらく「歩くとは何か」と考えたことなど無かったから、またひとつ「問い」が生まれたようにも思う。たった1か月半で足首はすっかり固くなっている。もう杖の魔法も使えない。もちろん杖は、いずれまた人生の中で巡ってくるはずだから、今は「見えない杖」を手にしておこうと思う。
これは自分が生きてきた時間に自覚的になったということかもしれない。「老いる」ということは心身一元論か二元論か、どちらが自分にとっては自然なのか今はまだよくわからない。ただ「いつまでも若い」とか、「いつまでも元気」という考え方には「時間」の観念が不在なので、音楽家である自分は取り入れないと思う。
冬至から節分までは暦の上でも特別な時間だ。神社には「茅の輪くぐり」が置かれたり、「一陽来復」のお札が配られるのもこの期間である。年始年末という季節の境界は本来グラデーションで、このくらいの時間の「幅」が必要なのだとも思う。特にこの国のクリスマスから大晦日までの、あの逆明治維新のような忙しない東西文化の大転換はそろそろ考え直すべきではないかと思っている。
そうえいばコロナ前、2019年の節分前夜には「鬼」をテーマにした「即興カフェ」を開催した。もう5年も経つのかと驚いてしまう。コロナ禍の3年間は実はとても長かった。今はあの頃の「場づくり」に心理的ハードルも感じてしまうが、やはり次世代の音楽家にとっても取り戻さなければならない場や時間だとも思う。
今年は元旦から能登地震もあって、杖使用者として見えてくる怖さもあった。年齢を重ねるということは世界がみえる、きこえるようになることだ。しかしその時期を越えると視力も聴力も衰えて、また自分のウチの世界に戻っていくものかもしれないとも思う。だからこそ、今やるべきことがある。
還暦とは人生が一周まわってゼロに戻ることならば、本当に相応しい2024年の幕開けなのだろう。
なぜなら今、私は歩く練習をしている。人生、またここから。
※2月3日、4日は昨夏のサントリーホール・サマーフェスティバル「ありえるかもしれないガムラン」の同窓会のような、嬉しい再会の時間となった。
ここからやっと、私の2024年が始まった気がする。
以下の写真はこの間のメモとして。詳細にご興味のある方は私のFBをご自由にフォローしてください。