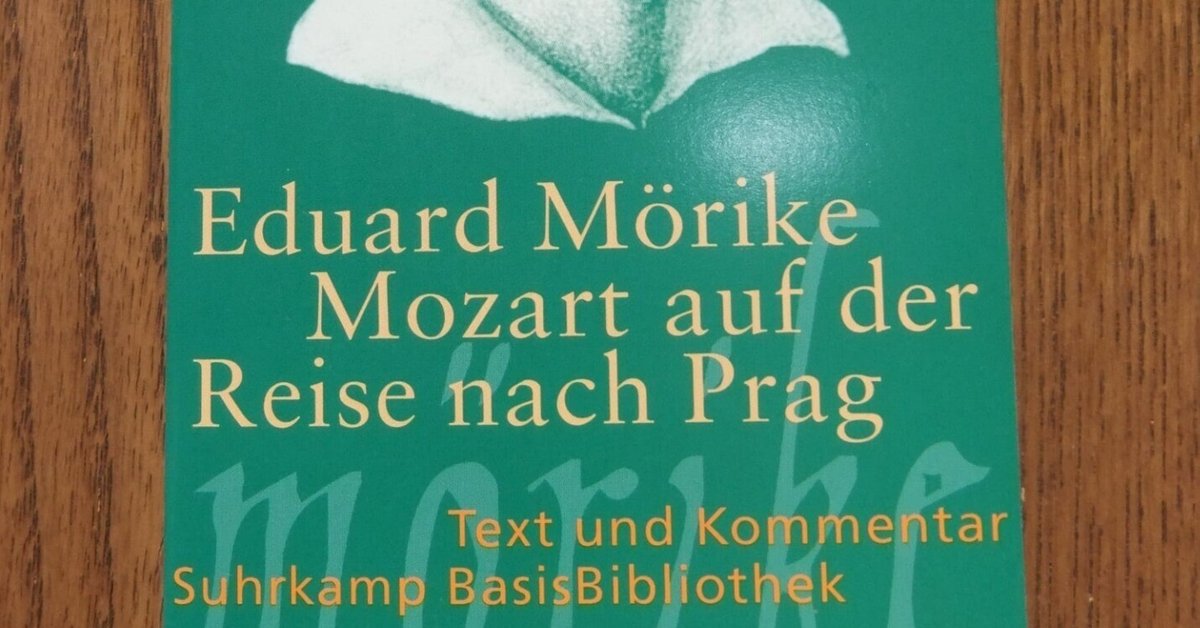
メーリケ「旅の日のモーツァルト」
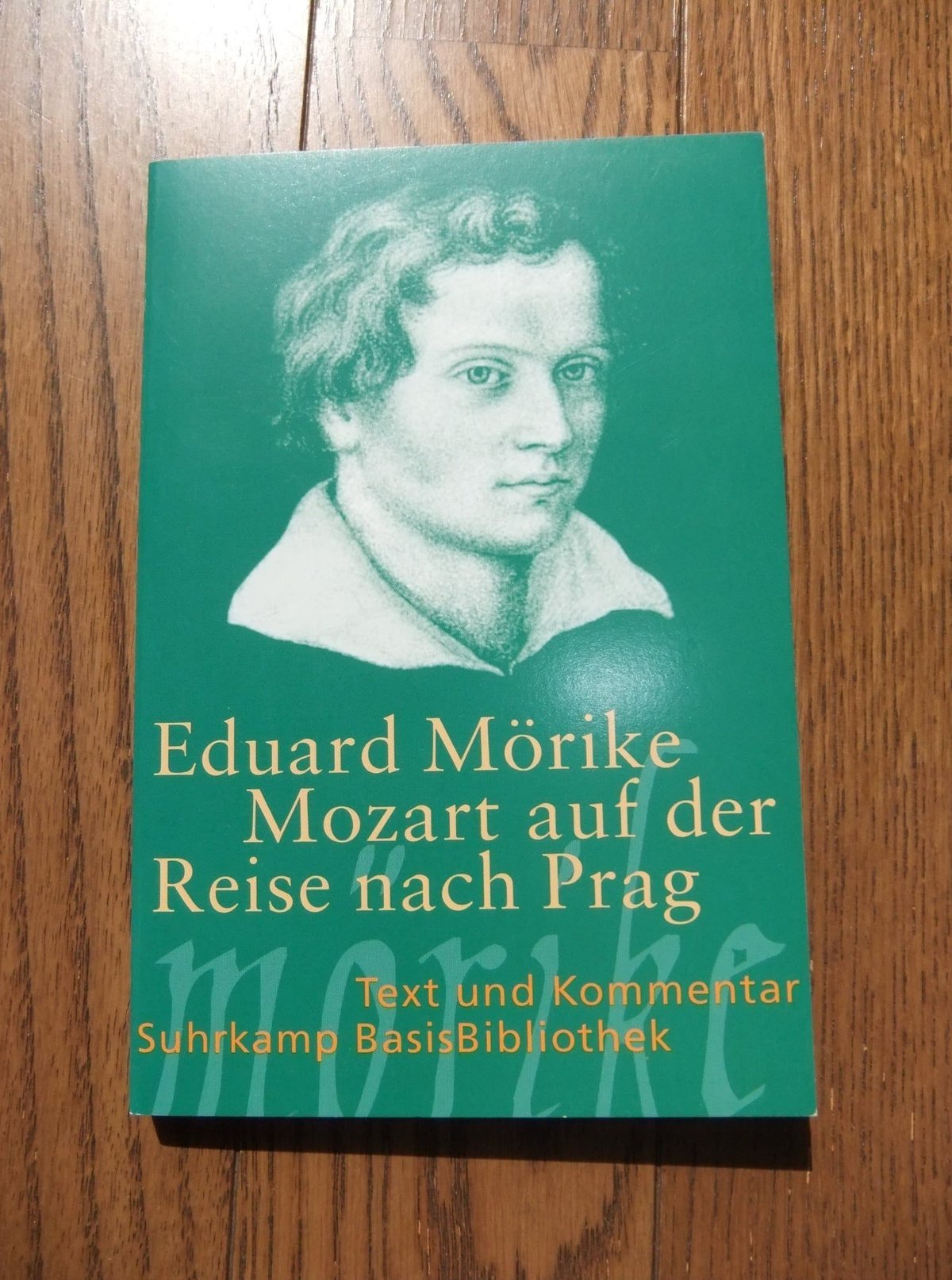
Eduard Friedrich Mörike:Mozart auf der Reise nach Prag
「旅の日のモーツァルト」は19世紀ドイツの抒情詩人メーリケが、長年傾倒していたモーツァルトを主人公にした小説。
あらすじは、ドン・ジョヴァンニ世界初演のため、1787年の秋、モーツァルトが妻コンスタンツェを傍らに、プラハへと旅に出た一日の出来事をつづったもの。芸術に理解がある伯爵家に一泊し、一家の人々を前に幼い日の思い出,創作の插話を語る。
伯爵一家を前にして、初演されるドンジョヴァンニのフィナーレ(女たらしのドンジョヴァンニが悔悛せず地獄に落ちる所)について、モーツァルトが、夜更けに2つの燭台の燈火を消し、ピアノで弾き語るシーンが戦慄的です。地獄落ちに「崇高美」を見出す作中のモーツァルトの語りを聞くと、まるでその場に居合わせた臨場感があり、オペラの場面がありありと目に浮かびます。
引用)モーツァルトがフィナーレについて弾き語る場面
「亡霊は速やかに悔悛せよ、とせまる。亡霊のために残された時間はもうほとんどなく、行く手は遥かかなたなのだ。
そしてドンジュアンはすさまじい我意を通して永遠の秩序に逆らいながら、押し寄せる地獄の軍勢と、負けると決まった闘いをあえてし、身もだえし、のたうちまわったすえについに滅びてゆくのだが、それでいてその一挙手一投足がすべて溢るるばかりの崇高美を浮かべる時、歓喜と不安のために胸の奥まで慄きふるえない者がいるだろうか?
それは猛り狂う自然力の壮麗な景観、あるいは豪華な船の炎上を眺める際に抱くあの驚きに似た感情である。
心ならずもわれわれは、いわばこの盲滅法な偉大さに与し、歯がみしつつも、自己破壊の激情に駆られて、その苦痛を分かつのだ。」
「作曲家は弾き終わった。だが暫くの間、誰も一座の沈黙をあえて自分から破ろうとする者はいなかった。」
Don Giovanni:finale
