
新世紀の寺子屋 第23回(ロボット)
今回のテーマは、「ロボット」です。男の子は心が躍りますね。
なぜ、ロボットを取り上げるかといえば、日本はロボット大国であり、これからの新たなロボット時代において、日本の基幹産業としてロボット、ロボティクス産業の成長が期待されるからです。
その前に、日本の産業の現状を確認しておきましょう。産業は古典的には3つに分けられます。農林水産業を中心とする第一次産業、製造業や工業、建設業などの第二次産業、そしてそれ以外の第三次産業です。例えば、牛のお乳を搾ってミルクを取る仕事は第一次産業です。その乳をミルクに加工したり、チーズを作成したりする仕事は第二次産業で、そうした製品を売るスーパーマーケットは第三次産業です。
ところで、日本ではどの産業区分で働いている人が多いでしょうか?その答えは第三次産業ですね。一般的に新興国では第一次産業で働く人の割合が多く、先進国化するにつれて、第三次産業へとシフトしていきます。

下のスライドの左側は、各国の第一次産業の割合を示しています。アフリカとかインドは高い比率ですね。先進国は一桁台です。日本は全体では約3.5%です。県別の状況では東北や四国が高く、東京や大阪は極めて少ない状況です。

簡単なクイズをしましょう。



今回は、簡単なクイズでしたね。さて、日本の産業構造は以下のようなイメージです。就業人口の7割、GDPの7割以上は第三次産業が生み出しています。ちなみに第一次産業の中で最大の項目は農業部門で116万人くらいの就業者がいます。但し、就業者の平均年齢は68歳程度であり、今後はどこかの時点で大きく減少する可能性があります。国は日本の大手企業が農業を事業として行うことを期待して、様々な優遇策を用意しています。これからの農業は成長産業です!!生徒さんから、「農業は3Kですよね」と指摘されました。「汚い、くさい、きつい」でしょと。3Kは臭いではなく、危険のKだよと修正しておきました。こういうイメージがあるのは払拭しないといけないですよね。例えば、「健康的、かっこいい、革新的」とか、「健康、快適、感謝」とか、新たな「3K」を普及させるべきでしょう。

日本の基幹産業は何でしょうか?色々な産業がありますが、その筆頭格は自動車産業でしょう。海外旅行に行くと、日本の車は世界中で走っています。トヨタグループは世界自動車ランキングで1位です。

自動車産業は、例えば2021年ベースでは全製造業の製品出荷額の約17%を占めます。自動車関連の就業人口は550万人を超え、全就業人口の8%程度です。自動車産業の存在感は非常に大きいですね。但し、現在の自動車業界は「100年に1度の変革期」と言われています。これは、また別途取り上げますが、トヨタといえども安泰ではないということです。
自動車産業には引き続き頑張ってもらうとして、日本には「ポスト・自動車産業」も必要です。これまでも、自動車産業に代わり、日本経済を牽引するような産業の育成が叫ばれてきましたが、小規模な成功事例はあるものの、自動車産業に匹敵するようなものは誕生していません。そうした中で、大きな期待を集めているのがロボット産業、ロボティクス産業です。

ちなみに、日本は「ロボット大国ですが、ロボティクス大国とは言えません」この両者は少し異なるのです。徐々に説明したいと思います。
まずは、ロボットの歴史から振り返りましょう。そもそもロボットとは何でしょうか?ロボットという言葉は、チェコの作家カレル・チャペックの「ロボット」という小説に最初に登場するようです。カレル・チャペックは私が大好きな「山椒魚戦争」の作者です。生徒さんにはお勧めしましたが、小学生にはまだ早過ぎる小説かもしれません。

ロボットの歴史は実は相当に古く、なんと期限前8世紀のイーリアスに登場します。人間の発想、想像力は本当に豊かです。そして、人間が頭に描いたものは、長い時間を経ながら、次々に実現するのです。ドラえもんは4次元ポケットから様々な未来の道具を出します。この未来道具のいくつかは、既に実現していることはよく知られています。私たちが使っているスマホは、ドラえもんの「糸なし糸電話」です。ビル・ゲイツも、イーロン・マスクも、ジェフ・ベゾフやスティーブ・ジョブスなども、幼少期にはSFに夢中になったと言われています。SFをたくさん読んで、未来へ想像を膨らませましょう!!

世界最古の機械は、紀元1世紀の古代ギリシャで哲学者のヘロンが発明しました。下の絵を見て、生徒さんにこれが何かを推測してもらいました。なんと、一発で正解が出ました。そうです。自動ドアです。素晴らしい。

時代が進むと、日本では人形を使った傀儡子が登場します。日本の大人気の漫画であるNARUTOでも傀儡子の忍者が活躍しますね。こうした人形は、やがて「からくり人形」に発展していきます。

ヨーロッパでは、スイスの時計職人が本格的なからくに人形を設計します。「オートマタ」という三体の機械人形は有名です。人形の内部構造は、精巧なスイス時計とそっくりですね。だんだんロボットに近くなってきました。

日本では1928年に「学天即」という人型ロボットが製造されます。学天即については、是非動画で見てください。人型ロボット、ヒューマノイドです。

アシモフのロボット3原則についても簡単に説明しました。

ロボットは、未来の戦争に使われると思います。既にそういう開発は急ピッチで進んでいます。第二次大戦では、実際にドイツ軍は「ゴリアテ」という遠隔操作の爆弾ロボットを使いました。費用対効果の悪い兵器であり、成功したとは言えませんが、現代の無人機(ドローン)や自律型兵器の原型とも言える試みであり、歴史的には重要視されています。

近代になり1950年以降は、日本ではロボット漫画が次々に登場します。1952年の「鉄腕アトム」は有名ですね。残念ながら女子の生徒さんは知りませんでした。しかし、同じ女子の生徒さんが「サイボーグ009」をなぜか知っていたことは驚きました。いつかリアル鉄腕アトムが完成するでしょうね。

これからのロボットは、「AIロボット」が広がっていくでしょう。世界初のAIロボットは1966年の「シェーキー」です。ビル・ゲイツはこのシェーキーを改良するために働こうと呟いたようですよ。お掃除ロボット「ルンバ」のご先祖様ですね。
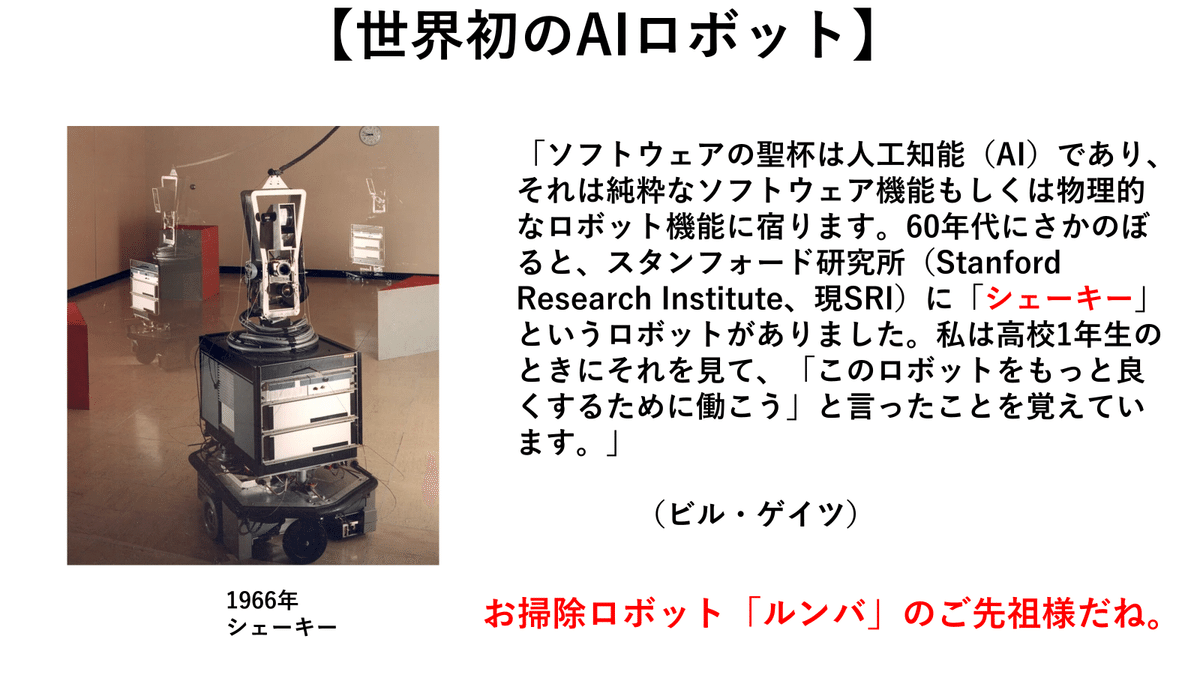
日本はロボット大国です。しかし、日本が得意とするロボットは「産業用ロボット」です。代表的なのは、ロボットアームなどですね。下の写真は1969年の川崎ユニメート2000型です。現在でも日本のファナック、安川電機などの産業用ロボットは世界で活躍しています。

1970年の大阪万博は、アジアで初めて開催された国際博覧会であり、その規模とテーマ、技術革新において世界的な注目を集めました。公式テーマは「人類の進歩と調和」で、当時の急速な技術進歩と、それをどのように人類社会に調和させるかという大きな問いを反映したものでした。この万博は、日本の高度経済成長期の象徴的な出来事とされています。月の石とか、岡本太郎氏の太陽の塔が有名ですね。この万博ではロボット技術も大いに注目されました。来年は再び大阪で万博が開催されます。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。ロボット・エクスペリエンスというプログラムにおいて、次世代のロボットが実証されるようです。楽しみですね。

1970年代以降は世界的にロボットSFが大流行します。1977年のスターウオーズの中には様々なロボットが登場します。もっとも作中ではドロイドです。なんでも修理してくれる「R2-D2」や人型の「C-3PO」は人気キャラです。
人型と言えば、何といっても1980年の「ターミネーター」は衝撃でした。ターミネーターは人類を抹殺すべく襲ってきます。生徒さんからは、「アシモフの3原則はどうなった?」と鋭い突っ込みがありました。

ロボットは、人間の作業の一部を助けてくれるものもあります。例えば、ロボットスーツのHALは改良が何度も繰り返されながら、現在では多くの病院でリハビリに使用されていますね。コストが低下してきたら、将来的にはヤマト運輸の荷物を運ぶ人は、こういうスーツが標準装備になるかもしれませんね。また、我々も自分の2本の腕のほかに、ロボットアームを2本くらい装着するのが当たり前の日常が来るかもしれません。全員、アシュラマンですよ。

ロボットは癒しの領域にも入っています。1999年にソニーがAIBOを発表したときは、結構話題になりました。私も欲しいと思いました。その後、最新のAIBOはすっかり可愛らしくなっているようですね。

今回は、ロボットの歴史を振り返りました。次回は、最新のロボットの状況や未来のロボットをテーマにするつもりです。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
