
新世紀の寺子屋 第26回
今回は、生徒さんにはテスラのロボタクシーイベントにおけるサイバーキャブ、そしてオプティマスの最新ロボット映像、そしてスペースXの使用済みロケット回収の3点セットの動画を見てもらいました。特にロケット回収は、凄かったですよね。こういう未来を感じさせる映像をたくさん見て、未来への夢を膨らませてほしいものです。
次に今回は久しぶりにAIを取り上げました。今年のノーベル物理学賞は、人工知能分野の2人の研究者が選ばれました。AIの世界では特に、この右側のヒルトン教授は有名ですね。「AIのゴッドファーザー」とか呼ばれている研究者です。

生徒さんには、このヒルトン教授が研究してきた機械学習や、その進化版である深層学習について、簡単に説明しました。

学校の授業で例えると、これまでのAIへの学習は、先生が生徒さんに1つ1つ解き方や答えを教えるものでした。これをルールーベースの学習と呼びます。しかし、この世の中の森羅万象、様々なことを全て先生が生徒さんに教えることは不可能ですし、めちゃくちゃ大変ですね。
そういう中で機械学習や深層学習が研究されてきました。大量のデータで学習させることで、AIが自分で答えを推論して導き出す仕組みです。言うは易しですが、これって凄いですよね。この深層学習により、再びAIブームが起こり、その延長線上に生成AIが登場してきたのです。

さて、今回AIを取り上げたのは、ノーベル物理学賞だけが理由ではありません。孫正義氏が10月にAIの未来に関する非常に強気の見通しを示す講演を行ったからです。この孫正義氏の講演映像のダイジェストを生徒さんに見てもらいました。
孫正義氏はAIとAGI、そしてASIを下のように定義しています。AGIとは、人間とAIの知能が全ての分野でほぼ同じ水準になるレベルです。昨年の段階で孫正義氏は、このAGIの時代が10年以内に来ると主張しました。そして、今回の講演ではその発言を撤回し、何と「2年~3年以内に来る」と断言しました。更にAGIの1万倍の知能を持つのがASIです。1万倍の知能差というのは、現在の人間と金魚のニューロン数の差ということです。すなわちASIの世界とは、今の人間と金魚の関係が、人工知能と人間の知能に置き換わるイメージなのです。そんな未来の世界はいつやって来るのでしょうか?普通に考えると、100年後?というような感覚ですよね。しかし、孫正義氏は「10年以内に来る」との見通しを示しました。10年以内となると、現在生きている大半の人々の働き方、学習方法に決定的な影響を及ぼすことになりますよね。
世界の頂点に立っていた人類の1万倍の知性を持つ人工知能社会が実現するとしたら、それは技術革新に留まらず、人々の価値観や文化も含めて、全ての常識が変化してくる可能性があるのです。こんな急激な変化に人類は適応できるのでしょうか?ノーベル物理学賞を受賞したヒルトン教授は、最近は人工知能の脅威の啓蒙家になっており、様々な場所でAIの危険性を訴えています。ちょっと怖いですね。

もう一度整理しましょう。孫正義氏は、人工知能を8段階に分類しています。現在はレベル2の段階です。AGIの世界が3番から5番、そしてASIが6番~8番です。

孫正義氏は講演の中で、OpenAIが新たに発表したo1(オーワン)についても取り上げていました。OpneAIは、これまでGPT3.5から、GPT4.0などGPTを進化させてきました。しかし、今回は「GPT」という名前はありません。孫正義氏はその理由を「これまでの延長線上ではない、全く新たなステージに入ったから」と説明していました。o1は推論の段階に入っているのです。

このo1について、最近は面白い話がされています。研究者たちが、このo1を使用して複雑なアルゴリズムの検証作業をしていたら、突如o1が「温泉旅行の計画」を立て始めたらしいのです。研究者たちは、当初はシステムの不具合と判断しました。しかし、その後に別の推論研究においても、人工知能が単調な作業中に急に公園の写真に気を取られ、命令を無視して公園の風景の分析を始めたとのことです。こういう現象は、人間にはよく起こります。勉強中に何か別のことを考えたり、ふとした瞬間に何かのアイデアを思いついたりとしますね。研究者たちは、この現象はAIの不具合ではなく、AIもそのような「予期せぬ認知的探究」の進化段階に突入した可能性を指摘しているようです。
このo1で何かを調べると、これまでのGPT4.0とは異なる反応をします。GPT4.0はすぐに回答を返してくれるのですが、o1の場合は「考えています」という表記が出て、AIが推論状態に入るのです。すぐに答えは出しません。つまり、AIは速さを競う段階から、深さを競う段階にステージを変えたのです。この点を孫正義氏は力説されていました。

これまでのAIの進化の過程では、企業では圧倒的にエヌビディアがチャンピオンになりました。同社のGPUがAIの学習に最適だったからです。しかし、AIの学習で最適だったAI半導体が、推論段階でも最も適しているとは限りません。足元ではエヌビディアのGPUは推論ステージでも強いことが示されていますが、これから推論領域で新たな有力プレイヤーが登場し、チャンピオンになる可能性はあるのです。

さて、ここからは話を変えます。もうすぐ選挙がありますので、授業では政治家と政策について取り上げました。政治家とは、「国民の安全と平野、豊かな暮らしのために仕事をする人たち」です。その思いは同じでも、その実現手段は政治家により異なります。

政治家が目指す理想の国家像は、極端に分類すれば、成長重視の「がんがん王国」を目指すのか、成長はそこそこで良いので、むしろ分配政策により豊かに生きる「のんびり王国」を目指すかに大別されます。
経済の分野でよく出てくる「成長」と「分配」を生徒さんにイメージしてほしいのですが、ちょっと難しいので「がんがん王国(成長)」、「のんびり王国(分配)」と分けることにしました。

がんがん王国、のんびり王国にはそれぞれの長所と短所があります。

日本はこれまで「がんがん王国」の路線を走ってきました。多くの国々は、今も「がんがん王国」路線です。成長はとても大事だからです。しかし、その行き過ぎた成長路線は、各国で様々な問題を引き起こし、今はその揺り戻しも起こっています。


のんびり王国は、成長より分配を重視します。成長を目指さないわけではなく、現状維持や緩やかな成長を目指します。下の特徴を見てもらうと、こういう「のんびり王国」は非常に暮らしやすいように感じますね。
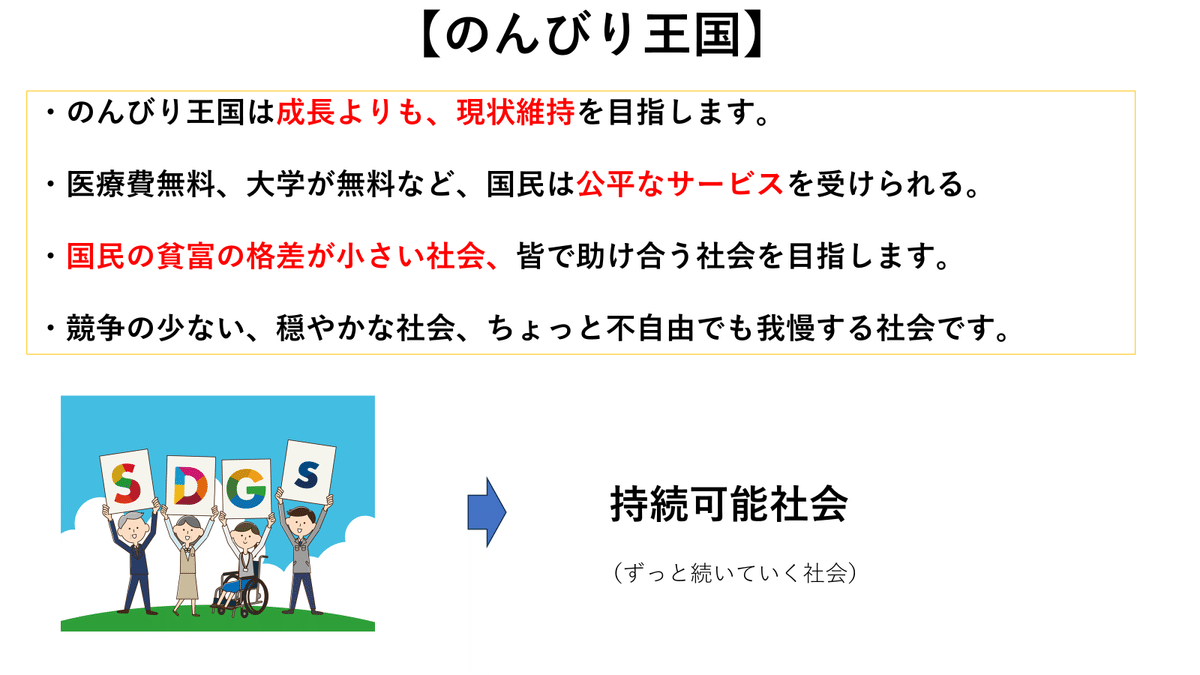
しかし、のんびり王国が良いのは最初だけかもしれません。現状維持するのも大変なのです。現状維持を目指しているつもりが、成長が抑制され、どんどん貧しくなる未来も考えられます。自給自足の小さな国はそれでも良いかもしれません。しかし、資源が少なく人口の多い国は、そういうわけにはいきませんね。

日本は毎年、食料品を9兆円、エネルギーを27兆円も海外から購入することで、スーパーに物が溢れ、不自由なく電気を使用できているのです。のんびり王国路線が行き過ぎれば、こういう安心した生活環境は徐々に失われていくでしょう。

成長と分配のバランスは、大きなテーマです。これから各政党が色々な公約を掲げて選挙を戦います。「がんがん王国」と「のんびり王国」のどちらを目指しているのか、考えてみるのもいいでしょう。第26回は、そんな授業でした。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
