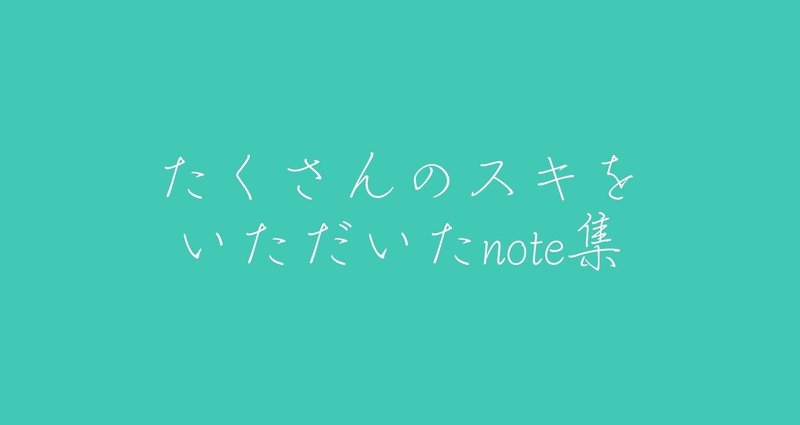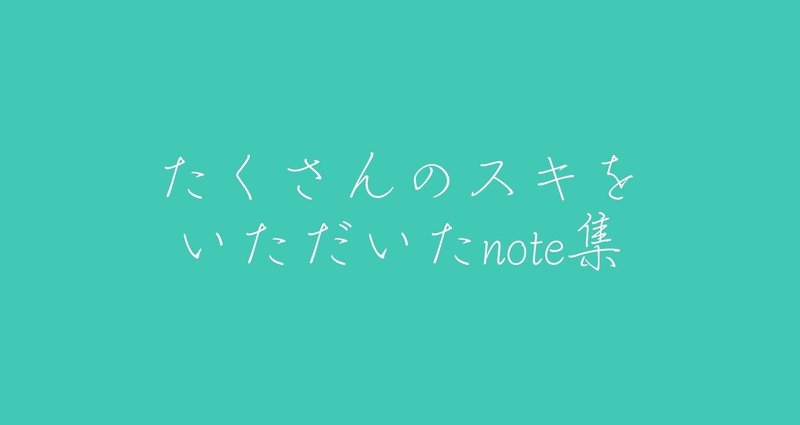コミュニティ時代の消費行動モデル「CoLoTASS(コロタス)」を提唱します
かつて、SNSの普及により消費者の購買における意思決定プロセスは劇的に変化しました。もはや企業からの一方的な情報発信だけでは消費者の心を動かすことは難しくなっています。さらに最近では、消費者は単なる個人としてではなく、コミュニティの一員として行動するようになってきました。
その結果、従来のAIDMAやAISASといった消費行動モデルでは捉えきれない、コミュニティを介した新たな購買プロセスが生まれています。そこで本記事では、この新しい時代の消費行動を表す「CoLoTASS(コ