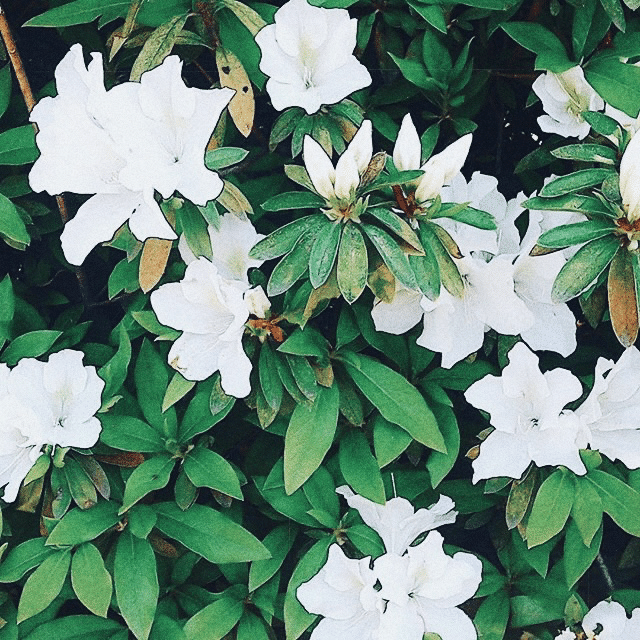八十八夜まで
令和4年4月某日、風が気持ちいいい。
とてつもなく良好な昼やな、と布団に寝ころぶ籠沼理事長は深く息を吸いこみ、吐いて、開け広げのガラス戸から流れこんでくる薫風を一身に浴びていた。
うす暗い畳の間で、干からびた蛙のように四肢を投げ出した籠沼はごろんと仰向けになり、風はその身体の上をすべり流れて、ちん毛がゆれる。
ベチ、と硬いような音の屁が出てからすぐ布団に当たって霧散した。それでこの男はカッと目を見開いていきなり詠むのである。
「群青の彼方、薫る風、畳の間、ちん毛靡く、立夏の午の静かなるをベチ屁で彩らん、これ画竜点睛なり」
「まぁ、お父さん…粋やわ」
と、こう嘆息するのは籠沼理事長と長年苦楽を共にしてきた糟糠の妻、春子である。和室の入り口近くに嫁入り道具の古い茶箪笥があって、その隣で彼女はだらしなく籐椅子に腰かけ、うちわを力なくあおいでいた。
垂れ下がってびよびよの乳は身体にへばりつき、肥満した腹に巻かれた自動腹筋ベルト「アブトロニック」がブルブルと震えて乳と乳のあいだに浮かんだ玉のような汗が、幾筋にもなってしたたり落ちていく。
「あぁしんど…」と漏らした春子の眼鏡は、身体から発せられる熱気で白くぼんやり曇っていた。

籠沼理事長は現在、かなり困難な立場にあった。というのも数年前に日本国内を一部騒がせた林友学園の補助金詐欺事件で、先日いよいよ高裁から実刑判決をくらったのだ。即日上告したものの高裁からは「こんなもんあかん」と一瞬で足蹴にされ、長期間の懲役がいかんともし難く、逃れようのない未来としてすぐ先に迫っていた。
こんな補助金がある、是非申請してはどうか。数年前のある日突如として、そう言われるがまま向こうの主導で話は簡単に進んでいった。そうして国から捨て売りの値でほとんど受動的に土地も購入し、新校舎建設の段階になって報道陣が図ったようにわらわらと籠沼のもとに嬉々として押し寄せたのである。
『"愛国教育"を謳う極右の学校法人が多額の補助金を不正に受給しとるぞ』みたいな記事が続々と紙面を埋めた。
担当者のブナシノという男を出せと籠沼があとで何度詰め寄っても国家機関は「そんな名前の人間は所属していない、一体誰の話をしている」の一点張りでこの理事長を突き放し、あっという間に「詐取」というので訴えられた。
記者会見では、席の白い机には形もさまざまなマイクが十本近くも置かれていた。
「なんでですのん。なんで上告が却られなあかんのですか、こんなんおかしいやないですか、一審も二審も。傍聴してた人やったらわかる思いますけど、あんなんまともな裁判とちゃいますで。そんなこと言い出したら、こんなもん最初っからぜぇーんぶ、おかしいけどやな。ともかく、不備もないのに、上告受理の申立書すらそのまま突き返してきたんですよあの裁判所は。どう考えても、仕組まれてますわ。ていうかなんで皆さんさっきからずっと笑ってはるの」
こんなことになるとは夫婦共々思ってもみなかった。どう考えても無罪、それしかあり得ないと信じきっていたし、こちらがしっかりと供述すれば、司法という独立した公権力が当然それを認めてくれると思っていた。
高裁に出廷する前夜、春子は明日に決戦を控える最愛の夫を慮り、夕食に大盛りのかつ丼をこしらえた。黒光りする漆のどんぶりに盛り、熱い味噌汁と共に足高の膳にのせて出す。それは最高の米を使い、最高の炊飯器で炊いた。最高の醤油だれを買った。最高の豚肉を最高の油で揚げた。
お父さん、お父さん。明日は勝つで。絶対に勝つで。曇った眼鏡の奥で春子の目がゆらめいて光った。
「ありがとう春子ぉっ。そうや、わしは負けん。絶対に勝つ」
いただきます、と言うのも忘れ籠沼理事長はかつ丼を丸飲みする勢いで食べた。ほとんど咀嚼せずとにかく喉に流し込み続け、眼は血走り、こめかみには青筋が太くくっきりと浮かんだ。
途中で咽せて大量の米粒が鼻に逆流し、涙と鼻水がだらだらと止まらなくなったものの、最後はどんぶりのふちにがっぷり口をつけて、かき込み、口の中がからになるなり声高に叫んだ。
「絶対に、勝ぁぁーっつ」
「そうや、勝つのはお父さんや」
春子は夫の食する姿を見守ってわなないた。
「お父さん…」と胸の前で両手を組むその様は、まるで十万億土の神仏に祈請するようでもあり、また、最愛の夫その人をこそ只々尊敬し、畏れ、自ずからそういうふうな格好に手を組んで「こんなもんどう考えても勝つのはお父さんや」とほとんど確信にちかい予断をしたものだったが、ところで春子はそのとき不細工な顔つきであった。
「絶対に、勝ぁぁーっつ」
「そうや」
「絶対に、勝ぁぁーっつ」
「勝てるでっ」
「おっしゃいくで、川のせせらぎ、立夏の宵、」
「あぁッお父さん」
「我が心は大勝負を前にして、乾坤一擲、」
「あっ、あァっ、お父さんええわぁ」
「いざ栄光をば、我と我が手で掴みに行かん」
「ほんまにかっこええわ」
「こんなんおかしいやないか、わてがいったい、何をしたっちゅうねん。何もしてへんやないか。こっちゃ真面目に学校の理事長やっとりますねん。それがなんで実刑やねん。真剣にこの国の未来を育てとるんや。それがやな、どこに捕まるような悪いことがあんねんな、この教育者に。おい誰や今笑ったやつ。どこの記者や。なにがおかしいねん、おいそこや、なにがおかしいんや」
判決の日は空が高く、群青の広がる天気だった。籠沼理事長は悠揚迫らぬ堂々とした態度で法廷に姿を現した。これ以上はないくらいの入念な準備と、昨日のかつ丼。その顔には被告人とは思えないほどの自信が綽々とみなぎって、開廷一番大声が響いた。
「絶対に、勝ぁーっつ」
で、あっさりと負けた。負けに負けた。話にならなかった。
それで上告も斥けられ、後におこなった会見ではカメラを向ける記者たちのシャッターをきる無数の音と、同数のフラッシュライトとを浴び、会場のほとんどの人間が籠沼の魂の叫びを聞いてにやにや笑っていた。
「おいそこ、なにがおかしいんや。なにをにやにや笑っとるんや」
会見会場はまさに籠沼理事長にとっては四面楚歌そのものであった。というのも最愛の妻春子が無意味で悪趣味な側杖を食らうことがあってはならないと、理事長が同席を許さなかったからである。
「春子、お前は家で大人しぃしとれ」
「お父さん…」
それでただひとり、理事長のみが顔から脇から背中から汗をしとどに滲ませて奮闘するのだった。しかしそれは虚しい抵抗であり、むしろ籠沼理事長が会場の無礼な雰囲気に対して怒りを露わにすればするほど、さらにその空間全体に蔓延する含みをもった嘲笑の調子は無慈悲にも濃くなってゆくばかりで、本筋から離れ、この会見で予定していた所期の弁明は一向に進捗しなかった。
「ええ加減にせんかい、なにがそんなにおかしいんや。あんな、おたくらな、よう聞きなはれ。人がやな、一生懸命に喋っとるんや。この国はおかしい。実刑なんておかしいちゅうて、こんなもんどう考えてもおかしいちゅうて理不尽な判決を受けた人間が、身一つで、ここに来て喋っとるんや。一つも笑われるようなことしてへんで、そもそも補助金もなんでブナシノちゅう男が林友の学あッッッこらそこっ、なにがおかしいんや言うてみぃッッ」
そんなことがあって以降、確定事項である「懲役」の二文字に頭を侵された籠沼夫婦は共にひたすら放埒な日々を送った。酒を飲んだ。やけくそというか、基本的に全裸で、春子はなぜか「アブトロニック」を腹に巻いて生活していたが、とにかくあと数日、その意識が2人の脳内をぐるぐると駆けめぐってパンクしてしまったのだ。
誰もみんな、自分たちの話を聞いてくれない。こちらが懸命になればなるほど、彼らは嗤う。
籠沼夫妻は、なにか巨大な遮蔽幕が自分たちを社会一般の領域から隔て、離しているような、そんな感じを味わった。脱出しようと幕に触れても、まさしく暖簾に腕押し、ふわりふわりと逃げるように翻るだけで虚しかった。
以前のような厳格で、引き締まった生活はすでにそこになく、特に籠沼理事長の方は一見して穏やかな表情で詩や句を創作したり「おおぉ、今日もいい天気になったねぇ」と安逸な感じがするものの、ふとした時に急に「ファァァック」とか「死ね!」とか顔を真っ赤にして叫んだ。
ほかにも、ウーバーイーツで注文した寿司をまとめて鷲掴みにし、配達員を猛然と追いかけ背中にその酢飯と魚肉の塊を投擲してへらへら笑う、公園で遊ぶ子供たちを一か所に集め、無理やり日清戦争の軍歌を歌唱させ「阿呆っ下手くそっ」と怒鳴り泣かせる、「夢っ、夢っ」と上機嫌で同じ横断歩道を何度も何度も跳ねながら行き来するなど、日に日に人間的な凋落の度合いはいや増し、ついには一句詠むことさえもなくなり、かつて自他共に認める堅物古風の人であった男の見る影など、今やどこにもない。
流石にこれはあかん、こんなん続けてたら、あかん。と、まだ幾分かの正気が頭の片隅に残っていたのは妻の春子の方だった。というのも実刑判決をくらったのは夫だけであり、彼が懲役に行った後も自分は普通の生活が続くのであるから、それを思うと狂うにも狂いきれなかった。
また春子が完全におかしくならずに済んだのは腹に巻いた「アブトロニック」のお陰でもあった。本人は気づいていなかったが、自動腹筋ベルトのしたたかな振動が、ともすると意識の奥深い陥穽に絶えず落下しかける春子を現実世界に引き戻し、自我の崩落をどうにか食い止めるありがたい命綱となっていたのである。
お父さん。さすがにあかん。そんな阿呆みたいなことになっとったらあかん。いくら刑務所入らんならんいうたって、しゃんとせな。もう懲役決まったもんはしゃあない。しゃんと背広着て、立派に入らなあかん。私が元に戻したる。
夫と反比例するように回復しはじめ、ふたたび服を着て生活を再開した春子のもとに、頃しも東京で働いている息子の太郎からお下劣な字のファックスがきた。

お父はんとお母はんと三人で、家族で団欒したい。息子の申し入れに春子は一も二もなく賛成し、すぐに大阪へ来るよう電報を打った。
なんちゅうええ子や。春子は胸いっぱいで、眼鏡は白く曇っていた。
「太郎、あんた今ええこと言うた。団欒や。そうやピクニックや。3人でピクニックするんはどないや。なんちゅうても、わたいら、家族やんか」
籠沼太郎は理事長と春子の一人息子で、林友学園の卒業生である。大阪の大学を出てからは東京の商社に勤務し、複数の女性社員に対する強制わいせつが問題となって退職。自らで籠沼商事を経営するも美人の女性若手社員ばかりを雇用して前から乳を揉んだり、うしろから尻を撫でたりしているうちに二年で倒産。
しばらく堕落した生活をつづけ、ある時ふと腕立て伏せをしてみたら「筋トレ楽しぃ」と気づいて「おれは好きなことだけして生きていくんや」と、彼の好きなものである女性と筋トレを合体させて女性専用ジムを設立。適当にインストラクトする合間にさりげなく、時には豪快に乳や尻や太ももを触り、押し、なで、揉み、叩き、さすり「人生最高」と顔を弛緩させムラムラしていた。
二日後の昼過ぎ、太郎は大阪の実家に帰ってきた。
【レディース筋肉塾 カゴヌMuscle】
というのがその完全マンツーマンの女性専用ジムであるが、一時的に休業するため、太郎は実家にFAXを送信したあと、しゃかりきになって動きまわった。
「ごめんよチハルちゃん、実はね、大事な用事があってね、来週はジムを閉めるんだ。うん、うんそうなんだ。ごめんね。でもね、チハルちゃん、その次の週になったらTAROUちんがね、いっぱいいっぱいチハルちゃんの筋肉、かしこくしてあげるからね」みたいな、親が聞いたら失神してしまうくらい気色悪い感じで会員の方々に無理をいってなんとか数日の余白をスケジュールに確保するなり新幹線に飛び乗った。親を心配する気持ちに偽りはなかった。

「ああっ太郎。よう帰ってきてくれた」
「お母はん、色々と大変やったな」
「わたいは何も大変なことあらへん、それより早よ、お父さんに会ったって」
脇目もふらず和室に直行した太郎が見たのものは、あられも無い姿で畳に寝転ぶ父の、無惨にも変わり果てた姿であった。
眼は落ち窪み暗くうつろで、太った痩せたは変わりないが、肌は土気色をして風呂に入っていないのか、饐えたような酸性の臭いが和室いっぱいに立ち込めている。禿げなのは元からにしても、残り少ない髪には白いものが増え、顔の下半分にも無精髭がごま塩になって茂っていた。
「お父はん太郎です。帰ってきました」
「……おおぉ。太郎かあ。よぉおぅ帰ってぇきたなあ。まあゆっくり…、していけえやあ。」
天井をまばたきせずに見つめる父の言葉は呂律も散々、まったく間伸びしていて、気力というものがその語勢になんらも加わっていない。
太郎はたまらず目頭を押さえ、これはあかん、とにかくピクニックや、それからその前に風呂や、と帰郷の挨拶もそこそこに、「お父はん、久しぶりに親子で風呂に浸かりましょうや」と言って抜け殻のような籠沼理事長の腕を自分の体にまわす。さすがジムの経営者なだけはある体躯──頑張って筋トレしたからではなく、ただ元々少しばかり体格が良いだけである──でしっかり支えながら浴室へと移動した。
「太郎あんたは、字ぃ汚いけどほんまにええ子や」
母である春子は、夫と息子二人がふらふら並び歩く後ろ姿を見つめ、鼻をすすりながら、またまた眼鏡を曇らせた。
外はまずまずの天気で暑すぎることもなく雲は千々になって浮かび、庭のツツジが真っ白な花を咲かせていた。甘い蜜を、その嫋やかなる花弁の奥に満々とたたえる季節のちょうど、たけなわの頃である。
それから丸三日かけて母と子は籠沼理事長をピクニックに連れていける程度にまでは「まとも」に戻そうと努めた。
まず服を着せた。次いで髭を剃って綺麗にし、栄養のあるものを無理にでも食べさせ丁寧に歯を磨く。朝はラジオ体操を二番まで止めず、飯のあとは道徳の教科書──それは籠沼理事長が林友学園初等科の授業教材として自らが選んだものであった──を読み聞かせることで人の心の機微、美しさを思い出させ、そして何より和歌、俳句、短歌、現代詩などを読み聞かせて日本の魂を理事長の心に呼び戻そうとした。
お父さんが、また詠むようになったらもう大丈夫や。背広着せて、自信持って送り出せる。
春子は何度も何度も歌集を開き、下手なりに節をつけて夫に聞かせた。「どや、お父さん。ずっとこんなんが好きやったやろ、自分で詠んでたやろ、それがかっこええのなんのって、もうわたいは毎回毎回、あんたに惚れ直してキリがないくらいや」
その甲斐あってか徐々に籠沼理事長は「まとも」に近づいてきていた。少なくとも発作的に気狂い行動を起こすことはなくなった。それで春子と太郎はある夜の帳が下りきった頃になるとリビングで話し合い「もう思い切って、いっぺんピクニックに連れて行ったらどないや」ということに相成って明後日がそのXデーと決まった。
そうとなれば急いで準備を。次の日二人はなんやかやとピクニックに要るものを用意し、家にないものは近くの商業施設で買い、剰え二人は勢い余って「ピクニック行くんやったらお父さんのええスーツがいるんちゃうか」という気になって仕立て屋で一張羅をあつらえる事に決め一旦帰宅し、父を引っ張り出してきた。
肩や胴や身体のありとあらゆる長さを計測し「一等ええ布で仕上げてつかぁさい」とか「完全防水にしてつかぁさい」とか「夏は涼しく、冬は暖かくなる感じ」などと母と子で好き放題言って三人は店を出たが普通に考えて生地から何からフルオーダーしたスーツが翌日までに出来上がるわけがなく、納期の頃本人はとっくに刑務所の塀の中なのである。
とにかく準備は整った、と春子と太郎は安堵し、今日のところはみんな早う寝ようで、と声をかけて寝た。
しかしその夜中、どこか近所の家で火事があったらしく、消防車、救急車、パトカーの阿呆みたいに大きなサイレンが家の前を何台も何台も通るのがやかましくて仕方がない。騒音に叩き起こされ、うちは大丈夫かいな、と火の累が及ばないかも気がかりなものだからそれから安眠とはどうにもいかず、結局、再び寝るには寝たが、誰しもの頭上へと等しく太陽がその姿をあらわす頃「もうピクニックやめて今日は寝とこうや」という言葉が出てしまいそうになるのを我慢しながら、不満足な思いで布団から這い出なければならなかった。
「ほなお母はん、ぼく家の前に車まわして来るさかい、ぼちぼちお父はん玄関まで連れて来たってや」
「ありがと。そしたらお母さん、お父さんの様子見てくるわ」
太郎と春子の話し声は、畳の間でぼんやり外の庭をうち眺めていた籠沼理事長の耳まで届いていた。昨晩の火事について、何処そこの家が火元らしいわ、ええほんまかいな、あそこの家の子供あんた小学校の時分の同級生とちがうかったか、いや、あそこのはちゃうわ、などと話していたが、ややあって太郎は家の外に、妻の春子はこちらに「お父さん準備はどないやぁ」と向かってくる。
洋風の部屋をあとから無理くり和室にリフォームしただけなので、籠沼のいる部屋には襖や縁側はなく、和風でもなんでもないガラス戸が調和せず残っている。そこからは庭の白いつつじが見えて、花の近くを色の淡い黄蝶が二匹ゆらりゆらと舞う、その大して模様のない羽根に陽の光が当たっている。見るからに暑そうな風景が広がり、五月も近づいて、しかし部屋は静かで、ひんやりと暗い。
「えらいえらい、お父さん一人で服ちゃんと着れたやんか。今な、太郎が表に車回してくれよるからな、もうちょっとしてから出るようにしょうか」
まるで頑是ない子供を相手にしているかのような妻の言い方に、籠沼理事長はわずかに顔を歪めた。それが笑った顔なのか、嫌悪の表情なのか、夫の横顔をみても判然としなかった春子は「あっそうや」とふいに部屋から出ていった。
「ちょっと待っとって」
角を曲がってキッチンの方へ消える春子の後ろ姿。頭には新婚当時にプレゼントしたベージュのフェルト帽が乗っかっていた。本当は、当時パチンコ仲間兼セフレであった中国人の女にプレゼントする予定だった帽子である。しかし渡す直前になってその女は帰国してしまったから、籠沼は落胆しながら、仕方なく妻に「春子、おまはんにな、わしのごっつぅ熱いこの想いを届けたいんや」と言って手渡したのだ。
今日そんな厚い帽子かぶったら外で汗かくで。違う帽子の方がええのに。心の中で籠沼はぼんやりと妻にそう囁いてから視線を庭に戻すと、つつじに群がる黄蝶がいつの間にか三匹に増えていた。そこにさらに数匹、集まって飛びはじめた、その時だった。
「どうも、こんにちは」
籠沼の視界の先のつつじは遮られ、見えなくなった。庭の横合いから黒スーツに黒シャツの男が音もなしにひょこりと出てきて、戸の外に立ったからである。それは籠沼に補助金の話を持ちかけ、とんとん拍子で話を進めていった役人のブナシノであった。
「今日ものすごぃ暑いですわ。こんなもん、おたくのあの太った嫁はん、あんなフェルトの帽子被って外出たら暑ぅて汗だらだらで死んでまうんやないですか」
ハンカチで首周りを拭っていたブナシノはそう言ってかけていた縁なしの丸眼鏡をはずし、後ろに放り投げてからやはははは、と屈託なく笑った。
「ブナシノ、おまえそこおったらわし、つつじの花がよう見えへんやんけ」
黄蝶が数十匹になっている。
「今からピクニック行くような人が自分とこの庭の花なんか、そんなん見んでもええやないですか」
「そんなわけにいくかい」
「それより僕と火事の焼け跡見に行きまへんか、ああいうの見るの、僕好き」
つつじの花に群がる黄蝶の数はまたさらに百匹くらいに増えてわらわらと舞っている。籠沼には、そのうちの何匹かが、ブナシノの身体越しにはみ出したり隠れたりしているのが見えていた。
「自分とこの庭の花やから見るんやんけ」
あんたも不幸な人やな、とブナシノはなんら同情する様子もなくそんなことを言ってから煙草に火をつけた。煙がタバコの先と、口から吐き出されて空気に混じる。
ブナシノは、ひと口大きく吸っただけですぐそれを横に放り捨て、また新しい煙草を咥えたが、なにが気に食わなかったのか、今度は火もつけずに捨てた。庭に集まった黄蝶の数は、すでに数百匹を超えていた。黄色い塊が、その意志を持った構成分子を失ったり吸収したりしながら流動し、宙に浮いている。
お父さん。という春子の声と足音が戻ってきて、和室に入るなり籠沼の前まで行って大きな丸い皿を、ほぅら、と言って見せてきた。
丸い皿の上には中央に円形、そこから放射線状に仕切りが付いていて、それぞれの仕切りの中には色々な中華料理が詰め込んであり、春子は声を張る。
「オードブルやで」
籠沼は妻の喋る大きな声を近くで、ぼんやり聞いた。目の前に皿がある。視界の奥には、千匹を超える黄蝶が集結し、その数をさらに増やしている。しろい花はそれで見えない。
「ええやろ、中華のオードブルやで。サンドイッチ作ったんやけどな、太郎もおるし、ちょっとお昼に物足りんか思うてな、こんなんもあったらええかと思うて、今朝作ったんや、お父さん中華好きやろ。太郎も中華好きやし、これ今日のランチに食べようなお父さん、ピクニック行こうで」
ほんまのこと言うたらこれ作った言うても冷凍食品もちょっと入ってるんやけどな、と笑う妻の声が聞こえる。籠沼はそれでもただ、安らかに外を眺め続けた。眺めて、目を離さず、一陣の風が静かに吹き過ぎると同時に口を開いた。
「良き天気、一陣の風吹き、黄蝶の波、中天を流るるは瑞雲なり」
「あッッッ、お父さんッ」
春子はあまりの驚きに皿から手を離してしまい、オードブルは畳に落ち、中身が飛び出した。揚げ餃子が散らばり、肉団子があちこちに転がる。春巻きは皮がやぶれて具がはみ出し、酢豚のあんが畳をべっとりと汚した。
「我、長夜の眠りより覚め、八十八夜の門出を待つ、行く末は獄なり、然るに安き心にある」
「あぁっ、お父さんが、お父さんがッ」
籠沼には、つつじの白い花はもう全く見えていなかった。数万匹の黄蝶が眼前の風景を波打つ黄色に埋め尽くしていたからである。
「藜羹を食らう者、大牢の滋味を知らず、されど藜羹の味を知る。我、大いなること、永きものを知らず、されど法界は晴天なり、オードブルを食し、屁をこきて、我と我が身はいっときの…」
すでに黄蝶は籠沼夫妻の家のぐるりを埋め尽くした。
「ああっ太郎、太郎ッ、お父さんが」
春子は腰が抜けて思うようにならない身体で、なんとか和室を抜けて、離れた場所で車を待機させる息子に声を届けようとした。
「あもしもしチハルちゃん?東京帰ったら今度さ、ジム終わりに一緒にTAROUちんの部屋で映画観ない?うん、うん恋愛系。」
そのとき太郎は車の中でダンス音楽をかけながら会員の女性に電話していて、母の呼び声など聞こえようはずもなかった。
人生最高。太郎は自分が自由で、愛すべきこの世界のどこへでも好きに羽ばたける鳥であるような気がした。
「ああッ、太郎」
やはり部屋からでは太郎に声は届かない。やはり玄関まで行くしかない。最初、春子は茶箪笥になんとか手をかけていたがバランスを崩してこけた。春子の曇った眼鏡がはずれ、箪笥の上に置いてあった「アブトロニック」もぼとんと落ちた。その衝撃で電源が入り、機体がひとりでに強く震えている。春子は夫の声が聞こえるたびにあああッと悶え、倒れ込んだ時に床に打ちつけた膝が痛んだ、がしかし気にしなかった。ンブブブブブブと自動腹筋ベルトが畳で震えて、うごめく。
「お父さんが詠んでるっッ」
太郎っ、お父さんが詠んでる、詠んでるで、という春子の馬鹿にでかい声が、その後もしばらくは家中に鈍く反響していた。