
【美術展レポート】恵比寿映像祭2025|マティアス・ピニェイロ監督のトークが面白過ぎた話
今年も恵比寿映像祭のシーズンがやってきた。恵比寿映像祭は毎年2月頃に東京都写真美術館で開催される映像作品を集めた祭典である。インスタレーションはもちろん、劇場一般公開が難しいような実験映画が上映されることから毎年注目している。過去には、FILM COMMENT誌未配給映画ベストに選出された『ヒューマンサージ3』や写真家のアンダース・エドストロームが義理の母・塩尻たよこの1年を相棒C・W・ウィンターと共に撮った8時間の作品『仕事と日(塩尻たよこと塩谷の谷間で)』、草野なつかのカルト映画『王国(あるいはその家について) 』などが上映されている。
1月31日(金)~2月16日(日)まで開催される恵比寿映像祭2025の目玉はなんといってもマティアス・ピニェイロ『You Burn Me』だろう。日本ではアテネ・フランセ主催のマティアス・ピニェイロ映画祭2014にて特集上映が組まれた程度で知名度こそ低いものの、『悪は存在しない』の濱口竜介監督が彼のファンであり、カイエ・デュ・シネマにて2010年代ベスト映画として『ビオラ』を、The Film Stageにて2021年ベスト映画に『Isabella』を挙げている。彼の作品は文学作品を脱構築していくスタイルであり、『Isabella』ではシェイクスピアの「尺には尺を」の世界を現代アルゼンチンへ置換しようと試みていた。
今回上映された『You Burn Me』はチェーザレ・パヴェーゼ「Dialogues with Leucò」《Sea Foam》における古代ギリシャの詩人サッフォーと人魚の女神ブリトマリスとの恋愛関係に惹きこまれたピニェイロ監督が、テクストを映像言語へ脱構築していく内容となっている。ピニェイロの作品はいわゆるストローブ=ユイレ系であり、そのハイコンテクストさから苦手意識を持っていたのだが、上映後Q&A含めたこの映像体験に興奮した。本記事では、『You Burn Me』のレポートを行い、その後、インスタレーション作品の中からいくつか気になった作品について語っていく。
マティアス・ピニェイロ『You Burn Me』
テキストを読む、印象に残ったものを集めていく。これは時空を超えた対話である。マティアス・ピニェイロは1947年に以前、1947年に書かれたチェーザレ・パヴェーゼ「Dialogues with Leucò」にトライするも挫折する。しかし、別のタイミングで挑戦したところ「面白いじゃん!」と興奮し、映像化を試みようとした。文学的体験を視覚・聴覚のメディアである映画へ落とし込むためにはどうすればよいか?彼はイメージとサウンドのつながりを意識した。そして、「記憶ゲーム」を作品へ盛り込む。建物の画/ボタンを押すアクション/垂れ流される蛇口の水、これら3つのイメージにTú(あなたは)/me(わたしを)/abrasas(燃やす)といった分割された言葉を挿入し、繰り返す。数度にわたる反復の後、イメージの並びはそのままに無音の空間を提示する。ただ、我々の脳裏には「Tú/me/abrasas」が浮かび上がってくる。印象に残る言葉は、時空を超えて反復される。この理論を軸に、ピニェイロは映像で遊んでみせるのだ。別の場面では、提示されるイメージと音が増えている。我々は同様に、音の反復を脳裏で行うのだが、それにはグラデーションがあり、複雑化していく記憶ゲームを前に抜け落ちてしまっている音が生まれて来る。ただ、イメージに関しては明白に「さっき見たイメージ」だと覚えているため、視覚・聴覚の記憶の揺らぎが意識されるのである。文学、特に詩が自分の中へと入っていく過程は、忘却/反復といった思索運動による経験の側面が強い。写真家の杉本博司はドキュメンタリー『はじまりの記憶 杉本博司』にて、「芸術」とは目に見えないものを物質化する技術だと語っていたが、ピニェイロが本作で実践した「記憶ゲーム」にはまさしく芸術における理論の物質化の側面があるのではないだろうか。


実際に上映後のQ&Aでは、監督によるある種のパフォーマンスが行われた。おもむろに床に紙のようなものを置き始める。スッと立ち上がり、紙を転がす。MCに「手伝ってくれ!」といいはじめ、巻物を広げていったのだ。


「破れてもいいんで、お客さんも手伝ってくれ!」
彼は、巻物の片方を持ち、客席の方へと回る。25mにおよぶ長い巻物は東京都写真美術館のホールに収まるわけがなく、客席をまたぐように伸ばされていく。
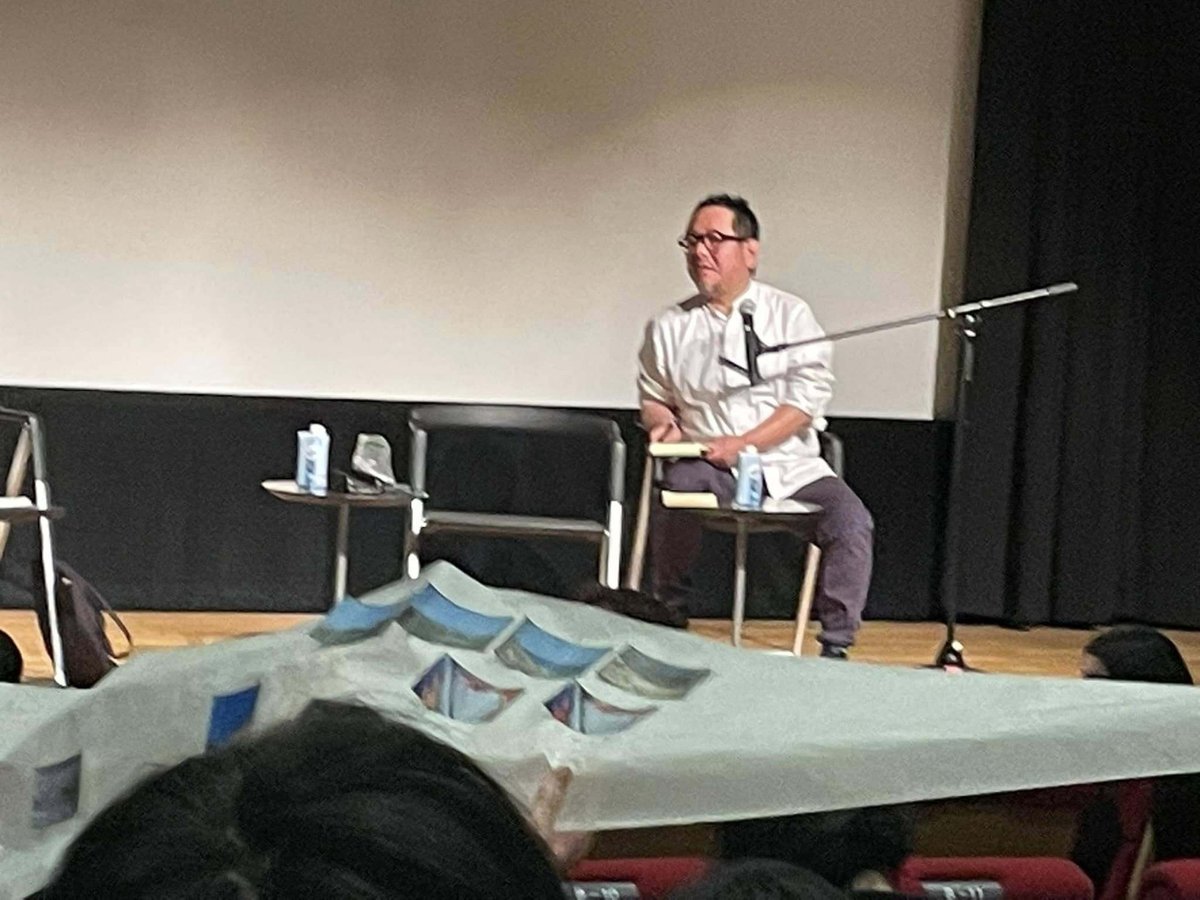
ピニェイロに動じることなく
翻訳していくスタッフさん


巻物は波のように客席右側から左側へと流されていく。最終的に通路に放置される形でトークが再開した。

ピニェイロは「Dialogues with Leucò」やサッフォーの言葉から連想されるイメージをメモしようとした。映像編集する際、横長のタイムラインにイメージやサウンド、エフェクトにテロップを乗せていく。
「パソコンの画面だと小さいんだよね、この問題を解決しようとした際に《巻物》といったアイデアが浮かんだんだ」

と語る。実際に通路に置かれた巻物を覗いてみると、映像編集ソフトのタイムラインさながらイメージやメモが規則正しく並んでいた。

思索を物質化していった

映画へ落とし込む前にピニェイロは思索を物質化していくため、いくつかの手法を試していたようで、巻物の他にはノートにイメージやメモをまとめていた。
たしか蓮實重彥が「凄い映画を撮る監督ほど平凡である」といったことを語っていたような気がするが、マティアス・ピニェイロの場合、まさしく映画よりも本人の方が面白いといった感じで、Q&Aを踏まえた後だと5割増しぐらいに『You Burn Me』が魅力的なものとなった。
↑「記憶ゲーム」の場面が気に入ったので自分で再現してみた。

「俺が散らかしたからあとでやるよ、そこに置いておいて」と
ピニェイロが言い始め困惑するスタッフたち。

アピチャッポン・ウィーラセタクン『Box of Time』

恵比寿映像祭インスタレーション部門を覗く。まず、初手がアピチャッポン・ウィーラセタクンである。アピチャッポン・ウィーラセタクンといえば『ブンミおじさんの森』でカンヌ国際映画祭最高賞にあたるパルム・ドールを受賞したタイのマジック・リアリズム系映画作家である。彼は、インスタレーションの数多く手がけており、昨年は上野SCAI THE BATHHOUSEにて『Solarium』を発表した。今回の作品は一風変わったものとなっている。
学芸員から手袋が渡される。ブースへ行くと、小さなクリアケースが陳列されている。箱を開けると50枚ほどのカードが出てくる。カードショップでレアカードを探すオタクのように捲っていくわけだ。最初は真っ暗な寝室の写真となっているのだが、30枚超えたあたりから陽が差し込み、寝ている老人の姿が顕となる。アンディ・ウォーホルが寝ている愛人ジョン・ジョルノを撮り続けた『Sleep』を脱構築したような内容となっていたのだ。
映画は1秒間に24コマのイメージが連なってできている。いわゆるパラパラ漫画のような世界である。しかし、あまりにもイメージの遷移が早いためデジタルな運動にもかかわらずアナログな運動に感じるのである。しかし、近年、映像メディアはデジタル化され、パソコンやスマートフォンで観ることができ、任意に巻き戻したり、飛ばしたり、早送りしたりできる時代となった。「映画に流れる時間へ介入する」ことを認知させる体験が今回の『Box of Time』での狙いだろう。映画も小説と同じように捲ったり戻したりしながら、そこに広がっている情景を読み解いていく。映画監督でありインスタレーション作家であるアピチャッポン・ウィーラセタクンならではの慧眼さに心奪われた。
カウィータ・ヴァタナジャンクール『A Symphoney Dyed Blue』

仄暗いブースへともぐりこむ。そこには2m×2mぐらいのモニタが床に設置されている。白い泡に囲まれた空間を裸の女性が大の字になりながら回転している。手、足、そして口でヒモを支えながら、回転と共に少しずつヒモがほどけていく。これは繊維工場から川へ流される産業廃棄物による影響を反映した作品となっており、ヒモ=繊維、肉体=市民の痛みを象徴させている。強烈な社会批判のイメージを浴びた。
藤幡正樹『藤幡版、これはパイプではない』『Capture in Half』
地下のフロアでは、藤幡正樹のインタラクティブアートが展示されていた。

まず、ミシェル・フーコー「これはパイプではない」が提示される。これはルネ・マグリット「イメージの裏切り」が本の表紙になったものだ。「イメージの裏切り」はパイプの絵に"Ceci n'est pas une pipe.(これはパイプではない)"と記述することで、言葉によってものが定義される様を捉えた作品だ。藤幡正樹の新作は、ここから着想を得ている。タブレット端末にパイプの絵が描かれている。画面にタッチすると、切り替わって"Ceci n'est pas une pipe."と表示される。また、画面にタッチすると元に戻る。イメージと定義が結びつく関係性を鑑賞者に体験してもらう作品に仕上がっており、興味深く観た。
彼はほかにも端末を使用したインタラクティブアートを展示している。『Capture in Half』では、額縁に写真と切り取られた葉が並べられている。タブレットで写真にフォーカスを当てると、展示されている葉が生み出される瞬間、つまり葉が切り取られる瞬間の映像が映し出されるギミックとなっている。写真、そして展示されている葉との間に断絶された時間を鑑賞者が取り戻していく奇妙な体験に心がざわついた。
杉本博司『劇場』シリーズ

映画好きとして嬉しかったのは、杉本博司『劇場』シリーズが観られたところにある。『劇場』シリーズとは、映画館の上映中にカメラを回し続けて撮られた写真群を示す。長時間撮影することによって、スクリーンからイメージが消え去り真っ白な画が浮かび上がってくるのだ。写真は真実を映すメディアだと思われがちだが、杉本博司は人間が知覚できない虚構的世界をカメラに収めてきた。実際に撮られているのに、存在しない空間の不思議さ。真っ白なスクリーンには何が映っていたんだろうとワクワクさせられたのであった。
■開催情報

企画名:恵比寿映像祭2025 Docsーこれはイメージですー
会期:2025年1月31日(金)~2025年2月16日(日)※基本10~20時
料金:無料(一部有料)
場所:東京都写真美術館
いいなと思ったら応援しよう!

