
『テヘランでロリータを読む』読書感想文
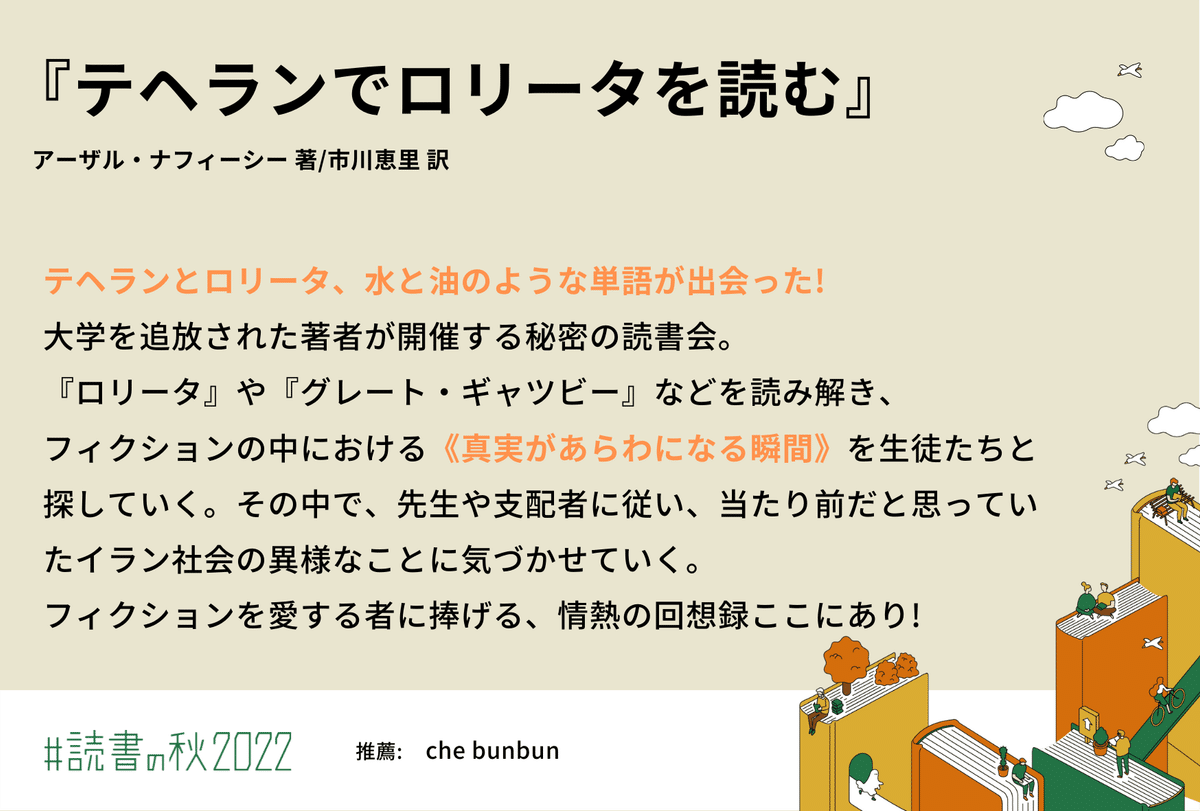
本屋へ行くと思わぬ出会いがある。何気なく、本棚を眺めていた時、思わぬタイトルが眼前に飛び込んだ。それが『テヘランでロリータを読む』である。
テヘランといえば政治的に厳しい国「イラン」の都市である。『ロリータ』といえば官能小説のイメージが強い。この水と油ともいえる2つの単語が結びつくことがあるのだろうか?
そんな興味からこの本を手に取った。既に一度読んでいるのだが、今回note企画「読書の秋2022」の課題図書に選出されていたので再読した。新しい発見もあったので、ここに読書感想文を書いていく。
■小説の中に真実を求めて
本作はイスラーム革命後1980年代から90年代にかけて、テヘラン大学で教鞭を取るも、ヴェールの着用を拒否したため追放され、秘密の読書会を通じてイランの女性たちに文学を教えていったアーザル・ナフィーシーの回想が綴られている。本書で扱われている人々のことを考慮して、一部脚色しているのである種のフィクションでもある。雰囲気としてはノーベル文学賞を受賞したアニー・エルノーの小説に近い立ち位置であろう。全部で4章に分かれているのだが、生徒に発した言葉の重みが後の章で明らかになることもあり、一度ページを捲ると次のエピソードが気になってしょうがない。惹き込まれる内容となっている。例えば、冒頭アザール・ナフィシーが生徒に対してよく語っていたと供述する場面がある。
「どんなことがあっても、フィクションを現実の複製と見なすようなまねをして、フィクションを貶めてはならない。私たちがフィクションの中に求めるのは、現実ではなくむしろ真実があらわになる瞬間である。」
我々はなぜ、小説やアニメ、映画などといったフィクションに触れるのだろうか?
仕事や勉強が辛い時の現実逃避としての役割もあるだろう。一方で、今や現実はコロナ禍や戦争、経済破綻に汚職などといったフィクションの中でもあまり見ないほどに凄惨な出来事が次から次へと押し寄せてくる。現実がフィクションを越えてきてしまっている。そうなってくるとフィクションは現実の複製に過ぎないと考えてしまうかもしれない。しかし、アーザル・ナフィーシーはそれに「否」を唱える。この分かりそうで、彼女がなぜこの言葉を発するのかについては最初の方は掴めない。これが明らかになるのが第三部《ジェイムズ》である。
1980年にイラン・イラク戦争が始まると、政府は公共の場で女性がチャドルと丈の長いコート、そしてスカーフの着用することを義務付けた。当然ながら、イランの女性たちは反対したが力づくでこの規制は行使されていった。彼女自身もその影響を受け、警備員に凄惨なボディチェックをされる羽目となった。異常な状況を前に彼女はあるゲームをするようになる。それは、「見えない存在」になることであった。人間との接触を避け、袖の中に手を引っ込め、幽霊のような存在になろうとしていたのだ。
無関係になった人間はどうするか。彼らは時として実際に逃亡し、それが不可能な場合は、もとの場所に復帰しようとする。征服者の特徴を身につけることで、ゲームに参加しようとする。さもなくば、内面に逃避し、ジェイムズの小説『アメリカ人』のクレールのように、自分の小さな居場所を聖域に変え、人生の本質的な部分を一目にふれぬところに隠してしまう。
彼女の念頭にあったのは小説だった。ヘンリー・ジェイムズ『アメリカ人』の登場人物であるクレールと自分を重ねた。そしてフィクションと現実を同一視した。彼女の「見えない存在」になろうとする行為は、イラン政府による抑圧の特徴を分析した行動であり、彼女はゲームとして現実をサバイバルしようとした。当時の彼女のことを「病的な状態」であると評価している。
冒頭で言及される「私たちがフィクションの中に求めるのは、現実ではなくむしろ真実があらわになる瞬間である。」というフレーズにおける《現実》とは、1980年において『アメリカ人』で描かれた内容がイランの政情と重なった瞬間を指し示していると考えられる。この病的な状態、居場所のなさから来る不安定な精神は彼女以外のイラン人女性に蔓延していた。そんな女性たちを救うべく、彼女は秘密の読書会を開く。小説に、フィクションに興味がある人を集める。しかし、読み方を間違えるとかつてのナフィーシーのような状況に陥る。小説に「真実」を求める旅路へと連れ出したのであった。
■『ロリータ』に向けられた官能小説の眼差しから逃れる
ウラジミール・ナボコフの『ロリータ』は、大学1年生の時に読んだことがある。「ロー……ロリータ」と囁くような文体は生々しく、官能小説の印象が強かった。それはひょっとすると、小説の表面的な部分、現実的な生々しさだけを見ていただけかもしれない。ここで描写される真実とはなんだろうか?ナフィーシーはナボコフの「優れた小説はおとぎ話だ」という言説を援用して次のように述べている。
あらゆるおとぎ話は目の前の限界を突破する可能性をあたえてくれる。そのため、ある意味では、現実には否定されている自由をあたえてくれるといってもいい。どれほど苛酷な現実を描いたものであろうとも、すべての優れた小説の中には、人生のはかなさに対する生の肯定が、本質的な抵抗がある。作者は現実を自分なりに語り直しつつ、新しい世界を創造することで、現実を支配するが、そこにこそ生の肯定がある。あらゆる優れた芸術作品は祝福であり、人生における裏切り、恐怖、不義に対する抵抗の行為である。
『ロリータ』の場合、「ある個人の人生を他者が収奪したこと」が真実であると彼女は語る。居場所のない12歳の少女ドローレス・ヘイズに対して、ハンバート・ハンバートは《ロリータ》と愛称を与える。そして《ロリータ》に死んだ恋人のイメージを注ぎ込み、支配していく。ドローレスは《ロリータ》の名の下に抑圧され搾取されていく。その渦中で、ドローレスとしての人生の片鱗が垣間見えるのだ。この真実に辿り着いた上で、現実を見回す。イラン政府によって、個人の自由が抑圧されていることが分かる。それは、自分の意志で正しいと思って行動していることですらイラン政府によって操られていることにも繋がっている。
後の章で語られる、当時イラン唯一の女子大であったアルザフラー大学でのエピソードがこのような状況の具体例として光る。イランで教鞭を取り始めて1年目。この大学で中間テストを行い採点していると、ある違和感に気づく。それは、自分が講義で話した内容を一語一語正確に再現したリポートが提出されたことだった。それも1人だけでなく4人もいたとのことだった。生徒たちの授業と対象の小説を踏まえた論考を求めているのに、提出されたのは複製されたアーザル・ナフィーシーの論考であった。カンニングではなかったにしてもこれは酷いと激怒する彼女だが、彼女は知らなかった、イランの生徒は小学生の頃から、先生の言われたことを丸暗記することが求められていたのだ。だから、この授業でも当然のように忠実に先生の話を再現しただけだったのだ。彼女たちに悪気はない。むしろ、先生を喜ばせようと書いてきたものだったのだ。
本書は、このように小説に対する論考と並行して80~90年代におけるイランの生活を描くことによって、フィクションの中に存在する現実ではなくむしろ真実があらわになる瞬間を見出していく。
■『グレート・ギャツビー』裁判
ある日、ミスター・ニヤージという学生が『グレート・ギャツビー』について「あの小説は不道徳であり、若者に悪影響を与える」と訴えてくる。フィクションと現実との間に差がないような学生であった。ナフィーシーはここで妙なことを思いつく。『グレート・ギャツビー』が罪か否かについて裁判をしようと。学生と共に議論をする場として「裁判」というフィクションを用意したのだ。最初は、『グレート・ギャツビー』と関係ないところで持論が展開されていくが、議論を深め合う中で、物語の構造が分析されていく。そして、やがてミスター・ニヤージの理想と、『グレート・ギャツビー』が批判している社会の側面が実は近いことに気付かされていく。
議論というと、日本ではいかに自分の論に相手をひれ伏せられるかといったプロレスのイメージがつきつつある。「論破」が一部の人の間で美徳とされつつある。しかし、本来の議論は、複雑な問題に対して互いの論を照らし合わせながらより良い解決策や論を導き出すことである。論破には、論を磨き上げる要素はない。『テヘランでロリータを読む』で展開される議論は、先生であるナフィーシーですら内省し、社会を見る目や小説と社会との向き合い方をアップデートしていく要素がある。
「異議あり!」
と逆転裁判さながらの盛り上がりの中、勝ち負けを越えた建設的な議論の空間が生み出されていく様に興奮する。また、私は会社で「議論」をできているのだろうか?と振り返るきっかけにもなった。
■映画の話あれこれ
実は、本書は映画の話も数多く登場する。VHSでハワード・ホークスやヴィンセント・ミネリのなどの作品を観たといったエピソードからイランの検閲制度への言及もある。
イランの映画検閲といえば非常に厳しいイメージがある。実際にヴェネツィア国際映画祭とベルリン国際映画祭で最高賞を受賞した巨匠ジャファール・パナヒ監督は2010年に拘束され、20年間映画制作と海外渡航を禁じられた。彼の場合は、フラッシュドライブの中に作品『これは映画ではない』を入れ、こっそりカンヌ国際映画祭に送り上映を実現させたり、タクシー運転手をするフリをしながら『人生タクシー』という映画を撮った。しかし2022年7月、イラン当局によって逮捕され収監されている。収監されている中、ヴェネツィア国際映画に新作『ノー・ベアーズ』が出品され、特別審査員賞を受賞するも会場に足を運ぶことは叶わなかった。
ナフィーシーによれば、1994年までイランの首席映画検閲官は盲目的であったとのこと。元々、演劇の検閲をしていたこの人物は、目の前が見えないような分厚いメガネをかけて、隣にいる助手が舞台上の動きを説明し、その内容を踏まえて削除すべき部分を指摘していたとのこと。その方式が映画にも踏襲されていたようだ。つまり、演劇も映画も実際の内容は知らないのだ。この検閲官が去った後も、脚本家に録音テープを送ってもらう方式が採用し効率化を図ったものの、実体を見ずに内容を判断する盲目的な検閲が続いた。市民が、イラン情勢によって行動を制御されていることは先述した。しかし、内部の人間ですら、組織によって作られた異様な行為を受容してしまっていることが分かる。
また、中盤にはミスター・フォルサティーという人物が、タルコフスキーと映画ファンの関係からジェイムズ・ジョイスとヘンリー・ジェイムズとの違いについて論考を語る場面があるのだが、これが非常に興味深い。
彼によれば、タルコフスキー・マニアは至るところにいて、石油相さえ家族と見に行ったという。人々は映画に飢えていた。ミスター・フォルサティーは笑いながら、理解できない映画ほど人はありがたがると言った。それが本当なら、みんなジェイムズを好きになるはずよと私は言った。それはちょっとちがいます、と彼はぬかりなく答えた。タルコフスキーのように尊敬されるのはジョイスです。ジェイムズに対しては、わかったと思うか、わかるはずだと思うから、頭にくるんですよ。ジョイスのような見るからに難解な作家より、ジェイムズのほうが受け入れるのが難しいんです。
確かにこの話はあると思う。日本映画の場合、英勉監督がジェイムズにあたるのではないだろうか?『映画 おそ松さん』や『映像研には手を出すな!』など、一見すると漫画、アニメ映画であり、アイドル映画なのだが、よくよく観ると、幾重にも映像の質感やジャンルを横断し駆け抜けていく作品となっており、カイエ・デュ・シネマが評価したジェリー・ルイス映画に近い高度なテクニックを用いた大衆娯楽映画へとしあがっている。掘り下げると難解な作品であるが、「わかった」と思うから過小評価されてしまうのではないだろうか。
■最後に(「読書の秋2022」に参加してみて)
「読書の秋2022」企画で12本もの読書感想文を書いてみたが、改めて読書の面白さと読書感想文の奥深さを感じた。映画の感想に関しては、基本的に観たらサクッと1時間ぐらいで書き上げてしまうが、本の場合、どこを引用するか悩むことも多い。それを探す中で新しい文脈を発見することもある。それはまさしく、山から金脈を当てるような作業である。読書を続けていく中で新しく、読みたい本も増えたので、読書感想文は続けていこうと思う。
今回の『テヘランでロリータを読む』記事はこの企画最後の読書感想文ということもあり、力を入れてみた。普段、映画というフィクションと現実との関係性を文章化している私にとって、アーザル・ナフィーシーの小説との向き合い方は刺激になった。劇的な状況が決まりきった日常になり、我々が自分の意志で行動していると思い込んでいるものが、実は社会による抑圧によって突き動かされたものかもしれない。フィクションを読み解くことは、隠されてしまった真実を明らかにし自分の生活を見直すきっかけとなる。と同時に、そこに潜む落とし穴も彼女は語る。落とし穴は誰しもがハマる。
だから私も、今日も、明日も、フィクションについて語り続け、仲間と語り合うのである。
いいなと思ったら応援しよう!


