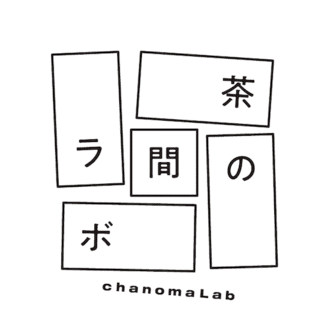最後まで出版人として走り抜けた蔦屋重三郎。脱帽のビジネスセンスを音声で解説!聴かなきゃそんしちゃうぞ。
仕事でこの人と一緒にやっていると刺激を受けるな〜っていう方、いませんか?日本史上最強の出版人、蔦屋重三郎と一緒に仕事をしていた人もそういう気持ちだったのだと思います。
和樂webでは、そんな魅力あふれる出版人でありプロデューサー、蔦屋重三郎の人生を3回にわけて音声で解説中!
20代では一介の吉原の本屋だった彼が、当時の江戸で大流行した狂歌の作者たちをまきこんで、インフルエンサーたちのハブになり、たった10年で日本橋の巨大出版社の経営者になったところまでが前回・前々回の話。
今回は「フォーエバーつたじゅう!蔦屋重三郎は最後まですごかった」と題し、30代後半から47歳で亡くなるまで、逆境をものともせず出版人としての人生を走り抜けた生き様を取り上げます。
▼第1回:一介の本屋が数年で出版社の経営者になるサクセスストーリー
▼第2回:貪欲にビジネスを拡大し、流行の最先端を作る側に
主力商品が規制の対象に!その時どうする?
積極的にビジネスを展開していた蔦屋重三郎に襲いかかったのは松平定信が行った寛政の改革(1787年〜1793年)。蔦屋重三郎がビジネスの軸としていた狂歌本や黄表紙などが取り締まりの対象になり、文武両道が推奨されました。
そんな状況下、あなたが蔦屋重三郎の立場ならどうしますか?
①反骨・諧謔の精神で立ち向かい、黄表紙を出し続ける
②改革に対する不満を捉えた本を出版
③他のジャンルを開拓
私だったら③をまずは選択するかな。でも日本史上最強の出版人、蔦屋重三郎はこれらをすべて行っています。さすが......!セバスチャンからは「サッチーは浅い!」というコメントが聞こえてきそうです。noteでは編集部スタッフサッチーがどんなことをしたのか、ばくっとご紹介します。
江戸の3分の1の出版物を占めた!?山東京伝とのタッグ
寛政の改革が始まる少し前の1785年ころから、蔦屋重三郎は吉原通の山東京伝と組み、吉原を舞台にした黄表紙・洒落本を独占的に出版していました。ちなみに山東京伝の生涯出版点数はなんと300点以上!現代のベストセラー作家もびっくりな出版点数なのでは!

山東京伝作 『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』。団子鼻がチャームポイントのブサメン・艶二郎(19歳)が悪友を利用してあの手この手で女性にモテようとする愉快なストーリー。国立国会図書館デジタルコレクション
そんな中で始まったのが寛政の改革。武士を中心に厳しく取り締まりを受けたため、戯作者だった多くの武士階級が黄表紙や洒落本の世界から身を引きます。
一方、もともと浮世絵師だった山東京伝は蔦屋重三郎とともに幕府批判ともとられる本を次々と出版。一時は江戸の3分の1の出版物を占めたとも!蔦屋重三郎が反骨の精神の持ち主と評される一端がここで垣間見えます。
しかし、幕府批判の本を販売したその理由は反骨精神だけではないと高木さんは言います。
寛政の改革で幕府への不満がたまっている時に、その気持ちを捉えた本があれば売れると考えたのでは......?というのがその見方。自分の会社の基軸がゆらぎかねない時に、時代の風潮を読んでビジネスを手掛ける冷静な姿勢に私は驚きました。
結果的に幕府に目をつけられた蔦屋重三郎は財産半分没収、山東京伝は手鎖50日の処分を受けます。資金力が低下しても、蔦屋重三郎は持ち前の若い才能を見つけて育てる術で不死鳥のように復活を遂げるのですが、その手法についてくわしくは音声コンテンツをお聞きください。
流通革命で全国を狙う
吉原の本を垣根を超えて日本橋から流通させた彼は処分後、書物問屋と呼ばれる学術書や俳句など、ちょっとお硬い本を扱う出版社の団体に加入します。
その理由は、
①寛政の改革により文武両道が推奨されたことで空前の学問ブームが起こっており、お硬いジャンルの出版ビジネスは盛況だった
②書物問屋の多くは京都や大坂発祥で、今まで彼が流通させていた地本問屋とはまた別の販売ルートをもっていた
ということから黄表紙のような本がだめならお硬い本を出版し全国に流通させようと考えたようです。
処分を受けてもなお、反骨の精神だけでなく持ち前のセンスを生かして出版を拡大していった蔦屋重三郎は47歳でこの世を去りますが、その後も彼が育てた若手作家(曲亭馬琴、十返舎一九など)が才能を開花させ人々を楽しませていくのでした。

曲亭馬琴作 『椿説弓張月』 葛飾北斎画 国立国会図書館デジタルコレクション
私にとって喜多川歌麿や東洲斎写楽のプロデューサーというイメージが強かった蔦屋重三郎。ビジネスパーソンの側面から人生を俯瞰してみると全然違って見えることや、今でも十分通用しそうな彼のビジネスセンスに驚きの連続でした。
▼蔦屋重三郎の人生を音声で解説!視聴はこちらから
※アイキャッチは「絵草紙店」葛飾北斎(1802年)国立国会図書館デジタルコレクションをトリミング。蔦屋重三郎が経営する書店「耕書堂」を描いたもの
いいなと思ったら応援しよう!