
「集まるのが大事」第一回合宿勉強会の記録+(政治的・宗教的)自己紹介
以下は七月三日から五日にかけて「集まるのが大事」と銘打って行われた合宿勉強会の記録である。
主催者は、自粛の圧力に抗してバーを開きつづけた松山孝法氏、共栄主義者、ファシストのトモサカアキノリ氏、そして現代アートの文脈で渋家(シブハウス)というネットワークないしシェアハウスを制作した齋藤恵汰氏の三名。大阪某所で行われた。日程は以下の通り。
七月三日 「技術と経済」
松田卓也: コロナとシンギュラリティ
井上智洋: 最強国家日本の作り方
七月四日 「芸術と批評」
大野左紀子: アートという病
黒嵜想: 批評がスパイ 尾崎兄弟に関する調査報告書、ならびに試論
五野井郁夫: コロナ禍後の生政治のグローバルな展開
七月五日 「音楽と革命」
切腹ピストルズ飯野隊長: 日本やり直し考二〇二〇
外山恒一、ロマノ・ヴルピッタ: ファシズム、現代、日本
外山恒一: 外山恒一トークライブ
以下の記録は以上の講演の内容をおおまかに書いたものである。ノートのもれ、記憶のもれ、記述上の割愛など講演の再現としては不完全であろう。また質疑応答は三日目の対談についてしか書かなかったが、どの講演に対しても興味深い質疑応答がなされている。
また一日目の晩から二日目の晩にかけて「無尽講ワークショップ」がひらかれたことも重要である。「無尽講」とは日本の民衆の間で自然発生的に生まれた相互扶助の会のことで、地域、時代によってさまざまな形態をとった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%B0%BD
ワークショップでは複数班に分かれて無尽講の知恵を現代に活かす方法が議論され、それが二日目の晩に発表された。この内容も興味深いものであるのだが、正確に記述できる自信がないので、ただそういうことも行われた、と触れるにとどめておきたい。
そしてもちろん一番重要な要素は様々な人が「集まった」ということである。コミュニスト、ファシスト、アナキスト、国粋主義者、リベラリスト、シーア派・・・・・・このような人々との出会いこそがこの会の最も重要な部分なのだが、それらについて詳述することは控えさせていただきたい(ただし、最後に付加した「(政治的・宗教的)自己紹介」のなかで、ある一幕だけは紹介している。これについては議論の流れや人の口ぶりなど不正確な部分もあると思われるがご容赦いただきたい)。
記事タイトルには「第一回」との文字を入れたが、具体的に次回の予定が決まっているわけではない。しかし何らかの動きがあることは確かであり、興味がある方は主催者たちの活動を注視しておくことをおすすめする。


(上図は事前に主催者の作成したビラ。五野井氏の講演は急遽決定したので、このビラには書かれていない。)
一日目 「技術と経済」
松田卓也: コロナとシンギュラリティ
松田卓也氏は天文学者、宇宙物理学者であり、現在人工知能についての研究を行っている。一九四三年生まれ、御年七十七歳である。今回は直接会場にはいらっしゃられず、zoom会議での講演となった。
勉強会は目下の「コロナ禍」の話題からはじまった。松田氏はまず感染症流行の数理モデル「SEIRモデル」について解説し、この理論にのっとるならば「何も対策を講じなければ約四十二万人死ぬ」という西浦教授の言は間違っていないことを確認する。
しかし現実はそうはならなかった。これは対策が効いたということだろうか。日本では実際の死者は約千人だが、イギリスでは五十一万人死ぬといわれたのが四・四万人、米国では二一〇万人といわれたのが十三万人であった。
海外の学者にはそもそもの理論に間違いがあるのではないかと「免疫的ダークマター」を提唱するものもある。またさらに日本、アジアは西洋に比べてなぜか単位人口死者数が異様に少なくこの「ファクターX」が何なのかは謎が多い。
さて、どうしてかは分からないが、今回の新型コロナは病気としては大したことがない。しかし、それは世界の既成秩序を明らかに破壊している。コロナはいわば「シンギュラリティ」である。世界がそれ以前に戻りえない不可逆点である。
講演はそこからいわゆる「シンギュラリティ」の話に入る。二〇二九年にコンピューター、AIが一人の人間の知的能力を追い越す「プレ・シンギュラリティ」が起こり、二〇四五年にコンピューター、AIが全人類の知的能力を追い越す「シンギュラリティ」が起こる。
松田氏は世界のさまざまなAIの研究開発を行っている企業を紹介し、誰か私の夢見る超知能研究所のために七五〇〇億円出資する者はいないか、と述べる。
さて、氏のシンギュラリティ観の特徴は強いシンギュラリティではなく弱いシンギュラリティを望む、という点にある。つまり意識をもったAI、強いAIの出現を望むのではなく、弱いAIで人間の知能を拡張することで生まれる「ホモ・デウス」の出現を望むのである。このことを彼は「私は半知半能の神になりたい」と表現する。
これは決して強いAIが技術的に不可能だから云々という理由にあるのではない。単に興味がないのである。その後の質疑応答の中で、人間の精神を完全に再現したAIは果たして可能なのかという問いに対し、彼は言う。
「鳥を模倣した飛行機は鳥を超えた飛行力を持ちますが、鳥と同じではありません。同様に人間を模倣したAIは人間を超えた知能力を持つでしょうが人間と同じものにはならないでしょう。そして私は人間と同じものを作ることには興味がないんです。私は鳥じゃなくて飛行機、人間じゃなくてAIを作りたいんです。だいたい人間を作るならもっと簡単で楽しい作業で済むじゃないですか。」
おじいちゃん然としたおだやかな声で何やら不穏なことを言うのが松田氏の特徴であった。「人間を解剖しても人権なんて出てこないでしょう?」とほがらかに言う彼の声が、zoom会議からこちらに響いてきたのが印象的である。
井上智洋: 最強国家日本の作り方
一八二〇年の時点で、世界のGDPの一位、二位は中国、インドであった。それがわずか数十年で植民地、後進国の地位にたたきおとされる。「大分岐」と呼ばれるこの事態は、イギリスで産業革命がおこったことによる。
産業革命は、とくに鍵となる技術によって四つに分けることができ、その技術をどこの国がいち早く開発したかによってヘゲモニー国家が定まる。蒸気機関とイギリス、内燃機関とアメリカ、ドイツ、そしてコンピューターとネットでまたアメリカ、最後にAI。
このヘゲモニーを握る国家はまだ定まっていない。だが中国は有力候補の一つである。この約二世紀間没落していた中国はふたたび世界の覇権を握るのではないか。「リオリエント」という言葉がささやかれている。
ところで、なぜヨーロッパは近代において発展したのだろうか。これについてはその「諸国併存体制」による、という考えがある。つまり、一国の覇権で安定していなかったために切磋琢磨し発展が加速したのである。
これに関連して面白い事実がある。「法治国家」、「国民皆兵」、「総力戦」、「富国強兵」。これらの言葉はいつ生まれたのだろうか。一見、近代に生まれたように思われる。だが実は中国の春秋戦国時代である。近代ヨーロッパの諸国併存体制は、いわば前三世紀の中国の諸国併存体制の焼き直しなのだ。この諸国併存体制を勝ち抜いたのは秦であったが、その勝利は有能な人材を外国から引き抜くことができた点にある。
これはエイミー・チュアが「最強国の条件」とみなす「寛容さ」に通じるだろう。産業革命をおこしたイギリスは亡命したマルクスの居住をゆるす寛容さをもっていた。アメリカも多様な移民に開かれた国であった。
満州国もそうなりうる素質をもっていたことは確かである。太平洋戦争はアヘン戦争に端を発する「近代世界システム」のもたらした必然であった。石原莞爾はその点を見据え満州国を建設したが、しかし敗北してしまった。
井上氏は読み古した『五分後の世界』を取り出して、敗戦の悔しさを訴える。だが日本は敗戦の悔しさどころかいまだ諸国併存体制のただなかにいることの危機感さえ失ってしまったようである。この世界で生き残るためには時間とお金の投資が必要なのに、たとえば山中伸弥教授はお金もろくに与えられないのにメディアに引っ張り出されて時間まで奪われている。
日本は平成の三十年間ですっかり落ちぶれてしまった。それは「デフレマインド」として国民の心までむしばんでいる。消費意欲もイノベーション精神も失われ、気持ちの保守化が進み、就活服の喪服化、「モンペファシズム」が進行している。「土建国家からドケチ国家」というありさまである。
ここから立ち直るためにはデフレからの脱却、ゆるやかなインフレ好況がつづく必要がある。井上氏は「ヘリコプターマネー」を提唱する。「最強国家日本」をつくるには少なくともこれが必要なのだ。
二日目 「芸術と批評」
大野左紀子: アートという病
外山恒一は東浩紀との対談のなかで、「アーティストは普段はラディカルなことをやっていても、政治に関心を持ち出すや否やリベラルになってしまう。黙ってアートをしていた方がラディカルなのに」といった意味のことを述べていた。
しかし、本当にアーティストは黙ってアートをしているだけでラディカルなのだろうか。
ラディカルは議会制民主主義と資本主義をどこまでも前提とするリベラルと違って、それらの条件に根本的な疑義をつきつけ新たなビジョンを模索しようとする。この根本的な姿勢において、ラディカルは哲学やアートと共鳴するように見える。
しかしアートがラディカルである、政治的である、というとき、注意が必要である。それは政治的意見を伝えるものではない。アートはそのような言語的メッセージに回収されないのだ。
アートはまず人の知覚と美意識を刺激し、次に知識と経験に働きかけ解釈へと誘う。端的にいって「アートは人をゆさぶりかける」のである。アートはそうした非言語的メッセージなのだ。
その一例として大野氏は藤田嗣治の戦争画をとりあげる。

(上図は「アッツ島玉砕」。一九四三年の国民総力決戦美術展に出品された。)
このような絵は「戦意高揚」というプロパガンダにつながらないことは当然だが「反戦平和」というメッセージにも回収されない凄みをもつ。このような非言語的メッセージこそがアート独自の「政治」なのだ。
さて、特に「アート」と呼ばれるのは近現代の芸術を指すのだが、それには二つの大きな流れがあった。一つは「規範をうたがう」運動であり、もう一つは、「リアルとは何か」「絵画とは何か」というように「本質に迫る」運動であった。アートはこうした革新・拡張化方面と自律・純粋化方面へ駆動されて、そのさまざまな形式を生み出していった。
だが一九七〇年代には「芸術の終焉」の語がささやかれるようになり、行き詰まりが見えてしまう。革新・拡張化方面はアートというカテゴリーを曖昧にし「領域の不在」をもたらした。自律・純粋化方面は、アートがアートであるのは単にアートと呼ばれているからにすぎないという「根拠の不在」を露呈させた。要するに、アートは「何でもあり」になってしまったのだ。こうなってしまうと、もはや革新性もなにもいえなくなる。
では、なぜアートはまだ滅びていないのか。それは簡単な話である。民主主義と資本主義にのっかって生き延びているからである。かくしてアーティストは構造的にリベラルたらざるをえない。
以上がアートの世界的現状だが、日本ではどのような経緯をたどったのだろうか。ここから大野氏は日本の歴史をたどる。
日本のアートはヨーロッパのように市民社会のものではなく、はじめから官製であった。欧化政策と国粋主義の二つの流れに応じて洋画(油絵)、日本画(膠絵)が日本の画壇を形作った。
しかし大正時代になって民間主導のアートもあらわれるようになる。一九一二年頃から未来派、ダダ、アナキストらがさまざまな雑誌を出版して芸術運動を推し進めてゆく。アナキストらは爆弾の意匠を好んだが、これは幸徳事件を意識したものであった。
もう一つは一九一〇年から始まる白樺派の流れである。彼らはセザンヌやゴッホといった画家たちを日本に紹介したが、印象派が本来もっていたラディカリズムを伝えることはできなかった。
雑誌『赤い鳥』もまた白樺派的なリベラルの間から生まれた。機を同じくして山本鼎は自由画運動を開始、従来の手本を模写するだけの美術教育から子供がのびのびと描く教育を称揚し、当時のクレヨンの発明にも助けられ一大ブームとなる。
さて、しかしこれらの活動は戦時下にあって下火となる。
前者の系統は六〇年代にネオダダとして一時復興するも、主流となるに至らなかった。後者が戦後の主流となった。しかし官製の美術教育として。自由と個性を重んじる自由画は戦後民主主義の花形として日本のアート観を形作った。
そのアート観とは次のようなものだ。
「アートは自己を肯定するものだ」
かけがえのない自分、その自己愛の発露としてのアートはしかしそれゆえに歴史とのつながりを失っていった。
「アートは社会的に意義がある」
だが「社会的に意義がある」と言ってしまう時点でそう言われる「社会」の意義を自明視してしまっているのである。
さて、それでは「アート」は本来いかなるものだろうか。それは「つくる」という孤独な作業である。それは「自分を肯定する」のでなく不断に「自分を破壊してゆく過程」、そのような自己破壊的な快楽として「アート」はある。
今日なお「アート」がラディカルであるとするならば、それは「アート」の語を一度も発せずに、「アート」などないかのようにふるまいながらなされるであろう、そう大野氏は講演を締めくくった。
黒嵜想: 批評がスパイ 尾崎兄弟に関する調査報告書、ならびに試論
一九二八年、朝日新聞社記者の尾崎秀実は、かねてから興味をいだいていた中国の、上海の地に特派員としておりたった。その二年後、リヒャルト・ゾルゲが、コミンテルンの諜報員として上海にやってきた。どういうわけか彼らは意気投合して、尾崎秀実はソ連のスパイとして活動をはじめることになる。
尾崎秀実を売国奴とみなす者もいる。同時に彼なりの現状認識のもと日本を救おうとした愛国者であったとみなす者もいる。彼は自分ではこのように述べている。
「結局において身をもって苦難にあたった大衆自体が、みずからの手によって民族国家の再建を企図しなければならない」
「私は元来単純なコンミュニストではありません。きわめて政治的な考慮に立っていたので、近来はほとんど民族主義者であったわけです。」
しかしその実態がどのようなものであったかは謎が多い。尾崎秀実は最後に自らの真実を『白雲録』と題した遺書に書き下ろし、これを東京拘置所所長に預けた。彼はこれを通読し、「おぼろげながらいい内容のものだと思った。将来何かの役に立つだろう。戦争が終わるまで保管しておこう。」という感想を抱いたが、その原本も写しも戦火のため焼けてしまった。
しかし残ったものもあった。それは尾崎秀実が獄中から家族に送り続けていた手紙である。手紙にはそれぞれ番号が振られているが欠けも多い(これは検閲され届かなかった手紙があることを示している)。この書簡集は『愛情はふる星のごとく』の題で戦後翌年から出版され、大ベストセラーを博した。中野重治はこの本について次のように書く。
「わたしの書きたかったのは、この手紙集を通して読みとれる一つの人生図の興味の深さについてである。共産主義者よりもさらに弁護の余地なきものとして発表された売国奴、国際諜報団、スパイの呼び名のあらしのなかで一つの家族がいかに美しく、今日は昨日よりも、明日は今日よりもかしこく強く生きたかというその人生図の感動だったのである。」
(中野重治「『愛情はふる星のごとく』について」より)
尾崎秀実の弟、尾崎秀樹は、兄の評伝を数多く書いている。だが黒嵜氏が注目するのは彼の大衆文学論である。彼はそのなかで講談のながれを引く時代小説と探偵小説の合流したところに松本清張を見、この作家を称揚している。
さて、黒嵜氏は彼の「大衆」文学論に、兄が断片的にしか残すことのできなかった思想を引き継ごうとする意志があったのではないかと示唆し、また彼の書いた兄の評伝は講談的に兄をフィクショナルで魅力的なキャラクターとして復活させる試みであったとみなす。さらにここに松本清張以後のミステリの歴史、社会的リアリズムが後退し、新本格へ、さらにキャラクター小説へ、を重ね見る。
尾崎秀樹は溢れ出る暗号、謎のなかから尾崎秀実という一人のキャラクターをつくりあげた。
そもそも近代文学のプロジェクトそのものがそのようなものなのではないか。言文一致とは、実はとめどもなく溢れ出る主観性をおしとどめるための装置であり、私小説の私とは主観性を吐露しつづけるための私である前に主観性をせきとめるための私なのではなかろうか。黒嵜氏はこうしてこの「私」に後のキャラクター小説の「キャラクター」を重ね見る。
五野井郁夫: コロナ禍後の生政治のグローバルな展開
生権力とは何か。それはフーコーが前近代の権力と対比して論じた、「人々の身体を通して行われる権力」である。それはそれまでの殺す権力に対する生かす権力である。この権力は、まず人々を社会にとって有用たらしめる「規律訓練権力」として十七世紀からあらわれた。そして十八世紀後半以降、生権力は統計学的に群れとしての人民を管理する「生政治」となるに至った。
生政治は、統計学を駆使して「偶然を飼い馴らす」。それは「生かす権力」であると同時に「これくらいなら死んでもいいか」の権力でもある。生かす対象と死んでもいい対象を国家が「科学」の名のもとで恣意的に線引きできるようになり、レイシズムや障害者に対する断種政策が実行される。
こうした生政治と市民社会の関係について語るためには新自由主義に触れなくてはならない。
新自由主義はホモ・エコノミクス、経済人を理想のロールモデルとして考える。彼らは「環境の可変的な変数に対して体系的に反応する」人々であり、つまり「もやウィン」が言うような変化することで生き残る人々である。経済人はそれまでの「公共につくす市民」とはまったく異なる。マンデヴィルの「蜂の寓話」のように自らの利益を追求することで、社会に貢献する、とされる。
ここで国家がすべきことは経済人が動きやすいような環境をつくることである。論考「カリフォルニアン・イデオロギー」も指摘するように、経済人の独立不羈の精神は、結局のところ国家のお膳立てあってのものなのである。
しかし、国家はそれ以上の経済政策を打ち出すことができない。経済は、当の経済人にとっても謎であり、それゆえ国家にとって手に負えるものではないからだ。そのため国家はそもそも経済を飼い馴らそうとしない統治を選択する。
そして「そのかわり」の統治の対象として浮かび上がるのが「市民社会」である。生権力、生政治はこうして市民社会の上に覆いかぶさる。それは国家の必要性を効率よくアピールできる上に、市民の自発的監視にも助けられ、万が一失敗したときには市民に責任を転嫁することもできる「最も安上がりな統治」である。
以上のことを認識しながらも、五野井氏は市民的なものになお希望をみる(0714訂正*)。国家によって規律訓練的にしこまれたものが事後的に自律性を得ることはありうるのではないか、彼はそう語った。
三日目 「音楽と革命」
切腹ピストルズ飯野隊長: 日本やり直し考二〇二〇
太鼓、三味線、謎の皿(あれは何て楽器だ?)。切腹ピストルズの演奏が終わると、落語の枕のように話がはじまり、切腹ピストルズ隊長、飯野団紅氏の半生の話がはじまった。
ひょんなことから仕事を辞めイギリスに渡り、若い頃から好きだったセックスピストルズゆかりの地でパンクな人々とともに暮らしはじめた飯野氏は、彼らが自分の街についてその歴史をよく知っており、深い愛着をもっていることを知る。「この家にかつて亡命したマルクスが住んでいて・・・・・・」とぽんぽん出てくるのだ。彼らのバックグラウンドには間違いなく「土着」的なものがあるのだ。一方、自分と言えば「わびさび」とは何かと聞かれてろくに答えられない。そんな自分に愕然とした。
そうしてしばらくして日本に戻ってみると、真新しい空港に出迎えられた。それは確かに綺麗なのだが、何かハリボテめいた空虚さがあって彼は電車に揺られながら泣いてしまう。彼は仲間とともにこの問題を話し合う。だが、パンクの精神はとりあえず何かやる、である。何か考えたり勉強したりするのでなく、素人がそのままやれることをやるのがパンクである。それゆえ、彼らは数週間で古典落語を一本おぼえて落語を一席やることにした。それが切腹ピストルズの初期の活動である。高円寺を中心に、日本的古典的なことを「とりあえずやってみる」。落語もやるし、和菓子もつくる、和楽器も演奏する。それが彼らの活動であった。
要するに我流なので、これに否定的な目を向ける人もいるかもしれない。しかしそもそも日本の民衆の間で受け継がれてきた伝統はこのようなものではないのか。たとえば祭りで太鼓を叩くおじさん、笛を吹くおじさん。彼らはいわゆる「ミュージシャン」ではなく、それぞれ生業を持ちながら祭りの日には盛り上げるためにとりあえず叩く、吹くのである。そうした民間のアナーキーな伝統を封じ込めてしまったのが明治維新ではあるまいか。
切腹ピストルズは、「着物」というしきたりに縛られた「伝統衣装」の代わりに「野良着」を着用する。それは民衆が普段着として野良仕事の際に着ていた和服である。つぎはぎだらけのその服は、「貧困」のイメージで語られがちだが、必ずしもそうとはいえない。
ある夫婦に野良着を見せてもらったとき、全部で五着あってその二着だけがつぎはぎだらけで着こまれていた。聞くに、かつては交通の便が悪かったので、商人が来たときに複数着買うのが当たり前だったらしい。そしてそこから自分の体に比較的合うものを選ぶのだが、そうするといつも着る服がだいたい同じになる。破れたからといって別の服は着慣れない。それゆえつぎはぎを当てて補修する。破れたところを直し、破れたところを直し、と繰り返していくと、いつの間にかその服は自分の体にもっともしっくりくる形になっている。
切腹ピストルズは現在、こうした野良着や雪駄を収集し保存する活動もしている。
外山恒一、ヴルピッタ: ファシズム、日本、現代
外山恒一氏は日本のファシストである。詳細は以下のサイトにゆずる。
対するロマノ・ヴルピッタ氏はイタリア人の外交官・作家・学者であり、ムッソリーニを肯定的に扱った『ムッソリーニ ――イタリア人の物語』を著している。
対談のテーマはもちろんファシズムである。
ファシズムの根底にはナショナリズムがあることを強調するヴルピッタ氏に対し、ファシズムとナショナリズムの違いについて外山氏が尋ねる。ヴルピッタ氏はファシズムが単に自国家の誇りを外国に主張するにとどまらず、社会主義的な問題意識のもと国内の問題に対処しようとするところに単なるナショナリズムとの違いをみる。
ヴルピッタ氏の意見を外山氏は「外向きのナショナリズムと内向きのファシズム」と要約する。もちろんこの「内向き」というのは内閉的というのでなく、自国の誇りをかけて外国と対抗しようとするナショナリズムと、自国の誇りをもって国内の社会問題を解決しようとするファシズム、という対比である。ヴルピッタ氏はここにファシズムは国際的な新秩序――英米を中心とした旧秩序に対する――を建設しようとした点を補足する。先発先進国(英米)に対する後発国(日独伊)を中心とした新秩序である。
外山氏はファシズムとナショナリズムの違いについてもう一つ重要な点を指摘する。それはナショナリズムが素朴に故郷に依拠するのに対し、ファシズムは日本浪漫派のように、故郷がすでにないことをふまえたイロニーの上に立つ、ということである。
外山氏はファシズムの成立には左翼思想の地盤が重要であることを強調する。左翼の最過激がファシストになり、ここにナショナリストが流れ込む。ファシズムが各地でその色合いが大きく異なるのは、この左右混淆の度合いによるのであるが、それはそもそも彼らが体系的な原理原則をもたないことを唯一の原則とするアナキズム的性質によるのである。
これについて、ヴルピッタ氏はアナキズムそのものでなくアナキズム的感覚の共有、と留保をつける。ファシズム的な反資本主義とは、資本主義というシステムに対する体系的な否定ではなく、資本主義の精神、人間疎外、拝金主義に対する否定であり、具体的には反アメリカニズムなのである。
これについて外山氏はファシズムとは反全体主義であり、アメリカニズム、スターリニズムに対する反対、要するに反グローバリズムなのだという点を強調する。ファシズムは世界を一色にそめる動きに対抗する。それゆえ地元のナショナリズムと結託して世界をまだら色に染めることを目指すのだ。
ヴルピッタ氏は「まったくその通り」と首肯する。ファシズムはその国独自の地盤の喪失を招くグローバリズムに断固たる否をつきつけるのだ。
質疑応答
質問:天皇とファシズムの関係について聞きたい。
「日本にファシズムはあったか」という問題にもなるが、と留保をつけつつヴルピッタ氏は日本には天皇を中心としたファシズムがあった、とする。
外山氏はこれをムッソリーニと王政の話に関連付け、ムッソリーニはもともと反王政だったが最終的に王政と妥協したとし、自分はもともと「天皇はいない方がいいが、いてもよい」程度の立場だったが、今は「天皇はいた方がいいが、いなくてもよい」の立場である、と述べた。
ヴルピッタ氏はこれについて王政との妥協は軍の支持を得るための現実的な決断であったこと、ただしムッソリーニ個人には王に対するシンパシーがあったこと、を補足した。また、イタリアにおける王政の伝統そのものが日本とは比べものにならないほど浅いので単純な比較は難しい、とした。
これに外山氏は「革命なんてものは政権をとってからやればいい」とのヒトラーの言葉をひいて、政権ととるためには多少の妥協は仕方ない、と応じた。ヴルピッタ氏はこれに「運動としてのファシズム」と「体制としてのファシズム」は相補的であり、ファシズムとはまさに「永続する革命」なのだ、と言い添えた。
質問:人権の問題、マイノリティの問題をファシズムはどう扱うのか。
ヴルピッタ氏は民主主義と人権とが異なるものであることを強調し、民主主義の停止が即座に人権の侵害にはつながらないとする。ファシストは「新しい人間像をつくりたい」という野望を抱えており、その野望は人民を抑圧することによっては叶えられない。もし仮にファシズム政権が戦後も生き延びたとしたら、民主主義的ファシズムもありえたであろう。ただしその民主主義はそれ以前のそれと同じものではありえないが・・・・・・。こう言った後、さらに言い添える。ファシズムは結局武器の力で崩壊せしめられたのだ、と。
外山氏はこれに、現代のファシズムは少数民族のナショナリズムとも結託するファシズムでなくてはならないとし、共産主義がソ連という形で現実世界に実験的に生まれ崩壊したのに対し、ファシズムの可能性は充分に実験されていないことを強調する。ファシズムはあの時代に登場したからレイシズム的色彩を帯びることになったが、しかし当時はアメリカの黒人問題もひどいもので、「ホロコーストの民間委託」と言ってもかまわない性質のものであった。そんなアメリカが戦後公民権運動を経て少しは心を入れかえることができたように(最近のBlackLivesMatterをみるに若干あやしいが)、ファシズムもかつてとまったく同じことをやるわけがない。
質問:なぜあえて「ファシズム」を名乗るのか。
これについて外山氏は「歴史性をごまかさないことがファシズムの美学である」と返答した。
外山恒一: 外山恒一トークライブ
外山氏はかねてよりオウム事件以後の世界を「第四次世界大戦」とみなしている。これは第一次世界大戦、第二次世界大戦、第三次世界大戦(=冷戦)につづく、第四次世界大戦、ということである。トークライブの前半は、彼がこの歴史観に至った経緯についてのものであった。
そもそもオウム事件とは何だったのか。現在ではこれは九〇年代の事件としてたとえばエヴァンゲリオンなどといったサブカルと関連づけられて語られることが多い。だが、オウム真理教という運動体について考えるならば、それは明確に八〇年代にピークを迎えた八〇年代の運動である。それは土井たか子や反原発運動、ブルーハーツにたけし軍団と並走しており、消費社会、監視社会に対する反発に裏打ちされていた。それゆえ外山氏はオウム真理教に対しては「別個に進んでともに撃て」というシンパシーを抱いていたという。
さてオウム事件である。このとき警察はかなり強引な捜査を行い、コインパーキングを横切ったためにオウム信者を不法侵入の罪で逮捕するなどの微罪逮捕を連発した。だが、このことに対する批判は驚くほど少なかった。少数の人は声を上げたが、ほとんどは沈黙し、あるいはかえって警察を擁護した。
気づくと世間は、ストーカー、ニート、引きこもりといった「不気味な連中」「あやしい人たち」を取り締まりの対象、更生の対象として包囲していた。人民のヒステリーが瀰漫していた。そして、人民のヒステリーは往々にして戦争の兆候である。外山氏は「戦争がせまっている」と直感した。機を同じくして柄谷行人が『〈戦前〉の思考』を著していた(一九九四年)。
九〇年代後半から、外山氏はダメ連福岡を組織しはじめる。これはこの社会で排除の対象とされる「ダメな人たち」「あやしい人たち」のネットワークをつくる試みで、いわば世間という自警団に対抗するための自警団をつくる試みでもあった。ところがそんななかリベラルな運動家が外山氏を国家によってストーカーと認定させることで運動の現場から追い出し牢獄へ追いやってしまう。この獄中生活のなかで彼は国家とリベラルに同時に立ち向かうことのできる立場、ファシズムに目覚める。
さて、獄中で外山氏は大澤真幸の『文明の内なる衝突』を読む。これは9・11以後の世界を分析した本である。そこでは国外の軍の活動が警察化してゆき、国内の警察の活動が軍隊化してゆく。この「世界内戦」の状況では軍人と民間人の違いもなくなってしまい、ただただ不審人物に早期に対処することのできるセキュリティシステムが拡大してゆく。大澤氏はこの事態をオウム事件となぜか結びつけないのだが、これこそまさに今日本で起きていることだ。戦争はせまっているのでない。すでにはじまっているのである。
外山氏はこのすでにはじまっている戦争を、笠井潔が冷戦を第三次世界大戦と呼んでいることにかこつけて第四次世界大戦とみなすようになる。このために一層奇異な目で見られるようになったというが、最近ネグリ&ハートの著書を参照したところまさに冷戦を第三次世界大戦、現在の世界内戦を第四次世界大戦と形容しており、ますます自分の歴史観の正しさを確信するに至ったという。
ところで外山氏は二年前(二〇一八年)、『全共闘以後』という本を著している。
https://www.eastpress.co.jp/goods/detail/9784781617466
この本は「全共闘以後は学生運動は退潮し、「シラケでバブルでオタクでサブカル」の時代になった」という従来の見方に否を突き付ける、全共闘以後の学生運動、社会運動の歴史の本である。
これが出版されてからというもの、彼はしばしばそれ以前、つまり「全共闘まで」の歴史も書くように言われるようになったという。現在、全共闘の歴史としてスタンダードとみなされているのは小熊英二の『1968』だが、リベラルである著者からの視点では個々の事件の整理は見事であるもののその意義を理解しておらず、単にべ平連を後の市民運動の基礎になったとして持ち上げるにとどまっているのである。
さて、全共闘の歴史を簡単にふりかえるなら次のようになる。一九五六年にスターリン批判が起きて、反ソ、反米、反日本共産党の新左翼があらわれる。六〇年に安保闘争が起きるも敗北、学生運動の冬の時代がはさまり、六五年にプレ全共闘、六八年に全共闘がもりあがる。ここで問題になったのは戦後民主主義批判である。このスローガンが意味するところの一つはベトナム戦争によって自覚されるに至った「自由で平和な日本そのものが冷戦という戦争を戦うためにつくられた欺瞞である」という事態である。冷戦においては後衛の平和それ自体が戦争を支えているのであり、その意味でこれはまさしく第三次世界大戦なのだ。
しかし、実際に書くとなると問題となるのは「いつから書き始めるか」だ。通常は五六年から書き始めるが、そのためには前提の理解のために若干昔に遡らねばならない。そうすると一九四五年が選ばれがちだが絓秀実に影響された身としてはそれだけは避けたい。そもそも佐藤卓己の『八月十五日の神話』にもあるように、一九四五年八月十五日を終戦の日とするのは国内的な「神話」にすぎない。考えようには一九五二年四月二十八日主権回復の日を終戦の日ととらえてもよいのである。
そのように考えて終戦の日はいつかを考えてみたところ、そもそも戦争は終わっていたのかが疑問に思われてきた。四五年と連続して第二次国共内戦が中国では巻き上がり、朝鮮戦争がそれに続く。また日本でも下山事件、三鷹事件、松山事件と不穏な事件が立て続けに起き、日本共産党は武闘派路線をつきすすみ、GHQの要請のもと日本の海上保安庁は特別掃海隊を朝鮮に派遣、事実上朝鮮戦争に参戦しているのである。
この熱戦と冷戦の切れ目について考えてみると、それは五五年、五六年からの平和共存路線(ジュネーヴ四巨頭会談、六全協)であると思われる。
こうしてみると、「全共闘」の歴史は一九一八年から書き始めねばならない。第一次世界大戦の廃墟からアメリカニズム、スターリニズム、ファシズムが三つ巴の熱戦を繰り広げたのが第二次世界大戦で、そこからファシズムが脱落し米ソが冷戦を繰り広げるのが第三次世界大戦、ソ連も崩壊した現在が第四次世界大戦=世界内戦の時代である。要するに、われわれは一度も戦争の外に出たことがないのである。
最後に一つ面白い点を言い足すなら、『全共闘以後』が一九六八年から二〇一八年の五〇年の歴史を描いたものであったのに対し、これから書く本は一九一八年から一九六八年、これもちょうど五〇年の歴史を描くことになるだろう。
***
(政治的・宗教的)自己紹介
私のnoteの他の記事の読者にとって、今回の記事は意外かもしれない。あるいは勉強会の他の参加者にとっても私の他の記事を読んでみてもこの場に参加する必然性がみえてこないのでやはり意外に思うだろう。なんか詩を書いていて、絵も少し描いて、脳外科手術後の異様な体験を記録していて、『残念 ――あるいはキャラクターとしての人間たち』などと題した革命家諸氏には単に「へなちょこサブカル」と思われかねない文庫本一冊分の論考を公開していて、西田幾多郎を研究しており、「舞踏」と批評に興味があるらしい。
主催者のトモサカ氏とは同じシェアハウスの同じ部屋で住んでいたこともあったが、特段彼から誘われたわけでもなく、何故参加したかと聞かれれば最も正確な答えは、六月になってようやく奨学金がそれまでの三ヶ月分いっきに入金され、比較的に金銭にゆとりがあったから、となるだろう。とはいえ金銭にゆとりがあったからといって、人は必ずしもファシストとコミュニストとアナキストと右翼とシーア派の溜まり場に足を運ぶものではない。
私の政治的態度を反映した唯一の記事は以下のものだ。
この記事は直接には『銀河英雄伝説』のヤン・ウェンリーの言葉、「専制政治の罪とは、人民が政治の失敗を他人のせいにできる、という点に尽きるのです。」に対する疑念に関するものである。だがこの執筆にあたって私が考えていたのは「白票に意味はあるかないか」の議論についてだった。
白票にも意味がある、この意見は定期的に出現し、そしてそのつど徹底的に批判される。
「白票にも意味がある」と考える人々はこのように考える。白票の存在は政治に関心をもちながらどの政党にも否を唱えている人々の存在をしめしている。それゆえ棄権が単に政治的無関心層の存在を示すにすぎないのに対し、政治的に不穏な効果をもつことができる・・・・・・。
これに対し、白票否定派はこう答える。白票は、単に政権与党に対する白紙委任状にすぎない。白票には何も意味がない。それゆえ白票を投ずるくらいなら自分の政治的態度と少しでも近い候補者に票を投ずるべきだ・・・・・・。
さて、白票に意味がないことは容易に理解できる。白票に「政治的に不穏な効果」を読み取ろうとする繊細な政治家が存在しないだろうことは容易に予想がつくことだ。
だが白票否定派のいう妥協的な記名票も、もともとの「どの政党も支持できない」という部分を曲げている点で、票を投じた人にとっては無意味だろう。この票に意味があるのは、投じられるその候補者にとってだけで、彼にとってその票は自分の支持者の存在を意味しているにすぎない。
さらに言うなら「政権与党に対する白紙委任状」という形容にみえるように、白票否定派は白票を否定すればその票は野党に流れるとしばしば考えているようである。だが、実際には妥協的に消去法的に候補者を選ぶ場合、その票はもっとも「無難そうに見える」ところに流れてゆく。このようにして消極的な支持を集めてきたのが今の与党なのではないか。そしてもちろん、この「妥協的」という濁りは与党にとっては何の意味もない。
投票者にとって意味のある一票とは、純粋にある政党、候補者を支持し応援する場合に投じられる「清き一票」だけである。
しかし、そのような「清き一票」を投じられる候補者はまれだ(政党は皆無だ)。そしてそのような立場から「投票」について考えてみると、それは○○に投票した/投票しなかった人民の責任だ、というレトリックを可能にするための装置にすぎない。投票にいかなかった政治的に無関心な人民の責任、あのような候補者を選出した人民の責任(もちろんここで「妥協的」などという濁りは考慮されない)、などなど(ひどい場合には「投票に行かなかったのだから/○○に投票したのだから」政治に文句を言う資格はない!と言い切る人々まででてくる)。
ここでヤン・ウェンリーの言葉は次のようにひっくり返すべきだろう。
「民主政治の罪とは、統治者が政治の失敗を人民のせいにできる、という点に尽きるのです。」
さて、このようにして私は民主主義における人民の責任なるものに疑問符をつけた。その背後の制度、構造を考慮にいれるなら「人民の責任」なるものは押し付けられたものにすぎないのではないか。・・・・・・しかし私がこの記事で書いたのは、そのように責任から単に逃れるためでなく、虚構の責任の背後にある真に迫りくる責任を示すためであった。
ある制度の内部で考える限り、我々はその制度の瑕疵には責任がないと考えられるだろう。王国が王国であることに対し人民は責任がないし、民主主義社会の制度的な難点についてもその人民には責任がない、と言いうる。ある制度の視点に立つとき、人が制度の中に安住すること自体を責めることはできない。だが、歴史の視点から見るならば、「では何故革命を起こさなかったのか」「その制度ではどうしようもないなら何故それを変えようとしないのか」と我々はつねに問われ得る。
そして英雄とは、革命家とは、「この制度のままでは成りゆかない」というときにその制度の内部で支給される責任に満足しないで歴史という究極の民主主義に直接参加した人であると言いうるだろう。彼らは自分の身に降りかかったことを「こういう社会だから仕方ない」と考えずに、自らの責任において捉え、それを変えることを選んだ。
銀河の歴史がまた一ページ。
さて、これである程度この勉強会に参加した背景が見えてくるかもしれない。上の考えは棄権をよびかける外山氏の立場とも親和的だろう(棄権は無意味という意見はよく見られるが、白票の意味さえ読み取ることのできない投票制度にとって棄権に意味がないことなど当然である。棄権が意味をもつのは投票制度の外においてなのだ)。
とはいえ疑問は残るはずだ。「歴史という究極の民主主義」などというものは結局、誰もが必然的に参加しているにすぎないのであり、それは何らかの立場ではない。この「民主主義」にどのような信条で、どのような方法で介入するか、それがその人の政治的立場であるはずだ。
ある講演のなかで、講師が参加者たちの政治的傾向をつかむために挙手をもとめた。左翼の人! 右翼の人! ファシストの人! コミュニストの人! アナキストの人! リベラルの人! 中立の人! 保守の人!
どれに対しても少なからず手があがった。「シーア派の人もいます!」と声をあげる人もいた。だが私はそのどれに対しても手を挙げることができなかった。それは「ウソ」になると思われたからだ。結局、「敗戦が悔しいと感じる人!」で、これに挙手しないのは逆に「ウソ」だと考え手を挙げた。が、この感慨そのものはなんら立場ではない。
その日の夜、みんなで夕食を摂り、無尽講ワークショップの班分けがされ、それも済んでしまうと三々五々に分かれて酒を飲みながらそれぞれ話し込んでいるといった態になった。そこに松山氏がなにやら人を車座に集めはじめた。私もまぎれこんでみると、彼は次のような議題を提出した。
この会は世間からもズレていることはもちろんだが、外山氏のようなファシストを呼んでいることもあり左翼運動家一般からもズレている。そのため、純粋な興味から参加するに至った運動家が、後で仲間から反省文を書くように詰められる・・・・・・というのは言い過ぎにしても変な目、冷たい目で見られることを恐れて、人目をしのんで参加しなければならないという悲しい現実がある。この問題について何かブレイクスルーとなるような考えはないか、諸氏に意見を求める。
ここに集まった人の多くはそれぞれ何らかの運動に所属・参加しているため、多くの前提を見逃しているはずだ。だが、大体上のような議題であろう。
そんななか、ある人が次のような意味のことを言った。
「今日の講演で、講師が「満州国はロマンだった」なんてことをいったのに何の声も上がらなかったのは意外だった。あれは結局のところ収奪にすぎなかったのではないか。あの時あの場で「ファシズム」と手を挙げた人のなかで今この場で同じように手を挙げることができる人はどれだけいるのか。」
一見、ここで新しい議題、「満州国はロマンか欺瞞か」という議題が追加されたように見える。だが実際にはそうではないだろう。その人が言いたかったのは、「他派の多くいる会合に参加をためらうことが一方的に「限界性」と言われ解決の必要な問題とされたが、しかしその「限界性」にもそれなりの正当性がある。むしろあの講師の発言をなあなあで済ませてしまって、周囲に合わせて軽いノリで「ファシズム」に手を挙げる人たちの方にも問題があるのではないか。」ということであろう。そしてその問いかけはある程度当たっていて、その後私はある人から「自分のファシズムには「絆されファシズム」という一面もあった」との反省の言葉を聞くことさえあった(しかし、きっかけは「はずみ」のようなものであったとしても後から内実をつけてゆくのが大事なのだ、とその人は続けた)。
しかし、その場では議題が二つに分かれたように見えた。この問題に答えるために右翼の人にもっと前に座るようにと呼び掛ける一幕があって、そこから討議がはじまる、ように思われたがそうはいかなかった。
トモサカ氏「「手を挙げることができる人」? はいはい、わたしファシストです。・・・・・・で、今何が聞かれているんでしたっけ?」
何が聞かれているのか。ここで左翼側が紛糾した。一人のアナキストが質問を整理しようとしているところに「いやそうではない」と反論がはさまり、またそれが別の論題を生み、といった状況。そして場が一瞬まとまったかと思ったら突然横から登場する「酒の無尽講(酒代のカンパを!)」! 右翼側はこれに対し、何が聞かれているかを把握しようと沈黙を保っているのである。
車座は三々五々に分裂した。それぞれが何やら議論しているが、私にはその内容を追うことはできない。
ここで右翼の人の声が耳に入ってきた。私は彼らと比較的近い位置に座っていたのだ。彼らは結局さっきは何を聞かれていたのかを話していて、どうやら議題が二つあったことを知り、答えようがないじゃないかなどと話していた。
私は先ほどの「議題」、「満州国はロマンか欺瞞か」について若干興味があったので彼らに話を聞いてみることにした。彼らは満州国の理念と成し遂げた近代化について語った。
しかし、私はそれに反論するほどの知識もない。どうせならこの問題について左翼と論議しているところが見たかった、なぜ私がオルグされている格好になっているのだろうか、などと失礼なことを思いながら、私は前々から気になっていることについて尋ねることにした。
前々から気になっていたのは次のようなことだ。
日本が東洋解放の理念を謳っていたことは確かなことだろう。そしてその理念にしたがってなされた施策も多いだろう。だが実際に収奪や差別として経験されるのは末端の役人、民間人による横暴ではないか。
たとえば現在、外国人技能実習制度が問題になっている。これも制度の理念としては正当なものがあるのかもしれない。だが実際には奴隷的な制度として民間利用されている。
国の理念は正しかった、国の責任についてはもう協定が結ばれた、それはそうなのだろう。だが制度の理念や国家間の取り決めでは解消できないような何かがあるのではないか・・・・・・。
だがこの話題は現実の「謝罪と賠償、いつまで?」の話に横すべりしていって、国家はすでに協定を結んだという話にうつっていってしまう。私の方でも自分の問いを上手く言語化できず、そして言語化できたとして答えることのできる種類の問いなのかも分からない。
ここでトモサカ氏が口をはさんだ。現在の社会では責任を取ることができるのは個人、団体、国家ぐらいで、エスニックグループ(民族集団)は責任と引き受けることのできる主体たりえない。だがファシズムはエスニックグループをそのような主体にすることを目指すのだ・・・・・・。
ここで松山氏が、さっきまでだんまりだったかと思えば何をしゃべってるんだとばかりに会話にわりこんできた。向こうの紛糾は一旦止んだらしく、再び車座が回復しつつあった。私はさきほどまで右翼の意見を聞きながら折角ならこれに対する左翼の意見も聞きたいと思っていたので、「いや、こちらの方が」と彼らの意見を伝えようとした。
だがこれが良くなかったのだろう。松山氏からすると、右翼同士でかたまって話しこんでいる中にいる私は当然右翼の一人に見え、「いや、こちらの方が」などというのは他人を矢面に立て自分の立場をごまかそうとする卑怯なふるまいに見えたはずだ。「お前に聞いとるんじゃい」と彼は一喝する。
「お前の立場を、お前の・・・・・・誰だ? とにかくお前の立場を聞いとるんじゃい!」
「右翼・・・・・・ではない? 左翼・・・・・・でもない? そんな奴がここの話にまざれるはずないだろ! 正直にいえや!」
私はとりあえず自分の立場、特異性を示す何らかの自己紹介を即座にする必要にかられた(ここで「普通の日本人」などと答えようものならそれは右翼と同義である)。そこで私はこう答えた。
「カルト教徒の息子です!」
それは間違いではなかった。
松山氏はそれを聞くや感極まって、場の全員にむかってわれわれはみんなトラウマ的な出発点をもっている、それをどう乗り越えてゆくか云々と演説をはじめた。彼に会ったのは二年ほど前のシェアハウスで行われたトークイベント以来なので、まったく個人的な印象になるが、彼には場をとりなして他人の意見を引き出そうとする「ファシリテーター」的性格と、場を圧して自分の意見を他人に叩き込もうとする「アジテーター」的性格という、相矛盾する二つの性格が同居しており、それが予測しがたい仕方で交代してあらわれるようである。
しかし断片的な邂逅から他人の性格について語るのはよそう。私にとって問題なのは私の立場であるはずである。そして「カルト教徒の息子」などというのは、これもやはり何らの立場でもない。
さらに言うならこの「カルト教徒の息子」というのはそれほど多くの人が想像するような「トラウマ的」性質の境遇ではなかった。
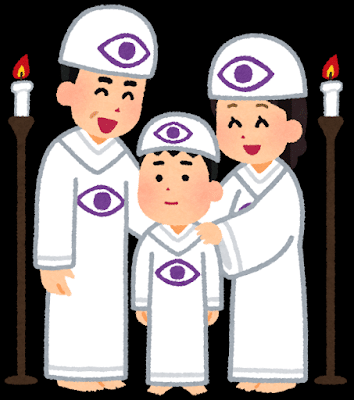
(上図:多くの人が想像するような「トラウマ的」性質の境遇)
というのは私には四人の姉、三人の兄がいて、彼らが多種多様な反抗期を済ませてしまったためかは分からないが、私が物心ついたときにはすでに両親は子供の自由を認める開放的な親になっていたのである。
兄などはたとえば「昔、複数の家族で共同生活していたとき、これまであまり料理してこなかった人が料理の担当になって、全員のスクランブルエッグを大きな一つの鍋でいっきにつくるものだから、緑色がかった金属の味がするクソまずい物体が毎朝出てくるようになって・・・・・・」といった類のエピソードを語ることができるのだが、私にはせいぜい「シチューにレーズンは絶対に合わないよ、母さん!」程度のほほえましいエピソードしかない。
こうして私は両親の信仰と自分の対立点をほとんど意識することなく、そして自分の信仰と世間との対立点をうっすらとしか意識することなく成長した。
私は自分では信仰を――両親のファンダメンタリズム的でその上にスピリチュアル色の加わったキリスト教とはだいぶ異なるにせよ――なんらかの形で保持していると考えていた。
というより考えていなかった。自分の信仰について反省的に考えることを避けてきた。だがそんななか、自分の信仰、不信仰と向き合う機会が奇妙な形で訪れた。
脳外科手術後(現実)、私は奇妙な経緯によって死線をさまよい(妄想)、その際思考の内容が何らかの装置によってかけつけた家族のもとに間断なく送られたのだが(妄想)、その制御できない私の思考は、「神を信じていない」ことを家族に告白した(妄想)。
要するにいわゆる「術後譫妄」にすぎない。(詳しくは以下の記事の後半、「病者の自己解剖」にそのおおよそを記述した。)
単に術後譫妄の生み出した妄想にすぎない、すぎないのだがこの妄想は私がもはや信仰に生きているとはいえないことを暴き出した。
なぜなら・・・・・・もしも信仰を保っていたなら術後譫妄の内容ももっと異なったものになっていただろうから。これ自体不信仰な仮定であるといえる。母はよく様々な人の「臨死体験」の事例について語っていたが、私はある種の極限状態ではそれまでの思想、経験から「臨死体験」が生成されるのではないかとかねてから疑っていた。さて、今回の体験はある種の極限状態はたしかに異様な体験を生むということの実証でもあったわけだ。
それでは私のこれまでの思想、経験はどのような体験を生んだのか。ニーチェの永劫回帰説の悪質なパロディ、ニヒリスティックなブラックジョークのなかに延々閉じ込められる体験。
このように疑似的なかたちで死と邂逅することによって、私は自分の信仰、不信仰に向き合っていなかったことを突き付けられた。私はそれらについて取り組んでいるようでいて、実のところ身をかわしつづけていたのだ。私は自ら信じているふりをして、自分の迷い、疑いを十分に直視していなかった。
正確には私は家族の前では信じているふりをして自らの不信仰を直視せず、世間の人々の前では信じていないふりをして自らの信仰――私をいわゆる「無宗教」の側に溶かし込むのを許さない何か――を直視していなかった。このような二重のごまかしに生きていたのだ。
そのことに気づいたとき、私は「信じている」と単に言うことによっても、「信じていない」と単に言うことによってもこの状況から逃れられないことをさとった。まずは自分の迷いを直視しなくてはならない。迷うことに誠実でなくてはならない。
少々話が脇道にずれてしまった。だが、私がこの勉強会に参加したのも、迷うことに誠実であるためなのである。すでに現行の投票制度を信頼することができなくなっている以上、漫然と投票に参加することは――「清き一票」を投じられるのでないかぎり――できない。しかし、「信じることができない」で立ち止まることはできない。それは迷いに対する不誠実な居直りである。ここからさらに「歴史という究極の民主主義」に踏み出すこと、それが重要なのであり、そのためには誠実に迷うことが必要なのだ。
さて、以上が私の(政治的・宗教的)自己紹介である。迷うことは、一人では単なる堂々巡りになりやすい。誠実に迷うために、私は「集まった」。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
*「あくまでリベラルを自認する」を訂正。
七月十四日、五野井氏本人から「記事を書いた方の「リベラル」とのレッテル貼りも誤りです。」との指摘をいただきました。記憶違いがあったようです。申し訳ありませんでした。
なお、五野井氏本人はご自身の立場を「国家理性とアナキストという多元的な立ち位置」と表現しています。重ね重ね失礼しました。
わたし自身は国家理性とアナキストという多元的な立ち位置で、かつ皆でただフーコーのテクストを読んで解説をし質問にすべて答えただけでとくに矛を交えるシーンはなかったですし、懇親会での外山恒一さんらとの会話もとても愉快でした。時間がなかったのが残念。またぜひ機会があればお声がけ下さい! https://t.co/HEl9C0oQFe
— Ikuo Gonoï (@gonoi) July 14, 2020
