
リモート即売会、課金は是か非か!?
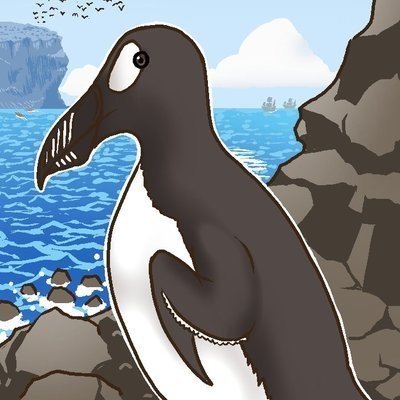
サービス開始に向けて
有料化に際しての料金体系について質問です。
— pictSQUARE@オンライン即売会サービス (@pictsquarenet) July 16, 2020
一般参加はイベント会場への入場は無料とし、店舗で買い物する際は「お買い物券」を注文してもらえば注文できるようになる、という料金体系はどうでしょうか?(1イベントにつき1枚あればOK)
入場は気軽にしてもらえるように、と考えております。
1案ではありますが、有料化の際、一般参加の会場への入場自体は無料にする案も上がっております。会場内で注文を行いたい場合に初めて参加料の決済が必要になるなどして、チャットなどのコミュニケーション機能は無料のまま御利用頂けるようにできないか思案中です。
— pictSQUARE@オンライン即売会サービス (@pictsquarenet) July 16, 2020
正式サービスに向けて、いよいよ課金形態の話が出てきた模様。
このお話はなかなか難しい話で、思うところが長くなってしまったので、ツイートよりもNoteの方に書き残そうかなと思う。
結論から言うと、自分は「お買物チケットは良いアイディアだと思うけれど、一般参加者への課金という流れ自体にはどちらかというと反対」という感じだ。だが、それは「費用の回収先はイベント主催とサークルに集約した方がいいのではないか」という見解からだ。
Webサービスと同人誌即売会
ユーザーとは、慣れていない課金先に対して非常にシビアであり、「確実に面白いという確信を持っているもの」や「瞬間最大風速的に射幸心や物欲を煽られた時」にしかお金を払おうとしない。
昨今、「基本無料」のゲームは巷にあふれている。基本的なゲームの機能は全て解放されているが、DLCやガチャなどの課金で、特効を持つ派手なキャラクターやイラストアイテムを提供し、ビジュアルを堪能したりプレイを有利に進められるということに、商品としての価値を置いている。ゲームのシナリオや体験自体よりも、それを構成する一要素を商品としてパッケージにして売っている、という趣だ。
基本無料は一部の重課金者がサービスを支えている、などと囁かれることもある。実際の所、無課金で遊べるところまでで遊ぶユーザーは決して少なくないし、私も身を持ち崩さない範囲での常識的な散財に留めている。…けものフレンズ3にオオウミガラスちゃんが来たら出るまで回すつもりではあるが。
では、なぜ収入に繋がらないユーザーにまでサービスを提供するかというと、「魅力的なコンテンツで、課金のタガを外して課金勢に引き込むこと」と「ゲームのユーザーの総数を増やし、賑わいを持たせること」あたりかと思う。みんながやっているゲームはやりたいし、ガチャが当たってるスクショを見ると、自分もガチャを回したくなるのだ。出るまで回したくなるのだ。ロードランナーとプロングホーンとパフィンちゃんは来なかった。
そんなこんなで。基本無料のゲームにおいては「タダであることが」最大の広告であると言える。原義を考えれば誤用ではあるが、このあたりは「ソーシャルなゲームだなぁ」と感じさせられる。
…さて、この「賑わい」。pictSQUAREというサービスにおいても求められるものではある。同人作家も、一般参加者もみんなが参加している即売会に参加したい。
…しかし私は、pictSQUAREはサービスの特性上、ゲームとは異なる方向の「賑わい」の重要性を持っているのではないか、そう考えている。
同人方面の温度感
現時点でのリモート即売会は「俺はリアルイベントがやりたいんだよ、リモートなんて興味ねーや」という認識で距離を置いている「リアイベのサークル参加者・一般参加者」が、それなりに散見される。
このコロナ禍の中においては、即売会の開催が困難である以上、もっとすぐに注目を集めるのではないかと思ったが、意外なことに現時点ではまだ「即売会がないと我慢できない、と代替手段を探す同人ガチ勢」「新しい分野に興味津々な冒険勢」にしか注目されていないように思う。…悲しきかな、同人活動自体を縮小することで「即売会のない世界」に適応を始めてるような作家さんも多い。
前回の私の記事にも書いたように、人とは新しい試みに対しては怠惰になってしまうところがあり、「これまでの仕組みと比べて劣る点」に注目し、出来る限り手を出さずにいようと考えてしまうところがある。
その点で、私はジャンルの同好の士に「リモート即売会がどんな空気か」を実体験してもらうことを重視していて、「参入障壁は低い方が一般参加者が増えていい」と思っている。その点で、先の運営の提示した「入場自体に課金しない」という方向性は、とても良いと思っている。
ただ、サーバー負荷で等の内幕の事情をいったん棚に上げて、主催者・サークル参加者の視点で見ると「参加者が減ったらサークル参加(頒布数)が減って元も子もないので、一見さんのユーザーにもできるだけ課金しないで欲しい」のである。個人的には「会員登録してないユーザーも、デモ部屋のように入室&散策と、トークの閲覧だけは出来るようにして欲しい」ぐらいである。
「リモート即売会が楽しそうに賑わっている」ことを、当事者としてすぐに体験させること、その中で「乗り遅れるな!このビッグウェーブに!!」という気持ちを高まらせること、これがpictSQUAREの最高の入り口であると、私は考えている。
誰がためにカネは成る
「pictSQUAREの顧客」には三種類の立場がある。イベント主催、サークル参加者、一般参加者だ。ここにpictSQUARE運営を加え、それぞれの立場からみた金銭的な関係を考えてみよう。
■イベント主催
現状は「誰でも同人誌即売会が開催できる!」という面白サービスに興味を持った熱量の高いジャンルオタクがメインである(ゆくゆくは、ここにリアルイベントの主催起業も入ってくる想定らしい)。
【収入】:サークル参加者からの申し込み料
【支出】:pictSQUAREへのシステム利用料
であるため、サークルがたくさん申し込んでくれると嬉しい。そのためには、「一般参加者がいっぱい来て、本もたくさん買ってもらえる楽しい場である」とサークルを安心させなければならないのだが、なかなか魅力を伝えることに苦戦していて、まだまだ前途は多難である。
■サークル参加者
お絵かきや執筆が大好きな、表現に生きる同人作家たち。リアイベの中止によって発表の場を(人によっては収入も)失ってしまっている。
【収入】:同人誌の売り上げ
【支出】:サークル申し込み料、pictSQUAREへのシステム利用料
であるため、本が売れるためには参加者が多くないと困る。というか、賑わってないと参加しようと思わないし、だからこそ新興分野でまだまだユーザー数が少ないpictSQUAREには、あまり関心を示していない場合も多い。
「人が来るほど賑わうようになったら参加したいな」というスタンスの方も多いと思う。
……むしろ、ファンをイベントに連れてきてくれたら主催の人は喜ぶぞ!!
みんなで作ろう!!リモート即売会!!
■一般参加者
イベント主催・サークル参加者双方から、熱烈なラブコールを送られるモテボーイズ&モテガールズ。彼らが来るかどうかで「次にまたリモートイベントを開催(サークル参加)しよう」と思えるかが決まる。
【収入】:新刊(お金で買えちゃう価値がある)
【支出】:新刊の代金、pictSQUAREへのシステム利用料(今回の争点)
…彼らは黒猫のように気まぐれである。「新しいことをやるからこっち来て」と言っても、プイッと目を逸らされてしまう可能性も高い。そこに課金が発生するならなおさらだ。
彼らを呼び込むためには「新刊」が、「憧れの絵師と話す機会」が、必要だ。…そして、彼らの意中の絵師が参加するかどうかは、「イベントに一般参加者がいっぱい来るかどうか」が判断基準になる。
卵と鶏のような循環参照だ。イベント主催の方は「サークル参加者の友人がいっぱいいて、協力者を集めることができるかどうか」が、イベント自体を賑やかなものにできるかどうかの分水嶺になると思う。多くの同人作家にとって「あの人が参加するなら、自分もやってみようかな…」って人は、きっといることだろう。
私は友達が少ないので、ここで滅茶苦茶苦労することになった。
■pictSQUARE運営
場の提供者。お世話になってます。
リアイベで言う立ち位置としては「商業会館やイベントスペースのオーナー兼机椅子のレンタル業者」と言ったところだ。
【収入】:各参加者のシステム使用料(今回の争点)
【支出】:サーバー代とか、人件費とか
運営は、現時点では唯一明確に営利を目的とする事業者としてpictSQUAREに関わっており、もっともリスクを負っている立場のため、サービス継続のためにも、かかった支出は絶対に回収しなくてはならない。そのため、イベント主催・サークル参加・一般参加者それぞれから、pictSQUAREの参加料の回収を予定している。
すれ違う思い
リアイベを想像してもらえば理解していただけると思うが、賑わうイベントにおいて、もっとも人数を抱えるのは「一般参加者」だ。サークル参加も主催も、自信の利益のためには「一般参加者に気軽に増えて欲しい&タダで入場して欲しい」と思う中で、運営は唯一「一般参加者が増えることで接続数などの負担が増える立場」であり、サーバーの増強などのために予算を割く必要も出てくる。それを考えると「一般参加者に課金する」というのは、利用者数がそのまま収益に繋がるので、理にかなっていると言えるだろう。
しかし、一般参加者は気まぐれでお金を使いたくない。「どうせ本を買うのだからお金は使うのでは?」という話なのだが、本という物質への出費と比べて、サービスへの出費は概念的で形に残らないので、楽しめないかもしれないという「失敗」を過度に恐れてしまうのだろう。リアイベでも「カタログやリストバンド」を入場料の対価にしているイベントは多い。
金銭的な警戒で一般参加者が増えないと、サークル参加者は本を出す意味がなくなり、サークルが集まらないとイベント主催の開催のハードルも上がっていく。ぶっちゃけ同人作家&主催にとって「人が来ないイベント」で長居時間を過ごすのは、心を蝕む…。
個人的な願望
個人的な願望としては
【一般参加者】(入場無料)
↓(新刊の代金)
【サークル参加者】
↓(スペース使用料)
【イベント主催】
↓(サークル・一般参加者のシステム利用料)
【pictSQUARE運営】
という形で、イベント主催が最終的にpictSQUAREに使用料を払うという流れにした方がスマートではないかなと思っている。
これは、先ほど述べた「リアイベで言うところの、商業会館やイベントスペースのオーナー兼机椅子のレンタル業者の様な立ち回り」というあたりからだ。イベントに魅力を感じたサークル参加者が申し込み料を主催に支払い、そこから金を出して「ハコ」を運営から借りる。
なんでも思い通りには運ばない…
…とはいえ、この流れだとイベント主催が「サークルから大きな金額を受け取り、運営に大きな金額を払う」ということになり、ファン感覚で楽しみたい主催を萎縮させる面もあると思う。そもそも一般参加者の数は流動的なので、個の課金の形態だと、下手に人数が増えてしまうととんでもない額を請求されかねないということにもなる。
ここに関しては、サークル参加と同様、会場のハコ自体に定員を設けて、同時接続数が一定のラインを越えないようにした上で(入場待ちがいる時は一定時間で退出など)、ハコの収容人数に応じて主催の料金プランを選択できるようにする、みたいになればと思う(…混雑がストレスに繋がるので、リモートの利点が一つ消えてしまうが…)
最初から追い出しが起こらないように大きなハコを確保するとして、例えば「500人入れるハコ」をシステム利用料100円*500人でそのまま考えると、イベント主催が毎回5万円を負担することになる。その場合、サークル参加費1000円*50スペースでトントンだが、「個人」としては額面が大きく不安になるし、「イベント主催会社」としては人件費の採算が取れないのであまり好ましくない…。
金勘定をしてみると「金を預かると責任も生まれるし、一般参加者から回収した方が確実だなぁ」となる。だが、それで参加者総数が減ると思うと……ままならない。
「イベント入場チケット10枚つづりセット」とか「月額プレミアム会員」みたいな、一度払ったら決済を意識しないで済むような、サービス内通貨やサブスクリプションの形態にして、金を使ってる意識を下げる、ってあたりが現実的だろうか…。
有償も悪いことばかりではないかも…?
あと、一般参加者への課金も、案外悪いことばかりではないかもと感じている、とフォローも入れておきたい。
出元は見つけられなかったが、有名な話として「喫茶店がメニューを値上げしたら、反発はあったものの厄介なユーザーが減って、平穏で雰囲気のいい店になった」という小話がある。少し複雑な金銭のやりとりや手続きが介在すると、人はその場で得られる体験をより良いものにしようと、良識的かつ協力的になる面はあると思う(ラーメン発見伝や才遊記にそんな話ありそうだ)
荒らしのようなユーザーも、イヤガラセしたい相手に金を振り込んだ上で、電話番号に紐づけられたアカウントが永久ブロックされるという悲しい末路しかないので、一般参加者全体を有料化すれば、なおのこと荒らしユーザーは未来永劫やって来なくなることだろう(これ、刑事問題になって開示請求したら一発で対象を特定できるだろうし、荒らしは本当に全く割に合わない…)
とりあえず
何はなくとも、課金形態が定まってない&タダで参加できる現状こそが、一般参加者・サークル参加者にpictSQUAREの楽しさをつかんでもらうチャンスだなと思うので、ベータ終了までの間にどうにか沢山参加してもらえる環境を作りたいところ。
そのためにも…


うちの即売会にも、サークル・一般参加者が増えて賑わって欲しいです。
