
復活してほしいミニコミ(『本の雑誌』2014年11月号)
ミニコミとはミニマム・コミュニケーションの略で、マスコミの対義語として生まれた和製英語である。なぜマスコミの対義語が必要だったのかといえば、マスコミが自分たちの関心ごとを取り上げてくれなかったからだ。一説には一九六〇年の安保闘争の最中にマスコミが発表した七社共同声明からといわれるが、マスコミはいつからか読み手とコミュニケーションをとろうとしなくなり、一方通行の情報発信で済ませるただのマスメディアになった。自分たちが伝えたいことを、自分たちの言葉で、自分たちの力で届けなくていけない理由が生まれた。そこからミニコミが誕生したのである。
マスコミがラジオ、新聞、テレビなど不特定多数に発信する巨大な媒体の総称であるように、当初はミニコミも海賊ラジオやビラ、地方新聞など不特定小数に発信する小さなコミュニケーションの総称だった。だが結果として一番制作と流通が手軽だったミニコミ雑誌だけが残り、それ自体がミニコミと同義になった。古い雑誌などを読んでいると、その言葉の使い方にたまに戸惑う。
ミニコミはそれまでにあった自主制作出版物の「同人誌」とは厳密には違うものだ。同人誌は同人=同じ志を持つ人のために作られる雑誌で、七〇年代まではほとんどが会員向けで少部数だった。同人誌を不特定の読者に頒布するのが常識となったのは、一九七五年末開始のコミックマーケット以降だと考えていい。今でも詩や小説などの文芸同人誌は会員向けのものが多い。
ミニコミは必ずしも同人に向けて発信されるものではない。不特定の中から同じ志を持つ人を見つけようとはしただろうが、あくまで最初は見えない誰かに問いかける。その点でフォーマットはマスコミを踏襲しており、他人に届けるための流通が鍵である。ミニコミ専門店に卸すか、気の利いた一般書店に置かせてもらうか、理解のあるショップにお願いするか、やり方は様々だが、届ける意志がそこにはある。ミニゆえの何かを託された雑誌形態の印刷物。それを今回取り上げるミニコミと定義したい。
それを踏まえて、今回与えられたテーマは「復活してほしいミニコミ」だが、先に書いたように、ミニコミとはおおよそ六〇年代に生まれたもので、それ以前の印刷物とはここでは区別する。ここで取り上げるのは、マスコミにはない言葉、自分たちの言葉を持っているミニコミだ。

(一)『話の特集』(日本社)
一九六五年に矢崎泰久が創刊したミニコミ誌。今となってはこれもミニコミなの?と思われそうだが、マスコミが報道しない小さな情報を載せる雑誌がミニコミと呼ばれた時代のミニコミだ。表紙絵を横尾忠則、デザインを和田誠が担当していた初期は、若者世代に寄り添った反権力志向が特徴で、当時のあらゆる表現者がこの小さな雑誌に集結し、多くのフォロワーを生んだ元祖サブカルチャー誌である。A5判の雑誌は以前からあったが、『話の特集』によって日本のA5判雑誌特有のカラーが決定されたといっていい。中村とうようは『ニューミュージック・マガジン』創刊時に『話の特集』があったから出せたと矢崎に挨拶に行ったというし、『新宿プレイマップ』は矢崎に話が来たのを編集部の本間健彦に話を振ったことがきっかけだ。一九六四年創刊の『平凡パンチ』でさえ後発の『話の特集』の執筆者をひっぱり出したという。それほど斬新だった。一九九五年に休刊。
ここから先は
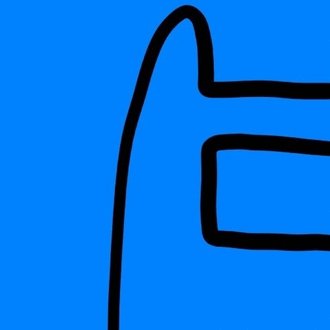
ばるぼらさんの全記事アーカイヴ
2001年以降に雑誌等に書いた記事を全部ここで読めるようにする予定です(インタビューは相手の許可が必要なので後回し)。テキストを発掘次第追…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
