
ロボットのすごいれきし(2011年『土星』2号)
(1)
ロボットという言葉が登場する以前から、人型の機械=ロボット的な概念は世の中に存在しました。空想上のロボットは、紀元前8世紀のホメロスの叙情詩『イーリアス』に登場する黄金でできたメイド(黄金の美女)や、紀元前3世紀のギリシア神話に出てくる青銅の巨人タロスなど、紀元前までさかのぼれますし、オートマタ(自動機械、からくり人形)についても、紀元前1世紀にアレクサンドリアの数学者ヘロンが『自動機械論』に既に詳しい記述を残しています。機械仕掛けの、人でないものに人の仕事や役割を任せたいという夢は何千年も前から存在していたということでしょう。ちなみに、10世紀末に言葉を話す人間の頭像(トーキング・ヘッズ)が、13世紀に自律歩行する召使がいたなどの伝説もありますが、十分な記録がなく信憑性がありません。
---------
(2)
ロボットを支える技術的進歩として、まず14世紀前後から時計が発達しました。これは修道院が定刻通りにお祈りを行うよう時間型管理をはじめたのが大きな理由のようです。1352年頃から作られたストラスブール大聖堂の天文時計はその代表的なからくり時計で、時間ごとに死神や天使、鶏などが出てきたといいます。15世紀前半には動力を蓄積できるゼンマイバネを使った小型の時計が登場しています。17世紀には歯車式の計算機が発明されました。まず1623年にドイツのウィリアム・シックハルトが考案し、1642年にブレーズ・パスカルが機械式の加減計算機を発明、1673年にゴットフリート・ライプニッツが加減に加え乗除も可能な計算機を開発、という流れです。こうした発展が、やがて来る科学技術時代の下地となっていきます。
ここから先は
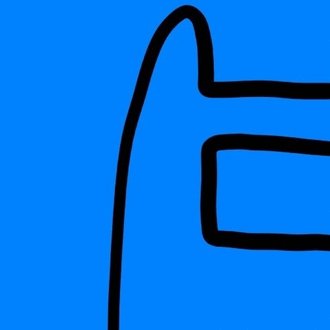
ばるぼらさんの全記事アーカイヴ
2001年以降に雑誌等に書いた記事を全部ここで読めるようにする予定です(インタビューは相手の許可が必要なので後回し)。テキストを発掘次第追…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
