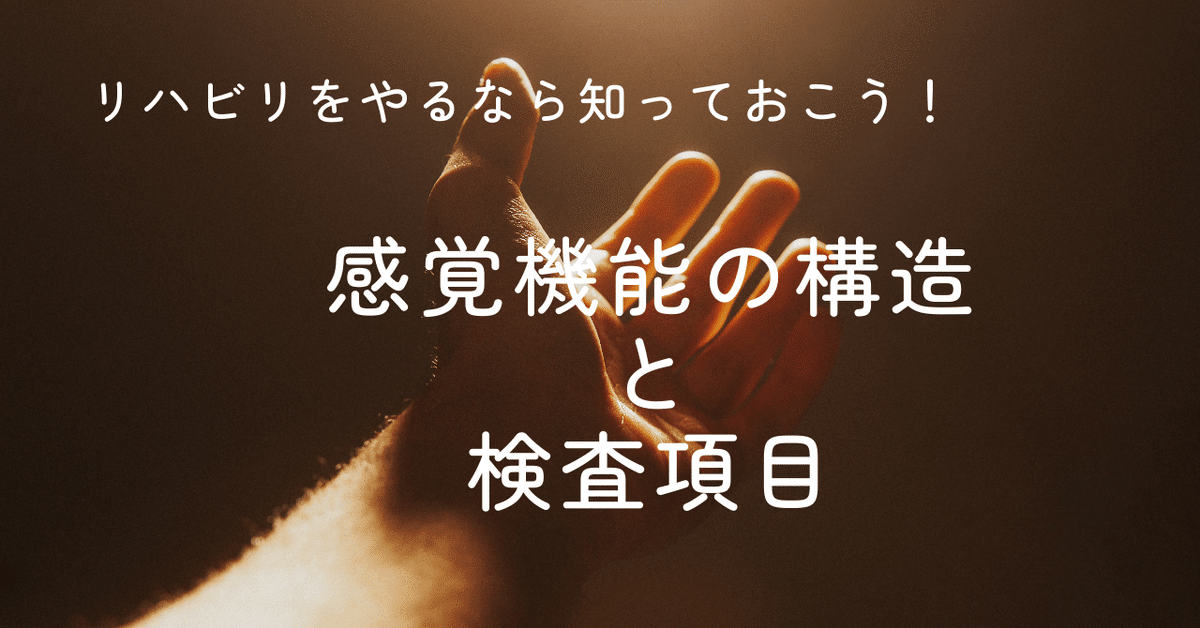
【リハビリを施行する上で知っておかなければならない】感覚機能の構造と検査項目
概要
手の機能における感覚機能の重要性は高い。受容器から末梢神経、中枢統合まで考慮して感覚障害の回復の程度を把握しつつ、useful handへ近づけていく必要性がある。そして、セラピストとして感覚検査における客観的・主観的評価の情報を正確に読み解いていく必要がある。
検査の意義
障害部位、範囲の確認
経過(感覚障害を患ってからの回復段階)の確認
実生活での実用性(現在の感覚機能がクライアント自身の生活に順応できているのか)の確認
感覚再教育の必要性の確認
末梢神経の種類と受容器構造
刺激に対する順応様式には2種類が存在します。
遅順応型:(SA;Slowly adapting system)
触刺激の間中、常に興奮します。
持続的な物品把持・把持力のコントロールに関与します。速順応型:(RA;Rapidly adapting system)
加えられた刺激に速順応します。
材質などの識別・道具を介した物品の操作に関与します。
受容器の種類としては以下のものが挙げられます。
メルケル盤(SA;小鈍)
ルフィニ小体(SA; 小鈍)
マイスナー小体(RA;小鋭)
パチニ小体(RA;大鋭)
自由神経終末(順応しない)
クラウゼ小体(SA;大鈍)

末梢神経の機能損傷分類
末梢神経の機能損傷分類としては以下の2つの分類が一般的に使用されます。
Seddonの分類
Sunderlandの分類
末梢神経の機能損傷した神経の回復は、損傷の程度により異なります。
太い神経の方が細い神経より損傷後の機能回復が遅延しやすく、細い神経ほど神経回復が早く得やすい場合があります。
Seddonの分類

Neuroapraxia:一過性神経伝導障害では、損傷が軽度で3ヶ月程度で回復に至る
Axonotomesis:軸索損傷では、ワーラー変性が見られ、麻痺筋は損傷高位に従い回復に至る
Neurotmesis:神経断裂では、神経が完全に断裂しているため回復の見込みが低い
感覚検査と感覚機能

感覚評価に対しての受容器は以下のものとなります。
また、S2PDがStatic 2PDの略で静的2点識別覚となり、M2PDがMoving 2PDの略で動的2点識別覚となります。
回復
神経回復速度としては、1日1〜4mmほど回復すると言われている。
神経回復の順序としては
痛覚(温冷覚)
30cps振動覚
動的触覚
静的触覚
256cps振動覚
SWT
M2PD,S2PD
物体識別覚
となる。
