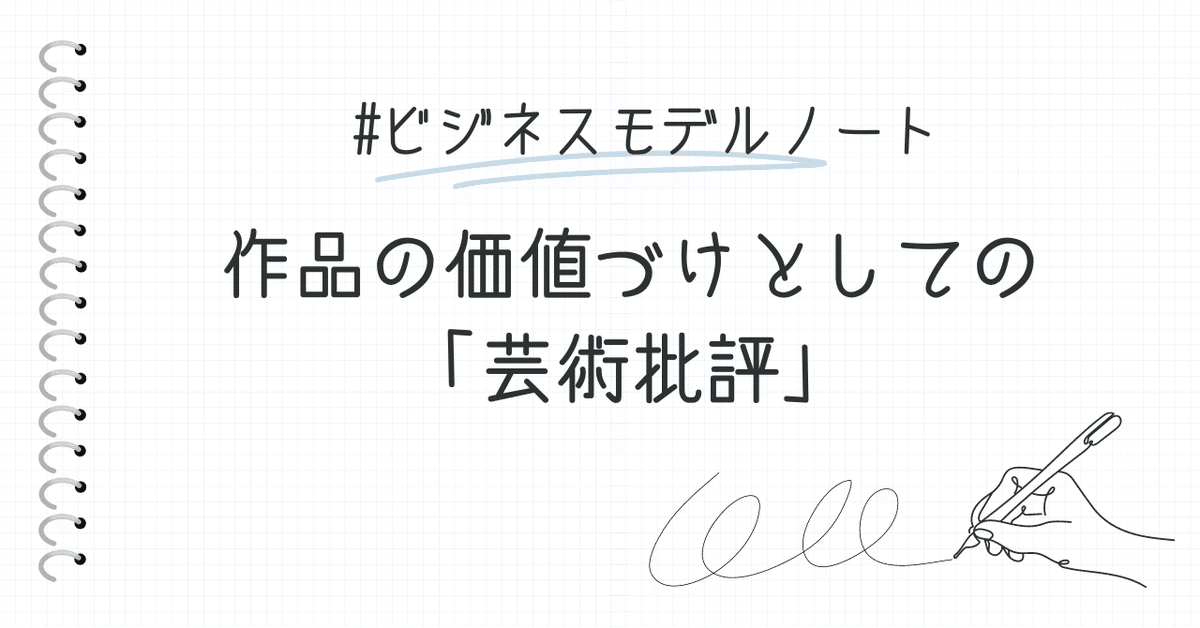
作品の価値づけとしての「芸術批評」
ノエル・キャロルの『批評について 芸術批評の哲学』は、なかなか骨のある本だった。もともと、芸術大学のゼミ授業で芸術批評を取り上げようと思い読み始めたのだが、学生に撮ってと言うよりも、私自身にとって参考になるものだった。
キャロルのこの本の執筆を支えているのは、伝統的な芸術批評の復権に対する強い情熱にある。ロラン・バルトの「作者の死」以降の作者よりも作品そのものに焦点を当てる批評、ラカンなどの心理学からの分析、構造主義的な解釈などが登場した現代において、キャロルの主張する、「作者の意図」に基づき、「根拠にもとづいた作品の価値づけ」を行う芸術批評は、少し古くさいようにも思える。
しかし、キャロルはむしろ、現代の批評の行き過ぎを諌める。アメリカの美学会会長をつとめたこともあるキャロルは、作者の意図をまったく無視し、作品の価値づけを行わない批評を徹底的に批判し、退けるのだ。
というのも、読者が批評に期待するのは、自分がまだ気づいていない作品の質についての理解を助けるものであり、それに寄与しない批評は、読者にとって価値がないからだ。「作者の死」を前提とした分析は、たしかにそれはそれで価値はあるが、その作品を鑑賞しようとする初学者が作品の価値を十分に理解しようとするには、むしろ逆効果にさえなるかもしれない。
キャロルはこうした批評について、次のような厳しい指摘をしている。
批評理論家の多くや批評の現場にいるその追随者たちは、人間以後(ポスト・ヒューマン)の、さらには反人間主義的(アンチ・ヒューマニスト)とすら言えるような批評(すなわち行為主体としての人に執着しない批評)に取り組んでいる
さて、キャロルは「根拠にもとづいた価値づけ」をするためには、次のような作業が必要になると言う。それが、記述(description)、分類(classification)、文脈づけ(contextualization)、解明(elucidation)、解釈(interpretation)、分析(analysis)である。そのうえで、価値づけ(evaluation)が行われる。
記述(description): 作品の客観的な特徴や構造を詳細に説明すること。
分類(classification): 作品のジャンルやカテゴリーを特定すること。
文脈づけ(contextualization): 作品が制作された歴史的・文化的背景を明らかにすること。
解明(elucidation): 作品内の意味論的、図像的および/もしくは肖像的な記号の表示関係を明確にすること。
解釈(interpretation): 意味論的、図像的、記号的な意味を超えて、ある程度の仮説と推測により、意味を特定すること。
分析(analysis): 作者の目的を踏まえ、その手段と達成度を測定すること。
ここで細かくこのプロセスを紹介はしないが、特に「分析」における作者の目的の位置づけにキャロルの芸術批評の特徴が現れている。作品全体で実現したい目的に対して、作品の各部分がどのように機能しているのかを示していくことで、そのあとの「価値づけ」につなげていくのである。
実はこの部分が、まさに作家としての意識とぴったり重なってくる。作家は、ある目的をもって作品を作っていく。作品の各部分の選択について−小説であれば単語の選択や、絵画であればコンポジションや色の選択など−すべてが作品の目的に寄与するように行われていく。他者の作品に対して、キャロル流のこうした作品分析に基づく批評を行うことで、作家としての学びを深められるのではないか、というのが私の仮説である。
小山龍介
BMIA総合研究所 所長
名古屋商科大学ビジネススクール 教授
京都芸術大学 非常勤講師
ここから先は

小山龍介のビジネスモデルノート
ビジネスモデルに関連する記事を中心に、毎日の考察を投稿しています。
よろしければサポートお願いいたします。いただいたサポートは協会の活動に使わせていただきます。
