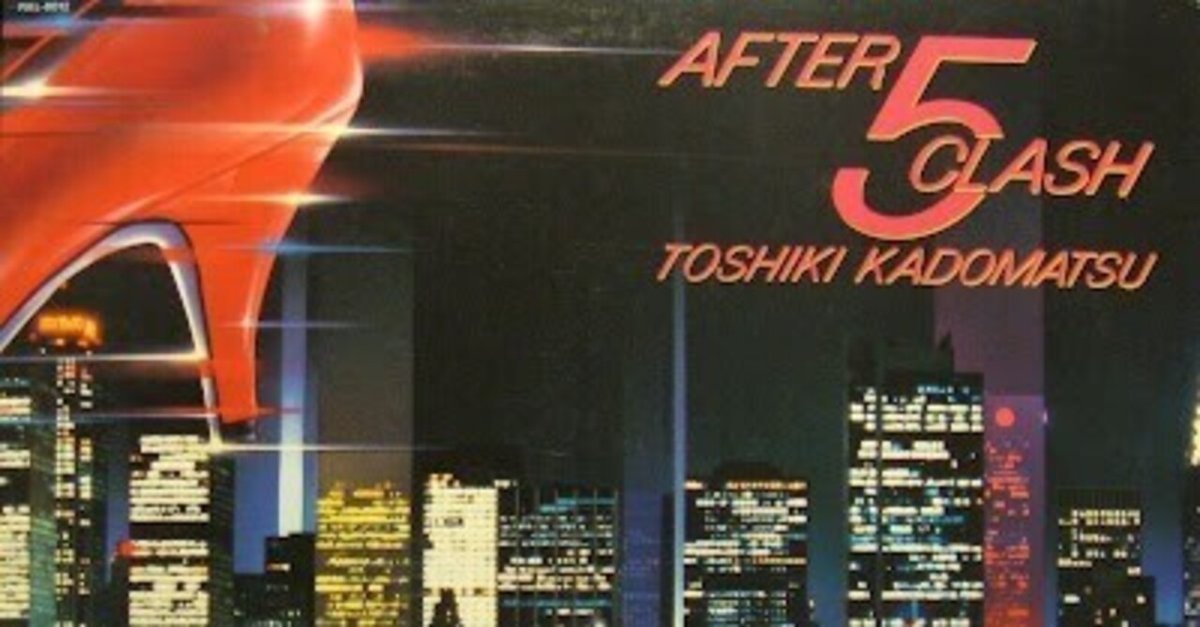
角松敏生 『AFTER 5 CLASH』 (1984)
トウキョウは昨日頃から暑さが嘘だったかのように消えて、秋の寂しさを感じさせる涼し気な季節を迎えた。あんなに疎ましかった夏が突然何も言わずに去ったことを思うと、なんとも物寂しい気持ちになった。
そんな夏のキラーチューンたちが揃うシティ・ポップ。
音楽的に多くの共通点がある一方で、シティ・ポップのアーティストたちはそれぞれ独自のテーマに特化している。例えば、夏をテーマにした音楽が欲しいなら、山下達郎や杉山清貴を聴くのが一番だ。ニューウェーブやユーロスタイルのポップを求めるなら、大貫妙子や高橋幸宏が最適だろう。しかし、もし「都会の夜のライフスタイル」がジャンルとして存在するなら、角松敏生がその代表的なアーティストとなる。彼の最も特徴的なアルバムは『After 5 Clash』、このディスコやブギーを取り入れた作品が、角松が自身の音楽美学を確立するきっかけとなったと言える。
今回は本作『AFTER 5 CLASH』を深堀りしていく。
夜行性と眠らない街
1983年、ポップシンガー・杏里の音楽プロデュースを手がけ、3枚目のアルバム『Off Shore』をリリースした後、角松敏生は当時のリゾートポップ市場の飽和状態から脱却したいと考えていた。新たな方向性を模索する中で、彼は当時のニューヨークのクラブシーンからインスピレーションを受け、同年10月に初の12インチシングル「Do You Wanna Dance」を制作。このシングルは、都会のナイトライフに焦点を当てたファンキーなシンセポップ・ディスコチューンで、より強力な都会的要素を取り入れたものだった。
彼の次の2枚のアルバムも、この音楽性をさらに進化させたもので、最初の作品が1984年にリリースされた『After 5 Clash』。このアルバムには、佐藤博(キーボード)、佐藤準(キーボード)、村松健(ピアノ・シンセサイザー)、そしてお馴染みのジェイク・H・コンセプション(サックス)が参加している。特筆すべきは、R&Bシンガーの宮本典子と中原英司によるラップ部分(意外にも悪くないラップが披露されている)だろう。さらに、コーラスには角松敏生自身、当時のアイドルシンガー・国分友里恵、トリオ「イヴ」のメンバー、戸越恵子が加わっている。何たる豪華さ。
このアルバムのMVPは明らかにベーシストの青木智仁であり、彼は1982年から角松の音楽に関わり、この作品でもシティ・ポップ史上最もグルーヴィーで力強いスラップ・ベースを披露している。彼は残念ながら2006年に亡くなったが、その影響力は今も色褪せていない。
『After 5 Clash』は1984年4月21日にリリースされ、オリコンチャートで最高18位に達したものの、最終的には54位にランクインする中程度の商業的成功を収めた。大きなヒットにはならなかったものの、角松はこの新しい音楽的アイデンティティを保ち続け、杏里のプロデュースで得た印税を使い、次のアルバム『Gold Digger』の制作のためにニューヨークへ渡る。
侘び寂び・ヴァイブス
角松敏生の「傑作」は、80年代のクリシェを詰め込んだ作品のように感じられるが、実際にはそのサウンドはWang ChungやCutting Crewと比べてもはるかに洗練されている。例えば、Wang Chungの『Everybody Have Fun Tonight』やCutting Crewの楽曲(彼らがMr. MisterやGlass Tigerと同じミュージシャンを使っていたのではないかというほど)よりも、はるかに上質な音楽を提供している。Steve LukatherやDavid Fosterが80年代の企業ロックのパイプラインを掌握していたかのようだが、それに比べても角松の作品には独特の洗練が感じられる。日本の仏教における「簡素さの美学(侘び寂び)」(枯山水や桜のようなもの)とシティ・ポップの間に直接的なつながりがあるかどうかは定かではないが、どちらも最終的に美的に完璧な結果を目指している点で共通しているように思える。シティ・ポップにおいても、横浜のナイトライフを讃えるグルーヴィーなベースプレイなど、美的に完璧な要素が重要視されている。
角松自身は特に魅力的なボーカリストではないが、彼の音楽においてはボーカルは全体の美学を完成させるための一つの要素に過ぎない。『Wait For Me』のような曲では、プラスチックのようなシンセサウンドがコカインのキーバンプをした後に看板が目に飛び込んでくるような刺激を感じさせるが、それでも退屈することはない。楽曲のタイトルも『Midnight Girl』や『I Need You』といった機能的なものが多いが、それでも飽きさせない力がある。
『Step Into The Light』,『 After 5 Crash』は、シンセベースの上に乗ったスラップベースが織りなすグルーヴの中で展開する楽曲で、角松のファンキーな歌唱が始まる。特に注目すべきはベーシストの青木智仁であり、そのスラップベースは過剰なまでにフィルを挟んでいるが、それでも音楽全体に溶け込み、曲をよりメロディアスで温かみのあるものにしている。「Never Touch Again」では青木のベースが曲のミッドセクションを完全に掌握し、「Heart Dancing」ではボーギーな要素を際立たせる役割を果たしている。
シンセポップが好きで、80年代風の音楽に抵抗がなければ、角松敏生の『After 5 Clash』は必聴のアルバムであることは明らかだろう。
御祭騒ぎ
前述したが、デビュー以来、山下達郎フォロワーと称されるリゾートミュージック路線を突き進んできた角松敏生だが、今作で大きな変貌を遂げた。「夏」「海」といった楽曲像が「夜」「都会」「男女」といったフレーズで表現できるような楽曲像になった。ニューヨークでのエレクトリックファンク・AORの人気に着目した形。タイトルは都会の男女の「アフター・ファイブ」を表したものだろう。今作は後の角松敏生の楽曲のサウンドを構成するきっかけとなった作品でもある。それは、前作『ON THE CITY SHORE』から参加し始めたベースの青木智仁がスラップを多用するようになったこと。ファンクナンバーが増えたので、その変化は当たり前かもしれないが。角松敏生のファンクには青木智仁の躍動感溢れるスラップが必要不可欠と言っていいほどだった。では、楽曲解説をどうぞ。
[A面]
(A1)『If You...』:アルバムは、聞き覚えのあるギターリフのフェードインで始まり、突然、タイトなホーンとキャッチーなフックを備えた壮大なディスコナンバーへと展開する。誰か特別な人をパーティに誘う内容であり、力強いサックスソロとパンチの効いたベースソロも特徴的である。分厚いホーンや国分友里恵による艶のあるコーラスが曲を盛り上げているが、それらを端に追いやらんばかりにスラップベースも激しく主張している。聴きごたえ溢れるサウンドに耳を傾けてしまいがちだが、メロディー自体は曲全体を通してかなりポップ。サビのキャッチーさは一度聴けばしばらく忘れられないことだろう。今作のテーマと言える「After 5」のフレーズが登場するのが特徴で、妖しく光を放つ、夜の都会の光景が浮かんでくるような世界である。それは今作の収録曲に共通していることではあるが。オープニングというポジションにふさわしく、今作の作風を象徴するような曲になっている。
(A2)『Midnight Girl』:今作と同日に発売されたシングル「Heart Dancing(あいらびゅ音頭)」のB面曲。AOR色の強いバラードナンバー。シンセサイザーを多用した、のんびりとしたヨットロック風の楽曲で、ある男が楽しい夜を過ごした後、酔い気味の素敵な女性と裏通りで出会う物語である。シンセの叙情的な音色が前面に出ており、美しいメロディーの魅力をより引き出している。危険な色気を持った音色のサックスソロはこの曲の聴きどころの一つ。落ち着いた曲調ではあるが、英語詞から始まるサビはしっかりとキャッチーな仕上がりとなっている。歌詞は一度愛した女性と再会した男性の心情が描かれている。「もう二度とこの街で 逢わずにいたいんだ」という歌詞は男性の心情が痛いほどに伝わってきて、何とも切ない心を演出する。情感のこもった角松のボーカルはこの曲の切なさを何よりも演出している。
(A3)『Airport Lady』:空港での「栗色の髪」のフライトアテンダントに対するときめきを描いた、心躍るディスコソングである。イントロではタイトルから想像できるような、飛行機が離陸する音が入っている。流線形(現:RYUSENKEI)の『エアポート’80』のようなシチュエーションが想像できる良い演出だ。突き抜けるように爽やかなメロディー、サビはそのまま何処かへ飛び立っていけそうなほどの開放感がある。そのようなメロディーと共に駆け抜けていくようなサックスやスラップベースは曲の高揚感を最大限に引き出している。落ち着く間も与えないような、忙しないアレンジがこの曲の魅力。歌詞はキャビンアテンダントの女性に恋心を抱いた男性の心情が描かれている。「思わせな笑顔に 誰もまどわされる 全て忘れた時の君がみたい」という歌詞は、相手の女性の人物像について色々と想像したくなる。圧倒的な空の上のアップビートで、人気曲だというのも頷ける。
(A4)『Maybe It's Love Affair』:ヨットロックにインスパイアされた楽曲であり、優れたシンセキーボードのソロを特徴としている。サビの弾むようなメロディーはかなり耳に残る。ボーカルとリズムの不一致が、その分サウンドを楽しみやすくさせている印象がある。タイトルの「love affair」は「情事」「浮気」というような意味があるが、歌詞もそれが描かれている。「誰にも知られたくない 君は そう言いながら ひそかな浮気心を 僕に見せた」という歌詞は生々しささえ感じられる。
(A5)『Will You Wait For Me』:アルバムの中でも典型的なバラードであり、80年代中期のシンセサウンドと70年代のR&B風のメロディを見事に融合させている。劇的なピアノ演奏と驚きのギターソロも含まれる。イントロのキーボードの音色からこの曲の世界に引き込まれてしまう。悲しいほどに美しいメロディーには聴き惚れてしまう。何かをやっているついででこの曲を聴いていたとしても、ついつい手を止めて聴き入ってしまうような訴求力がある。このような曲でもキャッチーなサビを忘れていないのは脱帽だ。
歌詞は恋人と一旦距離を置いて、関係を見つめ直そうとする男性を描いたもの。「君ほどのやさしさに もう二度と会えないと信じたい それだけさ」という歌詞が美しい。あらゆる要素が一体になって、切なさに満ちた世界観を築き上げている。角松敏生の名バラードの一つだと思う。
[B面]
(B1)『Step Into The Light』:一見歌舞伎風のドラムイントロから始まり、ファンク色の強いコンテンポラリーブギーに移行する。見事なコーラスワークが特徴で、ヒップホップの要素も取り入れられており、宮本典子、仲平栄二、角松自身によるユーモラスな「ラップ」も楽しめる。1983年のUniqueのシングル「What I Got is What You Need」をサンプリングしている。
(B2)『After 5 Crash』:LPの(ほぼ)タイトル曲であり、またしても壮大なダンスナンバーである。角松は、太陽が沈みネオンが点灯する大都会の様子を鮮やかに描写している。メドレー形式の曲。「Step into the Light」はインスト曲ではあるが、英語のラップやコーラスがフィーチャーされている。江口信夫による力強いドラムと、シンセが主体となったファンク色の強いサウンドが展開されている。そして、「After 5 Crash」は今作のタイトル曲。重厚なバンドサウンドが展開されたファンクナンバー。流れていくような、一切の無駄のないメロディーが印象的。唸りを上げるようなスラップベースが圧巻。色気のある歌声の女性コーラスも前面に出ており、この曲を華やかに盛り上げている。歌詞は仕事終わりの男女へのメッセージと取れるもの。当然「遊べ!」「踊れ!」と言うようなメッセージである。人々を誘惑するかのように輝き続ける都会の光景が想像できる詞世界だ。今になって聴くと眩しいほどだ。ところで、アルバムタイトルは「Clash」で、この曲は「Crash」と綴りが違うが、どちらかは誤植なのだろうか?
(B3)『Never Touch Again』:これもまた典型的なダンス曲であり、Zapp & Rogers風のトークボックスを使ったラップが最後にフィーチャーされている。イントロから迫力に満ちたスラップベースが聴き手に襲いかかる。そこからシンセによるものと思われるホーンが流れ込んでくる部分は、何度聴いても良い。メロディーは一度聴けば中々忘れられないほどにキャッチーな仕上がりだ。歌詞は難解で意味はよくわからないものの、猥雑な雰囲気に溢れた雰囲気となっている。都会の夜の狂気じみた部分が伝わってくるかのよう。この曲はやはりサウンドが凄まじい。演奏の聴きごたえは今作のどの曲にも共通しているのだが、その中でも特にキレがある。
(B4)『I Need You』:また別のスタンダードなバラードであるが、より官能的なピアノ演奏から、最初のバラードよりもゴスペルの影響を強く受けていることがわかる。佐藤博による、透き通るような音色のピアノ。この人選は山下達郎の影響を強く受けた角松敏生ならではものだろう。流麗な音色のストリングスやコーラスワークも、この曲の厳かな雰囲気を演出している。
歌詞は恋人への想いをストレートに語ったもの。「"愛するほどに切ない"と 君は泣いた もうどこへも行かずに そばにいてあげるから」という歌詞はドラマティックそのもの。思い切り情感を込めた角松敏生のボーカルは若さを感じさせるが、その若さこそがこの曲の美しさを構成する大きな要素なのだろう。この曲もまた、名バラードの一つといえる。
(B5)「Heart Dancing (あいらびゅ音頭)」:アルバムの最後を飾るこの曲は、伝統的な音頭のメロディとジャジーなビッグバンドのアレンジを見事に組み合わせ、驚くべき調和を見せている。曲のフェードアウトはスローダウンされたレコードのようであり、その後、花火の爆発でリスナーに感動を与える締めくくりである。なんてポップな名前なんだろう。大瀧詠一『A LONG VACATION』でも語ったが、日本の風土的に「唄」が強く定着している文化だからか、とてもしっくりとくる。日本古来のダンスミュージックと言える音頭と、当時としては最新鋭のファンクを融合させている
一つの完成形だろう。お祭囃子のような太鼓や笛の音と、今作の作風そのままのバンドサウンドが絡み合うのは中々に不思議なものである。後半では大勢のメンバーによる掛け声も入って盛り上がる。歌詞は誰かを愛することを肯定したもの。「誰も一人きりなんて 嫌なもの だから少しだけ素直に」という歌詞はそれが顕著に感じられる。正直、この曲はかなり今作の中で浮いている。ラストという配置も、他に置き場所が無かったからだろう。しかし、この曲の楽しげな雰囲気につい飲み込まれてしまう自分がいる。
あとがき
『After 5 Clash』は、杏里の『Timely』の夜バージョンと感じられるのも無理はない。どちらも角松敏生のプロデュース作品だからだ。このアルバムに対する印象は、『Timely』に対する印象とほぼ同じである。とてもグルーヴィーでありながら、曲自体はかなりクリシェなものが多い。しかし、そのクリシェはあまりに緻密で巧妙に作り込まれているため、気にならない。例えば『If You...』『Airport Lady』『I Need You』を聴けば、それぞれ山下達郎の『FOR YOU』収録曲からの明らかな影響が感じられる。ただ、角松には独自のアイデンティティがあると言えるだろう。彼の特徴的なブラスセクション、常に際立つスラップベース、そして村松健によるクリエイティブなシンセサイザーの演奏が光っている。角松が80年代のニューヨーク音楽シーンに強く影響を受けていたことは明らかだ。このアルバムの多くの曲は、Gap Band(『Everyday Love』がお気に入りだった、深夜の高速道路の落ち着いたヴァイブス)、Zapp、Lisa Lisa & Cult Jamと並べても違和感がないほどである。 『After 5 Clash』に対する最大の批判は、最初の曲でアルバム全体のアレンジのほぼすべてを見せてしまった点だ。1曲目を「After 5 Crash」と入れ替えても、アルバムの流れに影響はないだろう。もちろん、それが必ずしも悪いことではないが、曲の類似性が目立ってしまうのは事実だ。また、「Step Into The Light」と「After 5 Clash」が同じトラックに収録されているのも問題である。別々に聴くことができないのは残念だ。「Step Into The Light」はラップの部分が多少ダサいとはいえ、際立った曲の一つであるが、どちらの曲も個別に楽しめないのはナンセンスである。
最も際立っている曲は、実はクロージングトラックである『Heart Dancing(あいらびゅ音頭)』だろう。この曲は、伝統的な日本の民謡と現代ニューヨークのビッグバンド音楽を組み合わせた新しい音楽体験を提供している。大瀧詠一の『Let's Ondo Again』や『Niagara Triangle』で見られる手法を彷彿とさせるが、ここではさらに効果的に実行されている。
総評として、『After 5 Clash』は非常に楽しいアルバムであり、シティポップにおける最高のディスコアルバムの一つだろう。クラブでこのアルバムのどの曲が流れても、最高の体験になること間違いなしだ。角松敏生が陽光の差すトロピカルビーチから、ネオン輝く大都市へと移行したことで、彼はプロデューサーとして、そしてミュージシャンとしての真の可能性を解き放ったのだ。
