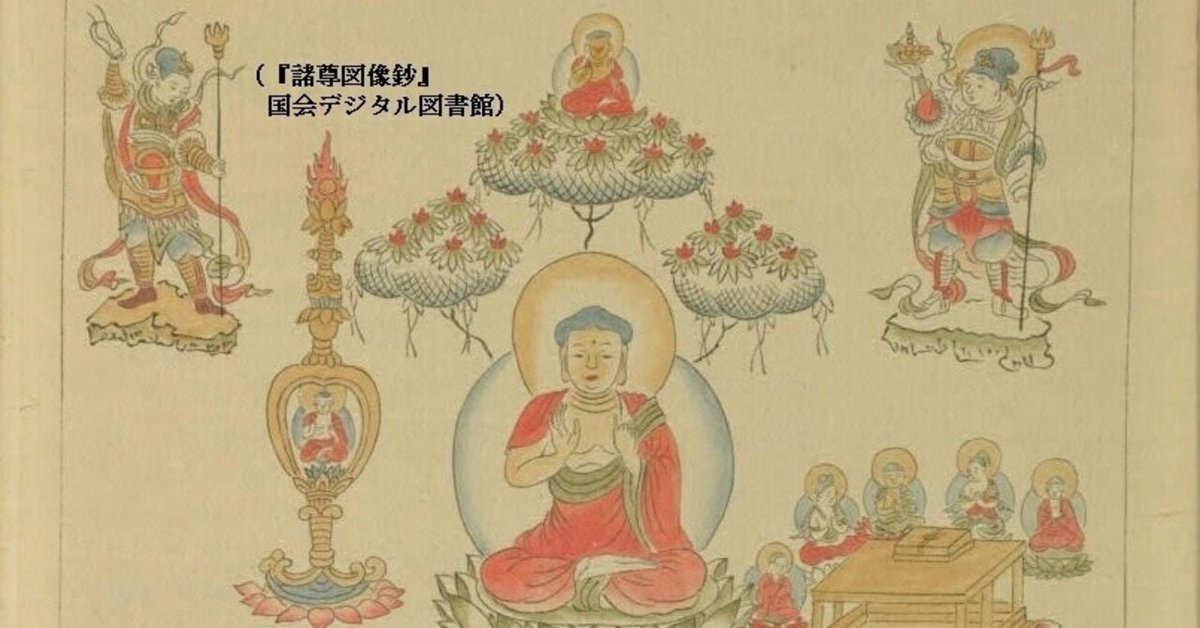
仏教書ではない仏教書
仏教徒は必ずブッダに帰依する
巷では多くの仏教書が数多く出版されているが、それらは大抵仏教になっていない。なぜかというと、著者のほとんどがブッダへの帰依の表明がなかったり、また日常的な読経や念仏、坐禅、種々の法要参列などのブッダに対する信仰告白がない。仏教には先ず何よりも三宝(仏・法・僧)への信仰、特にその筆頭であるところのブッダへの信仰がなければならない、ブッダへの信仰がないところで仏教を語ってもそれは仏教にはならないのである。
ツォンカパ大師の言葉
チベット仏教の中興の祖として知られる仏教史上における最大級の学僧であるツォンカパ大師が云っている、
〔自派の仏教者に入ったこと〕
一般的に内・外〔の外道と仏道〕について設定の仕方は多く見られるが、主尊(アーティシャ)とシャーンティパ(ラトナーカラシャーンティ)は帰依により区別すると知られているので、帰依〔処〕を得て捨てていないのをいうべきです。よって、仏教者に入るには、三宝を至心に教主などだと取ることが必要です。それが無いのなら、どんな善を為しても仏教者には入っていません。
(『悟りへの階梯 チベット仏教の原典・ツォンカパ〔菩提道次第小論〕』
ツルティム・ケサン、藤仲孝司 訳著、星雲社 107頁)
ツォンカパ大師ほどの学僧にしても、三宝への帰依がなければ始まらないと仰る。
チャンドラゴーミンの帰敬
ツォンカパ大師だけではない、各祖師方も同じ態度である。先ずはインド仏教の先徳の旋陀羅瞿民(チャンドラゴーミン)である。
チャンドラゴーミンは7世紀にナーランダー寺院で中観派の月称(チャンドラキールティ)と大論争を行った唯識派の大学者であり、『ターラナータ印度仏教史』に次のようなことが述べられている、
旋陀羅瞿民は聖観音堂に住しつつ、日々に月称の多くの論難に回答し、夜は観音に願い、朝に回答しけるに、月称はそれに答ふる能はざりき。かくして数月を送りしに、月称は思へらく、是は諍論を教ゆるものあるべしと思惟し、旋陀羅瞿民の後とに従ひてその堂に行けり。門外より聞くに、聖観音の石像は旋陀羅瞿民に説法し、阿闍梨耶は弟子に対して教師の如く『唯識』を教えてありしなり
(ターラナータ印度仏教史 寺本婉雅〔訳〕国書刊行会 224~225頁)
チャンドラゴーミンほどの大学者にしても、先ずは本尊への帰依(観音への祈願)が日課であり、その上で仏教教理や思想を展開していることは特筆すべきことである。
ツォンカパ大師の帰敬
ツォンカパ大師も先に取り上げた『菩提道次第小論』の序分において帰敬偈を挙げてから著作をしている。
〔帰敬偈〕
大悲をもった勝れた尊者たちの御足に敬って礼拝いたします。
〔この〕娑婆世界の自在者世尊、勝者の摂政マイトレーヤ・ナータ(弥勒主)法主、善逝すべての唯一の父マンジュゴーシャ(文殊師利)、
勝者〔仏世尊〕に予言されたナーガールジュナ(龍樹)・アサンガ(無着)に敬礼し、
甚深の見と広大の行の道の次第に、容易に入るために再びまた、
要約した方法によりここに説明しましょう。
(『悟りへの階梯 チベット仏教の原典・ツォンカパ〔菩提道次第小論〕』
ツルティム・ケサン、藤仲孝司 訳著、星雲社 29頁)
馬鳴菩薩の帰敬
馬鳴菩薩も『大乗起信論』の序分において、先ず帰敬偈から始まる。
尽十方の、 最勝業なる、徧知と
色無礙自在と 救世の大悲とある者、と、
及び彼身に体と相 (即ち)法性真如の海と
無量なる功徳の蔵、と、 如実修の行等、と、に帰命す。
(『大乗起信論』宇井伯寿・高崎直道〔訳注〕岩波文庫17頁)
自身の仏教思想を説く際にもしっかりとブッダへの帰依を挙げておられる。
天親菩薩の帰敬
天親菩薩も『往生論』の始めに帰敬偈がある。
世尊我れ一心に尽十方無碍光如来に帰命したてまつり。安楽国に生ぜんと願ず。われ修多羅の真実功徳の相に依て。願偈を説きて摠持して佛教と相応す。
(『浄土宗聖典』 望月信道〔編〕 浄土宗聖典刊行会 331頁)
ここにもブッダへの帰依、並びに修多羅(法)の帰依から願偈を説くとしている。
善導大師の帰敬
浄土教の大成者である善導大師は『観経疏』の「玄義分」の冒頭から云っている、
先づ大衆を勧て願を発し三宝に帰せしむ
道俗の時衆等、各無上心を発せ、生死甚だ厭ひ難く、佛法また欣ひ難し。共に金剛の志を発して、横に四流を超断すべし。彌陀界に入らんと願入して。帰依合掌して礼したてまつれ。世尊我れ一心に、尽十方の法性真如海と報化等の諸佛と、一一の菩薩の身と、眷属等の無量なると、荘厳および変化と、十地と三賢との海と、時劫の満と、未満と智行の円と未円と、正使の尽と未尽と、習気の亡と未亡と、功用と無功用と、証智と未証智と、妙覚および等覚の、正受金剛心と、相応一念の後の、果徳涅槃の者に帰命し上る。我等咸く三佛菩提の尊に帰命したてまつる。無礙神通力をもて、冥加して願くは摂受したまへ。我等咸く三乗等の賢聖の佛の大悲心を学して、長時に退することなき者に帰命し上る。請ひ願くは遙かに加備したまへ。念々に諸仏佛を見上らん。我等愚痴の身、曠劫より来流転して、今釈迦佛の末法の遺跡たる、彌陀の本誓願、極楽の要門に逢へり。定散等く廻向して、速に無性の身を証せん。我れ菩薩蔵頓教一乗海に依て、偈を説て三宝に帰して、佛心と相応せん。十方恒沙佛。六通をもて我を照知したまへ。今二尊の教に乗じて広く浄土の門を開かん。願くは此の功徳を以て、平等一切に施し同く菩提心を発て、安楽国に往生せん。
(『浄土宗聖典』 望月信道〔編〕 浄土宗聖典刊行会 343~344頁)
自身の解釈を述べるにあたって、先ず三宝への帰依を表明しているのである。
大珠慧海上人の帰敬
唐代の禅僧、大珠慧海上人もその著書『頓悟要門』の序分においてしっかりと帰敬偈を挙げている、
稽首して、十方の諸仏と、諸の大菩薩衆とに和南す。弟子今此の論を作るに、聖心を会せざらんことを恐る。願わくは懺悔を賜え。若し聖理を会しなば、尽く将って一切の有情に廻施す。願わくは、来世に於て尽く成仏するを得んことを。
(『禅の語録6 頓悟要門』平野宗浄〔訳注〕筑摩書房 6頁)
禅門の仏教者でさえも三宝への帰依を述べてから自身の教理・教学を展開しているのである。
最後に
上記の先徳によるブッダを始めとした三宝への帰敬から思うに、巷にあふれる多くの仏教書は仏教になっていないことがはっきりと解る。多くの有名人や文化人と云われる方々が仏教を題材にして著作を発表しているが、一体どれだけの著者が信仰心を発した上で仏教書を著しているだろうか。著書の中にも帰敬偈はまずないし、著者が日常的に別時念仏会や坐禅会などの種々の行を修しているという信仰表明もないことが多いことから、甚だ怪しいと感じてしまうのである。
私自身は浄土門の仏教徒なので日課称名や別時念仏を日常的に修する側からすれば、帰依もせずにブッダや教理について述べるのは偽りでしかないと思える。
帰依がなければ何を語ろうとも、ツォンカパ大師が云うように「仏教者には入っていない」のである。私が仏教書を読む時は先ず何よりも作者に帰依の心があるかどうかを調べてから読むようにしている。そうでなければその書籍は仏教でないのだから、仏教を学ぶことから外れてしまい、貴重な時間を無駄にすることとなる。
このことは非常に重要なことであるのに、あまり話題になることがないのでここで述べた次第である。
