
【読書メモ】「現代人のための読書入門 本を読むとはどういうことか」(光文社新書)印南敦史(著)
「現代人のための読書入門 本を読むとはどういうことか」(光文社新書)印南敦史(著)

[ 内容 ]
「最近の人は本を読まない」というような発言は、それが事実である一方、もうひとつの事実を覆い隠し、歪めてしまう可能性をはらんでいます。
つまり否定的な論調は、「程度の差こそあれ、誰でも過去に読書体験はあり、無意識のうちにそこからなにかを学んでいた」という事実を覆い隠してしまうということです。
(「はじめに」より)
「本が売れない」「読書人口の減少」といった文言が飛び交う現代社会。
だが、書店に足を運べば多くの人が本を探し、図書館にも人がいる。
いま目を向けるべきことは、もっと別のところにあるのかもしれない――。
純粋に本という存在が好きな稀代の読書家が問いなおす、「読書の原点」。
[ 目次 ]
はじめに
【第1章】本を読むとはどういうことか
【第2章】読書の原点
【第3章】読書習慣の方法
【第4章】ふたたび、本を読むということ
おわりに
[ 発見(気づき) ]
「忙しくて本が読めない」と感じる人が増えているのか、本書の様な新書が、
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」(集英社新書)三宅香帆(著)

「「若者の読書離れ」というウソ 中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか」(平凡社新書)飯田一史(著)
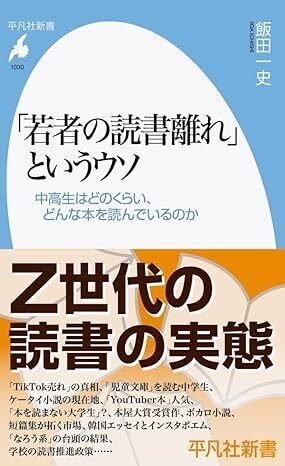
「いま、子どもの本が売れる理由」(筑摩選書)飯田一史(著)

近年ベストセラーになることは珍しくなくなりました。
その中で、本書は、年間700冊以上を読破する作家・書評家の印南敦史氏によるンプル過ぎる読書法に関して紹介した本です。
色んな情報が簡単に手に入る時代。
「誰も教えてくれないこと」というのも存在する。
そのひとつが読書術です。
読書は、何となく身に着けるものと思いがちですが、それとは逆に、以下の様に、たくさんの読書に関する本が出版されています。
「読書について」小林秀雄(著)

「千年の読書 人生を変える本との出会い」三砂慶明(著)

「百冊で耕す 〈自由に、なる〉ための読書術」近藤康太郎(著)

「本を読めなくなった人のための読書論」若松英輔(著)

「読書からはじまる」(ちくま文庫)長田弘(著)

「読む時間」アンドレ・ケルテス(著)渡辺滋人(訳)

しかし、そのような本がいつも言うことを超意訳すれば、
「自分に合った方法を見極めろ」
と言っているに等しいのではないでしょうか。
本書においても、読書を習慣化するためのいくつかの方法が紹介されており、実際にやってみて、自分に合った方法を選んで実行してみることが大切ですね。
[ 問題提起 ]
さて、世の中には、読書術の本の中でも、様々な読書術に関する本が出ていますが、確認してみると幾つかの対立する読書術が存在しており、書き手によって意見が分かれることがあります。
そこで、書き手によって異なる幾つかの対立した考え方を、以下の通り紹介しておきます。
■全部読むべきか、読まざるべきか?
①通読
本を最初から最後まで一冊読むスタイル。
ある思想体系をまるまる手に入れたい場合や、読んだ達成感に打ち震えたい人はこの方法がよい。
絶対に最後まで読みたい本向け。
面白い小説などもこの部類に入るだろう。
②ゴダール式
映画監督ゴダールは、一本の映画を最初の20分しか見ないらしい。
同様に、本に関しても10~30頁読めばいい。
面白くなけば、それ以上読んでやる必要はない、というスタイル。
読む本が多い、無駄な読書に費やす時間はない、という人はこちら。
無駄な本に早く見切りをつけて、損失を最小限に。
大量に借りて情報を得る人や、図書館の本向けの読み方。
■一文一文読むべきか、読まざるべきか?
①精読
一文一文をしっかり読んでいく方法。
よく中・高校の授業などでやるもの。
ボールペンで線を引いたり、声に出して読んだりもする。
難解な文や、慣れない文体などを読む際は、このようなスタイルが良い。
体得される、と言ってもよいだろう。
②流し読み(スキャニング&スキミング)
スキャニング(Scanning)は、テクストを見渡して情報を探すこと。
旅行雑誌やブログを読むように、ななめ読みにより情報を拾っていく読み方。
スキミング(Skimming)は、テクストを見渡してその文の大意をつかむこと。
「流し読み→精読」(あるいはその逆)というコンビネーションも可。
■はやく読むべきか、ゆっくり読むべきか?
①スローリーディング
本の種類によっては、じっくり一文一文を読んだほうがいいのではないか、という主張。
本の種類によっては読み方を変える必要もある、という意味では発見か。
②速読
1980年代あたりから徐々に人気の出てきた読み方。
心の中で逐語的に読まない、いくつかのまとまりで読む、眼球を早く動かす(!)などテクニックが必要。
まずはそれについての本を読んでみるべきか。
■溜めて読むべきか、必要な本だけ買う/借りるべきか?
①積読
机の端に今から読むべき本を「積んでおく」というところから。
図書館から借りた本であれば自分へのいいプレッシャーになるし、自然と自分の今の興味の対象も一目瞭然。
また、写真で背表紙を記録しておくことで、読書リストにもなる。
②すぐ読む
読める分だけ借りる/買う、というスタイル。
積んでおいてもどうせ読まない常習犯向き。
借りてきた本はその日に読むのが一番いいらしい。
[ 教訓 ]
参考までに、公共交通機関での移動時、ついついスマホを見たくなってしまうあなたを、読書家へと導く“究極の読書法”として、その一部を、同書から抜粋して紹介しておきます。
■「ついついスマホを見てしまう自分」から「読書する自分」に変える方法
デジタルデトックスを勧める記事などにはほぼ例外なく、「スマホを手の届かない場所に置こう」というようなメッセージが登場します。
スマホはいろいろな意味で誘惑に満ちたツールなのですから、そこから距離を置くべきだという考え方はとても理にかなっていると思います。
デジタルデトックスしようという場合に限らず、集中したい場合などにも、スマホを1メートル離れた場所に置くというような姿勢はとても大切です。
そしてもちろん、同じことは読書をする際の心がまえにもあてはまります。
いうまでもなく、スマホは読書の大敵だから。
たとえば電車に乗っていて手持ち無沙汰になったとき、多くの人は無意識のうちにスマホを手に取ってしまうはずです。
周囲の人たちがみなそうしていることからもわかるように、スマホは暇を潰すのに最適なツールです。
家で過ごしているときにしても同じで、テレビを観る代わりにスマホを眺めるとか、ひどいときには(いや、よくある話かもしれませんが)テレビを観ながらスマホをいじっているというようなケースもあるのではないでしょうか。
私自身も似たようなことをしていることがあるので、充分に納得できる話です。
そのため、人ごとのように偉そうなことをいう資格はないのですけれど、少なくとも読書習慣をつけたいというのであれば、スマホの誘惑はできる限り断ち切ったほうがいいと思います。
もちろん、非常に難しいことなんですけどね。
そこで試してみていただきたいのは、自分の内部に定着している「当たり前」を排除してみることです。
■電車でスマホをいじりそうになったら
たとえば電車でいつものようにスマホをいじりそうになったら、「きょうは本を読んでみよう」と気持ちを無理にでも切り替え、バッグから本を取り出すのです。
そして、(なかなか気が乗らないとしても)ページをめくって読んでみる。
すると、単に「本が読める」だけではなく、「自分はスマホではなく、本を選んでいる」という事実を通じて自主性を意識できるようになります。
当たり前すぎるとはいえ、それはとても大切なことでもあります。
「自分の意思でそうしている」のだという思いは、よい意味で自尊心を刺激してくれ、しかもそれを積み重ねていけば自信にもつながっていくからです。
いいかえれば、「周囲がなにをしていようと、自分はあえて本を開く」という判断、そこに大きな意味があるということです。
しかも人間は環境に慣れやすくもあるので、最初は気乗りしなかったとしても、何度か繰り返していくうちに、その行為はすぐに無理のない行動になっていきます。
そこまでたどりつければ、読書はさらに身近なものになることでしょう。
もちろん、家でくつろいでいるときでも同じです。
外であろうが家であろうが、スマホに誘惑されそうになったら、あえて本を手に取る習慣をつけるのです。
些細なことではありますが、読書習慣を定着させたいのなら、そういったことを意識し、実践してみる価値はあると思います。
就寝前、スマホをベッドに持ち込んでしまう方も多いのではないでしょうか。
いやいや、これまた人ごとではなく、私もついやってしまいます。
「眠くなるまで」などと思いながら、たいして意味のないネットニュースなどを眺めているだけというケースも少なくありません。
でも、「眠くなるまで」ということであるなら、いっそスマホを脇に置いて本を読んでみてはどうでしょう。
これは、私自身が「スマホを見ていたら逆に眼が冴えてしまい、結局は時間を浪費してしまった」という失敗を経てたどりついた結論でしかないのですが……。
ついスマホを見てしまいそうなときこそ気持ちを切り替え、本を開いてみるのです。
寝っ転がって本を読むのはなかなか快適なので、何度か繰り返してみれば意外と簡単に、習慣をスマホから本へとシフトさせられると思います。
■寝る前の読書で“補欠要員”を用意すべき理由
それに短時間でも本の世界に入り込んでしまえれば、そろそろ眠ろうかというときにもスマホに手を伸ばそうとは思わないはずです。
なお、私はベッドに本を持ち込む際、意識していることがあります。
まず、1冊ではなく2冊か3冊を用意すること。
読みかけの本であれば話は別ですが、これから読もうという本がイマイチだった場合、読み進めようという気持ちにならないことがあります。
そんなときのために、補欠要員を用意しておくのです。
そうすれば、「読もうと思ってたのに読む気になれなくて、結局は眠れなくなってしまった」ということにならずにすみます。
あ、それからベッドで読む本としては文庫本か新書をおすすめします。
重たい本だと、うっかり手を滑らせてしまう危険性があるからです。
これは冗談でもなんでもなく、とても重要なポイントです。
私にも経験がありますが、顔に落下してきた本のおかげで痛い思いをしたら、熟睡どころではなくなってしまうのですから。
■目覚めた直後に“布団で10分読書”の効果
本を読めない、読む時間がないというようなご相談を受けるたび、私はしばしば「起床直後読書」をおすすめしています。
文字にするとなんだか大げさですし、そもそもネーミングがイケてませんが、要するに、起きた直後に本を読みましょうというシンプルなご提案。
といっても起き上がってからではなく、起きる前、すなわち布団のなかでの、5分か10分程度の読書です。
読書とはいえないくらい短時間ではあるのですが、これがなかなか快適で、読書習慣をつけるためにも効果的なのです。
メリットとしてまず特筆すべきは、純粋に頭がシャキッとする点。
「覚醒直後は頭が冴えているから、集中しなければならない仕事は午前中に取り組むべき」というようなトピックをよく見かけますが、たしかに起きた直後に本を読むと不思議な心地よさがあります。
もちろん私は医者ではありませんから、これはあくまで感覚的な問題ですが、本の内容がすっと頭に入ってくるような感じ。
しかも、前の晩に寝る直前まで読んでいた本の続きだったとしたら、なおさらその世界に入り込みやすいような気がします。
最適な読書時間に関しては人それぞれ異なると思いますが、ほんの10分程度目を通しただけで、意外なくらいの覚醒効果があるように感じるのです。
なおポイントは、たとえば最初に10分と決めておいたなら、そのリミットをきっちり守ることです。
10分経ったときにちょうど本がクライマックスに差しかかっていて、「もっと読み続けたい」と感じたとしても、そこできっぱりやめてみましょう。
理由は簡単で、そうすれば必然的に「早く続きを読みたい」という思いが強まるからです。
すると、そんな気持ちが次の読書へとつながっていき、出勤途中の電車内とか、昼食後のお昼休みなどの時間を利用して読もうという気になれます。
いや、「読みたい」と気になってしまうのです。
そこでその感情を、読書の習慣化に向けて利用するわけです。
その際にも「電車が駅に着くまで」とか「始業時刻まで」など、読書を終えるタイミングを設定しておけば、それがまた次の読書時間へと引き継がれていくことになります。
「次は帰りの電車で」「その次は夕食後」「一日の終わりにはベッドで」「翌朝はまた起床直後読書」という具合に。
そうすれば無理なく、しかも読みかけの本に対する期待感を維持したまま、読書欲を継続していけるはず。
また、読み終えたら、その思いは「今度はどんな本を読もうかな」と、次の本への好奇心につながっていくことでしょう。
そうやってサイクルをつくっていけば、無理なく、そしてプロセスを楽しみながら読書習慣を身につけることができるということです。
■読書を習慣化させる“寸止め読書”とは
「時間がきたらきっぱりやめる」という方法について、もう少しだけ補足しておきましょう。
便宜的に「寸止め読書」と呼んでおきますが(これもまたセンスのないネーミングですね)、これは読書を習慣化するにあたって重要なポイントになります。
それは、あらかじめ決めておいた時間で一度きっぱりとやめることによって、盛り上がりつつあった読書熱を意図的に冷ますということ。
冷めてしまっては意味がないと思われそうですが、熱中して読んでいたのであればなおさら、それは理不尽な終わり方だということになります。
読み続けたいのだったら読めばいいのですから、当然の話ですよね。
もちろん読み続けるのもひとつの方法ではありますが、いまここでお伝えしようとしているのは、読書を習慣化することです。
日常の、たとえば一年のうち一日だけの読書ではなく、毎日続ける行為。
すなわち読書を“点”ではなく“線”として捉えるようになることを目的としているわけです。
だから、もっと読み続けたいという思いをあえて抑え、それを次につなげるのです。
また寸止め読書は、「読めない」というモヤモヤを解消してもくれます。
日常生活の隙間を利用することによって5分でも10分でも読むことができれば、それは「読める」ということになるのですから。
読書時間の長短の問題ではなく、もっと大切な「読んだ」という事実が少しずつ、けれども確実に積み上がっていくのです。
それはとても大切なことで、気がつけば読書は日常生活を形成するエレメントのひとつとして確実に定着するはずです。
[ 結論 ]
読書術に関する書籍のエッセンスだけを取り出し、読むという行為に関して、時系列順に並べ替えてみると、自分が気付いていない読書術が見つかるかもしれません。
■本を選ぶときにすること
①テーマを決める:今月の私のテーマは○○、と決めて、それについての本を借りる。
②堅い本&柔らかい本:何冊かの本を読むときに、硬さが偏らないようにしよう。
③ノルマを決める:一ヶ月に 20 冊読む!などと目標を立てる。
④まずは入門書:新しい分野の本を読む際は、入門書を一読。次に参考文献などから広げていく。
⑤本代 2/飲み代 1:一ヶ月に二回飲み会があって 6000 円払うなら、本代は 12000 円。
⑥人から借りた本は読めない?:そういう人もいる。おとなしく本を買うべき。お気に入りはその限りではない。
■読む前にすること
①アウトプットすると決める:経験を踏まえながら、SNS に書評を書くつもりで読む。引用する文も確保しよう。
②発想のための読書:知識だけではなく、著者の「発想法」を身に着けるつもりで。
③時間を決める:一日十五分は本を読む!など具体的に目標を掲げて習慣化する。
■読み始めにすること
①はじめにや目次で内容予測:目次をある程度の時間読んで、そこから内容を予測してから読み始めよう。
②気になるページから読む:興味・関係のないところ、目次で内容がわかるものなどは読まないのもあり。
■読みながらすること
①並行読み:何冊かの本を同時に読む。家の中にちりばめたり、場面で変えたりする。
②本を持ち運ぶ:カバンの中には常に本。持ち運ぶ用の新書や文庫本などをストック。
③どこでも読書:トイレの中でも読書。平行読書と組み合わせて、トイレ専用本を置くのもよい。
④批判・同意しながら読む:考えることも大切。
⑤ボールペンでマーク:図書館本にはダメ。意見や疑問を書きこんでおけば、後で読み返しやすい。
⑥メモを取る:借りてきた本などは、メモで代用。引用などを引き出しておくなどもよい。
■読みながら/読んだ後すること
①印象的な言葉を写してみる:引用などをノートに写す。書く練習にもなるそう。
②本を図解する:キーワードなどを用いて図解する。一冊分というより、気になったところか。
■読んだ後すること
①読書記録:この本読んだっけ?とならないように
「ブクログ」(ブクログ-Web 本棚サービス)
http://booklog.jp/
などを使用するのもよい。
②カード式図書記録:いわゆる「京大カード」を用いたもの。アナログ派にはこちら。
③愛読書を決める:「どんな本を読みますか」と聞かれた時のために。何度も読み返したくなる本を。
④本をプレゼントする:ソムリエのような感覚で。お返しを期待するのもいいだろう。
⑤本(の情報)を交換する:同じような興味のある人がいれば、実物(私物!)や情報の交換を。
[ コメント ]
「どんな本を読めばよいですか?」
と質問されたとして、どのような本を読めばよいかは、どう考えても、自分にしかわからないことのはずなのに、どうして他の人にそれを聞こうとするのだろうか?と、逆に、疑問に思ったことはありませんか?
この事象は、むしろ、そうした問いの多さこそが、いまの時代がはらむ深刻な問題を浮き彫りにしていて、
「自分が何をしたいのかがわからない」
「自分が何をするべきなのかを、誰かに教えてもらいたい」
「自分が何を好きなのかがわからない」
「自分が何を好きであるべきなのかを、誰かに教えてもらいたい」
という姿勢が、世の中に広く蔓延していることの表れなのではないかと思い至ったそうで、
■本を読まないのはあまりにもったいない
■本は「どこでもドア」のようなもの
と感じられると、本があれば、いつでも好きな時に読者の側にいてくれる友人とも呼べるような存在でもあり、決して孤独になることはないと言えるかもしれませんね。
「好きこそ物の上手なれ」
と言いますが、他人の尺度で本を選ぶのではなく、まず原点に立ち返って、自らの好奇心の導きに従って読書を始めてみてくださいというのが、本書を通じて一貫して著者が訴えていることに、私も同意します(^^)
