
【宿題帳(自習用)】視点の転換について
視点の転換は、順序を変えることによって、もともとあったのに、今では気づかなくなっていること、忘れてしまっていること、(従来の説明の順序では)隠されていることを明るみに出す、つまり起源、出生の秘密をあらためて思い知らせてくれます。
卑近な例で考えれば、健康をもっとも意識するのは病気の時です。
健康が分かるのは、病気を通してであり、ありのまま過ごしていると気づかない。
幸福だって同じで、不幸になって初めて強く意識するものです。
同じように、理性というのも理性だけで考えていては分からない。
狂気というものを通して初めて考えることができるのだと思います。
これを見事にやってのけたのがミシェル・フーコーで、視点を変えることによって、考古学のように「知」を掘り出しました。
バルトは、まず、フーコーが「狂気の歴史―古典主義時代における」において、狂気という人間の普遍の本性に属すると考えられてきたものを歴史の変遷のなかに置き直し、また、従来医学の問題とされていたものを文明の問題に移し替えました。
歴史の観点から見るなら、同じ狂気が、中世には気違いと呼ばれ、十七世紀を中心とする古典時代には、狂人とされ、やがて精神病医ピネル(1745-1826)によって、罪人と同一視されていた狂人を精神病者として、初めて医学の対象としました。
しかし、フーコーは、こうして、その名称の変遷を重ねてきた狂気を医学の対象とは考えておらず、バルトの理解するところでは、狂気とは病気ではなく、世紀によって変化することとしました。
おそらく異質的な意味であり、狂気とは、理性と非理性、眺める者と眺められる者とが形づくる一対に純然たる機能なのでしょう。
狂気が病気でなく意味であるとすれば、各時代の歴史的、社会的背景が作り出す記号作用の全体的構造のなかで、精神錯乱なる現象は捉えられねばならないと思われます。
これが、フーコーの実現した第一の構造分析(通時的分析)です。
次に、狂気とは、理性と非理性、観察する者とされる者とが一対をなす機能であるとすれば、これを共時的観点から見れば、問題は超歴史的なある種の形式(フォルム)であり、「社会全体のレベルで、排除される者と包含される者とを対立させ、また結合するひとつの相補性」なのであると考えました。
この点がフーコーの探求した第二の構造分析でした。
中世には、追放、古典時代には強制収容、近代には病院への拘禁に分かれたにせよ、常に同一であるのは、社会規範にはずれた者を排除するというひとつの行為です。
社会的正常者がありうるためには異常者がいなければならず、この意味で両者は相補的関係にあり、排除は狂気のほかに、シャーマニズム、犯罪行為等々に及ぶものであったと考えられます。
【参考図書】
「知の考古学」(河出文庫)ミシェル・フーコー(著)慎改康之(訳)
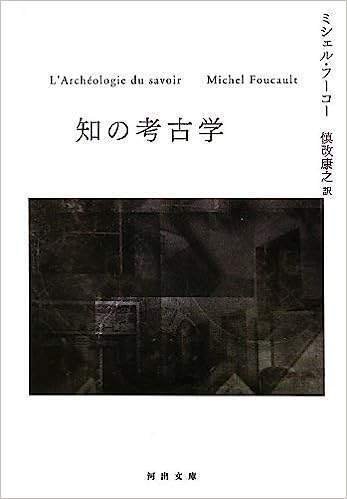
「狂気の歴史 古典主義時代における」ミシェル フーコー(著)田村俶(訳)

