
【読書メモ】「社会的ジレンマ 「環境破壊」から「いじめ」まで」(PHP新書)山岸俊男(著)

[ 内容 ]
違法駐車、いじめ、環境破壊等々、「自分一人ぐらいは」という心理が集団全体にとっての不利益を引き起こす社会的ジレンマ問題。
数々の実験から、人間は常に「利己的」で「かしこい」行動をとるわけではなく、多くの場合、「みんながするなら」という原理で動くことが分かってきた。
この「みんなが」原理こそ、人間が社会環境に適応するために進化させた「本当のかしこさ」ではないかと著者は考える。
これからの社会や教育を考える上で重要なヒントを与えてくれるユニークな論考。
[ 目次 ]
第1章 イソップのねずみと環境破壊
第2章 社会的ジレンマの発生メカニズム
第3章 不信のジレンマと安心の保証
第4章 ジレンマを生きる
第5章 「かしこさ」の呪縛を超えて
第6章 社会的ジレンマの「解決」を求めて
[ 発見(気づき) ]
社会的ジレンマの考えて方として、個人の合理的な選択や利益(個人的合理性)が、社会としての最適な選択や利益(社会的合理性)と一致せず、ジレンマが生じる状態。
<4種類の社会的ジレンマ>
■囚人のジレンマ:
お互いが自分の利益を最優先してしまって、協力した時よりも悪い結果になってしまうこと。
■非ゼロサムゲーム:
全員の利益がプラスになることもあれば、全員がマイナス利益もあり得ること。
■共有地(コモンズ)の悲劇:
共有地で皆が好き勝手に資源を利用した結果、資源が枯渇してしまうこと。
ハーディンの理論。
■フリーライダー:
コストや負担は他人に負わせて、制度・サービスの利益のみを受ける人。
経済学者のオルソンが提唱。
<社会的ジレンマの解決方法>
■選択的誘因:
協力者には報酬を与えて、非協力者には罰を与える。
■規範的意識の形成:
非協力者には罪の意識を植え付ける。
<参考図書>
「クリティカル・ビジネス・パラダイム――社会運動とビジネスの交わるところ」山口周(著)

【内容紹介】
私は、本書を通じて、ある希望にみちた仮説をみなさんと共有したいと思っています。
その仮説とは、社会運動・社会批判としての側面を強く持つビジネス=クリティカル・ビジネスという新しいパラダイムの勃興によって、経済・社会・環境のトリレンマを解決するというものです。
私は2020年に著した『ビジネスの未来』において、安全・快適・便利な社会をつくるという目的に関して、すでにビジネスは歴史的役割を終えているのではないか?という問いを立てました。
原始の時代以来、人類の宿願であった「明日を生きるための基本的な物質的条件の充足」という願いが十全に叶えられた現在、私たちはビジネスという営みに対して社会的意義を見出せなくなりつつあります。
この問いに対する前著での私の回答は「条件付きのイエス」というものでしたが、その後も、営利企業あるいはビジネスの社会的存在意義に関する議論が沈静化する兆しはなく、世界経済フォーラムをはじめとした会議の場においても、この論点は主要なアジェンダであり続けています。
ここ数年、世界中で盛り上がりを見せている「パーパス」に関する議論も、この「このビジネスに社会的意義はあるのか?」という、素朴だけれども本質的な質問に対して応えることのできなかった人々が引き起こした一種のパニック反応だと考えることもできるでしょう。
私は、本書を通じて、このウンザリさせられる問いに対して、ある仮説としての回答を提唱したいと思います。
それが前述した命題、すなわち「社会運動・社会批判としての側面を強く持つビジネス=クリティカル・ビジネスという新たなパラダイムの勃興によってそれは可能だ」という回答です。
「社会学の歴史I 社会という謎の系譜「(有斐閣アルマ)奥村隆(著)

「社会学の歴史II 他者への想像力のために」(有斐閣アルマ)奥村隆(著)

「関係からはじまる―社会構成主義がひらく人間観」ケネス・J・ガーゲン(著)鮫島輝美/東村知子(訳)
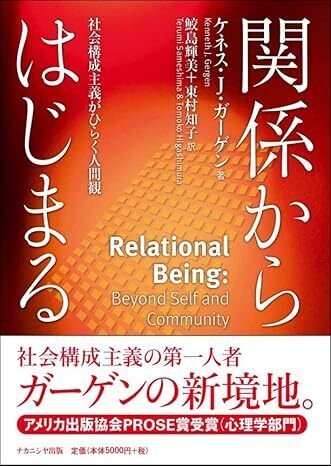
「集まる場所が必要だ――孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学」エリック・クリネンバーグ(著)藤原朝子(訳)

「21世紀を生きるための社会学の教科書」(ちくま学芸文庫)ケン・プラマー(著)赤川学(監訳)
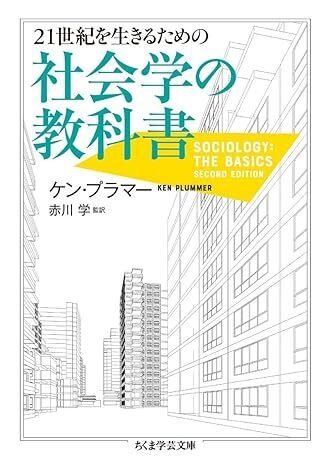
[ 問題提起 ]
本書は、
「囚人のジレンマ」
などの社会的ジレンマの問題に、進化心理学(というか行動生態学)的な知見を注入して、動的なモデルを作るという話である。
本書の記述からすると、こういう方向が社会心理学の中で強くなったのは1990年代に入ってからのようだ。
ただし、この場合の「進化心理学の注入」はあまり前向きの話ではない。
[ 教訓 ]
「社会的ジレンマ」
とは、個々の人が目先の利益だけを考えて行動することによって、かえって全体の利益が損なわれ、個々の人にとっても不利益となってしまうような状況をいう。
しかもやっかいなことに、だからといって一人だけが目先の利益を追うことをやめると、その人はさらなる不利益を負う。
いわゆる
「共有地の悲劇」
もこれに含まれる。
コミュニティ等において特に頻繁に現れるため、自治体にとっても他人事ではない。
例えば、みんなが車を使うことで渋滞が引き起こされるが、だからといって一人だけが車をやめて、例えばバスに乗り換えたとしても、その人は混んだバスの中でさらに渋滞に巻き込まれるというさらに悪い状態に陥る。
だったらエアコンを利かせた車の中で音楽でも聴きながら渋滞にはまっていた方がまだマシである。
だからみんなが車に乗り、結果として渋滞がひどくなる。
こうして
「社会的ジレンマ」
状況ができあがってしまう。
この種の難題を解決するにはどうすればよいのか。
その答えを、社会学上の実験から模索しようとするのが、本書である。
主にツールとして使われるのは、囚人のジレンマの実験。
本書で多用されているのは、500円を被験者に渡して二人一組で行うもので、
「500円を相手に渡せば相手には1000円渡る(実験者が500円を足す)」=協力行動、
「渡さなければ手元の500円のまま」=非協力行動、
という状況のもと、
「協力行動」
と
「非協力行動」
の選択を被験者に迫るものとなっている。
架空の設定ではなく、実際にお金の増減を伴わせるところが面白く、実験結果に真実味を与えている。
面白いのは、個々の被験者の行動が必ずしも目先の自己利益を最大化しようとするものであるとは限らないことである。
もちろん
「聖人」
のような100%利他的行動を取る人はごくわずかなのであるが、多くの人が(状況にもよるが)
「相手がそうするから、自分もそうする」
という相対的な戦略を取る。
つまり相手が協力的なら自分も協力的、相手が非協力的なら自分も非協力、という具合である。
もちろん、これらはあくまで
「実験」
であり、その結果がそのまま実社会に応用できるわけではない。
しかし、そうであっても示唆されることが非常に多い本である。
[ 結論 ]
著者によれば、実験において見られたような行動は、進化の中で集団生活を営む人類にビルトインされた
「本当のかしこさ」
の表れであるという。
とすれば、これを現下の環境問題やいじめ問題に応用するにはどうすればよいのか、ということになるが、もちろん本書はそのような
「解決策」
を軽々に示すことはしない。
むしろ、人間がこうした
「本当のかしこさ」
を持っているにもかかわらず、環境問題やいじめ問題などがなぜ生じるのか、という点こそが、本当に解くべき難問なのかもしれない。
あくまで推測だが、話の流れは次のようなものである。
社会的ジレンマの問題を(工学的な意味で)解こうとすると、合理的な判断を下す人間(プレーヤー)というものを想定する限り、望ましい結果を導き出すのが難しいことがある。
これは行動生態学の分野で言えば、利己的な遺伝子というものをベースにする限り、群選択(group selection)のメカニズムが働かず(普通は、これは自然環境中ではほとんど起こらないものとされる)、個体群全体で適応度が低い位置で安定し、ついには絶滅に至ってしまうというようなことが起こりうるという話に似ている。
ゲーム理論の分野で言えば、もし個体群の成員全体が協調戦略をとれば全員がより高い利得を得られるのだが、これに裏切り戦略が入ってくると協調戦略(が成員全員に行き渡るという状況)は安定的でないということである。
ところで人間の社会で生じる社会的ジレンマの実際の場では、協調戦略と裏切り戦略のミックスが見られることが多い。
これをどう理解すべきかという問題には、2つの方向がある。
(1)「合理的」なのはあくまで裏切り戦略であり、協調戦略は「不合理」な行動で、何らかのエラーである。
(2)協調戦略は長期的に見れば「合理的」であることがある。
後者の問題は、人間がこの
「長期的に見た場合の合理性」
をどうやって認識し、取りうるのかというところにあり、局所的に合理性を判断する、新古典派経済学の想定するのに似た経済合理的人間には不可能なことが多い。
だが、これに進化心理学の発想を注入すると、一見して不合理ではあるが長期的には合理的である、または状況によっては合理的であるような行動を取るような人の存在を所与のものとして想定することができる。
これは(その主張する内容は一見して正反対だが)経済学の分野で
「合理的期待形成論」
の果たした役割に似ているところがあり、非合理的な行動を合理的な範疇にむりやり収めることによって、根本にある「人の合理性」の観念を守るという機能を持っている。
具体的に進化心理学がどのように機能するかというと、こういうことになる。
長期的に見れば、あるいは個体群の成員の一定のパーセンテージが協調戦略を取れば、協調戦略の利得が高くなるような状況では、協調戦略をとった方が有利なことがある。
人間の脳は、この種の社会的状況にうまく対応できるように進化してきているので、
「新古典派経済学の想定するのに似た経済合理的人間」
には不可能な(しかし結果としては有利な)行動が進化してきていても不思議ではない。
経済合理的な行動をドライブするものを仮に「理性」と名づけるとすれば、それ以外の「非理性」的なところにこの種の結果としては有利な行動が埋め込まれている。
そういうわけで、これまでの「経済合理的行動」あるいは「理性」重視の人間モデルの下では誤作動/エラーとみなされがちだった「感情」とか「迷信」などのカテゴリーが適応的な行動パターンであると再解釈される。
いったんこういう発想が流行すると、それをサポートする研究結果とか解釈が続々と出るので、ますますそれらしく思えてくるわけである。
協調戦略を所与とするなかで、その協調の度合や性質をいろいろと考えて、コストとベネフィットのパラメータをうまく設定してやると、戦略ミックスの安定解が複数存在するような社会的ジレンマを考えることができる。
どの解に到達するかは初期値による。
そして望ましい解(協調がうまく行われる状況)に到達できるような初期値を、著者は
「限界質量」
と呼び、人々の行動を変える社会政策は、このような望ましい解に「自然」と到達するようにコストとベネフィットのパラメータを操作することであると規定する。
ここには強権的な社会政策がうまく機能しないことへの反省がある。
進化心理学の面から考えると、このような行動パターンが進化するためには群選択みたいな選択メカニズムがどうしても必要になると思われる。
実際の人間の社会生活の歴史を考えると、そのようなメカニズムが働いた可能性はたしかにありえそうだ。
なんというか小人数の「部族」みたいなやつです。
まあしかし全体として、進化心理学自体がいまだに怪しい分野なんで、本書で主張されているような事柄も割り引いて受け取らざるをえない。
いろんな楽しい与太話はできそうだけれども・・・
例えば、日本とアメリカは、信頼に関して、異なるアトラクタに落ち込んでいるとか、コミュニティの崩壊は本当に大問題だ、みたいな話。
ゲーム理論を使って日本的経営システムを救おうとする「文化の経済学」との連想は簡単にできる。
「脳のなかの幽霊」でも感じたことだが、世の中の論調はずいぶんと変わったものだ。
「優生学の復活」で批判的に取り上げられている、科学的人間観が新たな段階に入り、以前ならば非合理とか非科学的と呼ばれていたような範疇の事象を科学の合理の中に回収しようとする動きが猛烈に進んでいるように思われる。
例えば、恐竜の大絶滅の天体衝突原因仮説が果たした最も大きな役割は、地質学的斉一説をファッショナブルでなくしたことにある。
ウィルソンの「社会生物学」は、結果として、それと同じほど強力な影響を多くの分野に及ぼしたということになるだろう。
いわゆる「パラダイム・シフト」を実際に目撃しているような感がある。
[ コメント ]
そう言えば、4~50年前ですら、
「感情は進化してきており、適応上の意味を持っている」
とか
「天体衝突が地球上の生命に大きな影響を与えたことがある」
みたいな観念を、
「非科学的だ」
といって攻撃する
「と学会的な人」たちは大勢いたように思われる。
科学は、
「と学会的な人」
たちが期待するほど静的なものではない、ということだ。
