
【宿題帳(自習用)】視点を変える(その2)

アメリカのノーベル賞受賞者R・P・ファインマンは、冗談が好きな物理学者であるが、物理学とは神様がやっている壮大なチェスのルールを探り当てるようなものだと語っている。
「ファインマンさんベストエッセイ」ファインマン,リチャード・P.(著)大貫昌子/江沢洋(訳)

宇宙規模で行われる神様のチェスを、物理学者は、時おり、その盤を片隅からちらりとのぞき見て、それを手がかりに、ゲームのルールや駒の動きを推測するようなものだ。
時には、いきなり敵陣で駒が成るなど、予想外の展開に驚くこともある。
科学哲学者のカール・ポパーは、マッハの確証主義を批判して、科学的精神というのは、仮説がうまく適合しない事例を探し出し、その反証事例によって、その仮説が反駁されるかどうか吟味することを、最優先するような知の働きだといった。
つまり、自説がうまく妥当する事例ではなく、自説がうまく妥当しない事例に引かれ、それによって、自分の立てた仮説を自分自身で書き換えることに知的興味が集中するような人を、ポパーは、科学者と呼んだ。
そうでない人は、神様であり、そんな科学は、擬似科学なのである。
歴史を振り返ると、マルクスにしろ、ダーウィンにしろ、フロイトにしろ、本人の意図から離れて、すべてを説明しようとする追従者が生まれ、万能感を生んだ。
マルクスは、マルクス主義者ではなかったといわれる所以だが、その追従者たちは、解剖に、よく切れるメスを使っていたつもりが、切れすぎて対象を殺してしまうことが多かった。
ローマカトリック聖者の候補者について、生涯の事跡人格について調査論告するともいう「悪魔の代弁人」(Devil's Advocate/promoter of the faithとも)という手法がある。
主に、アメリカのことだが、ある学説や政策の妥当性を確かめるために、この方法を採ることがある。
これについて、朝日新聞の記者だった白井健策が「書く前に」で、次のように書いている。
「エッセイの書き方」日本エッセイスト・クラブ(編)

直訳すれば、悪魔の代弁人という意味である。
一般には、他人の弱点をとらえて難癖をつける人のことをさすことばだが、そもそもは、カトリック教会でのしきたりからきた表現である。
カトリック教会では、特定の人々を、聖人や福者として列する、ということをする。
その場合、聖人や福者に列せられるべき理由として、候補者たちの奇跡・徳行に関する証拠を提示しなければならない。
そうすると、それらの証拠の信頼性を見聞する役割が必要になる。
この任に当たるのが列聖(列福)調査審問検事といわれる人々で、これすなわち悪魔の代弁人というわけである。
つまり、聖人にしないように(悪魔の味方をして)あら探し、こきおろしをする人々、という含みである。
20世紀前半には、ピルトダウン人として有名な原始人類の頭蓋骨が発見され、人類学界を揺るがしたのだが、後に捏造と分かった。
「ピルトダウン」フランク スペンサー(著)山口敏(訳)

犯人は、コナン・ドイルという説もあったが、無罪だったことが判明した。
ネス湖のネッシーは捏造だという人が出てきたが、犯人も捏造だという人がいて真相はまだ分かっていない(と思う)。
2000年には、藤村新一という人による旧石器発掘の捏造が発覚したが、周りに誰も悪魔の代弁人がいなかったことになる。
疑義を挟む人はいたのかもしれないが、悪魔の代弁人のような制度が機能していなかったことになる。
ゴッドハンドと呼ばれ始めたころからおかしいことに気づかなければならないのに。
哲学には、ソーカル事件という有名な事件があって、今更書く必要もないが、アラン・ソーカルという物理学者が、哲学者たちの勝手な科学論の振り回しに怒って(?)「ソーシャル・テキスト」というカルチュラル・スタディーズの専門誌にパロディ論文を応募したのだが、真に受けた編集者が載せてしまったという事件があった。
詳しくは、「知の欺瞞」を読めばいいが、如何に思想が怪しい言説に包まれているのかが浮き彫りにされた。
「「知」の欺瞞―ポストモダン思想における科学の濫用」(岩波現代文庫)ソーカル,アラン/ブリクモン,ジャン(著)田崎晴明/大野克嗣/堀茂樹(訳)

文科系の学問が悪いと思うかもしれないが、史上最大の捏造は、物理学で行われている。
2002年に、ベル研究所の有名な研究者ジャン・ヘンドリック・シェーン(32歳)が解雇されたが、実験データを改竄したことが外部の調査委員会によって明らかになったためだ。
データが改竄された研究の中には、シェーンをはじめとする数名の科学者による超伝導(超電導)、分子電子工学、分子結晶といった最先端分野の研究が含まれていた。
研究結果は、「サイエンス」誌、「ネイチャー」誌といった有名な科学雑誌にも掲載されていて、売れっ子教授だった。
2005年には、世界で初めてヒトのクローン胚からES(胚性幹)細胞作りに成功したとする論文を米科学誌サイエンスに発表したソウル大の黄禹錫(ファン・ウソツク)教授が、研究成果のES細胞は存在しないと認め、論文撤回をサイエンス側に要請して認められた。
黄教授は、「ゴッドハンド」といわれ、韓国の国民的英雄として慕われていて、国家プロジェクトにする予定だっただけに、騒然となった。
科学と政治が結びつく時、悲劇が起きる。
プロジェクトが大型化すればするほど、政治力が必要となってくるから、科学者は、研究室の中だけで暮らせないのだ。
旧ソ連のルイセンコ事件がよく知られる。
農学者ルイセンコは、メンデルの遺伝学を否定したのだが、当時の共産主義思想に都合がよかったため、党と政府の強い支持を受け、生物学界を牛耳って、農業科学アカデミー総裁に上り詰めた。
そして、学説に反対する生物学者を徹底的に政治的迫害した。
小麦の起源の研究で知られる世界的遺伝学者バビロフは、獄死に追い込まれ、米科学誌に論文をのせた別の大物学者も「非愛国者」と非難され、自説を放棄した。
多数の生物学者が追放の憂き目をみたが、当のルイセンコも、独裁者スターリンの死によりやがて失脚の運命をたどった。
「背信の科学者たち―論文捏造、データ改ざんはなぜ繰り返されるのか」(ブルーバックス)ウイリアム・ブロード/ニコラス・ウェイド(著)牧野賢治(訳)

「研究不正 - 科学者の捏造、改竄、盗用」(中公新書)黒木登志夫(著)

「論文捏造」(中公新書ラクレ)村松秀(著)

浮き世離れしているはずの言語学でも、ニコライ・マールの理論が猛威を振るい、多くの優秀な言語学者が粛正された。
ただ、さすがのスターリンも自ら間違いを認め、マールの言語=上部構造論を否定した。
「言語の夢想者―17世紀普遍言語から現代SFまで」マリナ ヤグェーロ (著)谷川多佳子/江口修(訳)

<関連図書>
・英仏普遍言語計画 デカルト、ライプニッツにはじまる
・ライプニッツの普遍計画 バロックの天才の生涯
・キルヒャーの世界図鑑 よみがえる普遍の夢
・薔薇十字の覚醒 隠されたヨーロッパ精神史
・ペルシャの鏡 ライプニッツの迷宮をめぐる幻想哲学小説
・バロックの神秘 タイナッハの教示画の世界像
・綺想の帝国 ルドルフ2世をめぐる美術と科学
・地球外生命論争 カントからロウエルまでの世界の複数性をめぐる思想大全
・世界の複数性についての対話 フォントネルによるお洒落なSF
ブレヒトは戯曲「ガリレイの生涯」の中で「科学の目的は、無限の英知への扉を開くことではなく、無限の誤謬にひとつの終止符を打ってゆくことだ」(Es ist nicht ihr【die Wissenschaft 】 Ziel, der unendlichen Weisheit eine Tuer zu oeffen, sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen Irrtum.)とガリレイに語らせている。
ブレヒトがこの作品を書いたのは、祖国ドイツがナチズムに支配されていた時代で、学問の自由や科学者の良心が踏みにじられ、ユダヤ人であるアインシュタインの学説を攻撃する物理学者らが暗躍したからでもあった。
「ガリレイの生涯」(岩波文庫)ベルトルト ブレヒト(著)岩淵達治(訳)
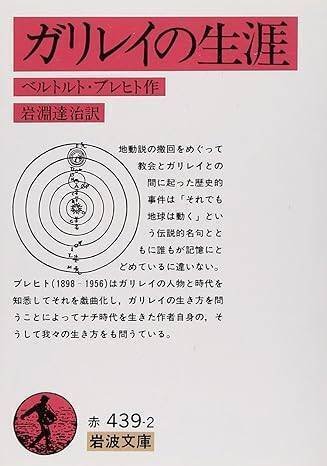
往年の007シリーズでは、国際秘密組織スペクターが敵となっていたが、みんなが不正に向かって働くことなどあるだろうかと思って見ていた。
しかし、オウム事件以降、科学と社会との関係は、しっかり考えなければならないと思うようになった。
フランスの微生物学者パスツールは、「科学に国境はないが、科学者には祖国がある」と言ったが、国家などの組織から離れて研究することは難しくなっている。
言葉の視点を変えるとジョークやユーモアになるが、視点を変えることは言葉でいうほど簡単ではない。
というのも、言葉自体が我々の思考を呪縛するものだからだ。
イタロ・カルヴィーノは、「カルヴィーノの文学講義」の中で、次のように書いている。
「カルヴィーノ アメリカ講義――新たな千年紀のための六つのメモ」(岩波文庫)カルヴィーノ(著)米川良夫/和田忠彦(訳)

ときとして、私には、何かしら疫病のようなものが人類をもっともよく特徴づけている能力、すなわち言葉を用いる能力を駄目にしているのではないかと思われることがある。
言葉の伝染病といったもので、その兆候は、識別的な機能や端的さの喪失、あるいは、また、表現をおしなべて、もっとも一般的な没個性的で、抽象的な決まり文句に均一化させてしまい、その意味を稀薄にして、語と語が新しい状況に出合うときに発する火花を、いっさい消し去ってしまおうとする一種の無意識的・機械的な振舞いとして現れている。
また、こんな例もあり面白い。
ある大学で、学生に座席表を書かせると、時々、学生から見た座席表を作るものがいる。
教師の立場で欲しいのは、教壇から眺めた学生の位置と名前なのだが、視点を変えることができない。
簡単な幾何学の問題でも、視点を変えることができずにつまってしまう。
セレンディピティというのは、心に補助線を入れることなのである。
将棋や碁の名人は、即座に相手の立場から盤上を眺めることができるのに、素人にはできない。
また、ある学校がPRビデオを作る時に、環日本海時代を表すために地球を逆さまにしたCGを作ってもらって、「私たちは発想の転換を大切にします」と流した。
ところが、何かおかしい。
結局、気象学の先生も見逃していて、雲の動きが逆になってしまっていた。
逆さまになった時も、左から右に流れるままになっていて、元に戻ると、東から西へ流れるようになるのだが、見逃していた。
視点を変えることは、本当に難しい。
視点をちょっと横にずらせば、逃げ道があるのに、目の前のガラスに阻まれる蠅のごときが、我々の姿なのである。
視点を変えるだけでなく、ひっくり返すことが大切だ。
最も鮮やかな例は、天動説から地動説への「コペルニクス的転回」であろうし、
「コペルニクス的転回の哲学」瀬戸一夫(著)

ドーキンスは、生命体が遺伝子を残すのではなく、利己的な遺伝子が生命体を遺伝子の使い捨て容器として使っていると逆転させたし、
「利己的な遺伝子 40周年記念版」リチャード・ドーキンス(著)日髙敏隆/岸由二/羽田節子/垂水雄二(訳)

「盲目の時計職人」リチャード・ドーキンス(著)日高敏隆(監修)中島康裕/遠藤彰/遠藤知二/疋田努(訳)

「進化とは何か ドーキンス博士の特別講義」(ハヤカワ文庫NF)リチャード・ドーキンス(著)吉成真由美(編, 訳)

「延長された表現型―自然淘汰の単位としての遺伝子」リチャード・ドーキンス(著)日高敏隆/遠藤知二/遠藤彰(訳)

ホイジンガやカイヨワは、遊びから、逆に、人間を照射したし、
「ホモ・ルーデンス 文化のもつ遊びの要素についてのある定義づけの試み」(講談社学術文庫)ヨハン・ホイジンガ(著)里見元一郎(訳)

「遊びと人間」(講談社学術文庫)ロジェ カイヨワ(著)多田道太郎/塚崎幹夫(訳)

ホルクハイマーやアドルノは、合理化が進めば進むほど文明は野蛮さを深めるという啓蒙の弁証法を考えた。
「啓蒙の弁証法 哲学的断想」(岩波文庫)ホルクハイマー/アドルノ(著)徳永恂(訳)

写真家の藤原新也は、写真を読むために有効な「あの人がさかさまなのか、わたしがさかさまなのか」という写真を撮っている。
「メメント・モリ」藤原新也(著)

長沼行太郎は、「思考のための文章読本」で、次のように、転倒の思考について述べている。
「思考のための文章読本」(ちくま学芸文庫)長沼行太郎(著)

転倒の思考は、順序を変えることによって、もともとあったのに、今では気づかなくなっていること、忘れてしまっていること、(従来の説明の順序では)隠されていることを明るみに出す。
つまり、起源、出生の秘密をあらためて思い知らせてくれる。
卑近な例で考えれば、健康をもっとも意識するのは病気の時である。
健康が分かるのは、病気を通してであり、ありのまま過ごしていると気づかない。
幸福だって同じで、不幸になって初めて、強く意識するものである。
同じように、理性というのも、理性だけで考えていては分からない。
狂気というものを通して、初めて考えることができるのではないだろうか。
これを見事にやってのけたのが、ミシェル・フーコーで、視点を変えることによって、考古学のように、「知」を掘り出したのである。
「知の考古学」(河出文庫)ミシェル・フーコー(著)慎改康之(訳)

バルトはまず、フーコーが、「狂気と非理性――古典時代における狂気の歴史」において、狂気という人間の普遍の本性に属すると考えられてきたものを、歴史の変遷のなかに置き直し、また、従来医学の問題とされていたものを文明の問題に移し替えた、とする。
「狂気の歴史 古典主義時代における」ミシェル フーコー(著)田村俶(訳)

歴史の観点から見るなら、同じ狂気が、中世には気違いと呼ばれ、十七世紀を中心とする古典時代には狂人とされ、やがて、精神病医ピネル(1745-1826)によって、罪人と同一視されていた狂人を精神病者として、初めて医学の対象とされたのであった。
しかし、フーコーは、こうして、その名称の変遷を重ねてきた狂気を、医学の対象とは考えていず、バルトの理解するところでは、「狂気とは病気ではなく、世紀によって変化する、おそらく異質的な意味であり、狂気とは理性と非理性、眺める者と眺められる者とが形づくる一対に純然たる機能なのである」とした。
狂気が病気でなく意味であるとすれば、各時代の歴史的、社会的背景が作り出す記号作用の全体的構造のなかで、精神錯乱なる現象は、捉えられねばならないであろう。
これが、フーコーの実現した第一の構造分析である。(通時的分析)
次に、狂気とは、理性と非理性、観察する者とされる者とが一対をなす機能であるとすれば、これを共時的観点から見れば、問題は超歴史的なある種の形式(フォルム)であり、「社会全体のレベルで、排除される者と包含される者とを対立させ、また結合するひとつの相補性」なのである。
この点がフーコーの探求した第二の構造分析であった。
中世には、追放、古典時代には強制収容、近代には病院への拘禁に分かれたにせよ、常に、同一であるのは、社会規範にはずれた者を排除するというひとつの行為である。
社会的正常者がありうるためには、異常者がいなければならず、この意味で両者は、相補的関係にあり、排除は、狂気のほかに、シャーマニズム、犯罪行為、同性愛等々に及ぶものである。
「ロラン・バルト―世界の解読」篠田浩一郎(著)

目的と手段を間違って、逆に、考えてしまう人が多い。
英語を学びたい、という人の多くが、目の前のコミュニケーションを避けて、いつか会える英米人との会話を夢見て、目的を考えずに英語を学んでいる。
いつか役に立つ、というのだが、そんなヒマがあったら、今役に立つことをしたらどうかと、皮肉の一つも言いたくなる。
三浦俊彦の小説「サプリメント戦争」に出てくる登場人物の一人は、例えば、カップめんを食べたあと、こんな錠剤を飲む。
「サプリメント戦争」三浦俊彦(著)
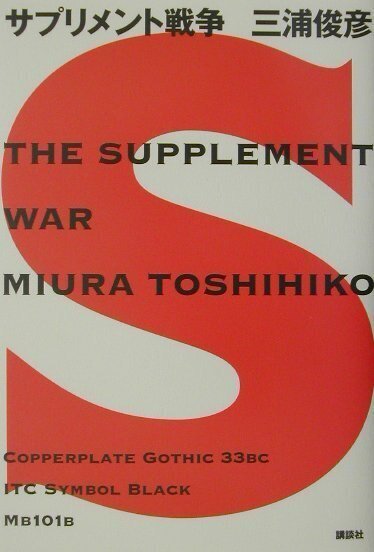
ビタミン剤各種、いちょう葉エキス、アガリクス、高麗人参、田七人参、大豆レシチン、エゾウコギ、すっぽん生血、葉酸、ブルーベリーエキス、牛黄、霊芝、ウコン、ソバ若葉等々。
それで体調はいいのか、と聞かれると「さあねえ」と言い、そして、答える。
「僕は健康マニアじゃなくてね、健康食品マニアなんで・・・・・・」
「健康のためなら死んでもいい」という人も多い。
酒もダメ、タバコもダメ、美食もダメとなると、生きていることが健康に悪いということになる。
考えられるべきことは、既に、考えられている。
言葉だって、オリジナルな言葉を使えるはずがない。
【関連記事】
【雑考】垂直思考と水平思考
https://note.com/bax36410/n/nc041319885eb
【雑考】対位法的思考
https://note.com/bax36410/n/nef8c398b72cb
【雑考】複雑系思考法
https://note.com/bax36410/n/neaab25206650
【宿題帳(自習用)】ふと目を向けた風景、しゃがんだ時に見えるもの。
https://note.com/bax36410/n/nad27a9739ea4
