
【宿題帳(自習用)】セレンディピティは偶然のチャンスを活かす力を指すキーワード

セレンディピティは、偶然と察知力の二つの要素があり、偶察力と呼ぶことも可能である。
セレンディピティは、「当てにしていないものを偶然にうまく発見する能力」と定義されており、
・発見・創造する能力とは、偶然を最大現に活かす能力である。
・感性を研ぎ澄まし、察知力を養えば偶然は偶然でなくなる。
偶然の幸運に出会う能力よりも、具体的で主体的(発見する>出会う)なニュアンスが感じられる。
これを契機に、偶然に思いがけぬ発見をするには、「不思議に感じたことは、それを追求すれば原因がある」と信じることが大事である。
この不思議に感じたことを放置すれば、そのまま偶然は、通り過ぎていくのである。
それが何であるかがわからなくても、とりあえず「あれ?」と思ったこと、あるいは、やっていてひっかかることに注目することは、発見への第一歩である。
具体的な発見の手順は、まず、「オャッ」と気付く感動から初めてみると、そのような事象、現象に出会ったときは、それを観察して記録を残し、ネーミングしておくことである。
さらに、課題の認識を行い、これに関する連想が働きやすい状態にする。
情報交換は、積極的に行い、関連記事を見つけたときには、手軽にファイリングできるシステムを作っておく。
行動範囲を拡大して、思いがけぬ連想の生じる機会を促進する。
因果関係が解明できれば仮説をたてて、これを検証する。
そして、思いもよらぬ因果関係を明らかにすることになれば、これは発見であり、これを応用することから創造が生まれる。
以上をまとめると、セレンディピティを活かすための手順は、
1.ひっかかったことを観察し記録する
2.名前を付ける
3.課題の形に変換する
4.関連する情報を集める
5.仮説を立て検証する
という5つのステップになる。
このように、自分が何となくやってしまっている、あるいは、無意識にできてしまっていることに、改めて目を向けて、その方法やメカニズムを、上記の手順で考えてみることで、セレンディピティを発揮し、未踏の領域への第一歩を踏み出すきっかけを作ることができそうである。
成功している人を見ると、「たまたま運がよかっただけ」と舌打ちし、「自分は運がないな」と自虐的になってしまう方もいるのではないだろうか。
こんな妬みの心理は、やる気を失わせる一因だが、確かに、幸運・不運は、人それぞれにあるように思える。
しかし、たまたまの幸運は、単に、どこからかやってくるものではない。
ある偶発的なことが身の周りで起こったとき、それを幸運に結びつけるか見逃すかは、心がけ一つと思う。
出会いは宝物というのは、人生訓の常套句だし、一期一会という故事もある。
幸運な出会いが度重なって、初めて一期一会という言葉の重みを実感するのかもしれない。
しかし、これを人生訓として受け取るだけでは、物足りない気がする。
偶然には、何か秘密が隠されているのではないかという思いが折りに触れ去来していた。
もちろん、偶然の秘密など、おいそれとわかるはずはない。
このテーマは、ショーペンハウアー、ニーチェ、ハイデガーなどの大思想家たちを悩ませた哲学の一大命題である。
「偶然性と運命」(岩波新書)木田元(著)

「意志と表象としての世界〈1〉」(中公クラシックス)ショーペンハウアー(著)西尾幹二(訳)

「偶然性の問題」(岩波文庫)九鬼周造(著)

思想 2021年 12 月号

〈共〉を生きるということ――J.-L.ナンシーのために
「偶像の黄昏」(河出文庫)フリードリヒ ニーチェ(著)村井則夫(訳)

偶然性について(1)偶然は無知の表われか
偶然性について(2)哲学は偶然を嫌う
「後悔と自責の哲学」中島義道(著)

「ニーチェは偶然と運命とのあいだの揺れを止めようとする。つまり、われわれの眼には偶然に見えるさまざまな事象の背後に「何か意志的なもの」があって、それがすべてを動かしていることを認めるのではなく、すべてがまさに偶然であることをそのまま認めよということ。」(「後悔と自責の哲学」より)
偶然に関心を寄せながらも、我々の理解は、偶然とは不思議なものだというレベルに止まっている。
その理解が突如、一気に飛躍することになったのは、セレンディピティという言葉だった。
辞書を引くと「あてにしていないものを偶然にうまく発見する能力」と記されていた。
しかも、この言葉はR・K・マートンという米国の科学社会学の大家によって使われ、科学的発見にまつわる偶然性を説明する言葉として注目されていた。
まず、言葉の由来を、歴史を遡りながら紹介しておく。
マートンが、この言葉を最初に使ったのは、1945年の論文である。
その10年後には、研究論文「セレンディピティの旅と冒険ー歴史的意味論と科学社会学に関する研究」(未完)を著し、科学的発見に、しばしば見られる偶然性を「セレンディピティ」と名づけて自分の科学社会学理論の新しいコンセプトとして公表した。
例えば、リンゴの落下を見て万有引力の理論をつくりあげたニュートン、乳しぼりの牛痘にかかった人は天然痘に罹らないことを知って種痘を開発したジェンナー、蛍光スクリーンが光るのを見てX線を発見したレントゲン等である。
これら歴史的な発見は、あてにしていないものを偶然にうまく発見する能力が閃いた成果である。
マートンの論文は、話題を呼び、議論を巻き起こした。
但し、「セレンディピティ」は、マートンの造語ではない。
この言葉と出合ったのは、「いわばブラブラ歩きをするように、何気なく『オックスフォード英語辞典(OED)』を拾い読みしていた時だった》」と自著のなかで書いている。
「小さなことばたちの辞書」ウィリアムズ,ピップ(著)最所篤子(訳)
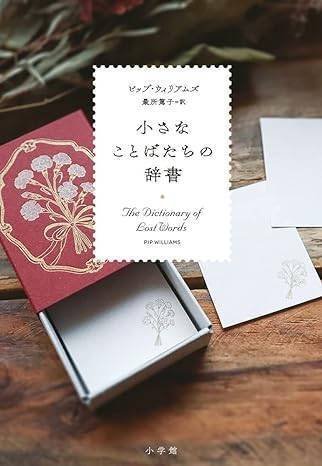
この言葉の誕生は18世紀まで遡る。
ホレース・ウォルポールという英国人文筆家が、知人あての手紙のなかで初めて使ったことが知られている。
その経緯は、次のようなものだ。
ある王妃の肖像画が、彼のもとに届き、その額に家紋を入れることになった。
しかし、王妃の一族の家紋が定かでない。
調べようとしていると、名家の家紋を記した古書が偶然見つかり、無事に額を仕上げることができた。
彼には、似たような体験が何度もあったらしく、それを「「セレンディピティ」と私が名づけた不思議な力によると考えています」と手紙に書き、言葉の由来についても、次のように記している。
「以前読んだ寓話「セレンディップの3人の王子」では、旅に出た王子が次々と起こる偶然のできごとに対し、それぞれの場に応じた察知力を発揮して思いがけぬ発見をしていきます。
これらの発見は本来探していたものとは違うのですが、とても大切な発見なのです。」
セレンディップとは、現在のスリランカ共和国のことで、同国の3人の王子の冒険物語はペルシャからアラビアを経てヴェネツィアに伝えられ、1557年に『遍歴セレンディップの3人の王子』として出版されている。
「セレンディップの三人の王子たち―ペルシアのおとぎ話」(偕成社文庫)竹内慶夫(編訳)増田幹生(イラスト)

ちなみに、さきの手紙は1754年に書かれており、寓話の出版から、ちょうど2世紀後に「セレンディピティ」という言葉が生まれたことになる。
さらに、それから、また、2世紀後の20世紀半ばに、マートンによって、その言葉が再発見された。
2世紀ごとの周期も単なる偶然だろうが、「セレンディピティ」の由来にふさわしい、意味ありげな歴史ではある。
ところで、マートンの再発見以後は、未来の2世紀後を待つことなく、「セレンディピティ」をめぐる話題は、じわじわと広がっていた。
1964年には、この寓話の児童向けの本が米国で出版され、1998年に記号論の大家、ウンベルト・エーコの「セレンディピティ」という本が出版され、原典のイタリア版寓話も2000年に復刻された。
「セレンディピティー―言語と愚行」エコ,ウンベルト(著)谷口伊兵衛(訳)

日本でも、着実に関心が高まっていた様だ。
とりわけ1985年に、米国の化学者であるロナルド・S・レノックスは、「セレンディピティ的発見のための教育」と名付けた論文を『化学教育ジャーナル』に発表して「科学者が研究するとき、発見と創造のすべての場面で活用できるセレンディピティを認識し、研究生に教育することが重要である」と述べた事の影響が大きかったという。
彼がここで紹介しているのは、
フリードリッヒ・ヴェーラー:有機物と無機物の差異の発見
レントゲン:X線の発見
アンリ・ベックレル:ウラニウムの放射性の発見
ルイ・パストゥール:結晶構造の発見
ニューヨークのふたりの遺伝学者:プロスタグラディンの発見
フレミング:ペニシリンの発見
その他、ルイジ・ガルヴァニ、アレッサンドロ・ヴォルタ、シャルル・リセ、ダム、パーキン、マラウス等の発見であるが、最後には、このようなリストはエンドレスに続くと断っている。
前述の通り、同論文で「科学者が研究するとき、発見と創造のすべての場面で活用できるセレンディピティを認識し、研究生に教育することが重要である」と強調されたことで、それ以後、日本の科学界、教育界では、すでに専門用語として定着した感がある。
そのおもしろさを紹介したいのは、この本であり、日本で初めて書かれたセレンディピティの解説書である。
「偶然からモノを見つけだす能力―「セレンディピティ」の活かし方」(角川oneテーマ21)沢泉重一(著)

では、この能力を体得するには、どうしたらいいか?
澤泉重一さんの同書には、技法がいくつか紹介されているが、なかでもカギとなる技法は、澤泉さんの、こんな体験から説き起こされている。
かつて米国の国内便の機内で、豊富な海外経験をもつ商社マンと隣り合わせたときのことである。
機内サービスで客室乗務員から「Coffee or tea?」と聞かれて、商社マンは「コーヒー」と返事をしたのだが、乗務員は何度も頭をひねってばかり。
結局、大声で5回も6回も返事を繰り返した挙げ句に、やっとコーヒーがつがれたが、乗務員は、納得した表情ではなく、商社マンも憮然としていた。
ここで、「発音が悪かったんだな」と了解してしまえば、それで終わりである。
しかし、海外経験豊富な商社マンの発音が通じなかったのか?と、隣席の著者は、目的地に着くまであれこれ原因を考えた。
しばらくして閃いたのは、こんな仮説だった。
「コーヒー」と「ティー」だから、「コー」と言っただけで伝わるはずなのに、なぜ伝わらなかったのか?
それは、「コー」のあとに続く、「ヒー」で乗務員が混乱してしまったからではないか?
「f」は、下唇をかんで発音する。
ところが、商社マンは、下唇をかまなかったから、「ヒー」と「ティー」がごっちゃになってしまった。
そう確信して著者は、遠くにいる乗務員にカップをかざして見せ、下唇をかむ口まねだけをしてみた。
すると見事にコーヒーが運ばれてきた。
おもしろくなって、それ以後も、カフェに行くと、いつも同じ実験を繰り返し、ひとり悦に入っていたそうな。
きっかけは、「アレッ?」と感じた、ささやかな偶然である。
その驚きや実感を、多くの場合は、「こんなこともあるんだな」程度に考えて、すぐに忘れて去ってしまう。
しかし、そこで、「ちょっと待てよ」と踏みとどまってみることが肝要だ。
そのとき、驚きや実感の不思議さを、自分なりに納得させる仮説を立てることがポイントである。
仮説を立てるためには、偶然のできごとを、じっくりと考え直すほかない。
そして、仮説を立て、それを検証するなかで、偶然のなかに、「原因ー結果」の道筋が見えてくる。
つまり、偶然に潜む必然が、にわかに姿をあらわすのである。
これで、澤泉重一さんの積年のテーマである偶然の秘密が解明されたとは言えないが、確かに、この技法には、偶然から幸運をつかむ能力、つまり、セレンディピティを身につける秘訣がありそうだ。
順序立てて表現すると、次のようになると考えられる。
(1)偶然その現象に出くわす。
(2)常識からはずれた現象に興味をしめす。
(3)常識を疑い、そこに新たな仮説を立てる。
(4)その現象を徹底的に分析し、仮説を裏づける。
これが本当に、幸運を呼ぶ黄金律かどうかは、お試しあれ!、というほかない。
但し、この技法が、単なるマニュアルに終わらないために、澤泉重一さんが、とりわけ強調していることがある。
それが、「当事者意識をもつ」ということである。
例えば、「会社は、誰が動かしていると思いますか?」との質問に対して、「社長です」や「実質的には部長です」等と答えが返ってきそうだが、「いや、会社を動かしているのは君自身。君がそう意識しなければ、会社はうまく動かないよ」と考えられるかどうかである。
当事者意識とは、正に、これである。
当事者意識を心がけていれば、自分の行動に責任を持つようになる。
そうなると、小さなことにも心配りをするようになり、単なる偶然も、大切なチャンスに見えてくる。
こうなれば、もうセレンディピティを体得したようなものなのかもしれない。
当事者意識を持って、偶然に拘る。
この心がけこそが、幸運を運んでくるのだ、というのがセレンディピティの肝ということになるのではないかと推定される。
【参考資料(松岡正剛の千夜千冊)】
0596夜 『花月のコスモロジー』 大峯顯 - 千夜千冊
https://1000ya.isis.ne.jp/0596.html
0689夜 『「いき」の構造』 九鬼周造
https://1000ya.isis.ne.jp/0689.html
1304夜 『セレンディピティの探求』 澤泉重一・片井修
https://1000ya.isis.ne.jp/1304.html
1330夜 『たまたま』 レナード・ムロディナウ
https://1000ya.isis.ne.jp/1330.html
1334夜 『偶然を飼いならす』 イアン・ハッキング
https://1000ya.isis.ne.jp/1334.html
1335夜 『偶然性と運命』 木田元
https://1000ya.isis.ne.jp/1335.html
1336夜 『市場社会の思想史』 間宮陽介
https://1000ya.isis.ne.jp/1336.html
1340夜 『確率論的思考』 田渕直也
https://1000ya.isis.ne.jp/1340.html
1345夜 『リスクのモノサシ』 中谷内一也
https://1000ya.isis.ne.jp/1345.html
1350夜 『偶然性・アイロニー・連帯』 リチャード・ローティ
https://1000ya.isis.ne.jp/1350.html
1482夜 『偶然の科学』 ダンカン・ワッツ
https://1000ya.isis.ne.jp/1482.html
1550夜 『人生論ノート』 三木清
https://1000ya.isis.ne.jp/1550.html
1648夜 『模型のメディア論』 松井広志
https://1000ya.isis.ne.jp/1648.html
1770夜 『小枝とフォーマット』 ミシェル・セール
https://1000ya.isis.ne.jp/1770.html
1838夜 『偶然とカオス』 ダヴィッド・ルエール
https://1000ya.isis.ne.jp/1838.html
【関連記事】
【雑考】垂直思考と水平思考
https://note.com/bax36410/n/nc041319885eb
【雑考】対位法的思考
https://note.com/bax36410/n/nef8c398b72cb
【雑考】複雑系思考法
https://note.com/bax36410/n/neaab25206650
系統樹思考はアブダクションとしての推論である
https://note.com/bax36410/n/n13a9cf9a3e9e
【宿題帳(自習用)】ふと目を向けた風景、しゃがんだ時に見えるもの。
https://note.com/bax36410/n/nad27a9739ea4
【短評】個人の自由は本当に人間の本質なのか?
https://note.com/bax36410/n/nc3f45d1a6aab
【短評】欲望の資本主義の行き着く先
https://note.com/bax36410/n/nbd72e02c7b08
