
系統樹思考はアブダクションとしての推論である
(左)エルンスト・ヘッケルの系統樹。
(右)チャールズ・ダーウィン直筆の系統樹のスケッチ。
失われた過去をいかに復元するか?
誰しも、一度は、自分の過去を顧みたことがあるのではないでしょうか?
noteの記事を書くとき、イメージが先にあって、何かを思いついたり考えたり、頭の中に何かしらの映像だとか図等が浮かんでいる事が多いです。
特に、「なぜそのときにそれが起こったのか?」を考えるときなどは、時間的な文脈がとても重要だと考えています。
さて、系統樹思考とは、進化の過程を見る視点を与えるものです。
ただし、この進化は生物に限ったものではありません。
その由来を図示するのが、系統樹です。
ここで言う系統樹とは、そもそもの由来を図で表したものです。
「樹」という言葉が入っているように、ツリー状に書かれることが多く、色々な多様性を系譜関係によって体系化し、整理するものです。
【課題図書】にも例が出てくるのですが、書体の進化なども系統樹として纏められます。
物事を整理するためには、2つの視点があります。
一つは本書に述べるような「系統樹思考」ですが、もう一つは、分類思考と呼ばれるもです。
その違いは、前者が対象物の系譜関係に基づいて体系化するのに対して、後者は対象物そのものをカテゴリー化するということです。
この考え方はビジネスなどにも応用できると考えています。
【課題図書】
「系統樹思考の世界―すべてはツリーとともに」三中信宏(著)(講談社現代新書)

【参考図書】
「思考の体系学―分類と系統から見たダイアグラム論」三中信宏(著)

「読む・打つ・書く―読書・書評・執筆をめぐる理系研究者の日々」三中信宏(著)

「系統体系学の世界―生物学の哲学とたどった道のり」(けいそうブックス)三中信宏(著)

「統計思考の世界―曼荼羅で読み解くデータ解析の基礎」三中信宏(著)

【関連図書】
「社会生物学論争史〈1〉―誰もが真理を擁護していた」セーゲルストローレ,ウリカ(著)垂水雄二(訳)

「社会生物学論争史〈2〉―誰もが真理を擁護していた」セーゲルストローレ,ウリカ(著)垂水雄二(訳)

「進化論の射程―生物学の哲学入門」(現代哲学への招待)ソーバー,エリオット(著)松本俊吉/網谷祐一/森元良太(訳)

「歴史・レトリック・立証」ギンズブルグ,カルロ(著)上村忠男(訳)

「分類の発想―思考のルールをつくる」(朝日選書)中尾佐助(著)

「科学的発見の論理 上」カール・ライムント・ポパー(著)大内義一(訳)

「科学的発見の論理 下」カール・ライムント・ポパー(著)大内義一(訳)

「推測と反駁―科学的知識の発展 (新装版)」(叢書・ウニベルシタス)ポパー,カール・ライムント(著)藤本隆志/石垣壽郎/森博(訳)

「系図が語る世界史」(シリーズ歴史学の現在)歴史学研究会(編)

「ダーウィン著作集〈別巻1〉現代によみがえるダーウィン」長谷川真理子/矢原徹一/三中信宏(著)

「文明のなかの博物学―西欧と日本〈上〉」西村三郎(著)

「文明のなかの博物学―西欧と日本〈下〉」西村三郎(著)

「超芸術トマソン」(ちくま文庫)赤瀬川原平(著)

[ 問題提起 ]
「系統樹思考の世界―すべてはツリーとともに」の持つ価値は、著者の「系統樹思考」が拓く豊かな地平とその大きな射程だ。
プロローグでは、生物に限らない進化的な捉え方としての「系統樹思考」が述べられる。
系統樹の適用範囲の生物への限定を外すことで、あらゆるものを系統という由来関係によって捉えることが可能になる。
それはすなわち、学問の壁を超え、進化論が導く新しいものの見方なのだ。
第一章のテーマは、歴史の科学は成立するか、成立するならばいかにしてか、という問いへの回答だ。
この問いへの著者の答えは、歴史の科学は進化論において成立し、その方法論はアブダクションによるというものである。
著者は、物理学を典型的な科学とみなす科学哲学を批判しつつ、ローカルな科学哲学、つまり「個別科学の研究者の側から積極的に「哲学」を作っていく」科学哲学を主張する。
この主張は、統一された科学というイメージから多様な科学というイメージへの変更、科学観の変更を促すとともに野心的な主張でもあるように私には感じられた。
生物学の哲学は、その創生期からこの野心を共有してきたと言えると思うが、それでもなおこの点は強調されつづける価値がある。
というのも、科学が描くのはわれわれの世界の像であるが、その像はただ一つしかないというのはおかしな話かもしれないからだ。
印象派が描く絵もキュビズムが描く絵も、どちらも絵画であり、そしてどちらか一方が他方に還元されることはないはずだ。
第二章は、系統樹というイコンが持つ歴史から話は始まる。
この章の役者は「分類」と「系統」である。
著者は、科学的な歴史研究の方法論が実はヒューウェルの「古因学」にすでに見られることを指摘しつつ、この歴史学の方法論こそが「比較法」に基づくアブダクションに他ならないと述べる。
同時に、この思考法の大変革は、現代生物学におけるであった「系統樹革命」を引き起こしたと著者は言う。
この革命は、無意識に採用しがちな類型学的な「分類思考」から、進化論的な「系統樹思考」への変革を促し、さらには生物学を超え「一般化された進化学・系統学」に至ると述べられる。
これは、著者も言及しているとおり、デネットやドーキンス(ただし本文のドーキンスへの言及はない)の主張する「普遍的ダーウィニズム」と軌を一にする主張であると考えられる。
ただし、興味深いのは、デネットなどは自然淘汰説を念頭に置いてこの主張を行っているのに対して、著者は「生命の樹」説(変化を伴う由来説)」に基づいて、彼らと同様の主張をする点だ。
私は、この差は、実は、大きいと考えている。
というのも、その差こそが体系学論争において一つの役割を果たしたのではないかと考えているからである。
インテルメッツォは、その後に続く難所に入る前の休憩といった趣である。
高校生たちが書いた楽しい素朴系統樹を見て笑いながら、私はどこか自分の鏡を見ているようような気がしてならなかった。
たぶん彼らの描く系統樹は、われわれの素朴な実感や常識の反映なのだ。
彼らの純粋な気持ちから透けて見える自分の姿を見つけて、私は自分の常識をちょっとだけ脇に置くことにした。
そうすることであとに続く章の理解がぐっと楽になったと思う。
この章後半の体系学論争小史における、著者の「三学派はすれちがっていた」という指摘は重要だ。
三学派は今も生きている。
数量分類学派は統計学に(あのS&RのSだ)、分岐学派は系統推定論へ、進化分類学派は分類学者の心の中で、いまも生きているのだ。
第三章からは、グラフ理論を使った系統樹構築の方法論が解説されている。
ここの記述は、本当に丁寧で大変わかりやすい。
とはいうものの、この本の中では最も形式的でとっつきづらい箇所であることも確かだろう。
私自身の経験では、無根系統樹という概念は、なかなか理解できず苦労した憶えがある。
ここでも、実は、「比較法」がポイントになっていることは明らかだろう。
比較法の図形的表現としての系統樹という主張は、これまでの議論を読めばたやすく理解できるだろう。
ただ、「形質状態」の箇所はやや駆け足である。
「端点がもつデータとは、ある「形質」(特徴)のとるさまざまな状態」と言われても、なかなか理解するのは難しい。
著者の意を汲むならば、「形質」は何かの特徴(たとえば〈赤〉)であり、「形質状態」とは外群と比較したときに、その外群の対象の形質と当該の形質とを比較してどのような状態にあるか(対象となる端点と外群がともに〈赤〉ならば状態〈1〉、端点が〈赤〉でないなら〈0〉、二値を取らず中間値や類似度を認める場合には〈ピンク〉〈0.5〉)、ということであろう。
この点を押さえれば、続く叙述は怖くない。
最節約性は比較法を使ったときに何がベストなのかを決める基準である。
この基準をもとにベストの仮説を選びとることは、たしかにそれが仮説に過ぎなくとも、それこそが「歴史科学」の基本的性格であるとともに、「系統樹の科学」にとってこうした基準自体を吟味することが求められるのだと著者は主張するのだ。
この章は他の章と比べると難しいが、エキサイティングな箇所でもある。
というのも系統学がただの生物学の一分野ではなく、生物学・統計学・哲学・計算機科学・数学が絡み合った挑戦しがいのある山がそびえ立っているのを感じられるからだ。
また、体系学は進化生物学/生物学の哲学において、ジャーゴン(仲間うちにだけ通じる特殊用語。専門用語。職業用語。転じて、わけのわからない、ちんぷんかんぷんな言葉。)が多い分野として悪名高いのだが、この章以下の叙述においてジャーゴンがほとんど使われていないのは驚くべき事である。
ここでは、「一般化した系統学」という理念が本書では通底していることを、強く認識させられたのである。
第四章は著者の回想で幕をあける。
この回想を読んで、著者の言葉を思い出した。
正確な台詞は覚えてないのだが、著者は、「学際的であるということは、二つの分野にまたがるという意味ではなく、二人分頑張るということです。」とわれわれに述べたと思う。
たいした言葉だとは思われないかもしれないが、私自身にはとても重要な一言だった。
この章の読むと、私が聞いた言葉が著者自身の経験から出てきたことがわかる。
3節と4節は科学哲学といってよい。
ガレス・ネルソンが提唱した分岐図の考え方が系統樹をモデルと見なす見方を開くこと、そしてその意味において個別要因説明と共通要因説明もまたモデルであると考えることができると主張される。
そしてそれゆえに、適切なモデル化が必要であること、モデルを支える適切なデータが必要であることが述べられる。
以上の点もからも、系統推定の標的が祖先子孫関係ではなく姉妹群関係を推定することに向けられているわかる。
本章の内容は、科学哲学で言うところの「科学的説明」「因果性」の問題を扱っている。
この二つの節に関しては詳しく検討しなければならない問題が数多く含まれているように思われるので、後述する。
本章の後半は「もつれ合った樹」の問題、ネットワークとスーパーツリーの解説である。
内容はやや駆け足だが、この二つの種類の系統樹は分岐学なしには成立しえなかっただろうことは感じられるゆえに、系統学の未来が垣間見られる箇所と言えるかもしれない。
エピローグは再び物事を「系統樹で見る」という「系統樹思考」の理念が述べられる。
これと正対する「分類思考」の限界とその哲学的背景、および諸学問の共通言語としての系統樹と系統樹思考に触れたあと、オペラは万物のもとにある系統樹を高らかに宣言することで幕を閉じる。
このように、多くの魅力を備えた本書ではあるが、いくつか理解しにくい点があったのも確かである。
ひとつは、著者が以前から主張している認知科学の研究対象としての種・分類という考え方についてである。
たとえば、「分類思考に即した自然分類は、おそらく認知心理学的な研究の延長線上に到達できるだろう」(124頁)などの叙述は、なかなか理解するのが難しかった。
まず、この叙述だけをとってみると、そこには認識の源泉を心の働きに置くという心理主義の主張のように聞こえるからである。
だが、何かの生物個体を観察するだけで、分類体系(自然分類)ができるわけではあるまい。
個々の生物個体を観察することによって得られるのは、ある個体と別の個体が異なる/同じであるということがわかるということだけである。
したがって、この記述は心理主義を標榜しているわけではないことは理解できる。
ではいったいこの記述は何を意味するのか。
ポイントは当然ではあるが、進化論的思考にあると思われる。
自然淘汰の産物であるわれわれの認知機構は、それが適応的であったがゆえに、あたかも種が存在するかのように振る舞ってしまうのだ、それゆえに自然分類についての研究とは認知的基盤の振る舞いについての研究だ、というのがここでの主張の意味であろう。
たしかにこれならばうまくいきそうである。
だが、そもそもこの主張が本質主義批判として有効なのかという点においては疑問が残るのである。
というのも私には「認知的本質主義」と(哲学的な意味での)本質主義とは異なるように思えるからである。
哲学の伝統にとって、本質主義についての問題は常に言語の問題と並行的であった。
「異なる事物が同じ名前で呼ぶことができるのはなぜか?」という疑問が本質主義を要請してきたのだ。
そして自然分類という理念は、分類学の使命が「命名」にあることからも示唆されるとおり、言語の問題と切り離すことはできない。
つまり、自然分類という理念を支えるのは、われわれの認知的傾向性ではなく、哲学的な意味での本質主義なのではないだろうか(本質主義は直観的ではない議論が多いことも傍証になるのではないか。本質主義は非常に誤解されることが多い議論だ)。
たしかに、この哲学的な本質主義は認知的本質主義を基盤に持つかもしれない。
だが、その基盤と形而上学的な本質とは決して同一とはなり得ないだろうと思う。
もし同一であるとしたら、それは心理主義に他ならないからだ。
二つめの疑問は、説明と因果についての態度がよくわからないということだ。
アブダクションを導入する第一章では、「理論の『真偽』を問うのではなく、観察データのもとでどの理論が『よりよい説明』を与えてくれるのかを相互比較する-アブダクション」(65頁)という叙述からは、いったい何を目指してアブダクションを行えばよいのか、よく理解できないのである。
まずアブダクションは「真正の原因」を見つけるための試行錯誤のやり方だという考え方があるのではないか?
ライヘンバッハの言う〈濾過〉とはそのような意味を持っている。
だが、たぶんこれは著者のとる見解ではないだろうと思う。
というのも「理論の『真偽』を問うのではなく」と述べる以上は、科学的説明についての実用論的な見解を採っているだろうからだ。
比較法とは、そのような実用論的見解と強い親近性を持っているように思われる。
なぜなら、単系統群の定義に現れているように、比較法は外群の設定が本質的な役割を果たすが、その外群と比較する端点によって、樹形やその系統樹の性格が変わりうるからだ。
つまり、著者の議論からは、系統樹の実在論は出てこないだろう。
もしかしたらcommon cause explanationを「共通要因説明」と訳したのは、私は、なぜこう訳したのかは理解できないのだが、このような意味を持たせたかったからなのかもしれない。
この見解は私も同意するものであるが、やはり問題もある。
まず、直観的に系統樹はやはり因果的説明の一種だと考えられる点である。
そのように考えたとき、系統樹の持つ説得力の源泉は因果関係を示していることにあるように思われる。
この見解にとって、サモンが主張する、濾過をしていくことによって相互作用的分岐を得ること、すなわち「真正の原因」を見つけることが、科学的説明であるというアイデアは魅力的である。
外群を取り替えながらアブダクションを遂行し、「真正の原因」を表すような系統樹を求めるという存在的な解釈も成り立つかもしれないからだ。
「このような比較法を通じて、私たちは直接には観察できない過去の事象に関する仮説を、はじめて経験的にテストすることができます。歴史(進化)に関するアブダクションは、比較法によって実行可能になるということです」(106頁)という叙述は、そうした解釈も可能であることを示唆しているようにも読める。
もし著者が科学的説明の実用論を採っているならば、現象を説明する系統樹(181頁)は、あくまでプラグマティックなものであり、経験的に十全であればよいということになる。
反対に、実在論を採っているならば、系統樹は真なる原因の系列を表しているものとなるのかもしれない。
著者がアブダクションによって明らかにしようとしているものはいったい何なのだろうか。
まだまだ疑問はあるのだが、私が最も大きな疑問を感じたのは上記の二点であった。
しかし、このような疑問が浮かんでくるのは本書を損なうものではない。
私が挙げた疑問はどちらも哲学における伝統的な難問と繋がっている。
そのような疑問を喚起させるほどの射程を持つからこそ、本書の価値はあるのである。
当たり障りのない主張に何の意味があろう。
最後に「一般化された系統学」の持つ射程について考えてみたい。
著者の意図はわからないのだが、本書では系統樹の描く世界の基礎的存在者が何かということについては触れられていない。
生物進化学/生物学の哲学において淘汰単位論争として表出するこの問題が触れられていないのは興味深い。
もしかしたら、それが系統樹思考のミソなのかもしれない。
「万物は系統樹とともにあり、それなしには何ものもありえない」という本書の扉の言葉が意味するのは、次のようなことだと考えられるからだ。
それは、クワインの有名なテーゼ「存在するとは、束縛変項の値となることである」をもじって、こう言ってよい。
すなわち、「系統を持つとは、系統樹の端点となることである」と。
何を端点とするかは、クワインのテーゼと同じく、われわれの系統学的コミットメントにかかっているのである。
【参照図書】
「個体発生と系統発生 - 進化の観念史と発生学の最前線」スティーヴン・ジェー・グールド(著)仁木帝都(訳)

「植物の神秘生活―緑の賢者たちの新しい博物誌」ピーター・トムプキンズ/クリストファー・バード (著)新井昭広(訳)

「生命の跳躍―進化の10大発明」レーン,ニック(著)斉藤隆央(訳)

「アフォーダンスー新しい認知の理論」(岩波科学ライブラリー)佐々木正人(著)

「心はすべて数学である」津田一郎(著)

「数学の認知科学」レイコフ,G./ヌーニェス,R.E.(著)植野義明/重光由加(訳)

「数学は最善世界の夢を見るか?―最小作用の原理から最適化理論へ」エクランド,イーヴァル(著)南條郁子(訳)

「数学はなぜ哲学の問題になるのか」ハッキング,イアン(著)金子洋之/大西琢朗(訳)

「インフォメーション―情報技術の人類史」グリック,ジェイムズ(著)楡井浩一(訳)

「数量化革命―ヨーロッパ覇権をもたらした世界観の誕生」クロスビー,アルフレッド・W.(著)小沢千重子(訳)

「物事のなぜ―原因を探る道に正解はあるか」ラビンズ,ピーター(著)依田光江(訳)

「「無知」の技法 Not Knowing―不確実な世界を生き抜くための思考変革」デスーザ,スティーブン/レナー,ダイアナ(著)上原裕美子(訳)

「知ってるつもり―無知の科学」(ハヤカワ文庫NF)スローマン,スティーブン/ファーンバック,フィリップ(著)土方奈美(訳)

「世界はシステムで動く―いま起きていることの本質をつかむ考え方」メドウズ,ドネラ・H.(著)枝廣淳子(訳)

「テクニウム - テクノロジーはどこへ向かうのか?」ケヴィン・ケリー(著)服部桂(訳)

「思考の技法―直観ポンプと77の思考術」デネット,ダニエル・C.(著)阿部文彦/木島泰三(訳)

「100の思考実験―あなたはどこまで考えられるか」バジーニ,ジュリアン(著)向井和美(訳)

「行為の代数学―スペンサー=ブラウンから社会システム論へ (増補新版)」大沢真幸(著)

「存在の大いなる連鎖」(ちくま学芸文庫)ラヴジョイ,アーサー・O.(著)内藤健二(訳)

「現代思想2022年1月号 特集=現代思想の新潮流 未邦訳ブックガイド30」石井美保/國分功一郎/新田啓子/朴沙羅/山内志朗(著)

「現代思想2022年8月号 特集=哲学のつくり方——もう一つの哲学入門」千葉雅也/山口尚/入不二基義/山内志朗/森岡正博 (著)

「現代思想2020年6月号 特集=汎心論――21世紀の心の哲学」デイヴィッド・J.チャーマーズ/永井均/飯盛元章/髙村夏輝/鈴木貴之/平井靖史(著)
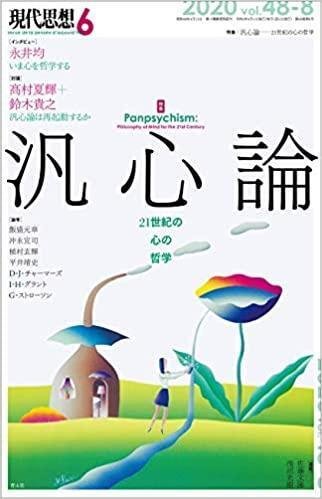
[ 発見(気づき) ]
「系統樹思考(tree-thinking=樹思考)と分類思考(group-thinking=群思考)という対比を、ここで考えてみましょう。
前者は対象物の間の系譜関係に基づく体系化を意味し、後者は同じ対象物を離散カテゴリー化によって体系化することを指しています。
たとえ対象が同じであっても、系統樹思考と分類思考では問題の立て方そのものが根本的に異なっています。
分類思考は眼前にある対象物そのもののカテゴリー化(すなわち分類群の階層構造化)を目標とするのに対し、系統樹思考は対象物をデータ源としてその背後にある過去の事象(分岐順序や祖先状態)に関する推論を行うからです。」
人間は、先天的には、分類思考をするという。
私たちは、何かを見たら似ていると認知して、あるカテゴリーへと分類する。
世界には、ばらばら(離散的)の群れがあると自然に考える。
これに対して、文化的に獲得する系統樹思考は、モノの歴史を推定して、カテゴリーを決めている。
著者が専門とする生物の進化の系統は、その考え方の代表例だし、祖先との関係を可視化する系図もそうである。
歴史を持つ対象を系統樹に位置づけるには、通常科学の推論方法である演繹と帰納だけでは間に合わない。
サルがヒトに進化する様子は、観察では確認できないし、ヒトに残るサルの痕跡を集めても、サルが直接のヒトの祖先だとは確定できない。
だから、「理論の「真偽」を問うのではなく、観察データのもとでどの理論が「よりよい説明」を与えてくれるかを相互比較する」アブダクションが系統樹思考では重要な役割を占める。
サルがヒトに進化したという説明が、他の説明と比べてもっともらしいと考えられるから、そのような系統樹を描いたのだ。
ツリー構造は、IT技術でもたとえばXMLで使われており、おなじみの構造である。
ある応用的な要素が、ある基本的な要素の子要素であるという形になっている。
構造自体は、疑いようがないけれど、親と子の要素の意味を考えてみると、この本が論じている系統樹思考があるのだと気がつく。
果物という要素の下に、リンゴがあったりする。
なんでそうなんだと考えていくと、リンゴは果物であるという説明が、野菜や肉だというより、もっともらしいからである。
生物学の進化論、言語学、世界中の神話や宗教など系統樹思考が文化文明の中に普遍的に現れる様をこの本は紹介している。
なぜ普遍的な思考になったのか、諸要因とともにこんな説明がある。
「分類思考が静的かつ離散的な群を世界の中に認知しようとするのは、私たちが多様な対象物を自然界や人間界に見るとき、記憶の節約と知識の整理にとってたいへん有効な手法であると考えられます。
そのような認知カテゴリー化は、記憶の効率化を通じて、私たちの祖先たちの生存にきっと有利に作用したでしょう。」
なるほど、私たちの世界認識の在り方は、記憶メカニズムに最適化されているのかもしれない。
そうであるなら科学の進歩は、世界についての知識量を増やすのではなくて、一番簡単な説明方法を探す旅だといえそうだ。
悟りの境地に至るというのもそういうことかもしれない。
日頃慣れ親しんでいるツリー構造の考え方を、改めて哲学的に考えてみる有意義な機会になった本である。
また、ギリシャ時代以来の「存在の学」としての形而上学が、人間の精神に深く染み込んだ「分類思考」(離散的な群の実在の標榜とその背後にある本質主義)に根ざしていたこと。
西欧普遍論争においては、カテゴリーとしての群が変化する(進化する)という選択枝はなかったこと。
今日、「種は実在するのか?」という、ことばの正しい意味での形而上学的な問題が繰り返し論じられていること。
◎「分類思考が静的かつ離散的な群を世界の中に認知しようとするのは、私たちが多様な対象物を自然界や人間界に見るとき、記憶の節約と知識の整理にとってたいへん有効な手法であると考えられます。
そのような認知カテゴリー化は、記憶の効率化を通じて、私たちの祖先たちの生存にきっと有効に作用したでしょう。」
◎「進化する実体、伝承される系譜、そして変化する系統が、存在論的にどのように意味づけできるのかという問題設定は、新しい形而上学を求めています。
進化的思潮が登場する以前の旧来の形而上学を補足するかたちで、進化的な形而上学を構築するのは十分に可能なことでしょう。」
◎「種問題をめぐる論争の錯綜ぶりを見るにつけ、「肉体化」した形而上学が科学者の意識に及ぼす深い影響を考えないわけにはいきません。」
◎「「種」の実在性を支持する心情とはいったい何か──それは時間的に変化する“もの”が、なお同一性(identity)を保持し続けるだろうという、本質主義の再来です。」
◎「無意識のうちに時空軸を貫く群の同一性を希求する思考は、ジョージ・レイコフがいう「心理的本質主義」の発現といえるでしょう。
たとえ、進化的思考がリクツの上で本質主義は間違いである(「種は実在しない」と主張したとしても、肉体化された心理的本質主義はその逆(「種は実在する」)を心情的に支持しているからです。」
◎「私たちは、生物としての人間であり、進化の過程でさまざまな肉体的特性と心理的特性を獲得してきました。
ですから、心理的本質主義者としてのヒトと進化的思考者としてのヒトとは、表層的には矛盾するのですが、深層的には各自がそれぞれ折り合いをつけていくしかないのだろうと私は思います。」
この最後の引用文で著者が示唆しているのは、とても大切なことだと思う。
私なりの言葉で言えば、「世界は系統樹思考(進化的思考)に基づく推論を行っている」ということになる。
世界は一冊の書物である。
この書物はある図形言語で書かれている。
その言語の名を系統樹という。
世界は系統樹思考をもって推論(アブダクション)をする。
推論の結果、世界は生成進化する「もの」と「こと」で満ち溢れる。
その「もの」や「こと」のうちに系統樹は入れ子式に挿入されているが、その「こと」を知る「もの」はいない。
あるとき、世界のなかの一存在者であるヒトの脳髄のうちに世界が折り重なり、歴史が復元される。
そのとき、世界は自らを知る。
わたしは今すべてを忘れようとする、わたしの中心に、わたしの代数学、わたしの鍵、わたしの鏡に達するのだ。わたしは誰か、今それを知るだろう。──ホルヘ・ルイス・ボルヘス「闇を讃えて」から(斎藤幸男訳)
また、この世界は「分岐」だけではなく、「分岐と融合」からなる高次の構造をもつ。
系統樹すなわち分岐による階層構造のツリーから、分岐と融合による非階層的な系統ネットワークへ、さらには「系統スーパーネットワーク」へ。
この第4章の最終節における「高次系統樹」をめぐる議論は、人間の「思議」を超えた世界の実相へと迫っていく(‘tree-thinking’ではなく‘network-thinking’に基づく推論世界?)。
そこにおいて、局所は全域と一致し、未来と過去が連続する。
中世の聖書写字生は「文字どおりに書き取るべし」という心理的プレッシャーのもとにあった(236頁)。
それは、実は聖なる章句の文字どおりの伝承(過去から未来へ)のためではなく、むしろ避けがたい「異本化」を通じて、来るべき啓示の「復元」(未来から過去へ)をめざすための戒律だったのかもしれない。
また、著者は「ネットワーク」の例として、ウィトゲンシュタインの「原稿の系譜」挙げている(238頁、240頁)。
「ゲノム的不連続構造」(鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこう考えた』15頁)をもつウィトゲンシュタインのテキストは、世界の実相、というより世界の論理を象っていたのかもしれない。
パースは『連続性の哲学』(伊藤邦武編訳,岩波文庫)で書いている。
「連続性の哲学」(岩波文庫)パース(著)伊藤邦武(訳)

《したがって、われわれの仮説は次のようになる。
時間とは、論理そのものが客観的な直観にたいしてそれ自身の姿を現す形式のことであると。
そして、現在という時点が非連続性をもつということの意味は、まさにその時点において、第一者からは論理的に派生できない、新しい前提が導入されるということである。》(170頁)
《ところで、われわれが何かを理解しようと試みるとき──何かを探求しようとするとき、そこには必ず、探求の対象自体が、われわれが使用する論理と多少の相違はあっても、基本的には同一の論理に従っているという想定が前提されている。
少なくともわれわれは、そのようになっていてほしいという希望をもっている。
本当のところ宇宙の論理は、われわれ人間が主観的に採用している論理よりも未熟で、その萌芽的な形態に過ぎないという可能性もある。
このような想定もたしかに、文明のある段階においては吟味に値する重要な想定である。
(略)
この想定に賛成したり反対する理由がどれだけ思い浮かぶにしても、現代において試してみるべき想定は、むしろ逆に、宇宙の論理とは、われわれがすでに獲得している論理ではなく、これからその高みへと至ることを鼓舞されるようなより高次なものだ、という想定のほうである。》(254頁)
また、生物の分類について、「類似度のみを用いよという表形学派、系統関係のみを用いよという分岐学派、そして系統関係と類似度の情報を併用すべきだという進化分類学派。(148頁)」と書かれていた。
分岐学派とは、少し前に読んだ 【ドーキンスvs.グールド 適応へのサバイバルゲーム キム・ステルレルニー著 ちくま学芸文庫】で彼ら(分岐分類学者)は、
「ドーキンスvs.グールド」(ちくま学芸文庫)ステルレルニー,キム(著)狩野秀之(訳)

類似性を客観的に測定できるとは考えない。(126頁)
われわれが下す類似と相違の判断は、人間の知覚および関心という偏向が反映されたもので、世界の客観的特性とはいえない。人間は視覚的生物である。(126頁)
仮に知覚力を備えたデンキウナギがいて、われわれと同じ情報を与えられていれば、われわれと同じように生物の系譜図―どれとどれが近縁か―を再構築できるはずである。
系統関係は、(中略)歴史の客観的事実であるからだ。
だが、デンキウナギは、異質性について人間と同じ判断を下すだろうか?(127-128頁)と、グールドの言う異質性に反論した分岐分類学ではないか。
[ 教訓 ]
系統樹思考とは、「由来関係」「系譜」の体系的理解ということ。
生物の進化も当然含まれますが、著者は生物ばかりではなく、フォントや言語、民俗、蕎麦屋にも系譜があることを示している。
このような由来関係を扱う学問を歴史研究としてとらえている。
そういう意味で、進化学も歴史の学問ということになる。
そのような歴史学は科学なのかということが第1章で取り上げられている。
当然のことながら、再現可能性等々の問題があり、実験科学と同じ基準は満たさないが、「歴史学には歴史学なりの「科学の基準」がある(55頁)」ということで、「理論の「真偽」を問うのではなく、観察データのもとでどの理論が「よりよい説明」を与えてくれるのかを相互比較する―アブダクション、すなわちデータによる対立理論の相対的ランキングは、幅広い科学の領域(歴史科学も含まれる)における理論選択の経験的基準として用いることが出来そうです。(65頁)」と書かれている。
アブダクションについては、第3章で詳しく書かれている。
アブダクションという推論形式については人工知能研究で詳しく研究されたということで、ジョセフソン夫妻による推論様式の定式化が紹介されているとアブダクションによる仮説判定の条件が紹介されている。
推論様式
前提1 データDがある。
前提2 ある仮説HはデータDを説明できる。
前提3 H以外の全ての対立仮説H'はHほどうまくDを説明できない。
結論 したがって、仮説Hを受け入れる。(178頁)
注意しないといけないのであるが、アブダクションで仮説Hが受け入れられたからといって、論理形式上では仮説Hが論理的に真というわけではない。
「HならばD、D、ゆえにH」は正しい推論形式ではないわけである。
しかしながら、ジョセフソン夫妻はアブダクションによりある仮説がベスト(真実ではありません)と判断される条件を示しているとのことで、それが紹介されている。
アブダクションによりある仮説がベストであると判定されるための諸条件(1994年の書物からのようである。)
(1)仮説Hが対立仮説H'よりも決定的にすぐれていること。
(2)仮説Hそれ自身が十分に妥当であること。
(3)データDが信頼できること。
(4)可能な対立仮説H'の集合を網羅的に比較検討していること。
(5)仮説Hが正しかったときの利得とまちがったときの損失を勘案すること。
(6)そもそも特定の仮説を選び出す必要性があるかどうかを検討すること。(179頁)
このように、ジョセフソン夫妻の言うように細かく条件をつければ、仮説間の優劣を決めるのには用いることは出来るであろう。
特に、(5)が大変実用的だと思った。
仮設Hの真偽は、アブダクションでは問えないわけであるから、万が一間違いが合った場合の損失を考えるということは、日常生活でも大変重要である。
大事なものが壊されていたとき、ネコがやったと考えて怒っても、間違えたって大した問題は生じないが、誰かのせいにするのは万が一間違った場合、大変な問題になる。
誰かのせいだという仮説を受け入れるには、相当の証拠・データがないとできない。
冗談はさておき、アブダクションでは仮説の真偽は保証されないから、著者も書いているが、「アブダクションはその出発点からして仮説の「真偽」に頼るわけにはいきません。それとは別の次元で、データに照らした仮説の「良否」を判定しなければならないということです。(180頁)」真偽ではなく、良否。
このようにアブダクションを理論選択の基準とするという考えでは、「科学理論はデータを説明する良い仮説の集合であり、仮説が述べていることが真実だったり実在したりするということには言及はできない」という立場に通じる気がする。
反実在論といえるではないだろうか。
そのような立場なのだろうと読めるような記述がある。
「「種は実在する」という言明がいかなる意味で発せられているのかは、注意深く論じる必要があります。
それは必ずしも、データに基づく経験的言明として提示されているとはかぎりません。
むしろ、分類学者の信念ないし願望がそこにある可能性も否定できないのです。」(259頁)
生物進化を系統樹として表して、種をどのように定義するか、ということは本書では触れられていないので、「種」というものの実在についてどのように著者が考えているのかはわからないのであるが、この記述を読む限りでは、ある意味では「種」は実在しないと主張されてもおかしくない雰囲気だと、私は思った。
著者は、「モノ」に対する関心が違っており、「私は、大学院にいた頃から一貫して、生物進化や系統発生に関わる概念的・理論的な問題に関心を向けてきました。
具体的な「モノ」に対してより強い関心を向ける生物系研究者の多い日本の学界の中では、その意味で、きわめて少数派に属していることを実感してきました。(188頁)」と書いており、「モノ」よりも概念等に関心があったようである。
「モノ」に対しての関心の差を比べると、分子生物学を専門とする学者と進化論を専門とする学者では、科学哲学に対する考えが、特に対象の実在の問題に関しては違いがあるのではないだろうか、と思う。
分子生物学者からすると、対象が実在しないものなんて科学の名に値しないというんじゃないだろうか、と勝手に推測している。
また、人は、系統樹が好きで、何でもそれで表すと安心する。
書体、系譜、系図、書写本、学問、言語などである。
系統樹(対象物間の系譜関係に基づく体系化)と分類(対象物そのもののカテゴリー化)は、異なるものであるが、人は心理的背景として分類思考を持っているが、系統樹思考には、それがない。
従来の典型科学が、持つべき性質は、観察可能、実験可能、反復可能、予測可能、一般化可能であるが、歴史学などはこれを持たない。
タイプ(ある性質を持つ集合としての型)とトークン(あるタイプに属するメンバー)という考え方があり、典型科学はタイプについて語り、歴史や進化はトークンについて語ってきた。
科学の推論法は、帰納と演繹であるが、それと別のアブダクションという方法を取れば、別の意味の科学が成立する。
アブダクションの推論形式は、ジョセフソン夫妻によれば、データ Dがある、仮説HはDを説明できる、H以外の対立仮説はHほどうまく説明できない、したがってHを受け入れるというものである。
そうして、ベストであると判定するためには、Hが決定的にすぐれている、H自身が妥当である、Dが信頼できる、対立仮説を網羅的に検討している、Hが正しいときと間違えているときの損得を考えること、特定の仮説を選ぶ必要があるか検討することという条件を満たさなければならない。
これは、AI研究から影響を受けている。
系統樹思考は、これに良くあっている。
ヒューウェルの古因学という過去の事象に関する因果法則を探すという学問があり、系統樹の探索に参考になる。
最適の系統推定の方法は次のとおりである。
最節約基準、最小進化基準、最尤基準、ベイズ事後確率基準などの最適化基準を設定する。
あらゆる可能な系統樹の中で最適化基準化から見てベストのものを選ぶ。
系統樹とは、すべての点を結ぶループを持たないグラフであり、無根系統樹と有根系統樹がある。
端点とは、1本の枝だけがつながっている点で、実際に観察されるものである。
内点とは2本以上の枝がつながっており、仮想的な点である。
無根系統樹で、根を指定すれば、有根系統樹になる。
系統樹はこの意味で、祖先子孫関係ではない。
生物の場合には、対象とする生物の他に、外群という遠縁の生物を含めて考える。
外群を除いた点の数をnとすれば、2n-3の枝があり、もう1つ点を加えるには、枝のどれかにつけることになるので、系統樹の数は、B(n)=B(n-1)*(2n-3)種類となる。
これは、n=50で75桁の数となり、np完全問題で解くのは実際上不可能である。
そこで、発見的探索によることになる。
最近は、ネットワーク、系統ジャングル、スーパーツリーという考え方も出てきている。
高次元ネットワークは、早田文蔵によって1900年代の初期に言われていた。
[ 一言 ]
本書は、博物学(natural history)を科学(science)として「復権」する試みであると同時に、今まで科学の俎上にのらなかったものを科学するメタ科学の本あり、そしてその手法として「系統樹思考」を紹介した本でもある。
メタネタがぎっしりつまった本であり、実に楽しい一冊なのだが、強いて難点を言うと読みやすさは今イチ。
また、以前流行の、2時間でぱっと読み終わる新書ではない。
「古い」タイプのオーセンティックな知識の書としての新書の風格を保ちつつ、書いてあることは野心的でアジテーションですらある。
でも、威風堂々。
優れた科学の新書には、全ページを貫くキーコンセプトが存在していている。
「ゾウの時間、ネズミの時間」ならアロメトリー式、「渋滞学」ならASEPといった具合に。
本書のそれは、「系統樹思考」そのものよりもむしろ「系統樹思考」を可能とする考えかたである「アブダクション」(abduction)だ。
これは、「演繹」(deduction)、「帰納」(induction)に加わる第三の推論法でもある。
いや、この二つの前段階として行われるので、「ゼロ番目」と言った方がよいか。
本書の志の高さ、視野の広さ、アブダクションや系統樹思考といった思考ツールの紹介といった美点についてはすでに他の書評等で言い尽くされているのでここで繰り返すことはしない。
以下ではもっぱら、本書を読んでいて気になった部分を列挙していく。
「系統樹思考は私たちの理解を支援してくれる」(26頁)というのが本書全体を貫くひとつの主張であると思われる。
しかし、系統樹思考にどこまでが含まれるのかがはっきりしない。
87~92頁のあたりでは、「図形言語としての鎖や樹」を階層的分類のツールとしてとらえているが、これは系統樹思考(tree thinking)の一種なのか、といった疑問が生じる。
表紙裏のセフィロトの樹の解説では「図形言語としての樹」と「系統樹思考」は別物だと述べているが、本文にはそれに類するはっきりした説明がない。
分類思考、図形言語としての樹、系統樹思考の関係とそれぞれの利点、欠点を整理してまとめてほしいところである。
86頁あたりから以降しばらくは学問分類の歴史を紹介しつつ図形言語としての「樹」の利点を説明するというのがひとつの眼目だと思う。
つまり、「樹」を使う思考に対する著者の態度は肯定的であると思われる。
しかし、「文系」対「理系」という区別こそ(「文系」という枝に属するものと「理系」という枝に属するものがふたたび交わり合ったりしないという含意を含む点で)まさに「樹」のイメージで学問分類を捉えた結果ではないか。
領域の横断や新しい視点からの統合を可能にするのはむしろ「ネットワーク」のイメージではないか。
それとも、やっぱり図形言語としての「樹」については分類思考の一部で否定的な評価をされているということか?
系統樹思考とは「系譜関係に基づく体系化」(121頁)と定義されているが、系譜関係とは何か、どこまでが含まれるのか。
「無根系統樹」(169頁)を使う思考や「分岐図」(229頁) を使う思考でも「系譜関係に基づく」と言ってよいのか。
そのあたりの用語の整理もほしかったところである。
[ 結論 ]
三中氏は「典型科学」と歴史科学を方法論的に対比するというやり方で系統樹思考の重要性を述べていく。
歴史科学の哲学について述べた日本語の文献はほとんどないので、三中氏のこのあたりの記述は非常に貴重である。
しかし、分かりやすさを追及するためか、これについての三中氏の記述はカリカチュア化された二分法のイメージを読者に与えかねない。
まず、「典型科学」の五つの条件(38頁)はどこから持ってきたものだろうか?
三中氏がおもいついたものを列挙したものだろうか?
少なくとも科学哲学で科学の定義をするときに「実験可能性」を挙げることはまずない。
観察科学と呼ばれる分野があることはふつうは前提となっている。
また、このように定義した典型科学対歴史学という対比(39頁)では科学というものの全体像が見えにくくなっているのではないだろうか。
歴史学的でない非「典型科学」もいろいろある。
たとえば分子生物学ですら宇宙で普遍的に成り立つ法則性をあつかっているわけではないので、一般法則化という条件をみたさない。
それと関連して、歴史科学の方法論の特異性についての三中氏の記述にも疑問が残る。
三中氏は科学的方法の複数性を主張している(44頁)が、ここで行っている作業は実際には多くの科学に共通する、より基本的な方法にさかのぼって「典型科学」と歴史科学のそれぞれの分野の方法を正当化しているだけではないだろうか。
複数化でもないところで複数性という言葉を使うのは相対主義といういらぬ批判をまねく。
複数性の具体的内容としては、歴史学や進化学の対象である個物には演繹や帰納という論証スタイルは当てはまらないのでデータと理論の「もっと弱い関係」としてアブダクションが必要になる、という趣旨のことを述べている(64~65頁)。
しかし、すでに「典型科学」でも広く用いられている仮説演繹法はどうなのか。
歴史科学の特異性を強調しようとするあまり「典型科学」を戯画化しすぎてはいないか。
おそらくこれと関連して、ルウォンティンが「ソフトな推論」を認めず、進化生物学や行動遺伝学の普通の方法論まで否定した、という趣旨の記述がある(128頁)が、自分自身も進化生物学者であるルウォンティンが自らの研究の科学性を否定するとは考えにくい。
私の理解では社会生物学に対する彼の批判点は進化生物学の方法論的基準からいっても社会生物学があまりに「ソフト」すぎるということだったのではないか。
また、「歴史や進化を論じる科学は「トークン」に関する考察をしていると言ってかまわない」(p.75)というのは勇み足だと思う。
ある出来事に至る因果の流れをモデル的に記述した時点(たとえばフランス革命にいたる諸要因を図式的に示した時点や、恐竜の絶滅に小惑星衝突というモデルを示した時点)で、すでに哲学的な意味ではトークンではなくタイプの話になっている。
「普遍法則を作る」こととあくまでトークンのレベルにとどまることの間にはさまざまなレベルの一般化があり、モデル化の際には低いレベルのローカルな一般化は少なくとも行っているはずである。
アブダクションとの対比で本書の中によく出てくるのが、「典型科学」の方法論としての「帰納」である。
これについての三中氏の記述にも少し疑問がある。
論理学でいうところの帰納(枚挙的帰納)と、20世紀なかばの科学哲学で問題になっていた帰納的推論は指示する範囲が違うので注意が必要であるが、三中さんはその区別をあまり意識していないように見える。
たとえば「論証スタイルとしての帰納」(59頁)という言い方は枚挙的帰納を念頭においているように見えるが、科学の方法論が枚挙的帰納だなどと思っている人は論理実証主義にはいなかったはずである(枚挙的帰納しか使わないのなら道具主義も出る幕がない)。
仮説演繹法を使って仮説の確からしさを評価するのも帰納的推論の一種とされるが、これはデータからの普遍法則の発見という枚挙の方法とは異なる。
科学哲学で問題となってきたのは、ampliative(情報増加的)な推論の中に妥当とみとめてよいものがあるかどうかということ。
ちなみに、ポパーはampliativeな推論全般に反対していたので、当然あとで三中氏が支持するアブダクションにも反対だった。
帰納の問題で論理実証主義が敗退したのはしかたがないというなら、ましてやアブダクションも敗退してしかたないということになるはず。
ついでにいえば論理実証主義が時代遅れになったのが帰納的推論の妥当性を示せなかったからだというのはかなりポパーやクーンとの論争にかたよった見方で、それ以外の要素(科学史の無視、理論語と観察語の区別、中立的観察文の呈示、極端な道具主義、科学理論についての文パラダイムなど)での失敗が総合的に論理実証主義の力を奪ったとみるべき。
ヒューウェルが科学哲学史上重要な科学哲学者であることはまちがいないが、本書における評価はちょっとポイントがずれているように思われる。
まず、「科学それ自体についての学」としての科学哲学の「祖」(50頁)という評価はどうか。
科学それ自体についての考察はそれ以前から存在していた。
ある程度の人数があつまって科学の方法論などについて論じ合う分野としての科学哲学の成立はたしかにヒューウェルらの時代に求められることが多い。
しかし、そのグループにおいても本の出版でいえばハーシェルのPreliminary Discourseの方が時期的には早く、ヒューウェルを「祖」と呼ぶのはむずかしい。
one of founding fathers くらいか。
ついでにいえば、intellectual lineageとしては現在の科学哲学はウィーン学団を直接の祖先としていて、ヒューウェルとの知的系統関係はうすい。
ただし、ポパーの師である心理学者ビューラーが属するビュルツブルグ学派がヒューウェルの影響を受けていたことが間接的にポパーにも影響しているのではないか、と示唆する論者もある。
その意味でも「祖」とはよびにくい。
さらに問題なのは、「イギリス経験主義を代表する思想家」という98頁の評価である。
ヒューウェルは同時代のハーシェルやミルといったベーコン流経験主義者たちを相手に、概念による事実の統合という非経験的な要素の重要性を主張した。
したがってむしろ反経験主義者という評価の方がふつうではないか。
もうひとつ、歴史的科学を統合するヒューウェルの古因学について、「現在の私たちの観点から見ても、ヒューウェルの主張は驚くほど柔軟な視点ではないでしょうか」(103頁)と言うが、むしろ現在から見ているからこそ柔軟に見えるのではないか。
というのは、ほんの数十年前までは世界の歴史が6000年で、最初の一週間を除いてはずっと人間が存在してきたというのをほとんどだれも疑わなかった、という時代背景からは、むしろ地質学と考古学と歴史学が同一扱いされるのは自然であろう。
「分野横断的に学問世界の切り直しをした」(p.104) というのは、ヒューウェル以前の学問世界についての誤解に基づく可能性があるのではないか。
三中氏が科学哲学の現況として呈示するものは、なぜか意図的に数十年前のものとなっているように思われる。
もちろん日本の科学哲学は英米とくらべるとそれくらい遅れているので、日本の科学哲学の記述としてはそれでよいのかもしれないが。
たとえば「これからは学問分野ごとの科学哲学ができあがってくるでしょう」(53頁)とあるが、三中氏も当然知っているとおり、生物学の哲学は独立の分野として30年程度は歴史がある。
何をもって独立の分野とみなすかという問題はあるが、種の定義や選択の単位といった生物学固有の論争に科学哲学者がくびをつっこむようになったというのをひとつの区切れとしてもよいか。
三中氏の歴史意識のなかでは70年代は「最近」なのだろうが、読者はそうはうけとらないだろう。
また「歴史学が科学でありうるか」ということが科学哲学で問題となってきたのは科学哲学が未熟だった証だという(129頁)が、進化学と人間の歴史を扱う歴史学では事情が違う。
進化学や古生物学が科学でありうるということはめったに問題になってこなかった。
歴史学については、単に繰り返しがきかないというだけでなく、歴史上の人々の意識についての理解や了解が求められるというウェーバー以来の論点が複合的にきいているのではないか。
「物語的説明」(69頁)が結局どういう説明なのかがよくわからない。
「過去の出来事を説明するひとつのスタイル」(68頁)というあいまいな特徴を与えられるだけでは、何をもって物語とし、何が物語でないのかの基準が分からない。
74頁の表現ではトークンを使った説明はすべて物語的説明ということになりそうだが、そんなに「物語的」という言葉を拡張しては、トリビアルになんでも物語的説明になってしまい、むしろ歴史科学に特有の説明スタイルだったはずのこの概念のいいところが失われてしまう。
[ コメント ]
私の理解では、法則のinstantiationでなく、しかも理解可能な原因結果関係で結ばれた出来事の連鎖が「物語」なのでは?
普遍論争が「そのまま」生物の種に関する近年の論争に持ち越されている(75頁)というのは不正確では?
唯名論者は、今の論争で「種は個体だ」という議論があるのと同じような意味で「赤さは個体だ」などと言ってはいなかったはず。
かれらの関心の対象となる個体は、「赤さ」ではなく「赤さを持つとされる個々の対象」の方だったのではないだろうか。
