
【書きたいテーマを探してみよう(読書編)】ノンフィクションが好き
■発見(気づき)
なんのために「本」を読むのか。
その切り口のひとつが、人文書は、あらゆる本は、特効薬たりえないのだということ。
そのことを十分理解したうえで。
なお、少しでも凝り固まった自分の視点を変えるきっかけになればと、ノンフィクション本を読んでいる。
この試みが、エゴだとしても、引きつづき、がんばるしかない。
しつこくやるしかない。
視点を変えて、
「ここではない世界」
を作る。
それが、フィクションの世界の面白さなのではないだろうか。
じっくりと時間をかけて。
言葉を練ることの面白さ。
それが、そこには、確かにあると、そう感じる。
それでは、ノンフィクションの面白さとは何か?と問えば。
物事を解き解すのが、ノンフィクションの醍醐味であると、そう感じられる。
そう感じるのは、フィクションが徹底構築。
つまり、
・世界をこしらえ
・そこに棲む存在をこしらえ
・その存在がなにに刺激を受け
・如何に反応をするか
を、どう拵えるのかに注力しているのに対して、現実の世界の曖昧模糊とした状況に、どう向きあい、その世界の再現の精度を、如何に高められるかを問い深めながら、世界を再構築する点にあるのではないかと考えるからである。
でも、その構築過程は、虚構の世界に向きあう作家の筆と、さほど変わらないのではないかと。
すごいノンフィクション。
それは。
一冊で、自分の常識を、一変させる。
目から鱗を、削ぎ落し。
世界の解像度を、上げる。
そして。
積み重ねた事実の上に立たせ。
偏見という壁の向こうを見せてくれる。
ノンフィクションには、そんな力がある。
■問題提起
ここで。
自身の常識をアップデートし。
偏見をとっぱらい。
世界をクッキリと見せてくれる。
「これはスゴい!」
と考える、ノンフィクションを、以下の記事を参考にしながら、選んでみた。
<参考記事>
『「ニセ医学」に騙されないために』NATROM(メタモル出版)
『「子供を殺してください」という親たち』押川剛(新潮文庫)
『100のモノが語る世界の歴史』ニール・マクレガー (筑摩選書)
『アフリカの日々』ディネーセン(河出書房新社)
『アポロ13』ジム・ラベル(新潮文庫)
『アメリカの奴隷制を生きる フレデリック・ダグラス自伝』フレデリック・ダグラス(彩流社)
『イメージ 視覚とメディア』ジョン・バージャー(ちくま文庫)
『イワン・デニーソヴィチの一日』ソルジェニーツィン(新潮文庫)
『インディアスの破壊についての簡潔な報告』ラス・カサス(岩波文庫)
『ヴァギナ』キャサリン・ブラックリッジ(河出書房新社)
『エンデの遺言「根源からお金を問うこと」』河邑厚徳(NHK出版)
『エンデュアランス号漂流』アルフレッド・ランシング(新潮文庫)
『オリエンタリズム』(エドワード・W・サイード、平凡社)
『オーパ!』開高健(集英社文庫)
『カラシニコフ』松本仁一(朝日文庫)
『がん‐4000年の歴史‐』シッダールタ・ムカジー(早川書房)
『ゲーデル、エッシャー、バッハ』ダグラス・R・ホフスタッター(白揚社)
『コンゴ・ジャーニー』レドモンド・オハンロン(新潮社)
『サイエンス・インポッシブル』ミチオ・カク(NHK出版)
『ゾウの時間 ネズミの時間』本川達雄(中公新書)
『チベット旅行記』川口慧海(白水uブックス)
『ちょっとピンボケ』ロバート・キャパ(文春文庫)
『デカルトからベイトソンへ』モリス・バーマン(文芸春秋)
『なぜエラーが医療事故を減らすのか』ローラン・ドゴース(NTT出版)
『なぜ私だけが苦しむのか』H.S.クシュナー(岩波書店)
『ナチスドイツと障害者「安楽死」計画』ヒュー・グレゴリー・ギャラファー(現代書館)
『パレスチナ』ジョー・サッコ(いそっぷ社)
『パワーズ・オブ・テン』フィリップ・モリソン(日経サイエンス)
『ヒトは病気とともに進化した』太田博樹、長谷川眞理子(勁草書房)
『ピュリツァー賞 受賞写真 全記録』ハル・ビュエル (ナショナル・ジオグラフィック)
『ファスト&スロー』ダニエル・カーネマン(早川書房)
『フォークの歯はなぜ四本になったか』ヘンリー・ペトロスキー(平凡社)
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』マックス・ヴェーバー(岩波文庫)
『マネーの進化史』ニーアル・ファーガソン(早川書房)
『レトリック感覚』佐藤信夫(講談社学術文庫)
『ロボット兵士の戦争』P・W・シンガー (NHK出版)
『隠喩としての病』スーザン・ソンタグ(みすず書房)
『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』米原万里(角川文庫)
『音楽の科学』フィリップ・ボール (日経サイエンス社)
『何でも見てやろう』小田実(講談社文庫)
『科学革命の構造』トマス・クーン(みすず書房)
『河童が覗いたインド』妹尾河童(新潮文庫)
『火の賜物―ヒトは料理で進化した』リチャード・ランガム(NTT出版)
『虚数の情緒』吉田武(東海大学出版会)
『凶悪―ある死刑囚の告発』「新潮45」編集部(新潮文庫)
『興亡の世界史 アレクサンドロスの征服と神話』森谷公俊(講談社学術文庫)
『金枝篇』フレイザー(ちくま文庫)
『金沢城のヒキガエル』奥野良之助(平凡社ライブラリー)
『系外惑星と太陽系』井田茂(岩波新書)
『現代の死に方』シェイマス・オウマハニー(国書刊行会)
『言志四録』佐藤一斎(講談社学術文庫)
『雇用・利子および貨幣の一般理論』ジョン・メイナード・ケインズ(岩波文庫)
『黒檀』リシャルト・カプシチンスキ(河出書房新社)
『思想のドラマトゥルギー』林 達夫、久野 収(平凡社)
『失われてゆく、我々の内なる細菌』マーティン・J・ブレイザー(みすず書房)
『銃・病原菌・鉄』ジャレド・ダイアモンド(草思社文庫)
『消された一家』豊田正義(新潮文庫)
『食品偽装の歴史』ビー・ウィルソン(白水社)
『深夜特急』沢木耕太郎(新潮文庫)
『人間の土地』アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ(新潮文庫)
『人間臨終図巻』山田風太郎(徳間文庫)
『人体 600万年史』ダニエル・E・リーバーマン(早川書房)
『垂直の記憶』山野井泰史 (ヤマケイ文庫)
『数学の想像力』加藤文元(筑摩選書)
『数学の認知科学』G.レイコフ、R.E.ヌーニェス(丸善出版)
『数量化革命』アルフレッド・クロスビー(紀伊国屋書店)
『世界システム論講義』川北稔(筑摩書房)
『世界屠畜紀行』内澤 旬子(角川文庫)
『世俗の思想家たち』ロバート・ハイルブローナー (ちくま学芸文庫)
『性食考』赤坂憲雄(岩波書店)
『生命の跳躍』ニック・レーン(みすず書房)
『千の顔をもつ英雄』ジョセフ・キャンベル(人文書院)
『戦艦大和ノ最期』吉田満(講談社文芸文庫)
『戦争の世界史 大図鑑』R・G・グラント(河出書房新社)
『戦争の世界史』ウィリアム・H・マクニール(中公文庫)
『戦争広告代理店』高木徹(講談社文庫)
『想像の共同体 : ナショナリズムの起源と流行』ベネディクト・アンダーソン(書籍工房早山)
『誰のためのデザイン?』ドナルド・ノーマン(新曜社)
『地球の食卓―世界24か国の家族のごは』ピーター・メンツェル (TOTO出版)
『中国臓器市場』城山英巳(新潮社)
『沈黙の春』レイチェル・カーソン(新潮文庫)
『転校生とブラックジャック』永井均(岩波書店)
『土と内臓』デイビッド・モントゴメリー(築地書館)
『土木と文明』合田良実(鹿島出版会)
『怒らないこと』アルボムッレ・スマナサーラ(サンガ)
『八月の砲声』バーバラ・タックマン (ちくま文庫)
『美術の物語』エルンスト・H・ゴンブリッチ(ファイドン)
『百年の愚行』池澤夏樹、フリーマン・ダイソン他(Think the Earth)
『不健康は悪なのか』ジョナサン・M・メツル(みすず書房)
『物乞う仏陀 』石井光太(文春文庫)
『補給戦―何が勝敗を決定するのか』マーチン・ファン クレフェルト(中公文庫BIBLIO)
『忘れられた日本人』宮本常一(岩波文庫)
『暴力と不平等の人類史』ウォルター・シャイデル(東洋経済新報社)
『夜と霧』ヴィクトール・E・フランクル(みすず書房)
『利己的な遺伝子』(リチャード・ドーキンス、紀伊国屋書店)
『旅をする木』星野道夫(文春文庫)
『料理の四面体』玉村豊男(中公文庫)
『冷血』トルーマン・カポーティ(新潮文庫)
『羆嵐』吉村昭(新潮文庫)
『服従の心理』スタンレー・ミルグラム(河出文庫)
■教訓
あなたには知りたいことがありますか?
人に伝えたいことがありますか?
会って話を聞いてみたい人はいますか?
記録に残しておきたい体験はありますか?
もし、すぐに思い浮かぶならば。
あなたは、とてもラッキーです。
それが、あなたのテーマだから。
「ノンフィクション」
といっても、
・ルポルタージュ
・サイエンス
・ジャーナリズム
・アカデミック
まで、その世界は、広大で豊穣です。
ガチの手記から写真レポート。
小説仕立てのノンフィクション・ノベルまで。
汲めども尽きない叡智の泉です。
それは、自分とは違う世界を生きる人の目線を知ることで、精神的な糧に出来ると考えられます。
■読書メモ
どんな一冊でも。
新しいページをめくった先に待っているのは、発見と感動。
それを吸収するたびに。
私という人間は、更新されていきます。
ここで、新書版ノンフィクションを5冊、紹介させて頂きます。
▶佐藤賢一「ダルタニャンの生涯 史実の『三銃士』」
「ダルタニャンの生涯 史実の『三銃士』」(岩波新書)佐藤賢一(著)
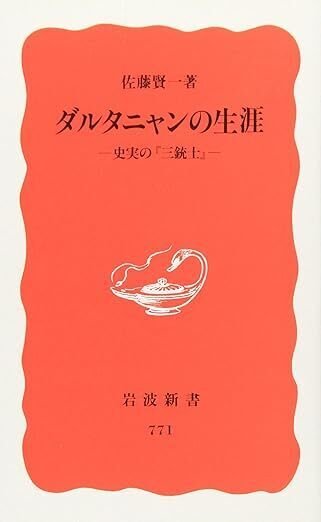
[ 内容 ]
上京、出仕した主人公がくぐった波瀾とは、現実の社会とは。
歴史の醍醐味を伝える著者初のノンフィクション。
[ 目次 ]
1 三銃士(デュマの銃士 クールティル・ドゥ・サンドラスの銃士 史実の銃士)
2 パリに出る(偽らざる素性 ガスコンの気風 なぜダルタニャンか)
3 出世街道(マザラン枢機卿 フロンドの乱 足場を固める フーケ事件 銃士隊 パトロンとして 栄達と苦悩 最後の戦争)
4 ダルタニャンの末裔(ダルタニャンの遺産 息子たち 歴史小説の主人公)
[ 問題提起 ]
ダルタニャンといえばデュマ『三銃士』。
ダルタニャンといえば、まさに歴史小説界の千両役者。
この本では、そんな人物を、これまた歴史小説家界の千両役者である佐藤さんが論じる。
しかも、佐藤さんによれば、デュマ『三銃士』には、クールティル・ドゥ・サンドランス『ダルタニャン士の覚え書』っていう種本があり、『覚え書』には、モデルがいた。
それがシャルル・ダルタニャン伯爵、ルイ一四世時代のフランスに実在した銃士隊長だ。
佐藤さんは、この三つのレベルを自由に行来しながら、実在したダルタニャンの生涯をたどった。
たしかに『三銃士』のダルタニャンには及ばないかもしれないけど、この伯爵もまた魅力的な人物であり、数奇な運命をたどった人物なのだ。
[ 結論 ]
この本を読んで、私は何よりもまず、佐藤さんの筆の運びの冴えに感心させられた。
「直木賞作家」(表紙見返し)って謳い文句はだてじゃない。
ダルタニャンの出身地である西南フランスは、ガスコーニュ地方の景観を描写することから始まり、貧しい戦乱の地だったこの地方が、地元出身のアンリ四世が即位して以来、多くの武人を輩出し、パリに一種のガスコン共同体を作り上げたことを語る。
リズムよくダルタニャンの生活を追い、武勇と誠実さを兼ね備えた彼が、マザラン枢機卿やルイ一四世に愛され、近衛歩兵隊長、銃士隊長、そして、北フランスは、リールの都市総督の地位に登りつめるまでをたどる。
その合い間に、彼が生きた一七世紀フランスの社会や、政治や、経済の解説を織り交ぜる。
ダルタニャンをはじめとする登場人物の造形も魅力的だし、生き生きとしてる。
さらに、佐藤さん初の「ノンフィクション」(表紙見返し)って謳い文句もだてじゃない。
佐藤さんは、詳しくはわからないけど、ダルタニャンの書簡や当時の出版物など、様々な資料を用いて、ダルタニャンの生涯に迫った。
多分、この本には、作家の創作は、ほとんどないんだろう。
そのうえで、佐藤さんは、
『三銃士』
と
『覚え書』
と、これら資料を付き合わせ、実在のダルタニャンが、どのように描かれ、造形されてくかを描き出した。
これまた興味深いアプローチだ。
最後の数頁で、佐藤さんは、実在のダルタニャンが魅力的だったのは一七世紀フランスに活躍したからであり、
「十七世紀フランスの魅力とは、実は公私の混在」
にあるって主張する。
つまり、現代は、
〈公〉
が
〈私〉
を圧倒する時代であり、私たちは、
「己の信念を貫く勇気」
が大切だってわかってるけど、実践できない。
これに対して、一七世紀フランスでは、〈私〉の気概、つまり、騎士道精神が〈公〉を圧倒した。
[ コメント ]
こんな、本音で生きられる時代に対する憧れが、ダルタニャンに対する拍手喝さいに結晶する。
これって、私には、ちょっと興ざめだった。
公私の混在と、〈私〉が〈公〉を圧倒することとの関係も、〈私〉が〈公〉を圧倒することと、騎士道精神が発揮されることとの関係も、説明がない。
己の信念を貫く勇気を発揮して、各地で地道に活動してる人々は、今でも沢山いるだろう。
歴史小説家が、現代社会を論じると、途端に話がつまらなくなってしまいがちなのは、本当に不思議だ。
▶佐野眞一「枢密院議長の日記」
「枢密院議長の日記」(講談社現代新書)佐野眞一(著)

[ 内容 ]
幕末に生まれ、明治、大正、昭和を生き、三代の天皇に仕えた倉富は、時代の変遷をどう見つめ、年月の足音をどう聞いて、記録にとどめたのか?
宮中某重大事件、皇族・華族のスキャンダル、摂政問題、白蓮騒動、身辺雑記…誰も読み通せなかった近代史の超一級史料をノンフィクションの鬼才が味わい尽くす。
[ 目次 ]
序章 誰も読み通せなかった日記
第1章 宮中某重大事件―怪文書をめぐる「噂の真相」
第2章 懊悩また懊悩―倉富勇三郎の修業時代
第3章 朝鮮王族の事件簿―黒衣が見た日韓併合裏面史
第4章 柳原白蓮騒動―皇族・華族のスキャンダル
第5章 日記中毒者の生活と意見―素顔の倉富勇三郎
第6章 有馬伯爵家の困った人びと―若殿様と三太夫
第7章 ロンドン海軍条約―枢密院議長の栄光と無念
終章 倉富、故郷に帰る
[ 問題提起 ]
大正時代に、枢密院議長をつとめた、倉富勇三郎という人物が書き残した日記についての「通読ドキュメント」である。
帯(裏表紙側)に、
「一読茫然」
とあるが、たしかに、読後、しばし、茫然たらざるを得ない。
人がものを書くということが、どういうことなのか、あらためて考え直した。
佐野眞一と「枢密会」(倉富日記の輪読会のために参集した数名のスタッフ)の面々は、2000年以来、6年間にわたって、倉富日記の一部(大正11年から12年、および大正期の重大事件周辺)を解読する作業に従事し、あわせて、日記本文をパソコン打ちのテキストファイルに打ち直した。
タイプされたテキストの量は、400字詰の原稿用紙で換算して、およそ5000枚にのぼるという。
普通の新書にして、約10~15冊分だ。
本書と同じ、辞書ライクな厚さの新書に直しても、5冊にはなる。
驚くべき、泥んこ仕事と申し上げねばならない。
が、その営々たる反復労働とて、ネタ元の書き手である倉富勇三郎、その人の作業量と比べれば、ほんの気まぐれに過ぎない。
倉富日記の分量は、おそらく世界一だ。
[ 結論 ]
手帳、大学ノート、便箋、半紙など297冊にペン書きにされた日記本文は、活字として、そのまま翻刻すれば、分厚な本にして、50冊はくだらないという。
一日あたりの文字量は、多いときには、原稿用紙50枚を超えたらしい。
本書は、基本的には、日記の内容を紹介する部分と、当該の日記本文が書かれた、当時の世相や、日記内の登場人物について解説する部分が、交互に登場するカタチで構成されている。
で、それらの合間に、佐野眞一の感想が挿入され、次の章に進む。
日記の文章そのものは、さして面白いものではない。
というよりも、佐野自身が、
「無味乾燥」
「死ぬほど退屈」
「益体もない」
「うんざりする」
と形容している通り、およそサービス精神のかけらもない役人の報告書の如きものである。
が、そのどこまでも、
「記録」
ということに専念しきった文体が、三越や白木屋での買い物の詳細や、職場でのやりとりを執拗に書き連ねる時、そこには、一種のユーモアの如きものが宿ることになる。
たとえば、耳鼻咽喉科での診療について記録したくだりは、以下の通り。
「午前八時より高成田の家に行き、耳及咽喉を療せしむ。
真鍮管を鼻腔に入れ、護謨(ゴム)管を以て風を送り、耳に通ぜしめんとす。
真鍮管の送入意の如くならず、遂に止め、只護謨管を以て外部より風を送り、鼓膜を震動せしむ」
ほとんど、癇性と言って良い記述の細かさである。
かように、倉富は、家庭内の些事であれ、政府の決定事項であれ、大臣や文化人との会話であれ、まったく差別なく、すべてを手抜きなく、昆虫の如き着実さで、執拗詳細に記述して行く。
まことに、驚くべき情熱である。
倉富の日記は、全体としては、
「日記中毒者」
による連綿たる独白以上のものでない。
が、枢密院という政権の中枢で、議長まで勤めた人間の手になる記述だけに、思わぬ場所に、第一級の歴史的証言がまぎれこんでいたりする。
たとえ、ば昭和3年10月20日付けの日記で、倉富は、元老西園寺公望との間でかわされた雑談を、例によって、細大漏らさず記録しているのだが、その中で、貞明皇太后と昭和天皇の確執(皇太后は、昭和天皇が皇室古来の神事を疎かにしがちであることについてかねてから不満を持っており、「神を敬せざれば必ず神罰あるべし」と、激越な言葉で批判した)についての、西園寺の証言をさらりと紹介している。
西園寺その他の人々が、事の重大さに配慮して、記録をはばかった当件について、
「宮中のテープレコーダーと化した」(←と、佐野は倉富の態度をかように評している)
倉富は、何の留保も無く書き留めている。
こういったあたりに、倉富日記の歴史的な価値がうかがえる。
ほかにも、当時の皇族・華族の女性問題を記したくだりなど、興味深い話題は多いのだが、倉富日記の魅力は、佐野が、
「大正期日本の“ベスト&ブライテスト”を網羅した点鬼簿の趣も持っている」
と言っている通り、なにより、日記内に登場する人物の顔ぶれの豪華さにある。
皇族華族元老大臣はもとより、森鴎外、柳田國男といった文化人から、内田良平(やくざ)のような変わり種まで、当時の日本の雲の上にいた人々の肉声が、偏見を持たない(というより、自分の意見をほとんど交えない書き手である)
「記録者」
の筆致の中で躍動している。
これは面白くないわけがない。
だから、日記解読者たる佐野は、ゴミの山の中の宝物を選り分けるようにして、倉富日記の迷宮の内に分け入らざるを得ない。
日記の内容そのものはともかく、倉富勇三郎という不可思議なプリズムを通して見た、大正という時代の相貌は、なんだかSFみたいに見えて、とても興味深い。
歴史マニアの人々には、もっと、色々な絵が見えるかもしれない。
私自身が一番面白く読んだのは、日記の解読&解説の作業が一段落したタイミングで挿入される、佐野眞一本人の感想だ。
厖大な作業量と、倉富の朴念仁ぶりに辟易しての愚痴みたいな話も多いのだが、人がものを
「書く」
ということについての省察には、さすがに作家ならではの視点が光っている。
佐野によれば、倉富は、
「ありあまるほどの漢学の素養がありながら、芸術方面にはほとんど関心がなかった」
男であり、その文章は、
「繰り返しを厭わない」
「くだくだしい」
「厳格な」
ものだった。
もとより、文章は、書き手の人格の反映であり、紙の上に定着された一言一句は、すべて書き手の脳髄が作り上げたものだ。
が、逆に考えれば
「書く」
という行為を通じて、人格が形成されて行く側面もある。
[ コメント ]
われわれは、書くことによって、はじめて思想を定着し、自己を確定している。
その意味では、佐野が、倉富の日記を藤枝静男という文学者の作品(『空気頭』という妄想小説)になぞらえて、〈藤枝の『空気頭』が私小説を装った究極のフィクションなら、倉富の文章は、日記を装った究極の私小説なのではないか。
あまりに厳格すぎて、逆に、浮世離れした倉富日記の記述からは、そんな倒錯した思いにすら誘われた〉と評しているのも、あながち的はずれではないのだろう。
いずれにしても、倉富の日記は、一生涯を、
「書く」
ことに費やした稀有な日記中毒者の記録として、一読に値する。
読むのは大変だが、なあに、これを書くことを思えば、たいした手間ではない。
▶笹山尚人「人が壊れてゆく職場 自分を守るために何が必要か」
「人が壊れてゆく職場 自分を守るために何が必要か」(光文社新書)笹山尚人(著)

[ 内容 ]
現代の労働者の困窮は、働く権利の問題だけではなく、「貧困」という生活全体の困窮の問題に広がり始めている。
本書は、実際に起きた事件から、「法令を守らない使用者」と「立場の弱い労働者」にスポットを当て、格差、ワーキング・プア、貧困問題に風穴をあける取り組みを紹介する。
[ 目次 ]
第1章 管理職と残業代―マクドナルド判決に続け
第2章 給与の一方的減額は可能か?―契約法の大原則
第3章 いじめとパワハラ―現代日本社会の病巣
第4章 解雇とは?―実は難しい判断
第5章 日本版「依頼人」―ワーキング・プアの「雇い止め」
第6章 女性一人の訴え―増える企業の「ユーザー感覚」
第7章 労働組合って何?―団結の力を知る
第8章 アルバイトでも、パートでも―一人一人の働く権利
終章 貧困から抜け出すために―法の定める権利の実現
[ 問題提起 ]
面妖なこともあるものだ。
一時期、プロレタリア作家、小林多喜二の代表作、『蟹工船』が、
「蟹工船 一九二八・三・一五」(岩波文庫)小林多喜二(著)

20代の、いわゆるワーキングプアの若者を中心に読まれていたという。
ソビエト領であるカムチャッカの海に侵入して蟹を取り、加工して缶詰にするボロ船を舞台に、人間的な権利も尊厳も根こそぎ奪われ、命を落とすほどの過酷な労働を強いられる乗組員の姿が描かれる。
その姿が、低賃金で働かされいつ解雇されるか分からない、自分たちの姿と重なる、というのだ。
何を寝ぼけたことを言っているのだろうか、との指摘も多くあったと記憶している。
この作品の発表は1929年。
今から約95年前のことだが、過酷な労働状況という点は認めるにしても、当時と今とでは、決定的な違いがある。
労働者の保護立法が、戦前と戦後では、竹槍と鉄砲ほどの差があった。
当時は、労働基準法も最低賃金法もなかった。
組合の合法化を目指した労働組合法制定の試みは、関係者の粘り強い努力にもかかわらず、1931年に頓挫。
非合法下の共産党に入党した多喜二が拷問死させられたのが、その2年後だった。
その様な背景の中で書かれた過去の、それもフィクションに現実を投影するより、いざとなれば、自分たちの身を守る最大の武器となる労働法規をしっかり学んでみるのに、本書は、手ごろなテキストである。
こむずかしい理屈は前面に出さず、法律が無視され労働者の人格や生活がないがしろにされている職場の実態を紹介する一方、法律を武器に、そうした職場を放置している企業と戦う方法を指南する。
取り上げられている事例は、弁護士である著者が、何らかの形で、解決に関わったものばかりだ。
判例をなぞっただけの無味乾燥な記述は皆無で、ある意味、弱い者に味方する正義の弁護士が、快刀乱麻を断つノンフィクションのようにも読める。
本書が、最も力を入れて説くのが、
「労働契約とは何か」
ということである。
[ 結論 ]
労働者が、社員として雇用されたということは、企業側と労働に関する契約を結んだことを意味する。
ここまではいいが、以下をきちんと認識している人が少ない、と著者は強調する。
契約とは、約束である。
つまり、
「契約は他方当事者の了解なく変更できない」
という契約法の大原則は、労働契約にも、当てはまるというのである。
その際に重要なのが、就業規則である。
読者のみなさんも、一度は、目にしたことがあるだろう。
職場の規律や労働条件について、記載された文書のことだ。
この就業規則は、労働契約の内容そのものとなることが多い。
ある日、不動産会社を退職した島崎さんという男性が、
「退職金の額が少なすぎるんですが・・・」
と著者に相談にやってきた。
彼の基本給は、35万円。
就業規則の一部である退職金規定によれば、基本給に応じて退職金は支払われるというが、実際の支給額は、それより遥かに少ない額で、支給額から逆算すると、基本給が、26万円に下げられて計算された、としか思えなかった。
思い当たることがあった。
辞める数カ月前、総務担当係長だった島崎さんに、ある役員が、
「お前はこれから(係長格より下の)店長格だからな」
という不可解な言葉をかけていたのだ。
著者は、彼が起こした差額退職金の返還を求める裁判で、担当弁護士を務めた。
結果、原告側に有利な形で和解が成立したが、これは、著者の尽力によるもの、というよりは、会社側の措置が、いい加減だから勝てた事例、と振り返る。
すなわち、会社側が、実際に、島崎さんを店長に配置転換させ、それに伴い基本給を減額する、もしくは、就業規則を変更し、係長の基本給を26万円に下げていたら、有利な和解は困難だった、というのだ。
なぜなら、就業規則は、労働契約の基礎ではあるが、その制定、および改定の権限は、使用者のみに与えられているからだ。
使用者は、従業員代表の意見を聞く義務はあるが、それに拘束されることなく、規則を作り、適宜、内容を変えることができる。
多数の労働者を、一定の規律のもとに就労させることで、会社組織は、統一され、それにより、生産性も向上する。
それぞれの労働者と一々、内容を確認し、労働契約(=就業規則)を取り交わしていたら、企業活動は立ち行かなくなるというわけである。
問題は、島崎さんの場合も起こりえたかもしれない、基本給の減額(ひいては退職金の減額)という、労働者に、明らかな不利益を強いる就業規則の変更が許されるのか、ということだ。
これに関しては、最高裁の判例を敷衍しつつ、著者はこう述べる。
就業規則の変更が、賃金、退職金といった労働者にとって、重要な権利に関わる事項に関係する場合、
「高度の必要性に基づく合理性」
が必要だ。
労働者本人が被る
「不利益の程度や内容の勘案」
に焦点を合わせ、そこまでせざるを得なかったのか否か、が討議されなければならない。
この原則に即して考えると、就業規則の変更による月9万円の減額という島崎さんの例が
「仕方ない」
と認められるためには、会社倒産の危機といった
「高度の必要性」
を伴わなければならない、ということである。
実は、現在施行されている労働契約法にも、
〈使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない(後略)〉(第9条)
という条項が盛り込まれている。
労働者にとって心強いことだ。
本書には、労働基準法や労働組合法と並び、今後の労働現場における基礎法令となる、この労働契約法が度々登場する。
条文の解説というより、前記のような具体的事例に即して、その意義が説かれるため、理解しやすい。
この労働契約法制定のもうひとつの意義が、安全配慮義務の明文化だ、と著者はいう。
具体的には、
労働契約法第5条〈労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする〉
を指す。
著者は、この
「生命、身体等の安全を確保」
の
「等」
には、労働者の
「人格権」
が含まれると解釈している。
例えば、使用者が、いじめやパワハラが起こっている環境を知りながら、それを放置している場合、人格権の侵害を見て見ぬふりをしていることと同義だから、責任を追及できるというわけである。
本書で紹介される、あるデザイン会社でのいじめ、パワハラはすさまじい。
いや、それ以前に、連日にわたる徹夜、長時間労働が常態化し、会社は、社員一人ひとりに、職場で寝泊りするための寝袋を支給していた。
残業代はもちろんゼロである。
しかも、社員は、会社が指定した住居に相部屋で住まわされ、おまけに、賭け麻雀にも強制的に参加させられていた。
こんな職場だから、上司による部下への暴力も日常茶飯事。
そんななか事件が起きた。
長時間労働による疲労でうたた寝していた社員に対し、上司の一人が
「なに寝てるんだよ!」
という怒声とともに、いきなり殴りかかった。
その男性は、あごに穴が開くほどの重症を負ったが、謝罪もまったくなく、
「病院にも警察にも行くなよ」
と念を押されたという。
著者は、この事件に民事と刑事の双方で対処し、暴力をふるった上司から、巨額の謝罪・賠償金を支払ってもらうことで和解が成立した。
これだけひどい暴力は、刑事事件で立件すべきだろうが、著者の論に従えば、もっと軽微なパワハラの場合、労働契約法が労働者の楯となる可能性が高い。
著者は、たとえ一人ででも、そして、どんな雇用形態でも、加入できる首都圏青年ユニオンという労働組合の顧問を務めており、本書後半は、労働組合の果たす役割と可能性を訴えた内容になっている。
労働組合に関する誤解で最も大きいのは、正社員のみが対象で、アルバイトやパート、派遣といった非正規社員は、組合に入れないということだろう。
牛丼屋チェーン「すき家」が「店舗をリニューアルするから」という理由で、ある店で働いていたアルバイトを全員解雇した事件があった。
リニューアル期間は、たったの1週間。
勤続年数に比例して時給が高くなったアルバイトを、この際だからお払い箱にしよう、という経営側の勝手な判断、という疑いが濃厚だった。
そこで、著者が行った助言は、解雇されたアルバイトらを、労働組合に加入させよ、というものだった。
解雇の違法性を巡って裁判を起こした場合、たとえ勝てたとしても、企業側に請求できるのは、賠償金の支払いまで。
「復職させろ」とは言えないからだ。
早速、解雇されたアルバイト6名が、首都圏青年ユニオンに参加。
解雇の撤回と復職を目指して団体交渉に臨んだところ、ついに会社側が折れ、復職にこぎつけたというのだ。
[ コメント ]
本書を読みながら思ったことがある。
自分が企業に雇用され、働くということが、法的にどんな意味があるのか、何をすると罰せられて、逆に、どんな権利が自分にあるのか、わかっていない社会人が多すぎるのではないか。
もちろんこれは、自戒を込めて、の言葉である。
例えば、いずれも、本書で意を尽くして説明されているが、
「会社に入るということは労働契約を交わすことである」
「出退勤の自由があり、部下の人事に関与でき、経営の重要事項の決定に関与し、地位にふさわしい十分な手当てを支給されていなければ管理職とはいえず、残業代を請求できる」
「企業は勝手に従業員を整理解雇することはできず、満たすべき条件がある」
といったことを頭に入れて、社会に出る若者がどれだけいるか。
一般市民のリーガルセンス、それも、労働法の基礎知識を社会に出る前に、しっかり教える必要がある。
「人件費抑制を目的とした大企業の政策と、それを後押ししてきた政府の無策に、現代の労働者が困窮にあえぐ根本原因がある」
といった、いささか図式的な見解は適当に読み流すにしても、最初に法律ありき、ではなく、あくまで現場の事例から議論を積み上げていく本書の価値は揺らぐものではない。
▶佐野眞一「私の体験的ノンフィクション術」
「私の体験的ノンフィクション術」(集英社新書)佐野眞一(著)

[ 内容 ]
新世紀になろうと、IT時代に突入しようと、人間が生きるうえで調査し、情報を集め、それらを評価して自分のものとする道筋に大きな変化はない。
ノンフィクションの方法とは、ある意味で、社会に生きるうえで必要なそれと驚くほど似ている。
私淑する民俗学者・宮本常一の「野の取材学」を導きの糸に、節目節目の自作を振り返って率直に検証し、そこに込めた思いを語る。
著者がすべての「歩き」「見」「聞き」「書く」人に向けて初めてまとめた、「自伝の面白さ」の文章・取材・調査論。
[ 目次 ]
第1章 あるく調査術、みる記録法
第2章 語り口と体験
第3章 仮説を深める
第4章 取材から構成、執筆へ
第5章 疑問から推理までの道のり
第6章 現代の民俗学をめざして
[ 問題提起 ]
佐野眞一さんの名前を知ったのは、『遠い「山びこ」』を目にしたときだった。
「遠い「山びこ」 無着成恭と教え子たちの四十年」(新潮文庫)佐野眞一(著)

山びこ学校の元生徒たちを探し出し、彼(女)たちの半生を互いに重ね合わせながら、庶民の目から見た日本の戦後史を浮かび上がらせるって力業に唸りながら、一気に読んだ。
そのあと佐野さんは、大作を次々に発表しては論議を呼び、ノンフィクション作家の第一人者になった。
これは、佐野さんがノンフィクションについて語った本だ。
それだけでも面白そうだが、この本は、民俗学者「宮本(常一)に触発された」ものだそうだ。
ノンフィクションと民俗学の取り合わせも怪しいし、以前、宮本さんの代表作『忘れられた日本人』を読んで、
「忘れられた日本人」(岩波文庫)宮本常一(著)

何が面白いのかわからなかったので、私の期待はふくらんだ。
[ 結論 ]
この本で佐野さんは、これまでの仕事を振り返りながら、ノンフィクションをどのように書いてきたか、良いノンフィクションとはどのようなものか、この二点を説いた。
第一点については、正力松太郎の伝記を執筆するのに十年かけたとか、東京電力OL殺人事件の真相を追って容疑者の母国ネパールの奥地まで足をのばしたとか、唸るようなエピソードが次々に登場する。
佐野さんは、ノンフィクションを、
「固有名詞と動詞の文芸」
と言っているけど、そのためには、精神と肉体の両面の体力が必要だってことが改めてわかる。
これだけのエネルギーを使ってはじめて、説得力や賛否両論を巻き起こす力が生まれるのだろう。
でも、体力勝負で、むやみに情報を集めたところで、良い作品になるわけじゃない。
佐野さんによれば、
「情報と情報を人間観や歴史観の紐でバインディング」
し、
「衝突させることで、情報ははじめて物語を動かす歯車となる」。
ノンフィクションだって、作者の思想や個性が問われる点に違いはないのだ。
ここで、宮本さんが出る。
経済的な豊かさと精神の劣化をもたらした高度経済成長は、日本戦後史最大の事件だと考える佐野さんにとって、ノンフィクションの任務は、普通の
「個々人が抱える重みを重みのまま伝えること」
にある。
これを佐野さんは、
「小文字で書く」
と表現するけど、小文字の世界を小文字で書くことの大切さを、いち早く理解し、実践したのが宮本さんだった。
『忘れられた日本人』を深く読めば、こんなことがわかるとは知らなかった。
[ コメント ]
でも、小文字の世界と、政治や経済などの大文字の世界との関係をめぐる佐野さんの説明には、私はひっかかりを感じた。
佐野さんは、一貫して大文字を否定し、小文字の大切さを訴える。
大文字で書くのは、
・大上段に振りかぶってるだけだ
・大文字の世界はうさんくさい
・小文字で書くとは誰にでもわかる生きた言葉で語ることだ
・小文字の世界にこそ神は宿りたまう
というわけだ。
でも、小文字(または大文字)の世界を書くことと、小文字(または大文字)で書くこととは違う。
佐野さんも、ダイエーの創業者とか、読売新聞中興の祖とか、
「冷めたピザ」
と呼ばれた元首相とか、小文字の世界とは、縁がなくなった人たちについて書いてる。
宮本さんは、小文字の世界に接することによって、大文字の世界の意味を嗅ぎとる人だった。
つまり、大文字と小文字を対立させて、一方を選ぶのではなく、大文字のなかに小文字を読みとり、小文字のなかに大文字を聞きとることが大切じゃないだろうか。
これまでの佐野さんの仕事も、そのことを証明してるようにみえるけど、そうではないのだろうか。
▶谷川俊太郎/徳永進「詩と死をむすぶもの 詩人と医師の往復書簡」
「詩と死をむすぶもの 詩人と医師の往復書簡」(朝日新書)谷川俊太郎/徳永進(著)

[ 内容 ]
看取る人、逝く人。
死を目前にした人は、何を思い訴えるのか―。
「命のエンディング」までの様々な臨床エピソードを、ホスピス医療に携わる医師が手紙に託し、詩人が詩と散文で応える。
二年間にわたり交わされた医師と詩人の心ふるえる往復書簡、魂の記録。
[ 目次 ]
朝の申し送り
夜の場所
ラウンジ語り
ラウンジの次元
意味ないじゃーん
感度良好です
なかなおり、至難
困ります
3号室の生徒たち
消えようとするとき〔ほか〕
[ 問題提起 ]
私が大好きだった祖母は、私が12才のとき69才で亡くなった。
人は年を重ねるにつれて
「失うこと」
の重さに気づき、その喪失を前にして慄くのかもしれない。
だから、この本を書店で見たとき、自然に手が伸びた。
故・谷川俊太郎氏は、言わずと知れた現代詩の第一人者。
対する徳永進氏は、鳥取市内でホスピス「野の花診療所」を開設した医師である。
勤務医時代に『死の中の笑み』で講談社ノンフィクション賞を受賞し、
「死の中の笑み」徳永進(著)
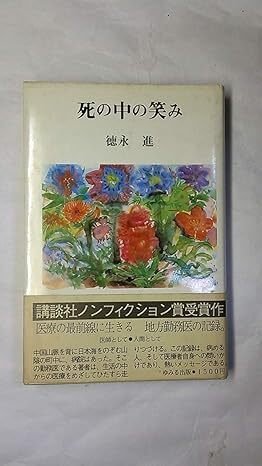
臨床医として働く傍ら、老いや死、医療をテーマにしたエッセイを数多く著わしてきた。
哲学者・鶴見俊輔氏を通じて、その当時、20年ほど前に出会ったという、歳が一回り以上も離れている二人。
本書には、その二人が、2年間にわたって交わしたメールのやりとりが記されている。
[ 結論 ]
現場から発せられる徳永氏の言葉は、一文一文が短く、ライブ感に溢れる会話調。
それを受けた谷川氏が、噛んで含めるような文と一篇の詩で応えていく。
徳永氏が投げたストレートを、谷川氏が、ぽーんと山なりのボールで放り返す、そんな感じのやりとりだ。
たとえば、徳永氏が、診療所の2階ラウンジで開かれる
「お話会」
での一幕を綴ったとき。
語り手は入院患者。
がん患者である83才の女性は、広島での被爆体験をひとしきり語った後に、
「でも自分の死はこわいです。
歩けなくなって、こんな体になってもやっぱり、死はこわいですね」
と言った。
79才の女性は、酸素吸入をしながら、魚の行商をやっていたときの思い出を笑いながら話し続けた。
徳永氏は、患者一人ひとりの語りに耳を傾けながら、
〈ラウンジで話される世界、放たれる言葉。
話し切ることからも、語り尽くすことからも遠いけど、そこに存在した空気が、聞き手の心といっしょにいつも小さく振動するのを覚える〉
と便りを締めくくる。
それに対して、谷川氏の返事は、
「ラウンジ」
という言葉の意味を調べることから始まる。
そして、診療所のラウンジは、
「病院での日常的なルーティンからちょっと浮き上がった空間と時間、病気の苦しみや不安に子どもみたいにタンマをかけることの出来る次元」
であり、そこで、
「お話し会」
が始まるのは、ごく自然なことだと受け取り、こう続ける。
〈物語ることで人は自分自身をより広い背景のうちに、より深い文脈のうちに捉えなおすことが出来るからです。
語ることには語り手と聞き手双方を解放する機能が秘められているのはないでしょうか〉
こうして連想ゲームのように、言葉が言葉を呼び、対話が膨らんでいく。
本書の冒頭で、徳永氏は、医療の現場を、
「言葉が群生する空間」
と表現し、だからこそ、谷川氏に宛てて、その言葉を投げてみたいと思ったと打ち明けている。
谷川氏は、それに応え、
〈死が迫っている人の内面にひそんでいることばは、どんなことばなのでしょう。
(中略)
おいそれとことばにならないものを抱えこんでいる人たちのことば、日常の暮らしのことばとは違う次元にはいろうともがいていることば〉
と返す。
詩と死をむすぶもの。
それは、言葉であると同時に、言葉では伝えきれない手触りやもどかしさ、言葉の余韻でもあるのだ。
徳永氏は、臨床を、
「豊かな矛盾に満ちている」
と言う。
現代医療は、科学的なエビデンスに基づいた医療が重視されすぎ、一人ひとりの物語に基づいた医療を忘れがちだと、批判されている。
だが、そのどちらか一方だけでも、医療は成立しない。
相反するものが共存する場所、それが医療の現場なのだ。
言葉であるものと、言葉でないもの。
科学的な医療と物語の医療。
人の営みは、とかく矛盾だらけだ。
だから、生と死の境も矛盾に満ちていている。
矛盾を受け容れ、
「豊か」
だと捉えること。
それが、丸ごと一冊を通じて伝わってくる。
途中、谷川氏がターミナルケア(終末医療)の先駆者で、精神科医であるエリザベス・キューブラー・ロスの晩年に触れるくだりがある。
ロスは、死にゆく人々のケアに、その生涯を捧げた人物である。
その体験をもとに著した『死ぬ瞬間』は、一大センセーションを巻き起こした。
「死ぬ瞬間 死とその過程について」(中公文庫)エリザベス・キューブラー・ロス(著)鈴木晶(訳)

70歳を前にして、脳卒中に襲われた彼女は、半身不随となった身で、テレビのインタビューに答えている。
そこで、神への怒りをあらわにし、自身の運命を呪った。
死にゆく人々へ尽くした人物が、いざ自らの死に直面して激昂する。
谷川氏は、ロスのこの変貌ぶりに、半ば困惑気味に、徳永氏に、
「どう思うか」
と問いかける。
それに対して徳永氏は、このインタビュー風景を見て、
「思わずにっこり笑った」
という。
人格者が、死を恐れて怒りをぶつける、それでもいいじゃないか、というわけだ。
だが、ロスの人生には続きがある。
彼女の訃報記事には、最晩年は、グループホームで穏やかに暮らし、2004年、家族に見守られるなか息を引き取ったことが記されている。
その記事を読んで思った。
インタビューを受けた当時の彼女は、自身も、また、5段階の2段階目、怒りのステップを踏んでいたのではないか。
そして、そのことを、彼女は、隠しもせず、あるがままを見せていたのではないかと。
[ コメント ]
本書を読んで、死への不安が消えたわけではない。
だが、死と隣り合わせの空間にも、喜びや笑顔がある。
不安は、不安のまま、抱きしめればいい。
そう思って、少し肩の荷が下りたことは確かだった。
■参考記事
■参考図書
社会の話を、
「今現在、議論が巻き起こっている問題」
として考えると、ちょっと辛くなってしまいます。
他人に、その問題について喋ると・・・
相手によっては、口論になることも(^^;
厳密にいうと、それは口論ではなく、意見のぶつかり合いという言い方の方が正しいのですが・・・
波風が立ってしまうことがあるのも事実であり、考えを、別の切り口から、考えてみてもいいのではないでしょうか?
かつて、若き大江健三郎さんは、飢えている子の前で、文学は可能か?と自問したそうです。
それでは、現代社会において、同じく日本社会で身を粉にして働く労働者の前で、やはり純文学は可能なのか?と。
まずは、文学の切り口から考えてみても良いかもしれません。
「文学で考える〈日本〉とは何か」飯田祐子(編)

本書は、森鴎外や太宰治といった文豪から、私たちにとっては、ちょっとマイナーな作家までを取り揃えた、オムニバス短編集です。
しかし、短編が、淡々と掲載されているわけではんくて、各小説の最後に、編集者たちからの解説と問題提起があります。
それを契機として、物語を軸にしながら、明治時代から現在に至るまでの日本の社会情勢を学べます。
・なぜこの作品を書こうと思ったのか?
・誰に向けられたストーリーなのか?
・作者が何を考えていたのか?
文学で作者が伝えたかったことから。
いろんなその時々の
「理由」
や
「実情」。
そして、みんなの
「悩み」
が見えてくるはず。
すべて昔の小説なので、もちろん。
現代の問題には触れていませんが・・・
例えば、
「人間とは?」
とは、よく聞かれる質問ですが、文学的に、人間の姿が描かれれば描かれるほど、人間の闇の部分は広がっていくものだと推定され、その状況下で、
「他人とは何か?」
と問われたら、どう答えるべきなのか・・・
この問題に対する答えは、未だに提出されておらず、こういった文学の視点からでも、私たちが何かを考えるときの材料として、上質なものが揃っていると思います。
■結論
書店などで、何気なく見かける詩集や小説などの作品も、以下の書籍の様に、その書かれた背景を知ることで、実は、作者自身が、社会情勢などに対して、問題意識を抱えた上でのアクションとして発表された作品ということ、を理解することができます。
坂井リョウ「どうしても生きてる」
渡辺和子「置かれた場所で咲きなさい」
茨木のり子「倚りかからず」
また、
「なんかこれって、おかしくない?」
「しっくりこないなぁ」
等々、こんな気持ちも、見過ごさずに、以下の様な図書のタイトルからヒントを求めて、読んでみる価値があったりします。
松田青子「持続可能な魂の利用」
川崎昌平「無意味のススメ 〈意味〉に疲れたら、〈無意味〉で休もう。」
中野信子、ヤマザキマリ「生贄探し 暴走する脳」
「本当に、それって必要ですか?」
「もっと大事なことって、あるんじゃないの?」
こうして、自分の中のモヤモヤについて考えることは、決してわがままなんかじゃないので、新たな気付きとして、活用できたら良いと思います。
■コメント
一例として、大塚英志さんは、
「物語消費」
という言葉で、東浩紀さんは、
「データベース消費」
という言葉でもって、小説の
「類型化と平板化」
という問題を指摘していました。
つまり、現代の文学界では、似たような話が乱発して、制作されてしまい、日本文学全体が没個性的な作風に陥ってしまっている。
その傾向は、ライトノベルの学園モノや「なろう系」をイメージしていただけると分かりやすいかと思われます。
この様に、まずは、人の意見を取り入れて、
「いいな」
と思ったものを、自分から発信していく。
もやもやとしたことを、そのまま口に出すだけではなく、より効率的なものの言い方や、相手をリスペクトしながら、対話する方法を探る。
そんなことからでも、何かを
「考える」
ことには、意味があります。
私たちは政治や経済、社会情勢についての話を、オープンにしづらい空気の中で暮らしてきたのは事実。
しかし、それは、これから変えていくべきです。
ゆっくりで構わないと思います。
気になったテーマをメモに残しておき、気になる本があれば、手に取ってみる。
私たちの小さな1歩は、確かに、社会の大きな1歩に繋がるのですから。
