
028.車いすで浅草七福神巡り|東京|バリアフリー旅行|東京メトロ銀座線・浅草駅→浅草七福神巡り|asakusa-seven-lucky-gods-tour
全国バリアフリー旅行情報センター
各社寺間のアクセスは、段差なく移動が可能です。車いす対応トイレは、浅草寺・浅草神社・石浜神社・鷲神社の境内にありますが、それ以外は下記の地図上に掲載してあるように、アクセスルート内にある公衆トイレなどをご利用いただけますので安心して、ご巡拝ください!参拝するルートは、時計回りでも、半時計まわりでもどちらでも大丈夫です。
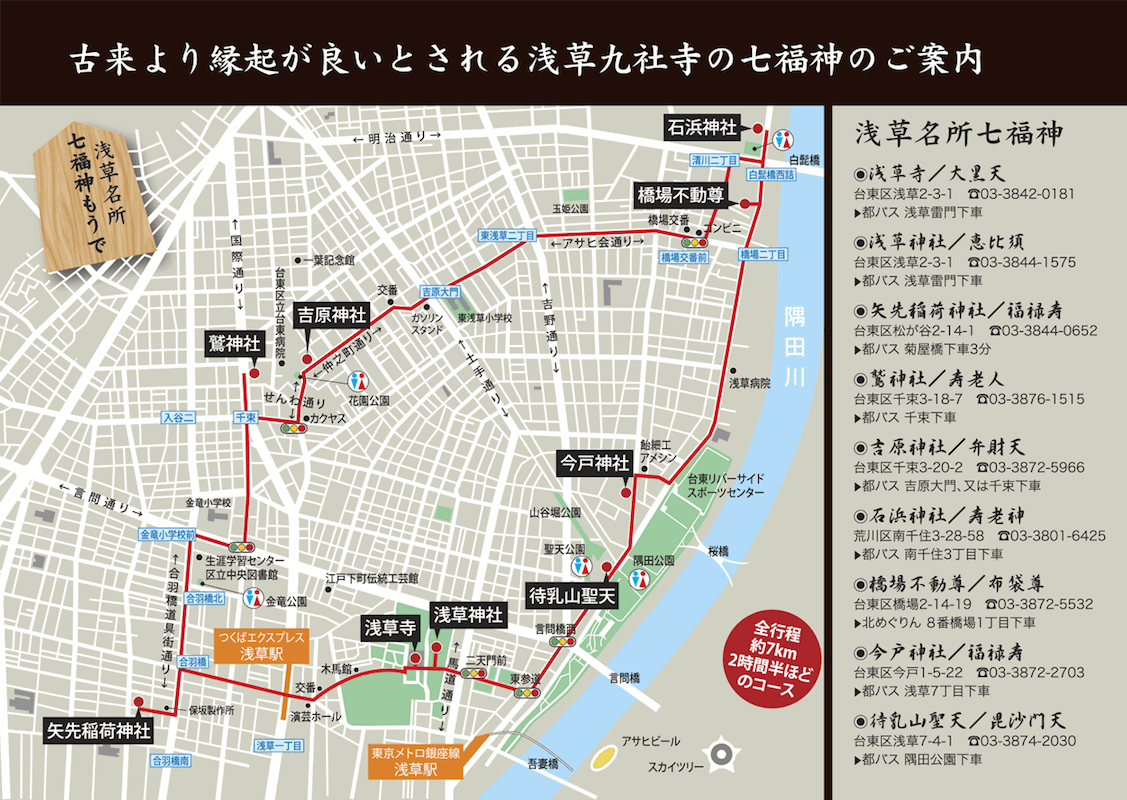
[1]浅草寺|大黒天(大黒天とは)
<施設情報>
浅草寺(せんそうじ)
住所:台東区浅草2-3-1 電話:03-3842-0181(代表)
(案内)大黒天をお祀りしているのは浅草寺です。推古天皇36(628)年3月18日未明のことでした。今の隅田川に投網漁をしていた漁師の檜前浜成(ひのくまのはまなり)、竹成(たけなり)兄弟の網に一体の仏像がかかりました。それを豪族の土師真中知(はじのまなかち)は、尊い観音像であることを知り、深く帰依して自宅を寺とし、その観音像を奉安し、礼拝供養に勤めました。これが浅草寺のはじまりです。大化元(645)年、勝海上人がこの地に留まり観音堂を建立、また夢告によりご本尊は秘仏と定められ武蔵国の観音信仰の中心地となりました。現在の本堂再建工事にあたって出土した数々の遺物から、金龍山浅草寺は少なくとも平安期には大寺の伽藍をここ武蔵野の一漁村に構えていたことが判りました。平安期はじめ、慈覚大師の巡拝により伽藍の整備が行われ、その後一層信者の層も厚くなりました。以来、慈覚大師を中興開山と呼んでおります。鎌倉期以降になると将軍自ら帰依するに及び、名将たちの篤い信仰を集めていよいよ観音霊場として知られるようになりました。江戸時代、天海僧正(上野東叡山寛永寺の開創)の進言もあって、徳川幕府の祈願所と定められ、いわゆる江戸の信仰と文化の中心として庶民の間に親しまれ、以後の隆盛をみるようになったのです。
















文化交流センター(雷門前)






[2]浅草神社|恵比須(恵比須とは)
<施設情報>
浅草神社(あさくさじんじゃ)
住所:台東区浅草2-3-1 電話:03-3844-1575
(案内)浅草神社では恵比須神をお祀りしています。推古天皇36(628)年3月18日、隅田川で漁をしていた檜前浜成・竹成兄弟の投網に観音ご尊像が現出なされました。郷長の土師真中知は、これを拝して篤く敬い、自宅に奉安し朝夕に礼拝、その生涯を安楽に終えました。 真中知の歿後、嫡子が観音様から夢告を受け、それ以来、祖先神、郷土神を祀る「三社権現社」として篤く祀られることになったと伝えられています。明治の神仏分離令により「浅草神社」と改称しました。その創建時代には不明なところもあるようですが、鎌倉初期が通説となっています。浅草神社では江戸三大祭の一つ「三社祭」が、「火事と喧嘩は江戸の華」といわれる江戸っ子の心意気を示して、神と人が一体となって行われることは周知の事実です。この三社祭の歴史は古く、一説には正和元(1312)年の船祭に始まるともいわれていますが、江戸期に入って三代将軍徳川家光の社殿ならびに神輿 の新たな造営を機に江戸市中の一大イベントとなりました。


[3]矢先稲荷神社(やさきいなり)|福禄寿(福禄寿とは)
<施設情報>
矢先稲荷神社(やさきいなりじんじゃ)
住所:台東区松が谷2-14-1 電話:03-3844-0652
(案内)矢先神社では福禄寿をお祀りしています。寛永19(1642)年11月23日、時の三代将軍徳川家光公が国家の安泰と市民の安全祈願ならびに武道の練成のために、江戸浅草のこの地に三十三間堂を建立しました。三十三間堂では弓の射技練成のために「通し矢」が行われました。通し矢は先人に勝てば堂に掲額できるとあって武士としての名誉となり、大いに流行したようです。この通し矢は江戸市民にも観覧が許され、評判を博しました。京都の三十三間堂にならって建立されたこの堂の守護神として稲荷大明神を勧請し、その場所がちょうど的の先にあたっていたので「矢先稲荷」と名づけられました。いまからおよそ360年前のことになります。ご祭神は倉稲魂命(うかのみたまのみこと) を祀りります。ご神体は上野東叡山寛永寺の祖慈眼(じげん)大師(天海大僧正)によって寄進され、「御府内寺社備考」によると「木造で翁の型をして稲を荷い、7寸8分、弘法大師作」となっています。創建以来、創業、学業、人徳の成就と武運長久の神徳に、武士、町人を問わずに尊信を篤くしました。ところが約60年後の元禄11(1698)年9月6日、浅草を中心として大火で焼失してしまい、三十三間堂の方は深川に移転を命ぜられてしまいましたが、その鎮守である当社は信仰心の篤い町民の要望で当地の産土神として再建が許されました。その後も関東大震災、東京大空襲などで幾多の困難に遭いましたが、いずれも難をくぐりぬけて現在に至っています。










[4]鷲神社(おおとり)|寿老人(寿老人とは)
<施設情報>
鷲神社(おおとりじんじゃ)
住所:台東区千束3-18-7 電話:03-3876-1515
(案内)酉の祭、酉の市で知られる鷲神社は寿老人をお祀りしています。江戸下町を代表する神社で、開運、商売繁昌、家運隆昌、子育て、出世の神徳が深いとされ、「おとりさま」と称されて古くから江戸下町の民衆に篤く尊信されてきました。









[5]吉原神社|弁財天(弁財天とは)
<施設情報>
吉原神社
住所:台東区千束3-20-2 電話:03-3872-5966
(案内)吉原神社でお祀りしているのは、弁財天です。吉原神社のご祭神は、稲荷神である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)と弁天様である市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)で、開運、商売繁昌、技芸上達などのご神徳です。元和3(1617)年、徳川幕府の命によって、江戸市中各地に散在していた遊女屋は日本橋葦町あたりに廓として統合されました。これが「江戸元吉原」です。その後、明暦3(1655)年の大火のあと千束村に移転を命ぜられ、そこに新しく造られたのが「新吉原」ということになります。新吉原遊郭には古くから鎮座されていた玄徳(よしとく)稲荷社、それに廓内四隅の守護神である榎本稲荷社、明石稲荷社、開運稲荷社、九朗助稲荷社が祀られておりました。この五社が明治5年に合祀されることになり「吉原神社」として創建されました。吉原神社の歴史は新吉原遊郭のそれと折り重なり、廓の鎮守の神として古くから崇敬されてきました。五社のなかでも 九朗助稲荷社の創建は古く、和同4(711)年、白狐黒狐が天下るのを見た千葉九朗助という人の手で元吉原の地に勧請されたのがはじまりとされています。そして廓の千束村への移転にともなって浅草新吉原の地にふたたび勧請されました。廓内の神のなかでも伝説や逸話に富み、遊女、遊客とからみ、開運、縁結び、商売繁昌のご利益のある神として華やかな信仰を集め、その様は江戸の小噺集などにもしばしば登場しています。





[6]石浜神社(いしはま)|寿老神(寿老神とは)
<施設情報>
石浜神社
住所:荒川区南千住3-28-58 電話:03-3801-6425
(案内)寿老神をお祀りしている石浜神社は、聖武天皇神亀元(724)年9月、勅願によって当地に鎮守され、源頼朝が藤原泰衡征討の折、当社に祈願して「神風や 伊勢の内外の大神を 武蔵野のここに 宮古川かな」と詠み、大勝の目的を果たしたので後日、社殿を造営寄進し、神恩に報いました。建久・正治(1190~1200)のころ、千葉氏、宇都宮氏の尊崇が篤く、また関八州の庶民が伊勢参宮にかえて当社に詣で、おはらいを受けました。当地は東に隅田川、西に富士、北に筑波を遠望する清浄な地で神域にふさわしく、隅田河畔の名所として江戸庶民の信仰厚く、隆昌をみたので「隅田名勝八景」「江戸名所図会」「東都歳時記」などにとりあげられております。 明治5年に郷社に定められました。白ひげ西地区再開発事業により昭和63年9月に現在地に遷座しました。






[7]橋場不動尊|布袋尊(布袋尊とは)
<施設情報>
不動院
住所:台東区橋場2-14-19 電話:03-3872-5532
(案内)布袋尊をお祀りしている不動院(橋場不動尊)は、天平宝字4(760)年、奈良東大寺建立に尽力のあった高僧良弁僧正の第一の高弟寂昇(じゃくしょう)上人によって開創されました。当初は法相(ほっそう)宗でしたが、長寛元(1163)年に時の住職教円(一説には長円)によって天台宗に宗派を改め、鎌倉以降は浅草寺の末寺となりましたが、現在は比叡山延暦寺の末寺となっています。江戸時代には、周辺の三条公、有馬候、池田備前候などをはじめとする武家の尊信をも集め、明治末年の大化、関東大震災、そして昭和20年3月の東京大空襲の際にも、不動院を中心とした橋場の一角だけは災禍をまぬがれたことから、霊験あらたかな橋場不動尊として現在でも広く庶民に尊信されています。現在の本堂は、弘化2(1845)年建立のもので、小堂ながら江戸時代の建築様式を保ち、美しく簡素なたたずまいをしめしています。



[8]今戸神社|福禄寿(福禄寿とは)
<施設情報>
今戸神社
住所:台東区今戸1-5-22 電話:03-3872-2703
(案内)福禄寿をお祀りしている今戸神社は、後冷泉天皇康平6(1063)年、時の奥羽鎮守府将軍伊豫守源頼義・義家父子が、勅命によって奥州の夷賊阿部貞任(あべのさだとう)・宗任(むねとう)の討伐の折、篤く祈願し鎌倉の鶴ヶ丘と浅草今之津(現在の今戸)とに京都の石清水八幡を勧請したのが今戸八幡(現在の今戸神社)の創建になります。その後、白河天皇永保元(1081)年、謀反を起こした清原武衡・家衡討伐のため、源義家が今之津を通過するにあたり戦勝を祈願しました。その甲斐あって勝ち戦をおさめることができ、義家は神徳に報いて社殿を修復しました。戦乱兵火に遭うごとに再建されることしばしばでした。江戸時代、三代将軍徳川家光は、今戸八幡の再建のために官材を下され、船越伊豫守と八木但馬守に命じて寛永13(1636)年に再建がなりました。大正12年9月の関東大震災によって社殿はまたも灰燼に帰し、まもなく復興したものの昭和20年3月の東京大空襲でも重ねて被災の憂き目に遭ってしまいました。こうした被災→再建の歴史をくり返しながら、同46年11月、現在の荘厳な社殿が氏子崇敬者の浄財によって造営されました。その間、昭和12年7月に今戸の隣地に鎮守されていた白山神社と合祀、社名が今戸神社と改称されました。






[9]待乳山聖天(まつちやましょうでん)|毘沙門天(毘沙門天とは)
<施設情報>
待乳山聖天
住所:台東区浅草7-4-1 電話:03-3874-2030
(案内)待乳山聖天では毘沙門天をお祀りしています。古い縁起によりますと、推古天皇3(595)年9月20日、突然この土地が小高く盛り上がり、そこへ金龍が舞い降りたと伝えられています。この不思議な降起は実は十一面観音菩薩の化身「大聖歓喜天」がご出現になるおめでたい先触れであったのです。それから6年後、天候不順に人々は悩まされていました。永い日照りが続き、人々を飢えと焦熱の地獄におとしいれました。そのとき大聖歓喜天がご出現になり、こうした人々を苦しみからお救いになられたそうです。それ以来、民衆からの篤い尊信が集まり、平安時代になると天安元(857)年、慈覚大師が東国巡拝のおり、当山にこもって21日の間浴油修行をなされて国家安泰、庶民の生活安定を祈願し、自ら十一面観世音菩薩像を彫って奉安されたと伝えられています。










■関連情報
全国バリアフリー旅行情報センター/note
要介護のご高齢の方たちが、旅を通して、いつまでも自分らしく、より豊かな人生を過ごすために、noteを活用して全国のバリアフリー旅行情報を発信して、ユニバーサルツーリズムの推進活動に取り組んでいます。
■伴流高志|banryu takashi (プロフィール)
1997年より、要介護高齢者及び障がいがある方と、そのご家族の旅行企画・販売(バリアフリー旅行)に携ってきました。介護福祉士の資格を取得し、世界72か国・国内47都道府県すべての地域のバリアフリー旅行(添乗員同行の募集型企画旅行商品)の旅行計画・手配・添乗業務を行ないました。今後は、個人向けのバリアフリー旅行の普及にも貢献したいと考え、本サイト(Note)を運営しています。
■全国バリアフリー旅行情報センター
2020年より、要介護高齢者や車いすユーザーが旅行に出掛ける際の「宿探しの手間」を少しでも省くことを目的に、バリアフリールーム・ユニバーサルルームの設備があるホテルを紹介するサイトを運営しています。(個人)
■近畿日本ツーリスト株式会社/ユニバーサルツーリズム推進活動
2018年より、長年取り組んできた(物理的な課題を解決する)バリアフリー旅行*募集型企画旅行から、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、超高齢社会や共生社会をキーワードにした様々な社会課題を、異業種や地方自治体と連携しながら解決していく社会課題を解決を目的としたバリアフリー旅行の企画提案を行なっています。また、2019年より、全国の中学・高校・専門学校・大学へ、生徒向けの「心のバリアフリープログラム」企画提案を行なっています。
Copyright © banryu takashi. All Rights Reserved.
本コンテンツに掲載の、記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。すべての著作権は、banryu takashiに帰属します。
