
クリーンエネルギーは私達を救えない
原文:https://freedomnews.org.uk/2024/10/10/clean-energy-cant-save-us/
原文掲載日:2024年10月10日
著者:ヤヴォール゠タリンスキー
グリーン消費主義から脱成長と抜本的システム変革へ
気候変動と深刻化する生態系危機によって、迫り来る大惨事が私達の社会を脅かしている。こういう話がますます語られているのは良いことだ。昨年はこうした問題が否定的に取り上げられていたが、それと比べれば、この点は改善されたと言えよう。また、市民や社会運動だけがこの緊急性を強調するのではなく、政府と民間企業も環境について懸念しているという印象を与えようとしている。もっとも、現在の混乱の主な責任は彼等にあるのだが。
しかし、多くの人々がこの問題を検証する方法には大きな問題がある。支配的システムの特性のためである。トップダウン型管理と経済成長という虚構の中に深く沈み込んでいるため、現在私達が直面している生態系諸問題の根本原因を完全に見逃しているのだ。
その顕著な例がエネルギー生産・分配の問題である。主流派の環境保護主義者と政治家は、汚染源となる化石燃料を再生可能エネルギーに置き換えるよう主張するようになっている。もちろん、こうした移行は、気候変動や環境悪化と戦うために重要ではあるが、決して唯一の必要条件ではない。この問題は技術的なものではなく、パラダイムの問題だからだ。
クリーンな再生可能エネルギーへの移行にだけ注目しがちな人々は、永続的な経済成長という現在の資本主義パターンを当然のこと、「自然」だとさえ思っている。この論理は支配システムの特性を疑問視せず、普段の生活を継続できるようにするために、それらを「グリーン化」する方法を模索しているに過ぎない。本質的に、この思考方法は、来るべき生態系破局を本当に解決しようとしているのではなく、それまで残された時間を長引かせようとしているだけである。
民主的な生態調和社会のエネルギーは、限りある資源の採掘と燃焼からではなく、再生可能資源から得られることは間違いない。これは、持続可能性の前提条件の一つではあるが、間違いなく唯一ではない。このことについてコルネリュウス゠カストリアディスは1980年代に既に社会運動に警告していた。「再生可能エネルギー資源を扱うプロジェクトは、部分的に、改良主義とすら呼びえない目的に--つまり、既存システムの穴をふさぐ目的に--取り込まれてしまう恐れがある」と書いていたのである。
取り組まねばならないのは、私達の社会が同じ永続的成長の途を歩み続けられるという考えである。ますます浪費的な生活様式で増え続けるエネルギー需要を満たすエコロジカルな方法などない。『Less is More: How Degrowth Will Save The World』でジェイソン゠ヒッケルはこの問題に向き合うよう呼び掛けている。
これが問題ではなかったとしても、自問しなければならない。クリーンエネルギーを100%手に入れた後、これを使って何をするのだろうか?経済の仕組みを変えない限り、化石燃料で行っているのと全く同じことを行い続けるだろう。クリーンエネルギーを使って採掘と生産をますます加速させ続け、生物界にますます圧力を掛けるだろう。何故なら、これが資本主義の要求だからだ。クリーンエネルギーは排出ガス対策には役立つかもしれない。だが、森林破壊・魚の乱獲・土壌の枯渇・大量絶滅を食い止めるには何の役にも立たない。クリーンエネルギーを原動力とした成長に執着する経済は、依然として生態系災害へ私達を陥れるだろう。
エネルギー使用の継続的増加は、再生可能エネルギーの絶え間ない拡大を必要とする。その生産に独自の環境的・社会的コストが伴わないわけではない。風力タービン・ソーラーパネルなどは全て、希少な鉱物や材料を使用して作られている。これらは地球から採掘しなければならず、生態系への重大な影響がある。極度の消費主義ライフスタイルに基づく社会にとって、充分なエネルギーなどなく、常により多くを求めることになる。
この問題によりホリスティックにアプローチする方法は、汚染源となる化石燃料を再生可能エネルギーで置き換えることを提唱すると同時に、支配的な資本主義パラダイムに抵抗し、経済の脱成長・不要な消費の削減などを求める代替プロジェクトを推進することである。こうすることでしか、迫り来る生態系破局を回避できないのだ。
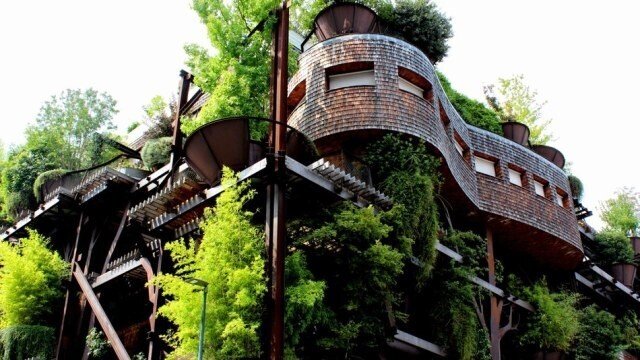
これは、私達が尊厳ある生活を送れるようにしながら、環境に負荷を与えないローテク技術を利用することを意味する。ハイテク解決策は、現在の資本主義基準では、より市場性が高く、計画的陳腐化をさせやすいとして好まれている。永続的経済成長という虚構から離れることで、日常諸問題の解消はハイテク解決策からだけでなく、より単純で古い方法と技術からも得られると実感できるだろう。こうした方法・技術は、迫り来る気候危機に対処し、生態調和社会への道を拓く上で極めて有益なものとなるかもしれない。ヒッケルが示唆しているように「テクノロジーとは何かに関する私達の理解は、複雑な機械に限定されるべきではない。より単純なテクノロジーの方が効果的で、効率的で、民主的な場合がある。例えば、自転車は都市交通の脱炭素化を支援するための信じられないほど強力なテクノロジーであり、アグロエコロジー手法は土壌肥沃度の回復に不可欠である。」
こうした非エネルギー集約型テクノロジーの例は、現代のイランに位置するヤズドという都市に見られる。2つの砂漠の間に建設されたこの都市では頻繁に気温が極度に高くなる。しかし、古来、この住民は独創的な冷房・換気方法を開発してきた。少しの粘土を使って、永続的で・自然で・真に再生可能な方法で、高価で環境負荷が大きいエアコンの仕事を行う驚異的なテクノロジーを考案したのだ。
ここで話しているのは、いわゆる「ウィンドキャッチャー」と呼ばれる煙突のような塔のことである。心地よい涼しい風を取り込み、それを居住者の家に送り込む。電気を使わず、炭素を使わず、メンテナンスコストが非常に低い、優れた自然のエアコンである。
実際、採風塔の多くは、地下の水道管に接続し、冷気を地下に送り込んで流水も冷却できるよう作られている。
このプロセスにより、このような暑い場所でも住宅内の気温を摂氏8度~12度下げられるのである。
公共交通機関もまた、世界の大部分の都市を席巻している主要交通手段である自動車よりも遥かに少ないエネルギーしか使わないアプローチである。都市環境は容赦なく車が支配している。この支配は、強力な産業と資本主義の時は金なりペースに後押しされたライフスタイルの結果である。そして、自動車による支配は公害に大きく寄与している。
主流派環境保護主義の反応は、化石燃料で走る自動車に対する「エコロジカルな代案」として電気自動車を推進する、というものだった。しかし、この観点は、電気自動車の生産が持つ環境的・社会的コストを見過ごしがちだ。実際、このいわゆる代案は、自動車に関わる消費主義ライフスタイルをそのまま維持しつつ、「グリーン化」しようとしている。
遥かにエコロジカルなアプローチは、都市の移動手段を自家用車から公共交通機関に変えることである。公共交通は、環境への影響が大幅に小さく、エネルギー消費も遥かに少ないため、より一層持続可能である。エコ社会主義者のサイモン゠ピラーニが示唆しているように、「公共交通機関が多く、車の少ない都市は、より社会的に平等で、より健康的で、汚染が少ないだけではない。温室効果ガスの排出量も少ないのだ。」

エネルギーへのこうしたアプローチは成長に執着する資本主義の枠組みでは採算が合わないように思えるかもしれない。その枠組みでは、計画的陳腐化がテクノロジーに埋め込まれているため、個人とコミュニティは、自分が既に持っているものを取り換えるよう強制される。修理して使い続けるのではないのだ。しかし、民主的でエコロジカルなポスト資本主義環境では、利益追求型の市場とエリートが運営するのではなく草の根で自主管理されるため、それは自明のことのように思われる。
「ポストカーボン研究所」の上級研究員で作家のリチャード゠ハインバーグによれば、私達に必要なのは「現実的なエネルギー削減計画であって、化石燃料以外の手段で消費者が永遠に豊かになるという愚かな夢を固辞することではない。現在、持続的経済成長に固執している根本には政治がある。これが、真実を語り、より少ないもので豊かに暮らす方法を真面目に計画することを妨げているのだ。」
こうしたパラダイムはトップダウンのやり方では実施できない。ヒエラルキーによって常に支配階級の利益が優先されるからだ。トップダウンでは、社会階層の中で立場が高ければ高いほど、そもそもその特権的地位に自分を就かせた基本的システム特性を維持することに関心が高くなる。このやり方では、意味ある変化を何ももたらせない薄っぺらな改良しか生まない。
逆に、このパラダイムは、ごく少数の企業エリート・政治エリートではなく、社会の全成員の必要と願望を反映するよう一から構築されねばならない。意思決定プロセスがオープンで・包摂的で・透明な直接民主制社会は、利益主導で成長志向のグローバル経済から、より持続可能で公平な代案への移行を可能にする。この代案では、地域の経済と天然資源に及ぼすコミュニティの管理権限をより大きくできる。こうした枠組みにおけるエネルギー生産と分配の可能性について、ピラーニは次のように書いて強調している。「分権型の再生可能エネルギー発電には大きな可能性がある。自治体・地域の発展に、そして共同所有の形態に適しており、より効果的なレベル、より低レベルの電力最終消費量と相性が良い。」
国家なきポスト資本主義環境では、誰もが権力を集団的に共有する。当然、物事を行う優先順位・やり方が根本的に変化し、例えば、「エネルギー?何故、誰のために?」といったような今日では考えられないような質問も提起されるだろう。この推論に従って、カストリアディスは次のように述べている。「もう一つの社会、自律的社会とは、自主管理・自治政府・自主制度だけを意味するのではない。文化という言葉の最も核心的な意味で、もう一つの文化をも意味する。もう一つの生き方・異なるニーズ・人間生活の別な方向性を意味する。」また、彼は次のように問い掛ける。「各個人・各グループ・各コミューン・各国が好きなように行動する『権利』(法的・集団的に保証された実効的な可能性)は、私達全員が同じ惑星の船に乗っていて、個々人の行動が他の人全員に影響しかねないと知った(既に知っているはずだが、エコロジー運動がハッキリと思い出させてくれた)なら、どこまで拡大できるのだろうか?」
結論として、以下のことが言える。生態系崩壊に対して支配的システムの枠組みではまともな解決策など全く生まれないとますます多くの人々に明らかになっている。誰が権力の座についていようとも、成長と競争という資本主義の強迫観念が本質的変革を許さない。ただ、変化の大部分は、消費主義パターンのグリーン化に関わるちょっとした改良に過ぎない。緊急に必要なのは社会組織の抜本的変革である。意思決定権力を(議会のような)官僚主義諸制度と(利益主導の資本主義市場のような)メカニズムから(民衆集会や代理人評議会のような)草の根参加型機関へと移行させることによってのみ、新しい・より持続可能で・生態調和的で・民主的な未来が生まれるのだ。
