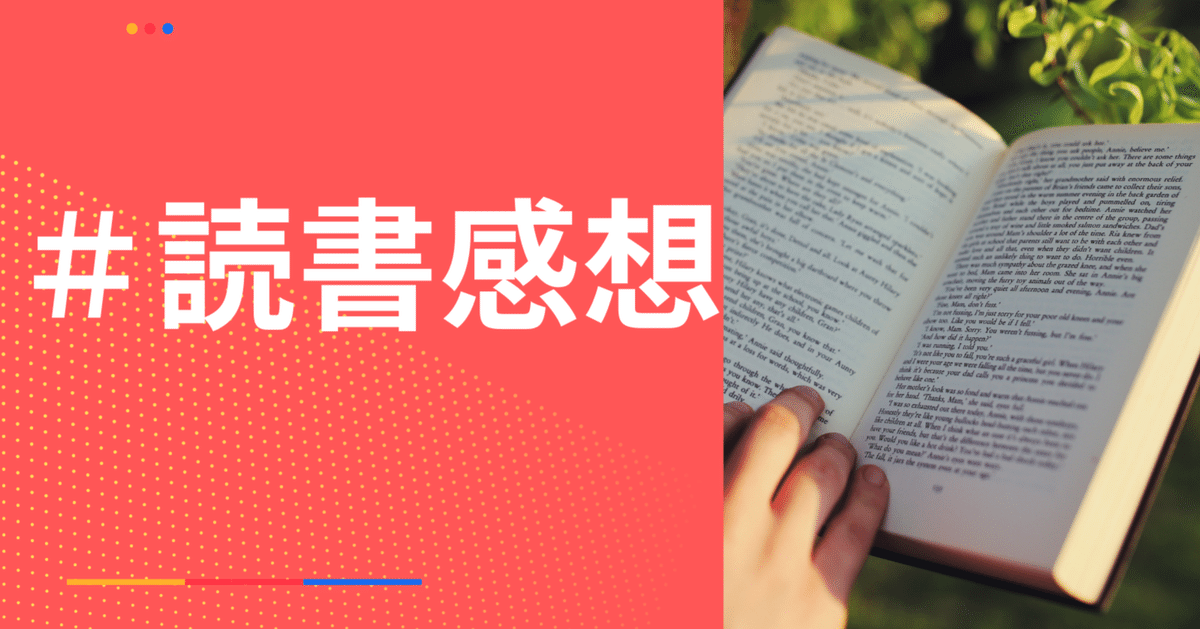
【読書感想】向日葵の咲かない夏/人は誰でも、終わらせなきゃいけない物語を生きている。
向日葵の咲かない夏/道尾秀介
※この記事は約9800文字、だいたい12分で読めます。
読み終えた感想。
なんか、モヤモヤする。
話としては解決した。
散りばめられた伏線も回収された。
数々の謎や違和感についても、それなりに納得できる答えらしきものが書かれている。
それなのに、どうもしっくりこない。
若い頃読んだ、夢野久作のドグラ・マグラの読後感のようだ。
このモヤモヤはどこから来るのか。わたしなりに考えてみた。
そもそもこの本で書かれているのは、「叙述トリック」なのか「ミスリード」なのか。
「叙述トリック」と言ってしまうには、圧倒的に読後の爽快感が足りない。
「う〜ん、騙された〜!この作者すごいわ〜」という、
まんまとしてやられたにも関わらず、その発想力の凄さに思わず「参りました〜」と白旗を揚げる、あの爽快感。
「騙された〜(喜)」というより
「騙された〜!(怒)」と感じてしまったことも、正直言うと、ある。
登場人物のほとんどが、少しずつ肝心なことを隠したまま話が進んでいくことも、
どこか「不誠実さ」を感じて、納得できない気持ちを後押ししている。
正直、リアルな友人に勧めるか?と聞かれれば、
「う、う~ん、やめとこ…」
と、なるだろう。
※※※※※
この本のおもてのテーマは、「世界観」
すべての人々に共通な「客観的事実」だけで書かれている部分と、
主人公が作り上げた「主観的な物語」の部分。
その双方が入り混じり、マーブル模様のような、あいまいな境界線を作り出している。
一体どこからどこまでが「虚」で、どこからどこまでが「実」なのか。
単なるファンタジーとも違う、読む人の読解力を試すような、ある意味、とても挑戦的な内容になっている。
では、そこから読み解く、真のテーマとはなにか。
それは、
「現実からの逃避と、そこからの抜けだし方」なのではないか。そう考えた。
弱さゆえのあやまち。未熟さゆえの失敗。
どうしても認めたくない現実に直面したとき。
それは自分のやったことだと、みずからの責任を認められる人ばかりではない。
「自分のせいじゃない」と、誰かや何かのせいにしたり。
「大したことじゃない」
そう言い聞かせることで、事実を軽く考えて気持ちを紛らわしたり。
そうやって、現実を直視せず、自分にとって都合のいい物語の中で生きていく。
でも、そんなのいつまでも続けることなんてできない。
そんなものは、まやかしなのだから。
人は誰でも、終わらせなきゃいけない物語を生きている。
自分で終わらせないかぎり、永遠にそこから抜け出すことはできない「ネバーエンディングストーリー」を。
終わらせなければならない。自分の手で。
では、どうやって?
人は、ときとして、
破滅的な考え、衝動的な行動により、
取り返しのつかないことをしでかしてしまうものだ。
それすら、弱さゆえ…、未熟さゆえ…のことなのかもしれないけれど。
※※※※※
この本の「事実」と「物語」の境界線は、いったいどこにあるのか?
ここからは、個人的な解釈になる。すべてわたしが勝手にそう思ったことを書いていく。
もちろん、いや違う、そんなわけない、という考えもあるだろう。むしろあっていい。
「そういう解釈もあるんだね…」
くらいの気持ちで読んでいただけると、ありがたい。
この先、ネタバレします。
まだ読んでいない方は、ここで、いったんブラウザバックしてくださいね。
そして、
読み終わったらまた戻ってきてくださると、大変嬉しいです。

ここからネタバレ
まず、結論から。
この本のほとんどは、主人公ミチオの作り上げた妄想の物語である。
夏休み明けに行われる「演劇会」に出たくないミチオが、「どうすれば、演劇会に出なくてすむか」を、必死で考えた、妄想の産物。そう考えた。
こどもなら、誰でも一度は考えたことがあるだろう。
運動が苦手だったわたしも、運動会が雨で中止になればいいのに…と、よく妄想したものだ。
以前よくニュースになった学校の爆破予告なども、このような妄想がきっかけで、短絡的に犯行を思いついただけだったのかもしれない。
ては、どこからが事実で、どこからが妄想なのか。
わたしが出した結論はこうだ。
S君の家にプリントや宿題を届けに行って、自殺を目撃。学校に戻ってその事を話し、音楽の冨沢先生と一緒に家に帰ったところまでは事実。
それ以降の、担任の岩村先生と刑事が家に来て、S君の死体が無くなってたという話からは、すべてミチオの妄想。死んだはずのS君が蜘蛛に生まれ変わって喋りだすとか、岩村先生の秘密とか、近所のおじいさんの過去とか、それもすべて妄想。
そして、ラスト。
ミチオが部屋で花火に火をつけ、火事になる以降は事実。
事実だけを繋げると、
S君が自殺をした20日後に、ミチオの家が火事になり、ミチオだけが助かった。ということになる。
なぜそう思ったのか。引用しつつ、解説していこう。
①名前の表記
まず最初におかしいなと思ったのは、主人公「ミチオ」のことだ。作者が「道尾」秀介で、主人公の名前が「ミチオ」。作者はなぜ主人公に自分と同じ名前をつけたのか。
いったん名前に違和感を覚えると、他の登場人物の名前も気になってきた。
すると、ある共通点が見えてきた。
「ミチオ」「ミカ」「スミダ」「ハチオカ」「タナベ」
こどもはみんなカタカナだ。
「岩村」「冨沢」「西垣」「古瀬」「谷尾」
大人は漢字表記。
とすると、「S君」だけが異質な存在だ。なぜイニシャルなのか。そもそも「S」が、名字なのか下の名前なのかわからない。どっちとも取れる表現になっているからだ。
もうひとつよくわからないのが「トコお婆さん」。本名が「ト子」なのか「「トコ」なのかわからないと書いてある。高齢者なのでカタカナ表記が本名の可能性だってありえる。でも、登場人物の名前は作者が勝手に考えていいのだ。なんらかの理由があっての「トコ」なのだと考えたほうがいいだろう。
「ミカ」「スミダ」「トコ」
最初、カタカナ名の登場人物は、昆虫や花などに生まれ変わった人なのかな、と思った。だとすれば、単なるクラスメートの「ハチオカ」「タナベ」はどう考えればいいのか。
最後にカマドウマに生まれ変わった”お爺さん“こと「古瀬泰造」は?
名前の表記に関する違和感についての結論は、まだ出ていない。でも、これがきっかけでこの話の根幹にかかわることに気がつくことになる。
②ミカの存在
次に感じた違和感は、ミカの存在だ。
S君の死体を見つけて学校に行き、音楽の冨沢先生と一緒にミチオの家に行く場面。このようなやりとりがある。
「ミチオ君、妹さんがいるんだっけ。いくつなの?」
たたきの端に揃えられている、ピンク色の小さな運動靴を見ながら、冨沢先生が訊く。
「今年で――七月で、三歳になりました」
「そう、じゃあ来年から幼稚園ね。そんなに小さな妹さんが、いつも一人でお留守番してるんだ」
「はい、うちは――」(略)「うちは、そうなんです。いつも」<引用>
3歳の子どもを家に置いて、パートに行く母親。
普通なら、保育園に預かってもらうだろう。なぜそれをしないのか。
それに、ミカは妙に大人っぽいことを言う。
3歳児なら、絶対に言わないことや、知らないことまで喋る。まるで大人と会話しているようだ。なにかひっかかる。
「ミカは一体、何者だ?」わたしはだんだん、ミカの存在が気になり始めた。
しかし、“死者が別の生き物に生まれ変わって主人公と会話を繰り広げる“というこの本の設定を、単なるファンタジーだと思いこんでいたわたしは、
違和感を持ちながらも、「そういうものなのか…」と、さして深掘りもせずにそのまま読み続けてしまう。
そして最後まで読み進め、こういう話だったのか!と理解した。
と同時に、答えが提示されているにも関わらす、それでも引っかかりを感じるところがいくつもあった。
わたしは、最初から感じていた違和感と、作者が回収した伏線を確認したくて、はじめからもう一度読み返してみた。
※※※※※
探していた答えは、思っていたより早く見つかった。
物語の冒頭も冒頭、15ページに、それはハッキリと書いてあった。
ちょうど一週間前、国語の宿題で書いた自由作文が、今日、みんなに返却されていた。それぞれの作文の最後に、赤い字で、岩村先生の感想が書き込まれていた。僕は、今年で三歳になった妹のミカが、お母さんのお腹から出てきたときのことを書いた。病院の処置室の外で、お父さんと二人して長椅子に座り、そわそわしながら待っていた、あの思い出を。岩村先生は、「気持ちがよく伝わってきます」と書いてくれた。<引用>
初めにここを読んだときは、ふつうに、妹のミカが生まれてくるのを心待ちにしている父子のことを書いた文章だと思いこんでいた。
でも、たったひとつの言葉の違和感に気づき、その瞬間、すべてを悟った。
病院の処置室の外で…
処置室。
普通、出産するなら、分娩室、もしくは陣痛室だろう。それが処置室とは…。
すくなくとも、われわれが普通想像する「出産」ではなかった可能性が高い。
そう思って読み返すと、
「お母さんのお腹から出てきた」「そわそわしながら」「思い出」「気持ちがよく伝わってきます」
これらの言葉が、まったく別の意味を成す。
妹が生まれてくる喜びを書いたのではなく、むしろその逆。ミチオは、生まれてこれなかった妹のことを書いたのではないか。
そうすると、すべてのつじつまが合う。
ミカは存在していない。いや、ミチオとその母親の「頭の中にだけ」に存在している。
③ミチオの母親
妹のミカが、生まれてこれなかった原因は、自分にある。ミチオはそう思っている。
3年前、母親の誕生日にプレゼントを買ったミチオは、母を喜ばせたくて一芝居打った。下駄箱が火事だと叫んで、飛んできた母親が下駄箱を開けると、そこにあるプレゼントを発見するという、サプライズ演出だ。しかし、想定外のことが起きた。母親が足を踏み外し、階段から落ちたのだ。お腹の中の赤ちゃんは助からず、そして母親は二度と子供が産めない体になってしまった。
ミチオの母親は、お腹の中の子が死んでしまったことを受け入れられなかったのだろう。人形に「ミカ」と名付け、まるで我が子のようにかわいがる。
それと同時に、ミカの死の原因を作ったミチオを赦せず、つらく当たってしまう。
目の前にいる「ミチオ」も、死んでしまった「ミカ」も、同じく血を分けた我が子には変わらないのに。ここまで「ミカ」に執着する理由はなんだろう。
死んだ子の性別もわからないのに女の子だと決めつけ「ミカ」と名付けるあたり、母親は、もともと女の子が欲しかったのかもしれない。
ミチオとの年齢差を考えると二人目不妊で悩んでいたのかもしれないし、もしかしたら、不妊治療をしていた可能性もある。
だからか。お腹の中の赤ちゃんは、一か月半だという記述がある。これを「妊娠1か月半」と読み替えれば、かなり、早い時期に妊娠を確認していることになる。一般的に、生理が遅れて妊娠に気づくころには「妊娠2か月目」に入っているからだ。
病院に運ばれたときに写真(=超音波エコー画像?)を撮ったということは、初めから妊娠していることがわかっていたんだろう。
つまり、予期していない妊娠ではなく、つらく苦しい時期を乗り越えた末の、待ちに待った、待望の妊娠だった可能性が高い。
にしても、だ。
たぶんミチオの母親も、分かっているはずだ。
お腹の中の赤ちゃんが死んでしまったことも。
ミカと呼んでかわいがっているのが、ただの人形だということも。
ミチオのせいで赤ちゃんが死んだわけじゃないことも。
だって、ミカが生きているなら、ミチオは何も悪いことはしていないことになる。
ミチオにつらく当たる必要なんてないはずなのだ。
それでもミチオに対する態度が変わったのはなぜか。
それは、自分を“被害者”にすることで、被害者だから何をしても許されるだろうという、
「甘え」があるのだろうと、わたしは考えた。
自分がかわいそうな被害者であるという妄想の世界にいられれば、自分の好き勝手にできる。
どんなに暴言を吐き、傍若無人に振る舞っても、非難されないどころか同情してもらえる。
ある意味、無敵ポジションを獲得したようなものだ。
誰も悪くない。もちろんミチオも、悪くない。不幸な事故だったのだ。
本当は、分かっている。
でも、それを認めてしまうと、自分が壊れてしまう。
起きてしまった現実を受けいれない。
自分でつくり出した「妄想の世界」で生きていく。
こうやって、かろうじて心のバランスを保っていた。
――その、バランスが、崩れた。
※※※※※
物語のラスト。
燃え盛るミチオの部屋に入り、真っ先にミカの名前を叫び、駆け寄る母親。
「ミカちゃん!」
「それは、ミカじゃない。お母さんが産んだミカじゃないんだ。僕の妹でも何でもない――」
炎に包まれ、ベッドの上でしだいに黒く焦げていくそれを見下ろし、僕は言った。
「ただの人形なんだよ」
僕の声を聞くまいとするように、お母さんは高い声で叫び、ぶるぶると首を横に振った。
(略)「お前がいけないんだ!いつだってお前が悪いんだ!お前さえ――」
(略)お父さんの右手が、ばん、とお母さんの頬を打った。<引用>
「最後に一つだけ教えて」
二人に聞いておきたいことがあったのを、僕は思い出した。火炎の音が周囲を包み、僕の声が二人に届いているのかどうか、わからなかった。
「知ってる?――僕、今日で、十歳になるんだよ」<引用>
母親の、心の、バランスが、崩れた。
(略)全身の感覚が、だんだんと消えていくのがわかった。それでも僕は、眼だけは閉じたくなかった。歪んで、ぼやけた視界の中で、お父さんとお母さんが、僕の方に両手を差し出すのが見えた。お母さんの口は、そのときたしかに、僕の名前を読んでいた。三年ぶりのことだな、と、最後に思った。<引用>
ミチオはずっと、期待して待っていたのだろう。
いつか、
元の母親に戻ってくれることを。
最初の方に、こんな記述がある。
「お兄ちゃん、悪いことしたんだ」
ミカは悪戯っぽい、でもどこか本気で心配しているような口振りで言った。近頃よくミカはこんな仕草を見せるが、その様子は、以前のお母さんにそっくりだった。ミカが生まれる前までは、お母さんもよくこんな仕草を僕にしてみせた。<引用>
3歳のミカが妙に大人っぽいのは、「ミカ」にあのころの母親を投影しているからだ。
人生経験を重ねないと言えないようなアドバイスをする。年齢に似合わないことを知っている。
それもすべて、自分の中だけにしか存在しない「優しかった母親」との脳内対話だったのだ。そう解釈すれば、納得できる。
④人は誰でも、終わらせなきゃいけない物語を生きている。
トカゲにミカと名付けて世話をしながら、
優しかった母親と脳内対話をする。
そうやってこの3年間、ミチオは生きてきた。
お腹の中の赤ちゃんを死なせてしまったという罪悪感から逃れるために、
自分にとって都合のいい物語をつくりだし、その世界に逃げ込んだ。
それは、人形を娘として育ててきた母親も同じだった。
そうやってふたりとも、つらく苦しい現実から目を背けることで、心のバランスを保ってきた。
※※※※※
そんななか、担任の岩村先生が夏休み明けに「演劇会」をやると言い出した。
岩村先生は、演劇部の顧問で、若い頃には小説を書いたこともあるらしい。
「(略)――でも僕は、嫌で嫌で仕方がなかった。だって、体育館の舞台で、大勢の前で自作の劇をやるなんて――ねえ」<引用>
演劇会には出たくない。どうすれば、出なくてすむか。
そもそも、演劇会そのものが中止になってくれないか。
ミチオは、ペアを組むS君が演劇会に前向きなのも気に入らなかった。
S君がいなくなってくれれば――
ミチオは終業式の朝、S君の家に行く。そして一言こう言った。
死んでくれないかな――
そう言って、S君の家を出て、学校に行った。
その日、S君は学校に来なかった。
※※※※※
この本の冒頭。
明日から夏休みの小学生なら、当然胸に抱くウキウキ感や解放感。
そんなものはみじんも感じさせない、暗く、重く、よどんだ空気――。
まさか、本当に自殺しちゃったんじゃないだろうな…。
いや、いつもカラダ弱くてよく休むし、今日だってそうだよ…。
自分がしてしまった事の重大さ。悪い予感。
そしてそれが、自分の思い過ごしであってほしいという、切実な願い。
窓ガラスをたたく風の中に、S君の姿を見た気がした。
それは、恐怖が作り出したまぼろしだ。
岩村先生が、誰かS君の家にプリントや宿題を持っていってほしいという。
自分の目で確かめなければ。S君にあって、謝らなければ。
気がつくと、手を挙げていた。
※※※※※
本当のことを確かめて、早く楽になりたい。
でも、もし本当に自殺していたら…。
S君の家に向かう道すがら。
額から伝う雫。
鉛色の雲が晴れ、太陽が顔を出したから――とは違う、別の種類の汗が混じり、滴り落ちる。
どうか、S君が、自殺なんて、してませんように…。
祈るような気持ちで、玄関にある呼び鈴を、押した。
※※※※※
――本当のことを言おうか――
お母さんね、先生から連絡がきてS君のことを聞いたとき、思ったのよ――
お前が□□□□□□□って――
最後の言葉は、そのとき僕の耳には聞こえなかった。僕の心が、それを拒絶したのだった。自分を守るために。自分が壊れてしまわないように。<引用>
また死なせてしまった。
自分のせいで、お腹の中の赤ちゃんが死んでしまった。
自分のせいで、S君が死んでしまった。
どうしても認めることができない、認めたくない現実を目の前にしたミチオが選んだのは、現実逃避だった。
なんとかして「なかったこと」にできないか。
どうにかして、記憶から消し去ることはできないか。
そう考えて、自分に都合のいい物語をつくりだした。
――そもそも演劇会なんて言い出した岩村先生が悪い。S君は岩村先生に殺されたってことにしよう。
――最近ニュースになってる動物殺し。あれ、S君がやったことにしたら、面白くなるな。
――あの日の朝、S君の家にいるのを見られたかな。じゃあ、お爺さんが全部やったってことにしちゃえ。
最初、尾行までして、あんなに岩村先生にこだわっていたのに、後半まったく出てこなくなる。
前半、学校では“イケてない感じ”だったミチオやS君が、急にヒーローぽいポジションになり、用意周到で頭のキレる、かっこいい感じにキャラ変する。
この本の評価を二分する原因は、ここなのかもしれない。
すべてミチオの妄想なんだから。
都合よすぎる展開も、一貫性のない登場人物も、
「小学生の考えた物語」だと言われれば、まあそういうことなのだろう。
※※※※※
「きみが言わないなら、私が言おうか。――きみは、自分がやったことを認めたくなかったんだ」<引用>
カマドウマに生まれ変わったお爺さんに、本当のことを言われてしまった。
追い詰められたミチオは、溜まっていたものを吐き出すように、言葉をぶちまけた。
「みんな同じなんだ。僕だけじゃない。自分がやったことを、ぜんぶそのまま受け入れて生きていける人なんていない。どこにもいない。(略)だからみんな物語をつくるんだ。(略)みんなそうなんだ。僕はみんなと同じことをやっただけなんだ(略)」<引用>
自分で勝手につくりだした妄想の物語だってことは、ミチオがいちばんわかっている。
そうすることでしか、自分を守ることができなかったのだ。
だから、現実に背を向け、都合のいい物語の世界に逃げこんだ。
3年前、ミカが生まれてこれなかった時のように。
「きみは、このままで、いいのかい?」
その質問は、やはり僕の予想していたものだった。
(略)
「――よくない」
僕はそう答えた。お爺さんは、どこか侘しげな声で、「そうか」と呟いた。「だったら、――どうすればいいと思う?このままで、よくないならば?」<引用>
この本のラスト、カマドウマに生まれ変わったお爺さんとの会話。
これも、ミチオの脳内対話なのだろう。
ミカに見立てたトカゲとの脳内対話。その相手が過去の母親なら、
お爺さんに見立てたカマドウマとの脳内対話の相手は、ミチオ自身。
「壊しちゃうしか、ないだろうね」<引用>
ミチオが壊したのは、物語か。それとも現実か。
それは、この本の一番最後。そして書き出し部分を読めばわかる。
ラストでは、頼れる父親と優しい母親、そして、妹のミカがいる。
冒頭では、大人になったミチオが、「妹のミカ」を回想している。
ミチオは、物語を壊すのではなく、現実を壊すことにしたのだ。
「逃げる」以外の解決方法がある。
その事を学ぶ機会を、自らの手で握りつぶしてしまったミチオ。
彼は今でもずっと、自分だけの物語の世界を生きている。
⑤まとめ
「僕だけじゃない。誰だって自分の物語の中にいるじゃないか。自分だけの物語の中に。その物語はいつだって、何かを隠そうとしてるし、なにかを忘れようとしているじゃないか」<引用>
わたしもそうだった。
都合の悪い現実から目をそらすために、自分でつくり上げた妄想の世界の住人だったのは、わたしも同じ、だ。
そのことに気づかされて、わたしは自分で物語を終わらせた。
簡単なことではなかった。
やってしまったこと。言ってしまったこと。
年齢不相応に未熟なまま、努力をせず楽な方に流されて生きてきたこと。
ときに吐き気をもよおし、のたうちまわりながら。
それでも、妄想の世界から決別した。
そうしたら、だんだんと楽になった。
楽に生きられるようになってきた。
あのときは…。
どうすれば自分を守ることができるのか わからなかったあのときは、そうするしか手がなかった。
でも、いまは、違う。
広い視野を持てるようになった。他の人の気持ちを推し量ることも、できるようになった。
だから、もう、終わらせよう。終わらせていい。
いつまでも自分を苦しめている、そんな物語にしがみつかなくても、
自分を守り、認め、愛してあげることは、きっとできるから…。
人は誰でも、終わらせなきゃいけない物語を生きている。
もう、終わりにしていい。
自分を楽にしてあげていい。
あなたにもきっとできる。
それができるのは、あなただけしかいないのだから。
向日葵の咲かない夏/道尾秀介

生きづらさを解消し、
本来の自分を取り戻すためには、
1)なによりもまず自分を深く理解すること。
2)自分を理解するために、他人の人生を知ること。
この両方が必要不可欠なのではないのでしょうか。
生きづらさを解消するために、
もっと他人の人生を知ってください。
「経験」「気づき」「考え」「学び」「生き方」
ほかの人の人生から学べることは、
思った以上にたくさんあります。
「コンプレックス」「黒歴史」「恥ずかしいこと」「失敗談」
みんな抱えて生きています。
そんな素振りを見せないで、平気な顔をしているから
わからないだけ。知らないだけ。
傷つくことが怖くて、人と深く関わってこなかった人こそ、
他人の人生を知ってもらいたい。
そのために個人出版の本がおすすめ。
現状の個人出版の活用法としては、
一番有効なんじゃないかなと思います。
わたしの人生にも同じようなことあったかも。
似たような境遇なのに、どうやって乗り越えたんだろう。
対話するように本を読む。
自分事として本を読む。
わたしたちは、もっと人生を楽しんでいいんです!!

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
スキ、フォロー、コメントなどを いただけると
たいへん励みになります。
ひとりでも多くの人が「 生きづらさ 」の原因に気づき、
自分の人生を歩き出すきっかけになってくれれば いいなぁと思い、
「感謝と応援の循環」を目指して 発信活動をしています。
応援していただけると、とっても うれしいです。
※あずききなこを一緒に面白がってくれる人、随時募集中!
あずききなこのリンクまとめ
あずききなこの電子書籍最新作!
「40代からの自己理解
こたえはすべて、自分の中にあった」好評発売中!
あずききなこの電子書籍第二弾
「わたしにも書けるかも!」好評発売中!
あずききなこの電子書籍デビュー作
「自分年齢で生きる」好評発売中!
※Amazonのアソシエイトとして、あずききなこは適格販売により収入を得ています。
いいなと思ったら応援しよう!


