
フランス視察記⑦「癒える場所」ではなく「活きる場所」の見極めが市民社会を強くする
この日もとっても快晴!
日本からフランス視察期間の天気予報を見ていた時はほぼ雨予報だったので、やはり私は晴れ女に違いない\(^o^)/
この日はアポ3件で、めっちゃ歩きました!!
最初の地はRépublique駅。République広場はとっても広く、建築物も見惚れます。大規模デモの出発地といえばここみたいですね。

海外に行くときは外務省 海外安全情報配信サービスの「たびレジ」に登録するよう言われますが、たびレジからの通知でも「○○あたりでデモがあるから!!気を付けてね!!」みたいなのが渡仏中たくさん来ていました。

広場を抜けて、お待ち合わせのカフェを目指します。
安發さんは身長が高いのもあるのですが、歩くスピードが半端なく早くて、とても鍛えられます(笑) 私が普通に歩くと10分かかりそうなところを5分くらいでついた感覚。

そして、ずっとオンラインでお世話になっていたアンソレンさんに初対面!1年ほどずっとお話していたので、はじめまして感がない・・・!(笑)


対面の喜びを分かち合ったのち、ブランチをオーダー。
『カフェを10人で予約するのはちょっと無理を聞いてもらった感じだったから、朝ごはんはあまり食べずにカフェで食事してね♪』といわれていたので、おなかをすかせてきたメンバーは到着時にはすでに腹ペコ。

マフィンやブラウニーにも惹かれる中、お店のおすすめは「パンケーキ」と「シャクシュカ(ソースの上に鶏卵を割り落とし、焼いた料理。)」とのことで2手に分かれることに。
シャクシュカが気になる私はとりあえず頼んでみる。
緑か赤かを聞かれ、よくわからないけれど赤にして、卵は何個にするかと聞かれ、「何個がおすすめ?」と聞いたら『何個でも行けるわよ!』といわれ、「とりあえず2個くらい・・・?」と言って出てきたのがコレ↓

・・・・!
なにこれ、めっちゃおいしい・・・!
ということでパクパク。赤はトマトベース、緑はホウレンソウベースだったようです。しかし卵は2個でよかったと思われます。「何個でもいけるわよ」ということはないような気が・・・(笑)
ちなみにパンケーキ組はこんな感じ。こちらもおいしそうでした。

さて本題。アンソレンさんは11年ほど児童養護施設で勤務されたのち、2018年から2022年まで、初日に訪れたパランパルミルの支部の代表をされていて、パレナージュのことについて、これまでもいろいろと教えていただいていました。
今は性暴力にあう子どもたちの当事者団体で、シェルターの施設長をされているそうです。
性暴力、というのは子ども支援をしている中では切り離せない問題なので、はじめはそのあたりからお話を聞かせていただくことに。
フランスでは風俗は完全に禁止されていて、売春の「買う側」には罰金と講習が課せられています。この「買う」加害に関わった人も処罰の対象になるので、直接でなくても、そそのかしたお友達や、場を提供した宿の人も処罰されます。SNSで声をかけるだけでも、もちろんNG。売る側は刑罰の対象にはなりませんが、必ず保護されます。
売春の罰金額は4億円なので、ほぼそれで抑止されているようですが、フランス人でない人が関与する事案が多く、パリオリンピックの時には大規模な啓発キャンペーンもおこなったようです。
何が社会に受け入れられて、何が社会に受け入れられないのかがあいまいにならないよう、性的評価が一般化されないこと、許可なく誰も触られないことが国民に明示されていて、児童保護団体は心配な状況が起きるたびに、加害に対する裁判を起こしまくっているそうです。

パレナージュを日本で進める中でも、性加害が起きない仕組みづくりは求められるところだし、現時点でも『そういうことは大丈夫なの?』と聞かれることも多いのだという話をしたら
『でも、リスクゼロはありえないから』とアンソレンさん。
フランスではリスクももちろん考えるけれど、とにかく動いてやるんだ、ないものはあるところから徹底的にパクるんだ、ということを安發さんからも聞いていました。
日本は逆に『リスクがあるから』『他国だからできることで、ここは日本だから』というような言葉を何度も耳にします。
とにかく、考え尽くした範囲の中で、やれることをやるということが大事。
『リスクがあるのは確かです。だけれども私たちは他のところに比べて、絶対に安全と言えるフォロー環境を創っています。』と言えるかどうかが大事なのです。
例として話されていたのが、印象的でした。
『スポーツクラブのコーチやピアノの先生は、専門職の資格を持っていない人も多いでしょう。子どもを1:1で見ることもできません。どうやってリクルートされた人かを知る由もありません。性加害や暴力についても専門的に学んでいる人は少ないはずです。そういった場所よりもはるかに厳しい選考を潜り抜けて、半里親たちは学びを詰んでいるんですよ、と自信を持てる仕組みにしないといけません。』
もちろん半里親の採用と、採用された半里親と子どものマッチングは総合的な判断になりますが、気になったことを面接でとことん聞いた上で、半里親として活動する地域の大人たちの動機について、こちらも納得感を得た上で進めていく必要があるのです。
ウィーズのパレナージュ・ド・プロキシミテの活動は、いきなり1:1で出かけたり、自宅に行ったりするのではなく、多:多のアクティビティである程度の信頼関係を築いてから、段階を踏んで深めていくことを想定しています。
アンソレンさんがいらっしゃった頃のパランパルミルでも、6人の子どもと6人の大人が(すでに担当のペアは決まっている状態で)パーティをしたことがあるそうです。子どもたちは『自分のことを1:1で見てくれる大人が来てくれる』という期待もあってとても楽しみに参加し、会はとても穏やかに、有意義に終わったそうです。
そのことを振り返りながら『それはいい進め方だと思うわ』と言ってくださいました。
パレナージュは、親が病気がちで子どもの関心に応えきれなかったり、親以外に頼れる大人がいなかったり、グループでの活動では自分を表現できなかったりする家庭にはとても有効だったとのこと。特に、きょうだいに病気があって、他のきょうだいが「自分のことは自分でしなければいけない」状況にある、といったケースにおいては、子どもの自己肯定感の保持という側面で成果があったとのことでした。
一方で、自傷などの行動トラブルがあるケースは、パレナージュの枠組みでは受けきることが難しいので線引きをしなければならないこと、知的障害などへの訓練はしっかり行う必要があること(フランスのパランパルミルでは今は充分に半里親が訓練を受けられるようになっている)なども教えてくださいました。
アンソレンさんとお話をしていてとても印象的だったのが、「半里親の選考とマッチング」についてです。支部の代表をされていたとき、アンソレンさんはすべての半里親応募者のフォーム情報を見て、確認してほしい点を面接官のソーシャルワーカーに伝え、その内容をもとに、代表であるアンソレンさんが最終的な判断をしていたそうです。
応募者自身の苦しみや喪失が解決されておらず、それを見えなくするために活動をしているケースでは、その人の話を聞いて『今この活動をすると、きっとあなたも大変になってしまう』ということを丁寧にお伝えするそうです。
アンソレンさんはこう仰っていました。
『半里親に応募をしてくれる人は、フォームに入力をしてくれた時点で「きっといい人」なのです。だからこそ、パレナージュで活躍の場がなかったとしても、どこかでその人を活かせる場所があるはずだと信じています。私はパランパルミルで半里親に不採用を告げるとき、冷たかったとか断られたといった印象を残さないよう、「あなたが活きる場所を調べて必ず連絡します」と伝え、そのようにしていました。』
児童文学が好きな女性が半里親に応募してきたとき、「児童文学をもっと子どもに伝えたい」という願いを語られました。しかし、パレナージュの目的は「子どもの関心を満たす」ことなので、アンソレンさんはこの女性に『広場で子どもに児童文学を伝える活動をしている団体』を紹介しました。
子どもが欲しくて不妊治療中である女性には、その問題が解決してからというアドバイスをしました。
職場で上席のポジションについて間もない方には、2年間続けてみて、お仕事が安定していたら、また応募をしてきてほしいというお話をしました。
どれも、子どものことを中心に置いているがゆえの判断ですが、言うまでもなく、半里親に応募をしてくれた方の人生が、半里親活動をしたことでしんどくならないための配慮でもあります。
同様の理由で、子ども時代に大変な経験をした半里親と、似た経験をしている大人もマッチングはしないそうです。どれだけ困難を乗り越えて落ち着いていたとしても、何をきっかけとしてどんな思いがあふれるかは誰にもわからないからです。
半里親としての活動は、応募をしてきてくれた人の真の状態はさておき、「誰かの役に立ちたい」という動機があることが多いです。ケアを受けたいという動機の人であれば、ケアに繋げばよいですが、『誰かの役に立ちたい』と門をたたいた人は、その人が「活きる」場所に繋ぐのが大切だと話してくれたことが、とても心に残っています。
ウィーズの支援員さんたちも、「誰かの役に立ちたい」という思いの上にあって、それを実現するためにウィーズにたどり着いてくれたからです。
私も、ひとりひとりが「活きる」場所があると感じています。
ボランティアが主となる活動は、それぞれの想いがうまく重なり合って、市民活動として成り立っていくことが大事です。
いろんなことを言う人も、理解をしてくれない人もいるかもしれないけれど、大切だと思うことに芯を持って行動すること、そしてその芯を共有できる人と歩んでいくことが、どんな評価より尊いことだと改めて思いました。
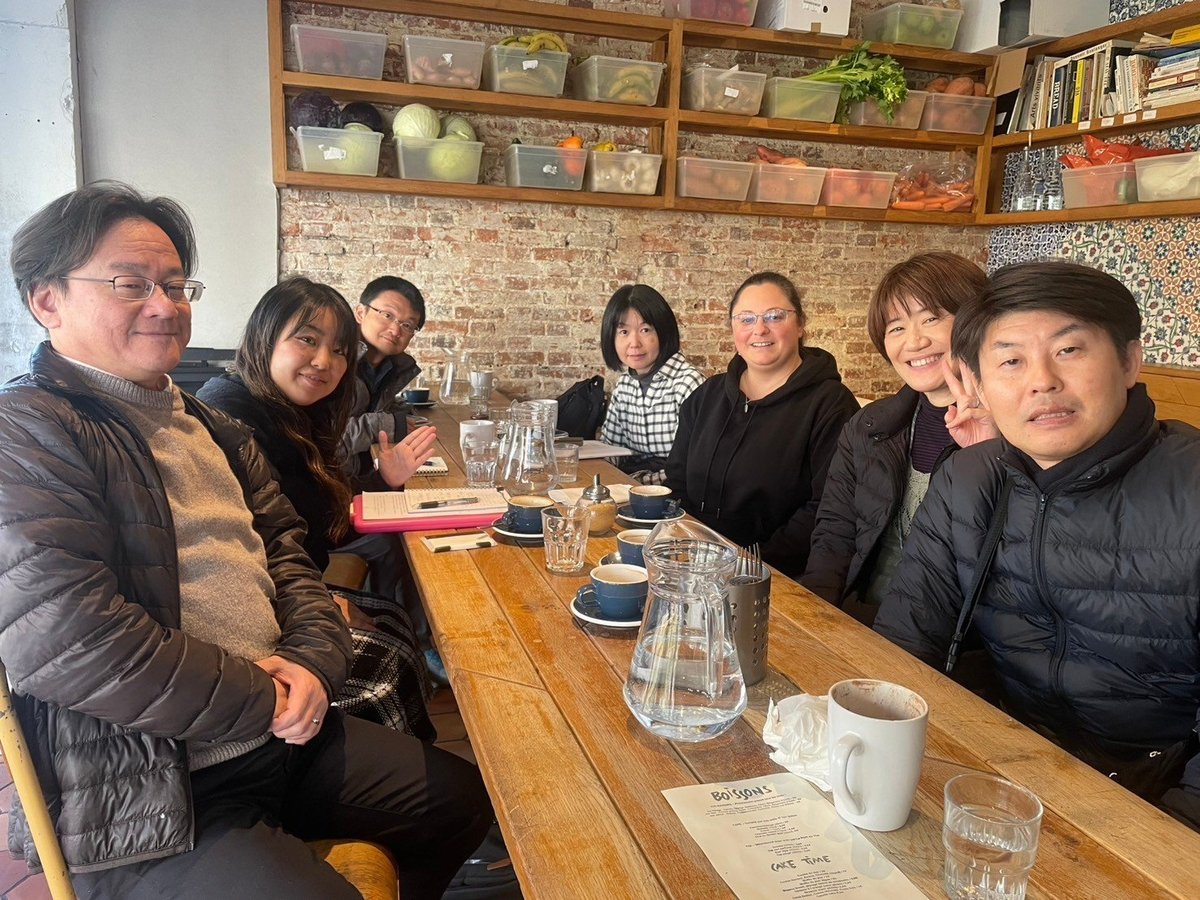
モノが上の方にたくさん格納されている(笑)
また引き続き、オンラインでもよろしくお願いします!ということで、これからお仕事に向かわれるアンソレンさんにバイバイをして、次の目的地へ向かうのでした。
ここからは安發さんコーディネートで、移動がてらの怒涛の(?)1時間ウォーキング&フォトスポットめぐり。あっちいってこっちいって、『ウィーズのみんな早く並んで!!』と言われ、促されるまま写真撮影・・・そして即退散して歩く・・・というのを繰り返します(笑)
しばらくそのお写真をお届けします。




(当時はどこに連れてこられているのか知らず)

(当時はどこに連れてこられているのか知らず②)

(当時はどこに連れてこられているのか知らず③)

「疲れたー?」と聞く安發さんは超元気そうw
こうして視察が終わって整理して、今さら「めっちゃ有名なところ行けてたんや!」と知る始末・・・(笑)安發さんありがとう(笑)
そしてめっちゃ歩いた後に、最後の上り坂を登り切った先にあったのが次の視察先ジャンコクセット協会。面会交流の支援をする組織です。
続きはまた次回!今回もお読みいただきありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!

