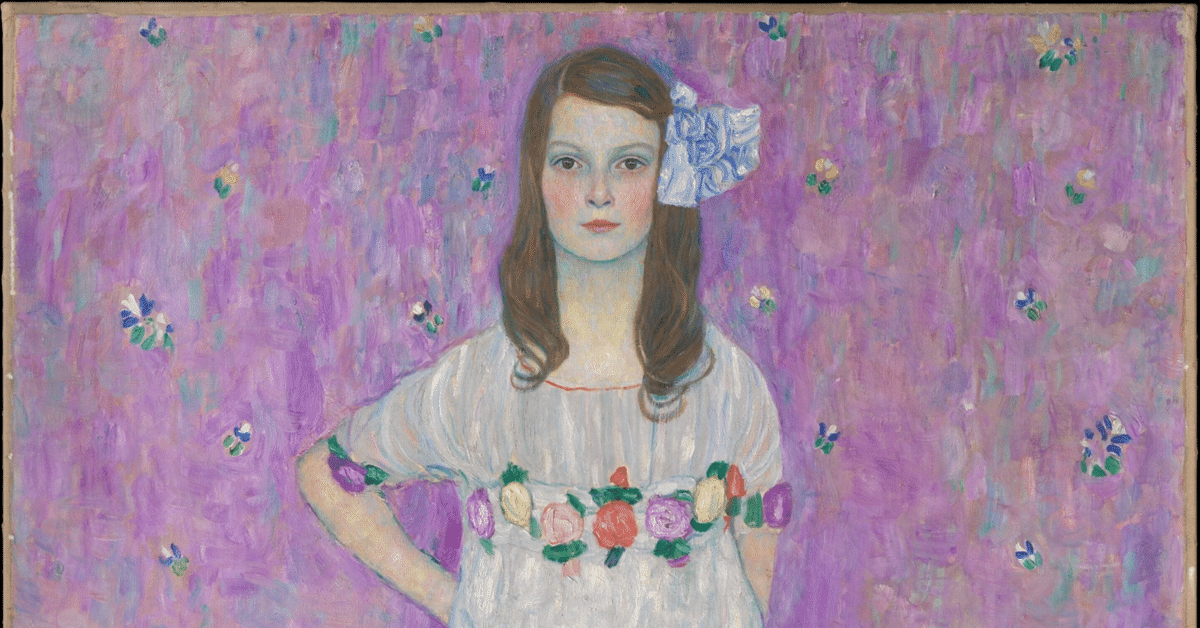
見習いギャラリスト、世界的オークションに現地参加する
銀座の洋画商ギャラリーヤマネに勤めていた頃にさせていただいた数々の貴重な体験は、今でも私の財産になっています。
世界2大オークションハウス
最大のイベントは、ロンドンでSotheby'sとChristie'sのオークションに現地参加させていただいたことでした。
誰もが一度は名前を聞いたことがあるオークションハウスがSotheby'sとChristie'sでしょう。歴史も長く、オークションが開催されるたびに世界中のアートコレクターが動向を注目しています。この2大オークションハウスでの落札金額が、アート市場の作品価格を牽引しているからです。
私が参加したのは、おそらく2007年の初夏だったと思います。今からもう16年も前のこと。この時、一緒に参加していて、のちに独立して湾岸画廊を立ち上げた山根章氏の著作では、こうしたオークションには参加するために3千万円の口座残高証明が必要であると記載されています。
当時20代の下っ端だった私はそんなこともつゆ知らず。機会をいただいたことに、あらためて感謝の念が堪えません。
ロンドンでは下見会から参加し、Sotheby'sとChristie'sそれぞれの、比較的安価な作品を売買するデイセール、高額品を揃えたイブニングセールを経験しました。
Sotheby'sの下見会場にはアート界の不文律に物申すアーティスト、ダミアン・ハーストが
到着して早々に出かけた下見会場には、デイセールからイブニングセールまで、膨大な数の出品作が全て展示されていました。作品とエスティメイトといわれる予想落札価格を照らし合わせながら、会場内の作品をどんどん見て周ります。特にデイセールは点数が多く、競りも昼過ぎから夕方まで続くぐらいですので、到底すべての情報は頭に入りきりません。ともかく目に焼き付けようと必死でした。
すると、同行していた先輩・山根氏が、「ダミアン・ハーストがいるよ」と、向こうを指します。見ると、ずんぐりとしたおじさまが。下見会に参加していたダミアンご本人でした。
この年のセールスでは異例の出来事がありました。それは、アーティストで
あるダミアン・ハースト本人が直接オークションに作品を出品したこと。
通常、オークションはセカンダリーマーケット(2次流通市場)と呼ばれ、一度誰かが購入したものが出品されます。アーティストが直接出品することはありません。法律で縛られているわけではないのですが、いわゆる業界の不文律があるのです。
ここに反旗を翻したのが、アクティビストでもあるダミアン・ハースト。なぜなら、1次流通市場では得ることができる販売益を、2次流通市場であるオークションでは、アーティストは得ることができないからです。販売益を得るのは、オークションハウスと出品者のみ。アーティストには一文たりとも支払われません。ダミアンの問題意識は当時そこにあったのでしょう。
オークションでの落札金額はアーティストにとっての成績表のようにも機能してしまう、活動と切っても切り離せないもの。なのに、オークションでどんなに人気が出て高値で取引されたとしても、作者であるアーティストが金銭的恩恵を受けられないのは、今考えてもどうにもおかしな話です。
この2次流通時のアーティストの不遇については、gallery ayatsumugiとして一つの対応策をとっています。また後の稿で詳しく紹介させてください。
ちなみに、この時のダミアンの作品、金額はうろ覚えですが、すごい金額で落札されていました。
アートの競りに熱狂する紳士淑女たち
身も蓋もない言い方をすれば、オークション会場で同席するのは、世界中から集まるアート好きの「お金持ち」の方々。
会場を見渡して目に入ってきたのは、とても上品な身なりで、杖をついて少し腰が曲がった80代ぐらいのおじいさん。その隣には、50代ぐらいの、昔は絶世の美女だったのだろうなと想像できる、迫力の美人が腰を掛けていました。ハリウッド映画などで描写される富裕層の姿は、かなり的を得ているんだなぁと、変な感想を持ったものです。目当ての作品を競り落としにきた方、出品されている方もいたでしょう。
競りがはじまり、オークショニアが作家・作品名を読み上げて「さぁ、皆さんいかがですか?」と会場に微笑みかけると、目当ての作品を競り落とそうと、会場のパドルが上がり、電話参加のブースからも声が上がります。
どんな人が、どれだけの価格で競り落とすのだろうと、会場内の方々は固唾をのんで競りの様子を見守るわけです。落札が決まり、オークショニアがハンマーを勢いよく鳴らすと、競りが成立。「オークションレコード」といわれる、最高落札額が更新されると、会場から拍手がまきおこります。
その一連の出来事を取り巻く独特の文化、独特の高揚感は、今でも濃く印象に残っています。
動いているのは、お金じゃない、本当は人の気持ち
こうした会場に出向くことができる人にとって、私のような庶民にはもうゼロの数を数えられなくなるぐらいの金額も「払える額」。
オークションというと、つい落札金額の方にばかり目が行きますが、実際に競り落としていく方々の姿を見ていると、作品に向ける何かの想いや感情が見え隠れしました。
人は根本的にアートに心を動かされたい、熱狂したいのです。やはり、額はどうあれ、落札額は単なる数字でしかなく、熱気の総量が形になったものに過ぎないと感じます。
アートの価値は人がつくるもの。感動の総量、人と人とのアートにまつわるさまざまなやり取りの総量が、くっきりとした数字になるのが、落札金額ともいえるでしょう。
アートマーケットはお金を指標にものを考えるのが苦手な方々からは毛嫌いされやすい世界です。私自身も、実際にこうした場に居合わせていなかったら、マーケットを毛嫌いしてしまっていたかもしれません。でも今は作品を鑑賞して感動する心の延長線に、ハイエンドなマーケットも存在しているのだと確信しています。
メールニュース登録のご案内
gallery ayatsumugiでは、ひとつの作品とひとつの言葉を、折々に「Letter」としてお届けしています。登録はこちら。
小さな展覧会のようなメールニュースをお楽しみください。
